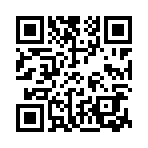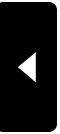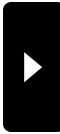2013年12月23日
サロン マナ・有機ゲルマニウムと水素
がんばるアナタに明日の元気を!

有機ゲルマニウムと水素
医療ミネラルと強力な抗酸化

手軽に駅前温浴
ゲルマニウムは、自然界にある物質です。肩や首のこり、腰や膝の痛みのあるところは、プラスイオンが集まっています。漢方薬に多く含まれる有機ゲルマニウムは、生体に作用して、不快な症状を取り除いてくれます。
水素は体内の活性酸素を除去します。なかでも一番の悪玉活性酸素『ヒドロキシルラジカル(万病の元)』に水素はよく反応します。水素は血管がない部位、たとえば関節の軟骨などにも届きます。また、脳にも入って活性酸素を除去するのです。
11:00-21:00(土日は19:00)
木曜定休・予約優先
ダンゼン安い水素吸入

駅近90m!
東西線浦安駅 西友むかい
オリジン隣 エレベータ4F

千葉県浦安市北栄1-15-27
熊川ビル18・401
047-702-9828

有機ゲルマニウムと水素
医療ミネラルと強力な抗酸化

手軽に駅前温浴
ゲルマニウムは、自然界にある物質です。肩や首のこり、腰や膝の痛みのあるところは、プラスイオンが集まっています。漢方薬に多く含まれる有機ゲルマニウムは、生体に作用して、不快な症状を取り除いてくれます。
水素は体内の活性酸素を除去します。なかでも一番の悪玉活性酸素『ヒドロキシルラジカル(万病の元)』に水素はよく反応します。水素は血管がない部位、たとえば関節の軟骨などにも届きます。また、脳にも入って活性酸素を除去するのです。
11:00-21:00(土日は19:00)
木曜定休・予約優先
ダンゼン安い水素吸入

駅近90m!
東西線浦安駅 西友むかい
オリジン隣 エレベータ4F

千葉県浦安市北栄1-15-27
熊川ビル18・401
047-702-9828
2013年12月23日
「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
週刊現代 2013年12月16日号
世界中のどこも、経験したことがない社会 65歳以上の4人にひとり、80歳以上は2人にひとり 何もわからない。訳もなく徘徊する。被害妄想に取り憑かれる。そんな人々が街中に溢れたら
「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

誰でも、歳を取ればもの忘れはひどくなる。「ド忘れしただけ」「自分は病気じゃない」と思いたい。だが認知症は、今もっとも身近な病気。怖いけれど、いずれ必ず直面する「現実」に向き合ってみよう。
治す方法はない
「うちのマンションに20年ほど住んでいる77歳の女性は、認知症です。10年前にご主人に先立たれてから発症したようですが、子供も親戚もおらず、一人暮らしを続けています。
最近、お金の管理ができなくなってきて、家賃を滞納しています。年金手帳をなくしてしまったらしいのですが、探すことも、再発行の手続きもしません。銀行口座も、暗証番号を忘れてしまったと言っていました。だから、お金を一切下ろせない。すでに、半年分の家賃をいただいていません」
こう語るのは、東京・大田区のマンション管理人・加瀬弘子さん(仮名)だ。古い物件で家賃が安いためか、全20室のうち7室に一人暮らしの高齢者が入居し、うち3室の住人が認知症を抱えているという。加瀬さんが続ける。
「家賃の督促に行くと、彼女は滞納しているということも忘れているので、『ちゃんと払っている』『年寄りだからって騙そうとしているんだ』と逆切れする。部屋を覗くといつも暗く、電気、ガス、電話が止められているようです。食事は配食サービスを頼んでおり、その料金は口座から引き落としになっているので命の危険はありませんが……。要介護認定を受けてヘルパーを受け入れるよう説得していますが、断固拒否しています。
他の認知症の方も、騒音をたてたり、79歳の男性は女性入居者の家のドアの前に居座るなど、ストーカーまがいの行為をしたり、問題が絶えない。このまま続くなら、強制退去も選択肢の一つだと思っています」
ここ近年で、認知症が爆発的に増加している。今年6月に発表された厚生労働省研究班の調査結果によると、'12年時点で65歳以上の認知症患者は約462万人、予備軍(生活に支障をきたさない程度の軽度認知障害)を含めると、860万人以上。実に、65歳以上の4人にひとりが認知症ということになる。
「80歳以上になると、予備軍を含めれば2人にひとりにまで増えます。私は、高齢になれば認知症はかかって当然の病気と思って、患者さんと向き合っています。でも、大病院のような3分診察では見抜けない。自分が認知症と知らない方も多いと思います」(在宅医療専門の「たかせクリニック」理事長・高瀬義昌医師)
認知症は、今のところ進行を遅らせる薬はあっても、治す方法はない。現在「予備軍」と言われる人も、いずれは認知症の症状が進行していく。800万人以上が認知症を発病したら、この国は一体どうなってしまうのか――。
認知症高齢者の理屈が通用しない言動は、時に危険を伴い、介護者の神経をすり減らす。認知症の代表的な症状で、アテもなくさまよう「徘徊」が、その一つだ。78歳の父親の徘徊に悩まされた、吉田正志さん(54歳・仮名)が語る。
「ある夜、10時過ぎに父親の寝室に様子を見に行くと、姿がなかった。パジャマ姿でお金も持っていないし、近所にいるだろうと思っていたんですが、一向に見つからない。これはヤバいと警察に捜索願を届け、家族は眠れぬ夜を過ごしました。そして翌朝、8km離れた隣の区の警察から、見つかったと電話があったんです。なんでも、知らないお婆さんと手を繋いで歩いているところを保護されたという。近所を歩いていたら、同じく徘徊していたお婆さんと出会い、デートのつもりで遠くまで行ってしまったらしい。これを境に、昼夜を問わず徘徊するようになりました」
施設にも入れない
吉田一家は、もう手におえないので、父親を施設に預けたいという。このように徘徊に悩み、施設に入れるケースが増加していると語るのは、千葉県の特別養護老人ホームの職員だ。
「徘徊癖のある入居者が増えたので、うちでは入居者の安全のためにも、両手をベッドに縛って拘束をするようになりました。人員が足りないので仕方ない。どこも人手不足ですから、徘徊をする入居者に限って拘束する施設は増えていくのではないでしょうか」
身動きが取れないよう体を縛りつけるのは、人間の尊厳にかかわる重い問題だ。だが、放っておけば命にかかわる事故に繋がる、という指摘もまた重い。
「認知症の人は、自分が病気と自覚していないことも多いので、平気で車を運転しようとするんです。認知症の診察を受けるため、車で来院した人もいました。『危ないから運転はやめて』といっても、大丈夫だと言って聞かない。しかし、徘徊と同じように、運転中に道が分からなくなったり、道路標識が分からなくなったりと、大変危険です。これから認知症高齢者による車の事故は、どんどん増えていくと考えられます」(前出・高瀬医師)
認知症による交通事故がもっとも心配だと語る高瀬医師だが、もう一つ懸念があるという。
「お金を払うことを忘れ、結果的に万引きをしてしまうという悲劇です。高齢者が多く収容されている刑務所には、認知症高齢者が多いと聞きます」
実際、万引きを取り締まっていぶセキュリティ会社の社員は、認知症高齢者の犯罪の増加に驚く。
「埼玉県内を中心に、約50店舗に万引きGメンを派遣していますが、月に80~90人捕まえる万引き犯のうち、およそ1割が認知症高齢者です。これまでは、万引きをした高齢者は自分は認知症だと嘘をついて言い逃れしようとするケースがほとんどだったのに、最近は本当に認知症患者なんです。万引きがきっかけで、認知症と診断された人もいました。こうした事案は今後増えるでしょう。深刻な問題であると弊社では捉えています」
「金銭感覚」や「社会性」を失っていき、さらに症状が進行すると「家族の顔」すら判断できない。その時、「家の中に知らない人がいる」と勘違いしたり、「いじめられている」と被害妄想が膨らんで家族を傷つけてしまうこともある。重度認知症をもつ68歳の義父を介護する佐々木文子さん(45歳・仮名)が、辛い出来事を明かす。
「同居している中学生の息子に、突然『泥棒! 俺の金を盗んだだろ!』と叫んで包丁を振り回したのです。止めようとした主人は腕を切られてしまいました。うちには小学生の娘もいるので、もう危険だからと施設に入れようと思いました」
ところが、すでに施設は満床で、少なくとも1年待ちだと言われたという。
「施設への入所が必要な認知症患者は約300万人いますが、高齢者住宅を含む収容施設の定員は150万人ほど。今も、施設でのケアが必要な認知症患者の2人にひとりがあぶれてしまっている。施設を増やそうと行政も取り組んでいますが、認知症高齢者が激増している今、施設不足は今後も解消されないでしょう」(介護に詳しい淑徳大学社会福祉学科・結城康博教授)
「老老介護」から「認認介護」へ
施設を利用できないと、その負担はもろに家族にのしかかる。身体的な負担もさることながら、金銭的な負担もバカにならない。50代の男性が、親の介護生活の現実を話す。
「同居していた母親が80歳になったころ、もの忘れの症状が出てきました。最初は買い物に行って、何を買うのか忘れてしまう程度だったので、私たち夫婦は二人とも仕事をしていました。ところがある日、家に帰ると母親がガスコンロの上に電気炊飯器を置いて火をつけていたのです。慌てて火を止めたら、母親は、『ご飯を炊こうと思ったのに火を消すなんて』と怒る。その時、認知症だと気がついたんです。危ないので、私は仕事を辞め、自宅で介護することにしました。
ところが、今度は妻の80歳の父親も認知症になってしまった。しかたなく妻も仕事を辞め、介護のために実家の北海道へ。夫婦別居の介護生活が始まり、今年で丸7年が経ちました。収入はゼロ。夫婦の退職金と親の年金をやりくりしていますが、生活に余裕はまったくありません……」
医療経済学者で、医療経済評価総合研究所所長の五十嵐中氏は、認知症患者の増加が引き起こす社会経済的負担をこう分析する。
「旧年の厚労省統計では、認知症患者一人当たりの年間医療費は、81万~152万円です。
しかも、認知症はゆっくり進行し、治ることもないので、医療費はズルズルとかかり続ける。その上、介護費用もあるので、たとえば進行が速く、比較的短期間で亡くなるがんなどの病気よりもトータルの金額が高くなることもある。先の夫婦のケースのように、介護のために仕事を辞める人も多く、医療費の負担が大きい一方で収入が減るという厳しい現実もあります」
ただし、息子や娘などが面倒を見てくれるならまだマシだ。これまでも高齢の夫婦同士で介護する「老老介護」が問題になっていたが、最近では介護する側も認知症という「認認介護」が増加してきている。
認認介護とは、どのような状況なのか。認認介護の夫婦の家の隣に住んでいた主婦が、その実情を語る。
「5年ほど70代の認知症の奥さんを介護していた旦那さんも、2年前に認知症になってしまった。お互いにご飯を食べたことも、食べさせたことも忘れてしまうため、夫が1日に何回も食事をさせ、奥さんは一時期かなり太っていました。去年の秋には柿を30個ぐらい買ってきて、皮ごと奥さんに一気に食べさせた。翌日、ひどい下痢になったようで、布団の上で全部漏らしていたんです。旦那さんは鼻がきかなくなっているのかまったく気に掛けず、異臭に気付いた私か駆けつけた時には、奥さんはウンチまみれ。その時は、私が一人で処理しました。
それからしばらくして、隣から一切物音がしなくなったんです。おかしいと思って警察を呼び、中に入ると、二人とも栄養失調になっているのを発見。慌てて入院させました。今度は、食べさせるのを忘れてしまっていたんです」
日本経済にもダメージが
認認介護の現場では、いつ何が起きても不思議ではない。たとえば今夏、記録的な猛暑の中で87歳の夫と78歳の妻が自宅で熱中症で倒れているのが発見され、介護していた側の妻が亡くなった。
また、'09年には富山県で、認知症の妻が認知症の夫を殺害する事件も発生。介護していた妻が、おむつを替えるのを嫌がる夫を叩き続けて殺してしまった。妻は、自分が何をやったかも、夫がなぜ死んだのかもわからないままだという。
在宅医療の第一人者・「川崎幸クリニック」院長の杉山孝博医師は、認認介護の現状を危惧する。
「夫婦ともに認知症になれば、介護どころか生活が成り立たなくなる。すでに、80歳以上の夫婦の11組に1組が認認介護の状況にあります。将来的に、認認介護は増え続けるでしょう。一人が亡くなった後、残ったほうの症状が劇的に重くなるケースも多いです」
また、アメリカで行われた研究では、高齢の夫婦で一方が認知症だと、もう一方も認知症となるケースが、そうでない場合より6倍多いという。「認知症が認知症を呼ぶ」-そうし
て、800万人もの認知症患者が街に溢れたら、この国はいったいどうなってしまうのだろうか……。
「70歳の男性の行方が分かりません。服装は緑のセーターに灰色のズボン。お心当たりがございましたら、××市役所までご連絡をお願いします」
すでに認知症高齢者が800万人を超えた20XX年の日本では、1時間に一回、街頭拡声器で高齢者の迷子放送が繰り返される。
交通渋滞は、日常茶飯事。認知症高齢者による交通事故が多発するからだ。事故を起こすほうも、事故に遭うほうも認知症高齢者が圧倒的に多い。
警察は、巡回する警官の人数を3倍に増員。徘徊、交通安全の取り締まり、そして頻発する高齢者による万引きに眼を光らせる。刑務所は、3分の2が65歳以上の入所者で占められ、まるで老人ホームのようだ。
施設は5年先まで満床。そのため、ただでさえ労働人口が減っているのに、在宅介護を余儀なくされた若者が仕事を辞めて世話をする。貧困家庭が増え、消費減少で日本経済にも深刻なダメージを与えている。
急増した認認介護の夫婦は、二人とも口座の暗証番号を忘れ、手元にお金はゼロ。近隣住民は、自分の親族の介護に手いっぱいで余所に目を向ける余裕はない。悲惨な最期を迎える高齢者夫婦は後を絶たないI。
このような地獄未来図は、やがて確実にやってくる。我々には何か、打つ手はあるのか。
「認知症は、完治は難しい。治療薬もありますが、治すというより、進行を遅くする薬です。これは、初期段階で使うか、ある程度進行してから使うかによって効き目が違う。初期であれば、進行を50%遅くできるというデータがあります。しかし、重くなっていれば、手遅れになる。認知症は、早期発見・治療がカギなのです」(認知症ケアに詳しい「お多福もの忘れクリニック」の本間昭医師)
決定的治療法のない病が、爆発的に増加する恐怖。それは、「長寿大国」の誉れを得た日本が対峙しなければならない、大きな試練なのかもしれない。
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
世界中のどこも、経験したことがない社会 65歳以上の4人にひとり、80歳以上は2人にひとり 何もわからない。訳もなく徘徊する。被害妄想に取り憑かれる。そんな人々が街中に溢れたら
「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

誰でも、歳を取ればもの忘れはひどくなる。「ド忘れしただけ」「自分は病気じゃない」と思いたい。だが認知症は、今もっとも身近な病気。怖いけれど、いずれ必ず直面する「現実」に向き合ってみよう。
治す方法はない
「うちのマンションに20年ほど住んでいる77歳の女性は、認知症です。10年前にご主人に先立たれてから発症したようですが、子供も親戚もおらず、一人暮らしを続けています。
最近、お金の管理ができなくなってきて、家賃を滞納しています。年金手帳をなくしてしまったらしいのですが、探すことも、再発行の手続きもしません。銀行口座も、暗証番号を忘れてしまったと言っていました。だから、お金を一切下ろせない。すでに、半年分の家賃をいただいていません」
こう語るのは、東京・大田区のマンション管理人・加瀬弘子さん(仮名)だ。古い物件で家賃が安いためか、全20室のうち7室に一人暮らしの高齢者が入居し、うち3室の住人が認知症を抱えているという。加瀬さんが続ける。
「家賃の督促に行くと、彼女は滞納しているということも忘れているので、『ちゃんと払っている』『年寄りだからって騙そうとしているんだ』と逆切れする。部屋を覗くといつも暗く、電気、ガス、電話が止められているようです。食事は配食サービスを頼んでおり、その料金は口座から引き落としになっているので命の危険はありませんが……。要介護認定を受けてヘルパーを受け入れるよう説得していますが、断固拒否しています。
他の認知症の方も、騒音をたてたり、79歳の男性は女性入居者の家のドアの前に居座るなど、ストーカーまがいの行為をしたり、問題が絶えない。このまま続くなら、強制退去も選択肢の一つだと思っています」
ここ近年で、認知症が爆発的に増加している。今年6月に発表された厚生労働省研究班の調査結果によると、'12年時点で65歳以上の認知症患者は約462万人、予備軍(生活に支障をきたさない程度の軽度認知障害)を含めると、860万人以上。実に、65歳以上の4人にひとりが認知症ということになる。
「80歳以上になると、予備軍を含めれば2人にひとりにまで増えます。私は、高齢になれば認知症はかかって当然の病気と思って、患者さんと向き合っています。でも、大病院のような3分診察では見抜けない。自分が認知症と知らない方も多いと思います」(在宅医療専門の「たかせクリニック」理事長・高瀬義昌医師)
認知症は、今のところ進行を遅らせる薬はあっても、治す方法はない。現在「予備軍」と言われる人も、いずれは認知症の症状が進行していく。800万人以上が認知症を発病したら、この国は一体どうなってしまうのか――。
認知症高齢者の理屈が通用しない言動は、時に危険を伴い、介護者の神経をすり減らす。認知症の代表的な症状で、アテもなくさまよう「徘徊」が、その一つだ。78歳の父親の徘徊に悩まされた、吉田正志さん(54歳・仮名)が語る。
「ある夜、10時過ぎに父親の寝室に様子を見に行くと、姿がなかった。パジャマ姿でお金も持っていないし、近所にいるだろうと思っていたんですが、一向に見つからない。これはヤバいと警察に捜索願を届け、家族は眠れぬ夜を過ごしました。そして翌朝、8km離れた隣の区の警察から、見つかったと電話があったんです。なんでも、知らないお婆さんと手を繋いで歩いているところを保護されたという。近所を歩いていたら、同じく徘徊していたお婆さんと出会い、デートのつもりで遠くまで行ってしまったらしい。これを境に、昼夜を問わず徘徊するようになりました」
施設にも入れない
吉田一家は、もう手におえないので、父親を施設に預けたいという。このように徘徊に悩み、施設に入れるケースが増加していると語るのは、千葉県の特別養護老人ホームの職員だ。
「徘徊癖のある入居者が増えたので、うちでは入居者の安全のためにも、両手をベッドに縛って拘束をするようになりました。人員が足りないので仕方ない。どこも人手不足ですから、徘徊をする入居者に限って拘束する施設は増えていくのではないでしょうか」
身動きが取れないよう体を縛りつけるのは、人間の尊厳にかかわる重い問題だ。だが、放っておけば命にかかわる事故に繋がる、という指摘もまた重い。
「認知症の人は、自分が病気と自覚していないことも多いので、平気で車を運転しようとするんです。認知症の診察を受けるため、車で来院した人もいました。『危ないから運転はやめて』といっても、大丈夫だと言って聞かない。しかし、徘徊と同じように、運転中に道が分からなくなったり、道路標識が分からなくなったりと、大変危険です。これから認知症高齢者による車の事故は、どんどん増えていくと考えられます」(前出・高瀬医師)
認知症による交通事故がもっとも心配だと語る高瀬医師だが、もう一つ懸念があるという。
「お金を払うことを忘れ、結果的に万引きをしてしまうという悲劇です。高齢者が多く収容されている刑務所には、認知症高齢者が多いと聞きます」
実際、万引きを取り締まっていぶセキュリティ会社の社員は、認知症高齢者の犯罪の増加に驚く。
「埼玉県内を中心に、約50店舗に万引きGメンを派遣していますが、月に80~90人捕まえる万引き犯のうち、およそ1割が認知症高齢者です。これまでは、万引きをした高齢者は自分は認知症だと嘘をついて言い逃れしようとするケースがほとんどだったのに、最近は本当に認知症患者なんです。万引きがきっかけで、認知症と診断された人もいました。こうした事案は今後増えるでしょう。深刻な問題であると弊社では捉えています」
「金銭感覚」や「社会性」を失っていき、さらに症状が進行すると「家族の顔」すら判断できない。その時、「家の中に知らない人がいる」と勘違いしたり、「いじめられている」と被害妄想が膨らんで家族を傷つけてしまうこともある。重度認知症をもつ68歳の義父を介護する佐々木文子さん(45歳・仮名)が、辛い出来事を明かす。
「同居している中学生の息子に、突然『泥棒! 俺の金を盗んだだろ!』と叫んで包丁を振り回したのです。止めようとした主人は腕を切られてしまいました。うちには小学生の娘もいるので、もう危険だからと施設に入れようと思いました」
ところが、すでに施設は満床で、少なくとも1年待ちだと言われたという。
「施設への入所が必要な認知症患者は約300万人いますが、高齢者住宅を含む収容施設の定員は150万人ほど。今も、施設でのケアが必要な認知症患者の2人にひとりがあぶれてしまっている。施設を増やそうと行政も取り組んでいますが、認知症高齢者が激増している今、施設不足は今後も解消されないでしょう」(介護に詳しい淑徳大学社会福祉学科・結城康博教授)
「老老介護」から「認認介護」へ
施設を利用できないと、その負担はもろに家族にのしかかる。身体的な負担もさることながら、金銭的な負担もバカにならない。50代の男性が、親の介護生活の現実を話す。
「同居していた母親が80歳になったころ、もの忘れの症状が出てきました。最初は買い物に行って、何を買うのか忘れてしまう程度だったので、私たち夫婦は二人とも仕事をしていました。ところがある日、家に帰ると母親がガスコンロの上に電気炊飯器を置いて火をつけていたのです。慌てて火を止めたら、母親は、『ご飯を炊こうと思ったのに火を消すなんて』と怒る。その時、認知症だと気がついたんです。危ないので、私は仕事を辞め、自宅で介護することにしました。
ところが、今度は妻の80歳の父親も認知症になってしまった。しかたなく妻も仕事を辞め、介護のために実家の北海道へ。夫婦別居の介護生活が始まり、今年で丸7年が経ちました。収入はゼロ。夫婦の退職金と親の年金をやりくりしていますが、生活に余裕はまったくありません……」
医療経済学者で、医療経済評価総合研究所所長の五十嵐中氏は、認知症患者の増加が引き起こす社会経済的負担をこう分析する。
「旧年の厚労省統計では、認知症患者一人当たりの年間医療費は、81万~152万円です。
しかも、認知症はゆっくり進行し、治ることもないので、医療費はズルズルとかかり続ける。その上、介護費用もあるので、たとえば進行が速く、比較的短期間で亡くなるがんなどの病気よりもトータルの金額が高くなることもある。先の夫婦のケースのように、介護のために仕事を辞める人も多く、医療費の負担が大きい一方で収入が減るという厳しい現実もあります」
ただし、息子や娘などが面倒を見てくれるならまだマシだ。これまでも高齢の夫婦同士で介護する「老老介護」が問題になっていたが、最近では介護する側も認知症という「認認介護」が増加してきている。
認認介護とは、どのような状況なのか。認認介護の夫婦の家の隣に住んでいた主婦が、その実情を語る。
「5年ほど70代の認知症の奥さんを介護していた旦那さんも、2年前に認知症になってしまった。お互いにご飯を食べたことも、食べさせたことも忘れてしまうため、夫が1日に何回も食事をさせ、奥さんは一時期かなり太っていました。去年の秋には柿を30個ぐらい買ってきて、皮ごと奥さんに一気に食べさせた。翌日、ひどい下痢になったようで、布団の上で全部漏らしていたんです。旦那さんは鼻がきかなくなっているのかまったく気に掛けず、異臭に気付いた私か駆けつけた時には、奥さんはウンチまみれ。その時は、私が一人で処理しました。
それからしばらくして、隣から一切物音がしなくなったんです。おかしいと思って警察を呼び、中に入ると、二人とも栄養失調になっているのを発見。慌てて入院させました。今度は、食べさせるのを忘れてしまっていたんです」
日本経済にもダメージが
認認介護の現場では、いつ何が起きても不思議ではない。たとえば今夏、記録的な猛暑の中で87歳の夫と78歳の妻が自宅で熱中症で倒れているのが発見され、介護していた側の妻が亡くなった。
また、'09年には富山県で、認知症の妻が認知症の夫を殺害する事件も発生。介護していた妻が、おむつを替えるのを嫌がる夫を叩き続けて殺してしまった。妻は、自分が何をやったかも、夫がなぜ死んだのかもわからないままだという。
在宅医療の第一人者・「川崎幸クリニック」院長の杉山孝博医師は、認認介護の現状を危惧する。
「夫婦ともに認知症になれば、介護どころか生活が成り立たなくなる。すでに、80歳以上の夫婦の11組に1組が認認介護の状況にあります。将来的に、認認介護は増え続けるでしょう。一人が亡くなった後、残ったほうの症状が劇的に重くなるケースも多いです」
また、アメリカで行われた研究では、高齢の夫婦で一方が認知症だと、もう一方も認知症となるケースが、そうでない場合より6倍多いという。「認知症が認知症を呼ぶ」-そうし
て、800万人もの認知症患者が街に溢れたら、この国はいったいどうなってしまうのだろうか……。
「70歳の男性の行方が分かりません。服装は緑のセーターに灰色のズボン。お心当たりがございましたら、××市役所までご連絡をお願いします」
すでに認知症高齢者が800万人を超えた20XX年の日本では、1時間に一回、街頭拡声器で高齢者の迷子放送が繰り返される。
交通渋滞は、日常茶飯事。認知症高齢者による交通事故が多発するからだ。事故を起こすほうも、事故に遭うほうも認知症高齢者が圧倒的に多い。
警察は、巡回する警官の人数を3倍に増員。徘徊、交通安全の取り締まり、そして頻発する高齢者による万引きに眼を光らせる。刑務所は、3分の2が65歳以上の入所者で占められ、まるで老人ホームのようだ。
施設は5年先まで満床。そのため、ただでさえ労働人口が減っているのに、在宅介護を余儀なくされた若者が仕事を辞めて世話をする。貧困家庭が増え、消費減少で日本経済にも深刻なダメージを与えている。
急増した認認介護の夫婦は、二人とも口座の暗証番号を忘れ、手元にお金はゼロ。近隣住民は、自分の親族の介護に手いっぱいで余所に目を向ける余裕はない。悲惨な最期を迎える高齢者夫婦は後を絶たないI。
このような地獄未来図は、やがて確実にやってくる。我々には何か、打つ手はあるのか。
「認知症は、完治は難しい。治療薬もありますが、治すというより、進行を遅くする薬です。これは、初期段階で使うか、ある程度進行してから使うかによって効き目が違う。初期であれば、進行を50%遅くできるというデータがあります。しかし、重くなっていれば、手遅れになる。認知症は、早期発見・治療がカギなのです」(認知症ケアに詳しい「お多福もの忘れクリニック」の本間昭医師)
決定的治療法のない病が、爆発的に増加する恐怖。それは、「長寿大国」の誉れを得た日本が対峙しなければならない、大きな試練なのかもしれない。
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
2013年12月21日
認知症800万人の時代に希望の光
認知症は、今のところ進行を遅らせる薬はあっても、治す方法はない。

週刊現代 12月16日号
老老介護の将来に待っている認認介護

ビートたけしのTVタックル 医療と介護の秘密スペシャル 2013年11月18日
高齢化の進展に伴い、75歳以上の高齢者について、慢性疾患による受療、疾患の罹患率、要介護等の高い者は増加しており、平均寿命と健康寿命の差を短縮することが課題となっている。
出典:厚生労働省平成22年都道府県別生命表の概況、平成25年版高齢社会白書
2013年12月11日
ロンドンG8サミットで認知症の共同声明

2025年までに治療法発見をめざす
2013年12月16日
内閣府の健康・医療戦略推進本部専門調査会


2020年までに治療の治験開始をめざす
水素によって認知症を予防できるか?
日本医科大学老人病研究所 教授 太田成男

3年前にアルツハイマー病型認知症の予防する方法が初めて開発されるかもしれないとの見通しがあった。
日本医科大学 街ぐるみ認知症相談センターNewsletter Vo.1(2010年12月)
http://www.nms.ac.jp/ig/soudan/pdf/Newsletter1012.pdf
2013年、認知症が改善した事例を発表
水素を含む機能性食品でヒトに対してのエビデンス
2013年6月 第28回 国際アルツハイマー病学会国際会議
2013年9月7日 第9回認知症サプリメント研究会(代表世話人 田平武先生)

佐賀女子短期大学 医学博士
長谷川亨教授
・アルツハイマー病研究の世界的な第一人者であるカリフォルニア大学のラフェーラ(Frank M. LaFerla)教授と、ホモシステイン酸の影響について共同研究
Treatment of Alzheimer's Disease with Anti-Homocysteic Acid Antibody in 3xTg-AD Male Mice
(PLoS ONE 2010年)
・認知症とホモシステイン酸の関連について、順天堂大学の田平武氏(元国立長寿医療センター研究所長・順天堂大学大学院医学研究科 認知症診断・予防・治療学講座教授)と共同研究
Urinary Homocysteic Acid Levels Correlate with Mini-Mental State Examination Scores in Alzheimer's Disease Patients
(Journal of Alzheimer's Disease 2012年)
【参考】
・水素水によるパーキンソン病の多施設共同臨床試験/順天堂大学病院
・水素水の飲用で脳の活性酸素が減少する/東邦大学
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

週刊現代 12月16日号
老老介護の将来に待っている認認介護

ビートたけしのTVタックル 医療と介護の秘密スペシャル 2013年11月18日
高齢化の進展に伴い、75歳以上の高齢者について、慢性疾患による受療、疾患の罹患率、要介護等の高い者は増加しており、平均寿命と健康寿命の差を短縮することが課題となっている。
出典:厚生労働省平成22年都道府県別生命表の概況、平成25年版高齢社会白書
2013年12月11日
ロンドンG8サミットで認知症の共同声明

2025年までに治療法発見をめざす
2013年12月16日
内閣府の健康・医療戦略推進本部専門調査会


2020年までに治療の治験開始をめざす
水素によって認知症を予防できるか?
日本医科大学老人病研究所 教授 太田成男

3年前にアルツハイマー病型認知症の予防する方法が初めて開発されるかもしれないとの見通しがあった。
日本医科大学 街ぐるみ認知症相談センターNewsletter Vo.1(2010年12月)
http://www.nms.ac.jp/ig/soudan/pdf/Newsletter1012.pdf
2013年、認知症が改善した事例を発表
水素を含む機能性食品でヒトに対してのエビデンス
2013年6月 第28回 国際アルツハイマー病学会国際会議
2013年9月7日 第9回認知症サプリメント研究会(代表世話人 田平武先生)

佐賀女子短期大学 医学博士
長谷川亨教授
・アルツハイマー病研究の世界的な第一人者であるカリフォルニア大学のラフェーラ(Frank M. LaFerla)教授と、ホモシステイン酸の影響について共同研究
Treatment of Alzheimer's Disease with Anti-Homocysteic Acid Antibody in 3xTg-AD Male Mice
(PLoS ONE 2010年)
・認知症とホモシステイン酸の関連について、順天堂大学の田平武氏(元国立長寿医療センター研究所長・順天堂大学大学院医学研究科 認知症診断・予防・治療学講座教授)と共同研究
Urinary Homocysteic Acid Levels Correlate with Mini-Mental State Examination Scores in Alzheimer's Disease Patients
(Journal of Alzheimer's Disease 2012年)
【参考】
・水素水によるパーキンソン病の多施設共同臨床試験/順天堂大学病院
・水素水の飲用で脳の活性酸素が減少する/東邦大学
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
2013年12月20日
温泉教授の健康ゼミナール
温泉教授の健康ゼミナール/松田忠徳(双葉社)

入浴の効果について、イシハラクリニック院長の石原結實先生(内科医)は、「入浴すると血栓を溶かすプラスミンという酵素が増えていることがわかっています。これによって心筋梗塞、脳梗塞といった血栓病の予防につながります」(春夏秋冬「体を温めて病気知らず!/三笠書房」)と述べています。
酸化還元電位とかミリボルト(mv)とか、科学的な用語が出てきましたが、これは温泉の”鮮度”を知る、まさに科学的な数値とその単位です。温泉は昔から「若返りの湯」などと呼ばれてきました。温泉に入ると肌がツルツル、しっとりとし、化粧のノリもよくなるといった経験は、多くの人が持っているでしょう。その理由は科学的に説明することが可能なのです。キーワードとなるのが”還元力”です。
浴槽に注がれた温泉がどのくらいの還元力を保っているか、逆にどれだけ酸化系になってしまっているかが分かれば、その温泉の”鮮度”を知ることができます。
ですから温泉浴は、日本人の生体防御反応、つまり健康力に大いに貢献してきたのです。「温熱作用による温泉気分=癒し=副交感神経優位->免疫細胞(リンパ球)強化」という図式が成り立ちます。

入浴の効果について、イシハラクリニック院長の石原結實先生(内科医)は、「入浴すると血栓を溶かすプラスミンという酵素が増えていることがわかっています。これによって心筋梗塞、脳梗塞といった血栓病の予防につながります」(春夏秋冬「体を温めて病気知らず!/三笠書房」)と述べています。
酸化還元電位とかミリボルト(mv)とか、科学的な用語が出てきましたが、これは温泉の”鮮度”を知る、まさに科学的な数値とその単位です。温泉は昔から「若返りの湯」などと呼ばれてきました。温泉に入ると肌がツルツル、しっとりとし、化粧のノリもよくなるといった経験は、多くの人が持っているでしょう。その理由は科学的に説明することが可能なのです。キーワードとなるのが”還元力”です。
浴槽に注がれた温泉がどのくらいの還元力を保っているか、逆にどれだけ酸化系になってしまっているかが分かれば、その温泉の”鮮度”を知ることができます。
ですから温泉浴は、日本人の生体防御反応、つまり健康力に大いに貢献してきたのです。「温熱作用による温泉気分=癒し=副交感神経優位->免疫細胞(リンパ球)強化」という図式が成り立ちます。
2013年12月18日
水素含有量日本一 石川県加賀市・山中温泉
中日スポーツ 2013年12月17日
水素含有量日本一
石川県加賀市・山中温泉

松尾芭蕉が愛した名湯、石川県加賀市の山中温泉は、水素の含有量が日本一で、老化防止に効能があるのが分かったという。
1300年の歴史誇る「菊の湯」
山中温泉観光協会によると、水素が多いと分かったのは昨春、金沢大学の廣瀬幸雄名誉教授の調査。温泉1リットル中の水素量604ppbあった。よく分からない数値だが水素量が多いとされる秋田県の玉川温泉の70ppb、鳥取県の三朝(みささ)温泉33ppbなどと比べるとずばぬけて高いという。水道水は0.02ppbだ。
水素は老化やガン、肥満など生活習慣病を引き起こす活性酸素を取り除く作用のあることが分かっている。温泉法で定義される温泉成分に水素量は該当しないが、入浴・飲用による効果が注目されている。
泉質はカルシウム・ナトリウム硫酸塩泉。女湯前の広場に無料の足湯、男湯の前には飲泉湯、温泉卵づくりもできる。備え付けのヒシャクで飲んだ。無味無臭。湯は24時間出っぱなし。手で触ると熱い(泉源48.2度)。
ペットボトルを手に湯を入れに来た年配の男性と雑談。年齢を聞くと78歳。肌にハリがあって白い。「毎日、くみに来てお茶やコーヒーにして飲んでる。家の風呂は入らず、毎日、菊の湯だ。おかげで風邪をひいたことがない」。料理人もくみに来た。釜飯に使うと言う。「ご飯が光るよ」
出会った人はお年寄りが多かった。でも皆、肌つやがよくて元気だった。市制情報を見ると、人口7万1540人中、80歳以上のお年寄りは6386人(10月1日現在)、最高齢は105歳。温泉の霊験あらたか、のようだ。
【関連記事】測定機械の故障かと思うほどの水素量、加賀市山中温泉
水素含有量日本一
石川県加賀市・山中温泉

松尾芭蕉が愛した名湯、石川県加賀市の山中温泉は、水素の含有量が日本一で、老化防止に効能があるのが分かったという。
1300年の歴史誇る「菊の湯」
山中温泉観光協会によると、水素が多いと分かったのは昨春、金沢大学の廣瀬幸雄名誉教授の調査。温泉1リットル中の水素量604ppbあった。よく分からない数値だが水素量が多いとされる秋田県の玉川温泉の70ppb、鳥取県の三朝(みささ)温泉33ppbなどと比べるとずばぬけて高いという。水道水は0.02ppbだ。
水素は老化やガン、肥満など生活習慣病を引き起こす活性酸素を取り除く作用のあることが分かっている。温泉法で定義される温泉成分に水素量は該当しないが、入浴・飲用による効果が注目されている。
泉質はカルシウム・ナトリウム硫酸塩泉。女湯前の広場に無料の足湯、男湯の前には飲泉湯、温泉卵づくりもできる。備え付けのヒシャクで飲んだ。無味無臭。湯は24時間出っぱなし。手で触ると熱い(泉源48.2度)。
ペットボトルを手に湯を入れに来た年配の男性と雑談。年齢を聞くと78歳。肌にハリがあって白い。「毎日、くみに来てお茶やコーヒーにして飲んでる。家の風呂は入らず、毎日、菊の湯だ。おかげで風邪をひいたことがない」。料理人もくみに来た。釜飯に使うと言う。「ご飯が光るよ」
出会った人はお年寄りが多かった。でも皆、肌つやがよくて元気だった。市制情報を見ると、人口7万1540人中、80歳以上のお年寄りは6386人(10月1日現在)、最高齢は105歳。温泉の霊験あらたか、のようだ。
【関連記事】測定機械の故障かと思うほどの水素量、加賀市山中温泉
2013年12月17日
健康・医療戦略 考え方まとめる
政府の健康・医療戦略推進本部の専門調査会は、認知症やうつ病などを根本的に治療する薬の開発に向けて、2020年ごろまでに人に投与して安全性を確かめる治験を始めるなどとした、健康・医療産業の振興についての基本的な考え方をまとめました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131217/k10013884191000.html
医療分野の研究開発に関する総合戦略(基本的考え方)
平成25年12月16日
1.基礎研究成果を実用化に繋ぐ体制の構築
医療の研究開発を持続的に進めるためには、基礎研究を強化し、画期的なシーズが常に産み出されることが必要である。基礎研究の成果を実用化に展開するためは、臨床研究・治験実施環境の抜本的な向上、及び我が国発の医薬品・医療機器の創出に向けたイノベーションの実現が鍵となる。
2.医薬品・医療機器開発の新たな仕組みの構築
国内に埋もれている有望なシーズをくみ上げるシステムを構築し、それを実用化に結び付けるため、最終的なビジネスとしての発展も視野に入れつつ、基礎から臨床研究、実用化までの一貫した研究開発の推進、さらに臨床現場における検証と新たな課題を抽出できる体制の整備が必要である。
3.エビデンスに基づく医療の実現に向けて
近年、エビデンスに基づく医療の重要性が増しているとともに、臨床研究・治験における国際競争力の強化に向けても、客観的データを活用した取組の必要性が増している
○疾患に対応した研究
関係省庁の有機的連携のもと、病態の解明に係る基礎研究から実用化に向けた研究まで一体的に推進する
【2015年度までの達成目標】
・精神・神経疾患については、
分子イメージングによる超早期認知症診断方法の確立
精神疾患の診断に関連するバイオマーカー候補の発見

【2020年頃までの達成目標】
・精神・神経疾患については、
日本発の認知症、うつ病等の精神疾患の根本治療薬候補の治験開始
精神疾患の客観的診断法の確立
脳全体の神経回路の構造と活動に関するマップの完成
【2020-30年頃までの達成目標】
・生活習慣病(糖尿病や脳卒中、心筋梗塞等)の劇的な改善
・発がん予測診断、抗がん剤等の医薬品副作用の予測診断の確立
・うつ、認知症の臨床研究の開始
・神経難病等の発症原因の解明
○革新的な医療技術創出拠点
文部科学省及び厚生労働省が一体となって新たな事業を創設することにより、両省の強みを生かしながら、アカデミア等における画期的な基礎研究成果を一貫して実用化に繋ぐ体制を構築するとともに、各開発段階のシーズについて国際水準の質の高い臨床研究・治験を実施・支援する体制の整備も行う
第5回 医療分野の研究開発に関する専門調査会の資料より

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131217/k10013884191000.html
医療分野の研究開発に関する総合戦略(基本的考え方)
平成25年12月16日
1.基礎研究成果を実用化に繋ぐ体制の構築
医療の研究開発を持続的に進めるためには、基礎研究を強化し、画期的なシーズが常に産み出されることが必要である。基礎研究の成果を実用化に展開するためは、臨床研究・治験実施環境の抜本的な向上、及び我が国発の医薬品・医療機器の創出に向けたイノベーションの実現が鍵となる。
2.医薬品・医療機器開発の新たな仕組みの構築
国内に埋もれている有望なシーズをくみ上げるシステムを構築し、それを実用化に結び付けるため、最終的なビジネスとしての発展も視野に入れつつ、基礎から臨床研究、実用化までの一貫した研究開発の推進、さらに臨床現場における検証と新たな課題を抽出できる体制の整備が必要である。
3.エビデンスに基づく医療の実現に向けて
近年、エビデンスに基づく医療の重要性が増しているとともに、臨床研究・治験における国際競争力の強化に向けても、客観的データを活用した取組の必要性が増している
○疾患に対応した研究
関係省庁の有機的連携のもと、病態の解明に係る基礎研究から実用化に向けた研究まで一体的に推進する
【2015年度までの達成目標】
・精神・神経疾患については、
分子イメージングによる超早期認知症診断方法の確立
精神疾患の診断に関連するバイオマーカー候補の発見

【2020年頃までの達成目標】
・精神・神経疾患については、
日本発の認知症、うつ病等の精神疾患の根本治療薬候補の治験開始
精神疾患の客観的診断法の確立
脳全体の神経回路の構造と活動に関するマップの完成
【2020-30年頃までの達成目標】
・生活習慣病(糖尿病や脳卒中、心筋梗塞等)の劇的な改善
・発がん予測診断、抗がん剤等の医薬品副作用の予測診断の確立
・うつ、認知症の臨床研究の開始
・神経難病等の発症原因の解明
○革新的な医療技術創出拠点
文部科学省及び厚生労働省が一体となって新たな事業を創設することにより、両省の強みを生かしながら、アカデミア等における画期的な基礎研究成果を一貫して実用化に繋ぐ体制を構築するとともに、各開発段階のシーズについて国際水準の質の高い臨床研究・治験を実施・支援する体制の整備も行う
第5回 医療分野の研究開発に関する専門調査会の資料より
2013年12月12日
ロンドンでG8認知症サミット共同声明発表
世界で患者が急増すると予測されている認知症についてG8各国が話し合う初めての「認知症サミット」が12月11日にロンドンで開催され、共同声明を発表しました。

認知症は、世界で患者の治療や介護などにかかる費用が年間60兆円を超えており、途上国などでは経済的にも大きな課題です。

共同声明では、G8各国が研究費を大幅に増額するとしています。また、研究を加速するために、各国政府の公的支援を受けた研究のデータをできるかぎり開示することも盛り込まれました。この中で「2025年までに治療法を見つけ出すことを目指して」との目標が掲げられました。

認知症に関する国際会議を、2014年に日本などで開いたうえで、2015年2月にはアメリカで2回目の「認知症サミット」を開催します。
■認知症サミット開催の背景
「認知症サミット」はイギリス政府がことし8月に開催を発表したもので、認知症について集中的に話し合うサミットは初めてです。
開催の背景には、高齢化に伴って認知症の人が急速に増えている現状があります。

イギリス政府によりますと、現在、認知症の人はイギリス国内におよそ80万人いて、治療や介護にかかる費用は年間230億ポンド(日本円にしておよそ3兆9000億円)に上っています。
そして2040年までには人数が倍に増え、対策にかかる費用も3倍になると予測しています。
このため、イギリス政府は抜本的な対策が必要だとして、2009年に「認知症国家戦略」を策定し、早期診断の徹底や、認知症の人や家族への支援体制の充実、認知症に対する理解促進などの取り組みを進めてきました。
さらにキャメロン政権は去年、認知症への対策を国の重要課題に位置づけ、新薬の研究開発などに5200万ポンドを拠出すると表明しました。
イギリス政府は、増え続ける認知症の人に、より迅速に対応するためには各国政府が連携し、企業や研究者、医療機関の協力体制を作ることが必要だとしてサミットの開催を決めました。
サミット開幕を前にキャメロン首相は、「認知症を克服するためには、ガンやエイズと同じように世界の重要課題だと認識し、各国、産業界、科学者たちが協力していかなければならない。今回の会議で、現状を打開するための方策を打ち出せることを期待している」と述べました。
■アルツハイマー病治療薬の開発
アルツハイマー病を巡っては、これまでに症状の進行を遅らせる薬は開発されていますが、治療薬や予防薬は依然、開発の途上にあります。
アルツハイマー病の発症は、「βアミロイド」という特殊なたんぱく質が脳にたまることが原因の1つだと指摘されています。
このためβアミロイドが脳に蓄積するのを防ぐ薬の開発が進められ、このうちアメリカの製薬会社が開発していた薬が関係者の期待を集めていましたが、去年8月、臨床試験の最終段階で患者の症状に改善が見られず、いったん開発は中断されました。
その後アメリカでは、症状が現れる前に予防的な治療を始める必要があるという認識が広がり、新たな取り組みが進められています。
アメリカのボストンにある病院が中心になって進めているプロジェクトでは、βアミロイドが脳にたまり始めていても症状が現れていない高齢者に、蓄積を防ぐ薬を投与して効果を調べる臨床試験が近く始まる予定です。
またアリゾナ州にある研究機関では、遺伝的にアルツハイマー病になるリスクが高い人たちを対象にした臨床試験が計画されています。
このうち南米のコロンビアでは、40代になるとアルツハイマー病を発症する特異な遺伝子をもつ住民が集まる村があるということで、この住民300人への臨床試験も行われる予定です。
今回の認知症サミットでは、こうした最新の研究についても報告され、研究開発の分野でのさらなる国際協力の必要性が議論されることになっています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131211/k10013757761000.html
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

認知症は、世界で患者の治療や介護などにかかる費用が年間60兆円を超えており、途上国などでは経済的にも大きな課題です。

共同声明では、G8各国が研究費を大幅に増額するとしています。また、研究を加速するために、各国政府の公的支援を受けた研究のデータをできるかぎり開示することも盛り込まれました。この中で「2025年までに治療法を見つけ出すことを目指して」との目標が掲げられました。

認知症に関する国際会議を、2014年に日本などで開いたうえで、2015年2月にはアメリカで2回目の「認知症サミット」を開催します。
■認知症サミット開催の背景
「認知症サミット」はイギリス政府がことし8月に開催を発表したもので、認知症について集中的に話し合うサミットは初めてです。
開催の背景には、高齢化に伴って認知症の人が急速に増えている現状があります。

イギリス政府によりますと、現在、認知症の人はイギリス国内におよそ80万人いて、治療や介護にかかる費用は年間230億ポンド(日本円にしておよそ3兆9000億円)に上っています。
そして2040年までには人数が倍に増え、対策にかかる費用も3倍になると予測しています。
このため、イギリス政府は抜本的な対策が必要だとして、2009年に「認知症国家戦略」を策定し、早期診断の徹底や、認知症の人や家族への支援体制の充実、認知症に対する理解促進などの取り組みを進めてきました。
さらにキャメロン政権は去年、認知症への対策を国の重要課題に位置づけ、新薬の研究開発などに5200万ポンドを拠出すると表明しました。
イギリス政府は、増え続ける認知症の人に、より迅速に対応するためには各国政府が連携し、企業や研究者、医療機関の協力体制を作ることが必要だとしてサミットの開催を決めました。
サミット開幕を前にキャメロン首相は、「認知症を克服するためには、ガンやエイズと同じように世界の重要課題だと認識し、各国、産業界、科学者たちが協力していかなければならない。今回の会議で、現状を打開するための方策を打ち出せることを期待している」と述べました。
■アルツハイマー病治療薬の開発
アルツハイマー病を巡っては、これまでに症状の進行を遅らせる薬は開発されていますが、治療薬や予防薬は依然、開発の途上にあります。
アルツハイマー病の発症は、「βアミロイド」という特殊なたんぱく質が脳にたまることが原因の1つだと指摘されています。
このためβアミロイドが脳に蓄積するのを防ぐ薬の開発が進められ、このうちアメリカの製薬会社が開発していた薬が関係者の期待を集めていましたが、去年8月、臨床試験の最終段階で患者の症状に改善が見られず、いったん開発は中断されました。
その後アメリカでは、症状が現れる前に予防的な治療を始める必要があるという認識が広がり、新たな取り組みが進められています。
アメリカのボストンにある病院が中心になって進めているプロジェクトでは、βアミロイドが脳にたまり始めていても症状が現れていない高齢者に、蓄積を防ぐ薬を投与して効果を調べる臨床試験が近く始まる予定です。
またアリゾナ州にある研究機関では、遺伝的にアルツハイマー病になるリスクが高い人たちを対象にした臨床試験が計画されています。
このうち南米のコロンビアでは、40代になるとアルツハイマー病を発症する特異な遺伝子をもつ住民が集まる村があるということで、この住民300人への臨床試験も行われる予定です。
今回の認知症サミットでは、こうした最新の研究についても報告され、研究開発の分野でのさらなる国際協力の必要性が議論されることになっています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131211/k10013757761000.html
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
2013年12月05日
イスラム圏のハラール認証コスメについて
12月5日、日本アセアンセンターで「イスラム圏のハラール認証コスメについて」セミナーが開催されました。
日本への観光客が増加する中、特に東南アジアからの旅行者が急増しています。
| 日本政府観光局(JNTO)によると、タイとマレーシアからの訪日客数は1~4月に計18万7000人と前年同期比で約4割増えた。所得水準の向上に伴い、海外旅行者が急増している。政府は13年に東南アジア全体からの訪日客を100万人に増やす方針で、ビザ緩和で取り込みを加速する。日本経済新聞 2013/6/11 日本政府観光局の発表によると、7月の訪日外国人は前年同月から約18.4%増加。統計をとり始めてから初めて月間100万人を超えた。中でもタイが84.7%増、ベトナム59.4%増、マレーシア25.2%増と、東南アジア各国の増加が際立つ。朝日新聞(神奈川版)2013年09月11日 とくに最近増えているインドネシアやマレーシアなどのイスラム教徒の受け入れ体制はまだ不十分です。イスラム教徒は豚やアルコールを口にしないだけでなく、原材料や調理の仕方にも制限があります。たとえば肉は、お祈りをしたあと苦しまないように一気に処理し血を抜きます。そうした基準を満たしたものを「ハラル」と言います。 NHKくらし☆解説「東南アジアからの観光客をもてなすには」2013年07月05日 |
このように東南アジアで中間所得者層の増加を背景に、日本への観光客が増え、特にイスラム圏からの増加傾向が続くと予想されます。ハラール認証が必要なのは食品のみだけでなく、化粧品等も取得しなければなりません。セミナーで川久保文佳氏(ビーモア株式会社 代表取締役 )は、化粧品・ボディケア商品のハラール認証について、マレーシアをはじめとしたイスラム圏でのハラール認証の現状を解説しました。
また、日本ハラール認証の窓口である、日本ムスリム協会理事で拓殖大学イスラーム研究センター室 客員教授の遠藤利夫先生がハラール認証の解説をしました。
2020年に東京でオリンピックが開催されることが決定し、今後も世界各国から多くの観光客が日本を訪問することが予想されます。川久保氏は「受入れる日本のホテルなどでは、ハラール認証の化粧品などを用意しておくことで、イスラム圏からのお客様に安心してご利用いただけます。それが、日本のおもてなしの一つになります」と話しました。
写真は、マレーシアのハラール認証コスメ『タナメラ』の製品
2013年11月30日
水素でダイエット、代謝アップのホルモン増加
ブル中野が100kgからマイナス37.5kgへ!
水素は脂肪代謝をあげます。
TBS「あの日に帰りたい特別編」9月25日19:00-21:00
http://www.youtube.com/watch?v=TePI0V2wvkk
Molecular hydrogen improves obesity and diabetes by inducing hepatic FGF21 and stimulating energy metabolism in db/db mice.
Kamimura N, Nishimaki K, Ohsawa I, Ohta S. Obesity (Silver Spring). 2011 Jul;19(7):1396-403.
水素水を飲むと肝臓から放出されるホルモンFGF21が増えることがわかりました。FGF21は、脂肪燃焼をはじめとするエネルギー代謝を活発にするホルモンです。
つまり、水素を摂取すると肝臓ホルモンFGF21が放出され、脂肪燃焼効果が上昇するので、体脂肪が増えず、脂肪肝にもならず、中性脂肪も増えすぎず、血糖値もあがらなかったのです。予備的研究ですが、水素はもちろん(マウスと同じように)、人間にも効果があります。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21293445/
水素は脂肪代謝をあげます。
TBS「あの日に帰りたい特別編」9月25日19:00-21:00
http://www.youtube.com/watch?v=TePI0V2wvkk
Molecular hydrogen improves obesity and diabetes by inducing hepatic FGF21 and stimulating energy metabolism in db/db mice.
Kamimura N, Nishimaki K, Ohsawa I, Ohta S. Obesity (Silver Spring). 2011 Jul;19(7):1396-403.
水素水を飲むと肝臓から放出されるホルモンFGF21が増えることがわかりました。FGF21は、脂肪燃焼をはじめとするエネルギー代謝を活発にするホルモンです。
つまり、水素を摂取すると肝臓ホルモンFGF21が放出され、脂肪燃焼効果が上昇するので、体脂肪が増えず、脂肪肝にもならず、中性脂肪も増えすぎず、血糖値もあがらなかったのです。予備的研究ですが、水素はもちろん(マウスと同じように)、人間にも効果があります。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21293445/
2013年11月24日
水素水とサビない身体: 悪玉活性酸素は消せるのか
水素水とサビない身体: 悪玉活性酸素は消せるのか
小学館 著者:太田成男
1,260円(税込)
2013年11月25日発売

水素水が万病に効く理由。第一人者初解説本
2007年、日本医大・太田成男教授がアメリカの医学誌に論文を発表し、世界の耳目を集めた水素水の健康効果。その後、各大学で臨床実験が進められ、昨年までに世界中で250もの水素関連の論文が発表された。体内に入る悪玉活性酸素を水素水が除去する(体に付いたサビを落とす、水として体外に流し出す)力が徐々に明らかになり、日本では2013年に入り、多くのメディアが水素水を取り上げ、副作用のない老若男女への水素水商品が一躍ブームに。二日酔い、シミシワなど肌の諸症状、歯周病、リウマチ、アレルギー、認知症、パーキンソン病、脳梗塞、心筋梗塞、不妊、そして癌……。万病に効くとされるそのメカニズム、最新データ、ビジネスの現状(優良商品の見分け方)、将来性など、水素水のAtoZを太田教授自身が初めて明らかにする。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4093883386/
小学館 著者:太田成男
1,260円(税込)
2013年11月25日発売

水素水が万病に効く理由。第一人者初解説本
2007年、日本医大・太田成男教授がアメリカの医学誌に論文を発表し、世界の耳目を集めた水素水の健康効果。その後、各大学で臨床実験が進められ、昨年までに世界中で250もの水素関連の論文が発表された。体内に入る悪玉活性酸素を水素水が除去する(体に付いたサビを落とす、水として体外に流し出す)力が徐々に明らかになり、日本では2013年に入り、多くのメディアが水素水を取り上げ、副作用のない老若男女への水素水商品が一躍ブームに。二日酔い、シミシワなど肌の諸症状、歯周病、リウマチ、アレルギー、認知症、パーキンソン病、脳梗塞、心筋梗塞、不妊、そして癌……。万病に効くとされるそのメカニズム、最新データ、ビジネスの現状(優良商品の見分け方)、将来性など、水素水のAtoZを太田教授自身が初めて明らかにする。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4093883386/
2013年11月19日
ミドル男性特有の体臭と原因、加齢臭とは別
ミドル男性特有の体臭と原因、マンダムが発見 加齢臭とは別 抑制する化粧品など発売へ
2013.11.18 18:22
マンダムは18日、世界で初めて30~40歳代の「ミドル男性」特有の体臭の原因物質を解明し、その発生を抑える成分を発見したと発表した。ミドル男性に多い不快な体臭は、加齢臭とは別の原因物質が作用すると特定し、同物質の働きを抑制する成分を見つけた。2014年2月には抑制成分を配合した男性用化粧品などを商品化する。
同社は男性の多くが「30~40歳代に体臭の変化を感じる」という調査結果から、50歳代以降に顕在化する加齢臭の原因物質「ノネナール」とは別の成分が働いていると予測。各年代の男性の体臭を調査したところ、ミドル男性の頭部から20歳代に比べ強い脂臭を発していることを突き止めた。その臭い成分を解析した結果、汗中の乳酸の酸化などで発生する悪臭成分「ジアセチル」が原因と特定した。
さらに、臭気成分の抑制が期待される102種類の植物エキスを調べると、フラボノイドを含むカンゾウやケイヒなどが、乳酸の変質を抑制する高い効果があることを見つけた。西村元延社長は「体臭が気になるミドル男性は増えており、これに対応する商品は男性化粧品市場の活性化につながる」と強調する。
まず来年2月24日には、ジアセチルの抑制成分を配合した薬用シャンプーやボディウオッシュなど4つの製品(840~1522円)の発売を予定しており、その後も制汗剤など商品群を拡大する方針だ。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131118/biz13111818230018-n1.htm

マンダム宣伝販促部 吉田隆史さん
「臭いに悩んでいるミドル男性は、考えている以上に多い。
女性も期がついている市場で、かなり期待できる」
五味クリニック 五味常明院長
「男女を問わず年齢を問わず臭いで悩む人が相談に来る。
自分のニオイが人に迷惑をかける、人から嫌われる(スメルハラスメント)
人間関係の中で悩んでいる」
ワールドビジネスサテライト(TV東京 2013年11月19日放送)
2013.11.18 18:22
マンダムは18日、世界で初めて30~40歳代の「ミドル男性」特有の体臭の原因物質を解明し、その発生を抑える成分を発見したと発表した。ミドル男性に多い不快な体臭は、加齢臭とは別の原因物質が作用すると特定し、同物質の働きを抑制する成分を見つけた。2014年2月には抑制成分を配合した男性用化粧品などを商品化する。
同社は男性の多くが「30~40歳代に体臭の変化を感じる」という調査結果から、50歳代以降に顕在化する加齢臭の原因物質「ノネナール」とは別の成分が働いていると予測。各年代の男性の体臭を調査したところ、ミドル男性の頭部から20歳代に比べ強い脂臭を発していることを突き止めた。その臭い成分を解析した結果、汗中の乳酸の酸化などで発生する悪臭成分「ジアセチル」が原因と特定した。
さらに、臭気成分の抑制が期待される102種類の植物エキスを調べると、フラボノイドを含むカンゾウやケイヒなどが、乳酸の変質を抑制する高い効果があることを見つけた。西村元延社長は「体臭が気になるミドル男性は増えており、これに対応する商品は男性化粧品市場の活性化につながる」と強調する。
まず来年2月24日には、ジアセチルの抑制成分を配合した薬用シャンプーやボディウオッシュなど4つの製品(840~1522円)の発売を予定しており、その後も制汗剤など商品群を拡大する方針だ。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131118/biz13111818230018-n1.htm

マンダム宣伝販促部 吉田隆史さん
「臭いに悩んでいるミドル男性は、考えている以上に多い。
女性も期がついている市場で、かなり期待できる」
五味クリニック 五味常明院長
「男女を問わず年齢を問わず臭いで悩む人が相談に来る。
自分のニオイが人に迷惑をかける、人から嫌われる(スメルハラスメント)
人間関係の中で悩んでいる」
ワールドビジネスサテライト(TV東京 2013年11月19日放送)
2013年11月17日
スイソ スリムで無理なく健やかに、水素で始まる理想のカラダヘ。
2013年11月17日、アッチェは、代謝促進をサポートする水素のすぐれた特性を活かし、体内リズムに着目した新発想ダイエット水素サプリメント「スイソ スリム」を発売しました。

※デイ(写真左)とナイト(写真右)の2袋で1セットとなります。
「体内リズム」という、誰もが持つバイオリズムを活用し、日中の活動時に働きかける燃焼系成分をスイソスリム・デイに、睡眠中の休養・リセット時に働きかけるスッキリ系成分をスイソスリム・ナイトに配合。

異なる成分のサプリメントを昼と夜に飲むことで1日を通じて好循環を生み出し、より健やかに、よりナチュラルにスマートな体型へと導きます。
スイソ スリムで無理なく健やかに、水素で始まる理想のカラダヘ。
スイソスリム(デイ・ナイト)
会員価格:16,800円(税込)一般価格:18,800円(税込)/ 形状:カプセルタイプ
容量:180カプセル(デイ90、ナイト90)/ 目安量:1日6カプセル(デイ3、ナイト3)

スイソスリム(デイ)
会員価格:9,000円(税込)一般価格:10,000円(税込)/内容量:37.8g(420mgx90カプセル)
原材料名:サンゴカルシウム、L-カルニチンL-酒石酸塩、穀物発酵エキス末(穀物発酵エキス、マルトデキストリン)、α-リポ酸、コエンザイムQ10、黒胡楸抽出物、結晶セルロース、HPMC、ステアリン酸カルシウム、着色料(紅花黄、クチナシ)
スイソスリム(ナイト)
会員価格:9,000円(税込)一般価格:10,000円(税込)/内容量:36.9g(410mgx90カプセル)
原材料名:サンゴカルシウム、植物性乳酸菌発酵物(大豆ペプチド発酵物、デキストリン、乳酸菌(殺菌))、穀物発酵エキス末(穀物発酵エキス、マルトデキストリン)、有胞子性乳酸菌末、HPMC、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、カラメル色素

①水素パウダーの更なる研究
ひと口に水素パウダーの性能と言っても、その評価の仕方には一定の基準がありませんでした。
例えば、水に溶けた個体のカプセルから発生する水素を計測するにしても、さまざまな方法があり、業界で統一された基準が定められていません。
論文発表に耐えうるレペルを実現するためのファーストステップとして、2013年度からは長岡技術科学大学に第三者専門機関として物性解明の研究を委託し、より高品質で性能の高い水素パウダーの開発に取り組み始めました。水素担持カルシウムの物性を解明するために、X線による構造解析、赤外分光光度計で原子と原子のつながりを科学的に解明していきます。
②医療分野での応用
水素は、抗酸化作用によるアンチエージングや生活習慣病予防といった医療分野における研究が進み、ますます注目を浴びています。
さらに、ゲノムレペルでの水素の可能性を追求します。
専門的には「がんmRNA発現解析検査」で、血液中にある異常を起こした遺伝子の発現量を調べることによって、がんが発生するリスクを確認できる検査なのですが、このテストの結果、がん予防という観点から見ると、水素が有効である可能性が高いことがわかってきています。健常者8名に水素ピュアゴールドを一カ月食べてもらい、がんリスクを4段階に分類した変化を見ました。その結果、リスク中が7名・リスク低1名が、一カ月後にリスク中2名・リスク低6名へと変化しました。
まだ研究段階なので「水素でがんが治る」とは言えませんし、そういった報告もなされていませんが、がんになりにくい体質作りに役立っている可能性が明らかだと言えるでしょう。
③二日酔いなど身近なことへの応用
お酒を飲み過ぎたときや二日酔いのときに、ウコンやヘパリーゼ等の入った飲料を摂るという方も多いと思いますが、一部ユーザーの方から「水素にも同じような効能がある」という声が届き、それではモノは試しにと、実際に実験してみたところ、これが単なる体感ではなく、アルコールの代謝がよくなっているという結果を得ることができました。27-44歳の男女7名が、水素サプリメントを食べることで具体的にアルコールを飲んだときに体内で作られる中間代謝物質アセトアルデヒドの量が、水素を摂った時に減少することがわかりました。
医学分野では糖尿病や認知症といった分野で、マウスや人体レベルで専門家による水素を使った臨床実験が始まっていますが、私たちアッチェはそういった実験の結果や成果をにらみつつ、ゲノムに代表される最新の医療技術による実証的研究から、二日酔いへの応用など、ごく身近なことにも研究開発の目を向けていきます。
④ユーザーの声を製品に反映
アッチェが昨年から行ってきたユーザー体感アンケートに、会員の皆様約800名の回答をいただきました。その結果を、統合医療推進機構理事長の久保明ドクターに分析していただいたところ、非常に興味深いことがわかってきました。
従来、水素は抗酸化という機能に焦点が当てられてきたわけですが、実際の体感ベースで見ると代謝と免疫力の向上にも貢献している事実が浮き彫りになってきたのです。
中でも私たちが着目したのはその代謝機能でした。ユーザーである皆様の声をしっかりと分析しながら、製品作りにフィードバックさせ、着実に進化させていく。
その思いは、予想したよりも早く、今回の新製品開発に反映させることができました。
代謝機能に優れた水素と活性型酵素を結合させることで、理想の体作りを目指すためのダイエットに役立つ製品ができるのではないか-。
そのアイデアを元に研究を重ねた結果、ついに私たちはまったく新しいコンセプトの製品の開発に成功しました。
新製品を世に送り出す過程でも会員の皆様の協力を得ようとしてまいりました。新製品の効果を検証するモニター参加型のテストプログラムでは、一カ月で体重が1kg以上減少した人が59%、三カ月で体重が1kg以上減少した人が82.6%と、はっきりした変化が見られました。

その他、効果的なマーケティング手法やプロモーション企画を、全国の代表リーダーと討議を重ねました。
株式会社アッチェ
ACCHE Corporation
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-16-16 虎ノ門1丁目MGビル10階
TEL : 03-3539-3099
FAX : 03-3539-3131

※デイ(写真左)とナイト(写真右)の2袋で1セットとなります。
「体内リズム」という、誰もが持つバイオリズムを活用し、日中の活動時に働きかける燃焼系成分をスイソスリム・デイに、睡眠中の休養・リセット時に働きかけるスッキリ系成分をスイソスリム・ナイトに配合。

異なる成分のサプリメントを昼と夜に飲むことで1日を通じて好循環を生み出し、より健やかに、よりナチュラルにスマートな体型へと導きます。
スイソ スリムで無理なく健やかに、水素で始まる理想のカラダヘ。
スイソスリム(デイ・ナイト)
会員価格:16,800円(税込)一般価格:18,800円(税込)/ 形状:カプセルタイプ
容量:180カプセル(デイ90、ナイト90)/ 目安量:1日6カプセル(デイ3、ナイト3)

スイソスリム(デイ)
会員価格:9,000円(税込)一般価格:10,000円(税込)/内容量:37.8g(420mgx90カプセル)
原材料名:サンゴカルシウム、L-カルニチンL-酒石酸塩、穀物発酵エキス末(穀物発酵エキス、マルトデキストリン)、α-リポ酸、コエンザイムQ10、黒胡楸抽出物、結晶セルロース、HPMC、ステアリン酸カルシウム、着色料(紅花黄、クチナシ)
スイソスリム(ナイト)
会員価格:9,000円(税込)一般価格:10,000円(税込)/内容量:36.9g(410mgx90カプセル)
原材料名:サンゴカルシウム、植物性乳酸菌発酵物(大豆ペプチド発酵物、デキストリン、乳酸菌(殺菌))、穀物発酵エキス末(穀物発酵エキス、マルトデキストリン)、有胞子性乳酸菌末、HPMC、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、カラメル色素

①水素パウダーの更なる研究
ひと口に水素パウダーの性能と言っても、その評価の仕方には一定の基準がありませんでした。
例えば、水に溶けた個体のカプセルから発生する水素を計測するにしても、さまざまな方法があり、業界で統一された基準が定められていません。
論文発表に耐えうるレペルを実現するためのファーストステップとして、2013年度からは長岡技術科学大学に第三者専門機関として物性解明の研究を委託し、より高品質で性能の高い水素パウダーの開発に取り組み始めました。水素担持カルシウムの物性を解明するために、X線による構造解析、赤外分光光度計で原子と原子のつながりを科学的に解明していきます。
②医療分野での応用
水素は、抗酸化作用によるアンチエージングや生活習慣病予防といった医療分野における研究が進み、ますます注目を浴びています。
さらに、ゲノムレペルでの水素の可能性を追求します。
専門的には「がんmRNA発現解析検査」で、血液中にある異常を起こした遺伝子の発現量を調べることによって、がんが発生するリスクを確認できる検査なのですが、このテストの結果、がん予防という観点から見ると、水素が有効である可能性が高いことがわかってきています。健常者8名に水素ピュアゴールドを一カ月食べてもらい、がんリスクを4段階に分類した変化を見ました。その結果、リスク中が7名・リスク低1名が、一カ月後にリスク中2名・リスク低6名へと変化しました。
まだ研究段階なので「水素でがんが治る」とは言えませんし、そういった報告もなされていませんが、がんになりにくい体質作りに役立っている可能性が明らかだと言えるでしょう。
③二日酔いなど身近なことへの応用
お酒を飲み過ぎたときや二日酔いのときに、ウコンやヘパリーゼ等の入った飲料を摂るという方も多いと思いますが、一部ユーザーの方から「水素にも同じような効能がある」という声が届き、それではモノは試しにと、実際に実験してみたところ、これが単なる体感ではなく、アルコールの代謝がよくなっているという結果を得ることができました。27-44歳の男女7名が、水素サプリメントを食べることで具体的にアルコールを飲んだときに体内で作られる中間代謝物質アセトアルデヒドの量が、水素を摂った時に減少することがわかりました。
医学分野では糖尿病や認知症といった分野で、マウスや人体レベルで専門家による水素を使った臨床実験が始まっていますが、私たちアッチェはそういった実験の結果や成果をにらみつつ、ゲノムに代表される最新の医療技術による実証的研究から、二日酔いへの応用など、ごく身近なことにも研究開発の目を向けていきます。
④ユーザーの声を製品に反映
アッチェが昨年から行ってきたユーザー体感アンケートに、会員の皆様約800名の回答をいただきました。その結果を、統合医療推進機構理事長の久保明ドクターに分析していただいたところ、非常に興味深いことがわかってきました。
従来、水素は抗酸化という機能に焦点が当てられてきたわけですが、実際の体感ベースで見ると代謝と免疫力の向上にも貢献している事実が浮き彫りになってきたのです。
中でも私たちが着目したのはその代謝機能でした。ユーザーである皆様の声をしっかりと分析しながら、製品作りにフィードバックさせ、着実に進化させていく。
その思いは、予想したよりも早く、今回の新製品開発に反映させることができました。
代謝機能に優れた水素と活性型酵素を結合させることで、理想の体作りを目指すためのダイエットに役立つ製品ができるのではないか-。
そのアイデアを元に研究を重ねた結果、ついに私たちはまったく新しいコンセプトの製品の開発に成功しました。
新製品を世に送り出す過程でも会員の皆様の協力を得ようとしてまいりました。新製品の効果を検証するモニター参加型のテストプログラムでは、一カ月で体重が1kg以上減少した人が59%、三カ月で体重が1kg以上減少した人が82.6%と、はっきりした変化が見られました。

その他、効果的なマーケティング手法やプロモーション企画を、全国の代表リーダーと討議を重ねました。
株式会社アッチェ
ACCHE Corporation
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-16-16 虎ノ門1丁目MGビル10階
TEL : 03-3539-3099
FAX : 03-3539-3131
2013年11月16日
大腸発生水素による酸化ストレス軽減と生活習慣病予防の可能性
■大腸発生水素による酸化ストレス軽減と生活習慣病予防の可能性
名寄市立大学 保健福祉学部栄養学科・教授 西村直道
はじめに
食物繊維は、コレステロール正常化作用(低下作用)、血糖値上昇抑制作用、便通改善作用、大腸がん発症抑制作用などさまざまな生理作用を有することが報告され、現在でもこれらの作用に関連する研究ならびに開発が行われている。しかし、食物繊維の生理作用は本当にこれまでに報告されているものだけであろうか。数多くの研究がなされ、これまでの既存の考え方では合理的に説明できないような現象も多々見受けられる。同じような経験をしている人は結構多いはずである。にもかかわらず、新たな考え方や可能性を示すことができなかったのは、私を含め食物繊維の研究を行っている研究者の怠慢であったかもしれない。今回ここでは我々が最近4年間で力を注ぎ、たどり着いた新しい食物繊維の機能を解説したい。
食物繊維は大腸に常在する多数の細菌によって発酵分解を受ける。このとき多くの発酵産物が生成され、その中には大腸上皮細胞の主要なエネルギ一源となり、大腸がん発症の抑制因子としても働く酪酸も存在する。酪酸のほかにも酢酸やプロピオン酸など短鎖脂肪酸が比較的多量に生成される。これらに生理作用が認められるため、食物繊維の生理作用に関する研究もこれらの成分に焦点を当てたものが多く見られる。発酵産物としてガス成分も多量に生成されるにもかかわらず、こちらの研究がおろそかになっていたのは否めない。我々が研究の焦点としている水素(H2)も同様であった。H2は極性がなく反応性に富んでいないことから、大腸で発生したH2は生体に何ら作用を及ぼすことのない物質として捉えていたのである。無機化学においてH2分子が白金やパラジウムのような触媒存在下で還元性を示すことは古くから知られていた。生体内でも同様にH2が還元性を示す可能性はあったわけであるが、先に示したような触媒が存在しない生体内で有力なエビデンスを示した研究は長い間なかった。
H2分子による生体内抗酸化と大腸発生H2の可能性
2007年にOsawaらは、脳虚血-再灌流(IR)処置によって酸化ストレスを与えたラットにH2ガスを吸入させることによって、生成されたヒドロキシラジカルが特異的に捕捉され、酸化障害が軽減されることを見出した。この研究は、生体内でH2が還元性を示すことを初めて明らかにしたものであり、その後も、さまざまな酸化ストレスに対しH2分子が抗酸化作用を示すことが報告されている。一方、食物繊維をはじめとする難消化性糖質は、大腸内発酵によるH2生成を促し、そのH2は呼気および放屁に排泄されることが知られている。我々は、このH2も同じように生体内で抗酸化作用を発揮する可能性をひらめいた。大腸内発酵を利用してH2を生体内に供給できれば、安定的かつ持続的に生体内還元性を維持できると期待される。生体内における不必要な酸化反応を防御することで、酸化障害を発端とする生活習慣病の発症や進展を抑えることが可能であろう。
我々は、Savaianoらの報告にもとづいて、ラクトース(20g)摂取後のヒト呼気中H2濃度の変動から、ヒト門脈血中の平均的H2濃度を推定した。一般的な生理学的データより換気量に約500mL/分、呼吸数に16~18回/分を用いて、8時間で呼気中に排出されるH2量の推算を行った。その結果、20gのラクトース摂取で96~108mL/8hのH2が排泄されることがわかった。さらに、拍出量に約5L/分を用い、門脈血流量を消化管に流入する血流量(全血流量の約28%)と同じとして算出した。この結果、門脈血中の平均H2濃度は6.4~7.2μMであると推定できた。このH2濃度は、我々のラットによる実験結果(後述)ともほぼ一致しており、この濃度で酸化ストレスが軽減されることを確認している。また、これまでに酸化ストレスの軽減を示したH2ガスやH2水による研究でも、同程度の血中H2濃度が報告されている。したがって、大腸でH2生成を促進する基質を十分に供給すれば、生体で酸化ストレスを軽減できうることを示唆している。
大腸発生H2による生体内抗酸化と酸化障害軽減
実験動物のブリーダーでは、動物の腸内細菌叢を均一化するため、出生直後にいくつかの腸内細菌を接種している。それにもかかわらず、発酵基質となる高アミロースデンプン(HAS;難消化性画分を50~60%含む)やペクチンを摂取させたときのラットH2生成能に大きな違いが存在する。そこで、このばらつきを利用してH2生成量と酸化障害との関係を調べた。H2生成能にばらつきのある66匹ラットにHASを与えると、7日後の門脈H2濃度に大きな違いが各個体に認められた。これらのラットすべてに肝IR処置で酸化ストレスを与え、血漿アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)活性(肝障害マーカー)の変化を観察した。門脈H2濃度をカテゴリ変数(五分位数)として血漿ALT活性変動を解析すると、図1のような関係がみられる。門脈H2濃度が低い場合、肝IR酸化障害によって血漿ALT活性は高値を示したが、H2濃度が8.4μmol/L近辺でメジアンは最小値を示した。それ以上のH2濃度では血漿ALT活性はわずかに上昇を示した。これは門脈H2濃度が極端に低い領域では、酸化ストレスに対する防御能がないことを示している。門脈H2濃度が高い場合、大腸内発酵が活発であり、それにともなってさまざまな物質が生成される。その中には酸化障害による炎症を助長するものもあるかもしれない。例えば、細胞毒性の強いアンモニアなどは、虚血-再灌流によって機能の低下した肝臓では炎症を引き起こす可能性も考えられる。H2は生体内における酸化障害を抑制する能力を有するが、大腸H2生成を高める場合、やみくもに発酵を盛んにすることを考えるだけでなく、その他の発酵産物の影響が大きくなる可能性も考慮する必要があるだろう。
次に、高H2生成能ラットを用い、発酵性の高いHASやペクチンを与えたときの酸化ストレスヘの影響を調べた。セルロースを食物繊維源とする精製飼料を与えたラットの(放屁+呼気)H2排出量が0.13μmol/5min以上を示す個体を選別し、HASやペクチンを与えると門脈H2濃度は3~15倍に上昇する(図2)。このようなラットの肝臓にIR処置で酸化ストレスを与えると、IRによって低下した肝グルタチオンの還元型/酸化型比はHASやペクチン投与によって改善した(図2)。これぱHASやペクチン投与によって多量に生成したH2が肝臓で還元性を示し、IRによって酸化状態に傾いたものを回復させたと考えられる。これに伴って、IRによって著しく上昇した血漿ALT活性は、HASやペクチン投与ラットで低下した(図2、3)。これらの結果より、大腸内で生成したH2は門脈を経て肝臓で酸化ストレスを軽減しうることが明らかとなった。また、これまでに虚血後の短時間(30~60分)の再灌流だけでなく、長時間(24~48時間)の再灌流による酸化障害にも、HAS投与によるH2生成が有効であることも示した。
糖尿病、虚血性疾患、動脈硬化症、アルツハイマー病などのような生活習慣病の多くは、酸化ストレスの増大に伴った障害によって発症および進展が誘導される。また、肥満も生体内酸化ストレスを増大させ、生活習慣病発症の引き金となっている。大腸で生成したH2でこれらの酸化ストレスを軽減できれば、さまざまな生活習慣病予防につながることが期待される。そのためには生体内のさまざまな組織に安定的に持続してH2を供給することが重要であるといえよう。
大腸H2生成と持続的H2供給
生体内へのH2の直接的な供給方法として、H2ガスの吸入やH2水の飲水がある。実験動物やヒトを対象とした研究もなされており、それらがH2供給法として有効であることは間違いない。しかし、日常生活における持続的な供給という観点に立てば、決してこれらの方法が有効とはいえない。H2ガスの吸入は病院などで大掛かりな設備が必要であるし、吸入をやめればH2が供給されなくなる。また、H2水であれば、投与直後のH2供給量は多いが、飲める量に限界もある。H2の水への溶解度はとても低い(0.8mmol/L)ため、生体内に高濃度のH2を長時間にわたって供給し続けることは困難である。さらに、摂取後にH2血中濃度がピークを迎え、元に戻るまでの時間も30分程度しかない。この点において、大腸内発酵によるH2の供給は合理的である。大腸に発酵基質を十分量存在すれば、たとえ睡眠時に食事を摂っていなくとも生体内に24時間H2を供給できるはずである。
我々はこれまでにラットを用いた実験で、十分量の発酵基質を大腸に送れば、24時間H2生成が高く維持されることを確認している(図4の20%HAS食群)。一方、大腸内で24時間に資化できる量とほは等量の基質を与えると、投与開始から24時間後のH2生成量はほとんど消失する(図4の10%HAS食群)。このことから大腸に十分量の発酵基質を送り届けることの重要性がわかる。大腸内に滞留している時間も重要であり、十分量に基質を供給しても、滞留時間が短ければ、基質当たりのH2生成が抑えられると考えられる。さらに、H2が長期間にわたって安定的に生成し続けることも生体内還元力を高めるために欠かせない。単一の発酵基質をラットに与えると、投与初期はH2生成量が多く、その後減少するという現象を頻繁に目にする。酸化還元電位の低い大腸内に常在する嫌気性細菌は発酵基質として大腸に流入してきた糖質を主に利用し、ATPを生成している。つまり、発酵基質からH+を獲得し、電子伝達系で自由エネルギーを獲得している。しかし、嫌気性細菌では酸素を利用できないため、H+およびe-からH2ガスを生成する。この状態が過剰になると、H2分圧が高まるため、H2生成がうまく進まなくなる。これが長期間にわたって、極端に高いH2生成能を維持できない理由かもしれない。このような状態にH+およびe-を利用してメタン、硫化水素、酢酸を生成する細菌が活性化すると、H2分圧が下がるため、H2生成がうまく進むかもしれないが、H+がほかに利用されてしまうため、H2ガスの生成はやはり低下する可能性が高い。ヒトの食生活を考えれば、単一の発酵基質を摂取し続けることはありえないが、サプリメントのように単一のものを長期間多量に摂取しても、高H2生成能を長期にわたって維持することは期待できないかもしれない。今後生体内で安定的かつ持続的に多量のH2を生成できるような発酵環境条件を見出すことが重要な課題となると思われる。また、大腸内発酵産物で有用とされている酪酸生成との関係も考えておく必要はあるだろう。H2生成を高めても、逆に酪酸生成は低下するかもしれない。このようなときにどういった発酵がヒトにとってベストもしくはベターであるかを考慮すべきだと考える。
おわりに
H2分子の生体内抗酸化作用はすでに多くの報告がされており、疑う余地はほぽない。大腸内発酵によってH2が生成され、何ら生体に影響をもたらさない分子として考えられていたが、我々の研究によってその抗酸化作用が明らかになった。これまで食物繊維の生理作用として、現象は再現よく観察されるにもかかわらず、それを説明するに足る作用機構が明らかになっていないものがある。その一部はこの大腸発生H2による作用で説明できるかもしれない。まさしく、これは食物繊維の新機能と言えるのではないだろうか。最近の我々の研究で、大腸で生じたH2が腹腔に拡散し、とりわけ脂肪組織に局在していることも見出した。食物繊維など難消化性糖質の摂取で脂肪組織をはじめとする腹腔内の組織にもH2が供給されるという事実は、肥満時の脂肪組織における酸化ストレスも軽減できる可能性を示している。こういった酸化ストレスを大腸生成H2によって制御できれば、食物繊維が新たな局面で生活習慣病予防に大きく寄与すると思われる。この機能を踏まえ、食物繊維の可能性をさらに探究していく価値は多いにあると考える。また、これまでの概念や思考にとらわれず、食物繊維の消化管を介して引き起こす生理作用にさまざまな角度からアプローチしていく気概が食物繊維の研究や開発に取り組む研究者に欠かせないだろう。
食品と開発2013年1月号 UBMメディア

名寄市立大学 保健福祉学部栄養学科・教授 西村直道
はじめに
食物繊維は、コレステロール正常化作用(低下作用)、血糖値上昇抑制作用、便通改善作用、大腸がん発症抑制作用などさまざまな生理作用を有することが報告され、現在でもこれらの作用に関連する研究ならびに開発が行われている。しかし、食物繊維の生理作用は本当にこれまでに報告されているものだけであろうか。数多くの研究がなされ、これまでの既存の考え方では合理的に説明できないような現象も多々見受けられる。同じような経験をしている人は結構多いはずである。にもかかわらず、新たな考え方や可能性を示すことができなかったのは、私を含め食物繊維の研究を行っている研究者の怠慢であったかもしれない。今回ここでは我々が最近4年間で力を注ぎ、たどり着いた新しい食物繊維の機能を解説したい。
食物繊維は大腸に常在する多数の細菌によって発酵分解を受ける。このとき多くの発酵産物が生成され、その中には大腸上皮細胞の主要なエネルギ一源となり、大腸がん発症の抑制因子としても働く酪酸も存在する。酪酸のほかにも酢酸やプロピオン酸など短鎖脂肪酸が比較的多量に生成される。これらに生理作用が認められるため、食物繊維の生理作用に関する研究もこれらの成分に焦点を当てたものが多く見られる。発酵産物としてガス成分も多量に生成されるにもかかわらず、こちらの研究がおろそかになっていたのは否めない。我々が研究の焦点としている水素(H2)も同様であった。H2は極性がなく反応性に富んでいないことから、大腸で発生したH2は生体に何ら作用を及ぼすことのない物質として捉えていたのである。無機化学においてH2分子が白金やパラジウムのような触媒存在下で還元性を示すことは古くから知られていた。生体内でも同様にH2が還元性を示す可能性はあったわけであるが、先に示したような触媒が存在しない生体内で有力なエビデンスを示した研究は長い間なかった。
H2分子による生体内抗酸化と大腸発生H2の可能性
2007年にOsawaらは、脳虚血-再灌流(IR)処置によって酸化ストレスを与えたラットにH2ガスを吸入させることによって、生成されたヒドロキシラジカルが特異的に捕捉され、酸化障害が軽減されることを見出した。この研究は、生体内でH2が還元性を示すことを初めて明らかにしたものであり、その後も、さまざまな酸化ストレスに対しH2分子が抗酸化作用を示すことが報告されている。一方、食物繊維をはじめとする難消化性糖質は、大腸内発酵によるH2生成を促し、そのH2は呼気および放屁に排泄されることが知られている。我々は、このH2も同じように生体内で抗酸化作用を発揮する可能性をひらめいた。大腸内発酵を利用してH2を生体内に供給できれば、安定的かつ持続的に生体内還元性を維持できると期待される。生体内における不必要な酸化反応を防御することで、酸化障害を発端とする生活習慣病の発症や進展を抑えることが可能であろう。
我々は、Savaianoらの報告にもとづいて、ラクトース(20g)摂取後のヒト呼気中H2濃度の変動から、ヒト門脈血中の平均的H2濃度を推定した。一般的な生理学的データより換気量に約500mL/分、呼吸数に16~18回/分を用いて、8時間で呼気中に排出されるH2量の推算を行った。その結果、20gのラクトース摂取で96~108mL/8hのH2が排泄されることがわかった。さらに、拍出量に約5L/分を用い、門脈血流量を消化管に流入する血流量(全血流量の約28%)と同じとして算出した。この結果、門脈血中の平均H2濃度は6.4~7.2μMであると推定できた。このH2濃度は、我々のラットによる実験結果(後述)ともほぼ一致しており、この濃度で酸化ストレスが軽減されることを確認している。また、これまでに酸化ストレスの軽減を示したH2ガスやH2水による研究でも、同程度の血中H2濃度が報告されている。したがって、大腸でH2生成を促進する基質を十分に供給すれば、生体で酸化ストレスを軽減できうることを示唆している。
大腸発生H2による生体内抗酸化と酸化障害軽減
実験動物のブリーダーでは、動物の腸内細菌叢を均一化するため、出生直後にいくつかの腸内細菌を接種している。それにもかかわらず、発酵基質となる高アミロースデンプン(HAS;難消化性画分を50~60%含む)やペクチンを摂取させたときのラットH2生成能に大きな違いが存在する。そこで、このばらつきを利用してH2生成量と酸化障害との関係を調べた。H2生成能にばらつきのある66匹ラットにHASを与えると、7日後の門脈H2濃度に大きな違いが各個体に認められた。これらのラットすべてに肝IR処置で酸化ストレスを与え、血漿アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)活性(肝障害マーカー)の変化を観察した。門脈H2濃度をカテゴリ変数(五分位数)として血漿ALT活性変動を解析すると、図1のような関係がみられる。門脈H2濃度が低い場合、肝IR酸化障害によって血漿ALT活性は高値を示したが、H2濃度が8.4μmol/L近辺でメジアンは最小値を示した。それ以上のH2濃度では血漿ALT活性はわずかに上昇を示した。これは門脈H2濃度が極端に低い領域では、酸化ストレスに対する防御能がないことを示している。門脈H2濃度が高い場合、大腸内発酵が活発であり、それにともなってさまざまな物質が生成される。その中には酸化障害による炎症を助長するものもあるかもしれない。例えば、細胞毒性の強いアンモニアなどは、虚血-再灌流によって機能の低下した肝臓では炎症を引き起こす可能性も考えられる。H2は生体内における酸化障害を抑制する能力を有するが、大腸H2生成を高める場合、やみくもに発酵を盛んにすることを考えるだけでなく、その他の発酵産物の影響が大きくなる可能性も考慮する必要があるだろう。
次に、高H2生成能ラットを用い、発酵性の高いHASやペクチンを与えたときの酸化ストレスヘの影響を調べた。セルロースを食物繊維源とする精製飼料を与えたラットの(放屁+呼気)H2排出量が0.13μmol/5min以上を示す個体を選別し、HASやペクチンを与えると門脈H2濃度は3~15倍に上昇する(図2)。このようなラットの肝臓にIR処置で酸化ストレスを与えると、IRによって低下した肝グルタチオンの還元型/酸化型比はHASやペクチン投与によって改善した(図2)。これぱHASやペクチン投与によって多量に生成したH2が肝臓で還元性を示し、IRによって酸化状態に傾いたものを回復させたと考えられる。これに伴って、IRによって著しく上昇した血漿ALT活性は、HASやペクチン投与ラットで低下した(図2、3)。これらの結果より、大腸内で生成したH2は門脈を経て肝臓で酸化ストレスを軽減しうることが明らかとなった。また、これまでに虚血後の短時間(30~60分)の再灌流だけでなく、長時間(24~48時間)の再灌流による酸化障害にも、HAS投与によるH2生成が有効であることも示した。
糖尿病、虚血性疾患、動脈硬化症、アルツハイマー病などのような生活習慣病の多くは、酸化ストレスの増大に伴った障害によって発症および進展が誘導される。また、肥満も生体内酸化ストレスを増大させ、生活習慣病発症の引き金となっている。大腸で生成したH2でこれらの酸化ストレスを軽減できれば、さまざまな生活習慣病予防につながることが期待される。そのためには生体内のさまざまな組織に安定的に持続してH2を供給することが重要であるといえよう。
大腸H2生成と持続的H2供給
生体内へのH2の直接的な供給方法として、H2ガスの吸入やH2水の飲水がある。実験動物やヒトを対象とした研究もなされており、それらがH2供給法として有効であることは間違いない。しかし、日常生活における持続的な供給という観点に立てば、決してこれらの方法が有効とはいえない。H2ガスの吸入は病院などで大掛かりな設備が必要であるし、吸入をやめればH2が供給されなくなる。また、H2水であれば、投与直後のH2供給量は多いが、飲める量に限界もある。H2の水への溶解度はとても低い(0.8mmol/L)ため、生体内に高濃度のH2を長時間にわたって供給し続けることは困難である。さらに、摂取後にH2血中濃度がピークを迎え、元に戻るまでの時間も30分程度しかない。この点において、大腸内発酵によるH2の供給は合理的である。大腸に発酵基質を十分量存在すれば、たとえ睡眠時に食事を摂っていなくとも生体内に24時間H2を供給できるはずである。
我々はこれまでにラットを用いた実験で、十分量の発酵基質を大腸に送れば、24時間H2生成が高く維持されることを確認している(図4の20%HAS食群)。一方、大腸内で24時間に資化できる量とほは等量の基質を与えると、投与開始から24時間後のH2生成量はほとんど消失する(図4の10%HAS食群)。このことから大腸に十分量の発酵基質を送り届けることの重要性がわかる。大腸内に滞留している時間も重要であり、十分量に基質を供給しても、滞留時間が短ければ、基質当たりのH2生成が抑えられると考えられる。さらに、H2が長期間にわたって安定的に生成し続けることも生体内還元力を高めるために欠かせない。単一の発酵基質をラットに与えると、投与初期はH2生成量が多く、その後減少するという現象を頻繁に目にする。酸化還元電位の低い大腸内に常在する嫌気性細菌は発酵基質として大腸に流入してきた糖質を主に利用し、ATPを生成している。つまり、発酵基質からH+を獲得し、電子伝達系で自由エネルギーを獲得している。しかし、嫌気性細菌では酸素を利用できないため、H+およびe-からH2ガスを生成する。この状態が過剰になると、H2分圧が高まるため、H2生成がうまく進まなくなる。これが長期間にわたって、極端に高いH2生成能を維持できない理由かもしれない。このような状態にH+およびe-を利用してメタン、硫化水素、酢酸を生成する細菌が活性化すると、H2分圧が下がるため、H2生成がうまく進むかもしれないが、H+がほかに利用されてしまうため、H2ガスの生成はやはり低下する可能性が高い。ヒトの食生活を考えれば、単一の発酵基質を摂取し続けることはありえないが、サプリメントのように単一のものを長期間多量に摂取しても、高H2生成能を長期にわたって維持することは期待できないかもしれない。今後生体内で安定的かつ持続的に多量のH2を生成できるような発酵環境条件を見出すことが重要な課題となると思われる。また、大腸内発酵産物で有用とされている酪酸生成との関係も考えておく必要はあるだろう。H2生成を高めても、逆に酪酸生成は低下するかもしれない。このようなときにどういった発酵がヒトにとってベストもしくはベターであるかを考慮すべきだと考える。
おわりに
H2分子の生体内抗酸化作用はすでに多くの報告がされており、疑う余地はほぽない。大腸内発酵によってH2が生成され、何ら生体に影響をもたらさない分子として考えられていたが、我々の研究によってその抗酸化作用が明らかになった。これまで食物繊維の生理作用として、現象は再現よく観察されるにもかかわらず、それを説明するに足る作用機構が明らかになっていないものがある。その一部はこの大腸発生H2による作用で説明できるかもしれない。まさしく、これは食物繊維の新機能と言えるのではないだろうか。最近の我々の研究で、大腸で生じたH2が腹腔に拡散し、とりわけ脂肪組織に局在していることも見出した。食物繊維など難消化性糖質の摂取で脂肪組織をはじめとする腹腔内の組織にもH2が供給されるという事実は、肥満時の脂肪組織における酸化ストレスも軽減できる可能性を示している。こういった酸化ストレスを大腸生成H2によって制御できれば、食物繊維が新たな局面で生活習慣病予防に大きく寄与すると思われる。この機能を踏まえ、食物繊維の可能性をさらに探究していく価値は多いにあると考える。また、これまでの概念や思考にとらわれず、食物繊維の消化管を介して引き起こす生理作用にさまざまな角度からアプローチしていく気概が食物繊維の研究や開発に取り組む研究者に欠かせないだろう。
食品と開発2013年1月号 UBMメディア

2013年11月13日
【水素】市場規模、200億円の大台に到達!
水素商材の市場がいよいよ200億円の大台を突破―― 今回本紙では、主要メーカー100社への取材およびアンケートで、各社の業況を調査(回答35社)。調査を元に、2013年度の各社の水素商材の売上高を合算した結果、約180億円(前年比109%)となり、市場全体では200億円の大台に到達したと予想される。TV番組や雑誌など、水素の効果や関連商材がメディアに取り上げられる機会が増えたことで新規ユーザーの獲得に成功、裾野が広がった。小売店舗を中心に販路も飛躍的に拡大し、水素が人目に触れる環境が整いつつある。さらに海外進出も活発化している。一方で、市場は玉石混交の様相。主導権争いも熱を帯びてきている。こうした中、市場の健全な発展に向けて新たな業界団体も発足。水素商材市場は次なるステップに進み始めた。
◆ヒト臨床など広がる水素研究背景に、関連商材市場も拡大
2007年のネイチャー発表以降6 年が経過し、国内外の大学や研究機関から発表された水素の有用性に関する論文は、国際ジャーナルレベルで250報以上になる。現在までに確認されている水素の有用性は、抗酸化作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用、エネルギー代謝亢進作用―― など。具体的には、心筋梗塞やⅡ型糖尿病、動脈硬化、虚血再灌流障害、学習・記憶能力の低下予防、脳梗塞、パーキンソン病、ミトコンドリア病、リウマチ―― など。現在は基礎研究から動物試験を経て、筑波大では認知障害、順天堂大ではパーキンソン病など、複数の大学でヒト臨床試験も行われている。実際に医療現場で水素を活用する動きも見られる。一方、美容・アンチエイジング分野でも、水素のコラーゲン構築効果や脂肪滴・セルライト抑制効果、メラニン抑制・美白効果――などのデータが発表されており、医療や予防医療、健康に加えて美容分野でも水素の有用性に注目が高まっている。
これら豊富なエビデンスを背景に、水素商材の市場も拡大している。今回本紙では、水素商材の取扱メーカー100社を対象に、取材およびアンケート調査を実施、35社より回答を得た(昨年25社)。2013年度の各社の水素商材の売上高(見込みも含む)を合算した結果、約180億円となり、対前年比109%だった。全社から回答を得た訳ではない点、回答企業の対前年増加率の平均値などを考慮した結果、市場全体では200億円の大台に到達したと予想される。また日本トリムやパナソニック等が展開する「アルカリイオン整水器」を水素商材に加えた場合、市場規模は300億円を超え、いよいよ水素商材が健康・美容分野の1 ジャンルとして台頭してきた。
◆小売店採用拡大、新規ユーザー獲得海外進出も活発化
今年の市場動向をみると、この数年来、撤退する企業も見られた「アルミパウチ入り水素水」の売れ行きが大幅に復調。回答のあったアルミパウチ入り水素水の充填工場や販売メーカー各社の対前年増減率は平均で150%、なかには200%という回答もみられた。背景には、ここ1,2 年TV番組や雑誌を通じて水素の健康や美容、アンチエイジング効果が頻繁に特集されるようになり、新規ユーザーが増加していることが挙げられる。新規ユーザーにとっては、ネット通販などで簡単に購入できるアルミパウチ入り水素水が身近な水素商材として認識されている。
この動きは業界全体にとっても追い風だ。ここ数年の市場は、水素のヘビーユーザー中心に動いており、今一つ大きな盛り上がりに欠けていた。今回の取材からは、これまでのヘビーユーザー中心の市場から脱却し、新規ユーザーを取り込むことで、市場の裾野が広がり始めた。
実際、今年に入って水素商材の販売ルートが拡大している。昨年の本特集で一般流通への広がりについて触れたが、今回の取材ではドラッグストアや薬局・薬店、コンビニエンスストア、百貨店、バラエティショップ、スーパー、量販店などが、アルミパウチ入り水素水や水素サプリメント、水素水生成スティックなどを積極的に採用、家電量販店や電器店でも複数ブランドの水素水生成器を取り扱い始めるなど、特に小売店舗での水素商材の採用が飛躍的に増加している。さらに、「大手量販店からPBの案件が来ている」「一部上場企業がコンビニルートでの販売を検討している」―― など、来年に向けて明るい話も多く聞かれた。
今年の新たな動きとしては、医療ルートと美容ルートの伸長が挙げられる。医療機関では、特に歯科医や獣医ルート、治療・施術院などへの水素商材の導入が増えていることが分かった。なかでも今回、多くの企業が「採用が増えている」と回答した歯科医ルートでは、水素水サーバーを導入して、口を濯ぐ水を水素水にする、水素ガムや水素水の物販など、口腔ケアや歯周病予防のために水素商材が活用されるケースが増加しているようだ。また美容ルートでは、エステサロンや美容院、ダンス教室、ホットヨガ、スパ施設などで店頭サービスとして水素水サーバーを導入するケース、メニューに水素水洗顔や水素化粧品などを加えるケース、物販商品として水素水や水素サプリメント、水素化粧品を採用するケースなどが増加している。9月の「ダイエット&ビューティーフェア」でも水素商材の取扱企業が数多く出展し、初めて「水素ゾーン」ができるなど、美容業界でのニーズが高まっている。
その他、水素水サーバーをオフィスに拡販する企業、プロスポーツ団体や大学、高校の運動部に導入を進める企業、携帯電話ショップに導入を図る企業、水素スティックをプロの料理人を通じて外食産業に拡販する企業、水素水を農業分野に導入して成果をあげる企業、大型の水素水生成装置を競走馬の厩舎に導入する企業―― など、ユニークな取り組みを展開する企業も複数見られた。これら盛り上がりを見せる国内市場に加え、今回の取材では水素商材メーカーの海外進出が進んでいることも分かった。進出先は、中国や台湾、韓国など東アジアが最も多く、フィリピンやシンガポール、マレーシア、タイなど東南アジア、カナダ、ロシアなど様々。水素商材の市場は今後、グローバルな展開にも期待される。
健康産業新聞1506号(2013.11.13)より一部抜粋
http://www.this.ne.jp/news/detail.php?nid=407
◆ヒト臨床など広がる水素研究背景に、関連商材市場も拡大
2007年のネイチャー発表以降6 年が経過し、国内外の大学や研究機関から発表された水素の有用性に関する論文は、国際ジャーナルレベルで250報以上になる。現在までに確認されている水素の有用性は、抗酸化作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用、エネルギー代謝亢進作用―― など。具体的には、心筋梗塞やⅡ型糖尿病、動脈硬化、虚血再灌流障害、学習・記憶能力の低下予防、脳梗塞、パーキンソン病、ミトコンドリア病、リウマチ―― など。現在は基礎研究から動物試験を経て、筑波大では認知障害、順天堂大ではパーキンソン病など、複数の大学でヒト臨床試験も行われている。実際に医療現場で水素を活用する動きも見られる。一方、美容・アンチエイジング分野でも、水素のコラーゲン構築効果や脂肪滴・セルライト抑制効果、メラニン抑制・美白効果――などのデータが発表されており、医療や予防医療、健康に加えて美容分野でも水素の有用性に注目が高まっている。
これら豊富なエビデンスを背景に、水素商材の市場も拡大している。今回本紙では、水素商材の取扱メーカー100社を対象に、取材およびアンケート調査を実施、35社より回答を得た(昨年25社)。2013年度の各社の水素商材の売上高(見込みも含む)を合算した結果、約180億円となり、対前年比109%だった。全社から回答を得た訳ではない点、回答企業の対前年増加率の平均値などを考慮した結果、市場全体では200億円の大台に到達したと予想される。また日本トリムやパナソニック等が展開する「アルカリイオン整水器」を水素商材に加えた場合、市場規模は300億円を超え、いよいよ水素商材が健康・美容分野の1 ジャンルとして台頭してきた。
◆小売店採用拡大、新規ユーザー獲得海外進出も活発化
今年の市場動向をみると、この数年来、撤退する企業も見られた「アルミパウチ入り水素水」の売れ行きが大幅に復調。回答のあったアルミパウチ入り水素水の充填工場や販売メーカー各社の対前年増減率は平均で150%、なかには200%という回答もみられた。背景には、ここ1,2 年TV番組や雑誌を通じて水素の健康や美容、アンチエイジング効果が頻繁に特集されるようになり、新規ユーザーが増加していることが挙げられる。新規ユーザーにとっては、ネット通販などで簡単に購入できるアルミパウチ入り水素水が身近な水素商材として認識されている。
この動きは業界全体にとっても追い風だ。ここ数年の市場は、水素のヘビーユーザー中心に動いており、今一つ大きな盛り上がりに欠けていた。今回の取材からは、これまでのヘビーユーザー中心の市場から脱却し、新規ユーザーを取り込むことで、市場の裾野が広がり始めた。
実際、今年に入って水素商材の販売ルートが拡大している。昨年の本特集で一般流通への広がりについて触れたが、今回の取材ではドラッグストアや薬局・薬店、コンビニエンスストア、百貨店、バラエティショップ、スーパー、量販店などが、アルミパウチ入り水素水や水素サプリメント、水素水生成スティックなどを積極的に採用、家電量販店や電器店でも複数ブランドの水素水生成器を取り扱い始めるなど、特に小売店舗での水素商材の採用が飛躍的に増加している。さらに、「大手量販店からPBの案件が来ている」「一部上場企業がコンビニルートでの販売を検討している」―― など、来年に向けて明るい話も多く聞かれた。
今年の新たな動きとしては、医療ルートと美容ルートの伸長が挙げられる。医療機関では、特に歯科医や獣医ルート、治療・施術院などへの水素商材の導入が増えていることが分かった。なかでも今回、多くの企業が「採用が増えている」と回答した歯科医ルートでは、水素水サーバーを導入して、口を濯ぐ水を水素水にする、水素ガムや水素水の物販など、口腔ケアや歯周病予防のために水素商材が活用されるケースが増加しているようだ。また美容ルートでは、エステサロンや美容院、ダンス教室、ホットヨガ、スパ施設などで店頭サービスとして水素水サーバーを導入するケース、メニューに水素水洗顔や水素化粧品などを加えるケース、物販商品として水素水や水素サプリメント、水素化粧品を採用するケースなどが増加している。9月の「ダイエット&ビューティーフェア」でも水素商材の取扱企業が数多く出展し、初めて「水素ゾーン」ができるなど、美容業界でのニーズが高まっている。
その他、水素水サーバーをオフィスに拡販する企業、プロスポーツ団体や大学、高校の運動部に導入を進める企業、携帯電話ショップに導入を図る企業、水素スティックをプロの料理人を通じて外食産業に拡販する企業、水素水を農業分野に導入して成果をあげる企業、大型の水素水生成装置を競走馬の厩舎に導入する企業―― など、ユニークな取り組みを展開する企業も複数見られた。これら盛り上がりを見せる国内市場に加え、今回の取材では水素商材メーカーの海外進出が進んでいることも分かった。進出先は、中国や台湾、韓国など東アジアが最も多く、フィリピンやシンガポール、マレーシア、タイなど東南アジア、カナダ、ロシアなど様々。水素商材の市場は今後、グローバルな展開にも期待される。
健康産業新聞1506号(2013.11.13)より一部抜粋
http://www.this.ne.jp/news/detail.php?nid=407
2013年11月09日
ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
「認知症」最新研究
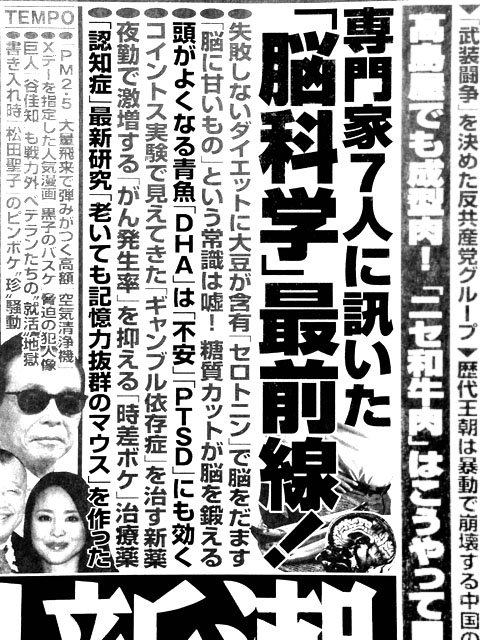
脳研究に我々が最も期待しているのは、認知症の予防・治療ではないだろうか。本人のみならず周囲を奈落の底に落としかねないこの難病に、科学者たちは日々立ち向かっている。
〈ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果〉
こんな見出しが新聞各紙に躍ったのは昨年7月のことだった。
富山大学によると、同大和漢医薬学総合研究所の東田千尋准教授らのグループが、ヤマイモなどに多く含まれているジオスゲニンという成分をアルツハイマー病のマウスに20日間投与したところ、神経細胞が回復し、記憶力の改善が見られたという。
"これを人間に当てはめた場合、1日10kgのヤマイモを食べないといけない"というオチがつくが、それでも朗報には違いない。
日本人が平均、年に約78回食べているというカレーもアルツハイマー病と関係が深そうだ。
「"クルクミン"という成分が、アルツハイマー病の進行を食い止めるとされています」
とは先の久保田名誉教授。クルクミンは、カレー粉の原料であるウコンなどに多く含まれている成分である。
カリフォルニア大学の研究チームが、細胞培養実験で3人のアルツハイマー病患者から免疫細胞を採取しクルクミンで処理したところ、アルツハイマー病の原因の一つとされるアミロイドベータというタンパク質が減少したという。他にもマウス実験などさまざまな方法でクルクミンの効能が確認されている。
「インド人はアメリカ人と比べてアルツハイマー病の発症率が4分の1であるというデータもある」(同)というのだから、食卓にカレーが登場する頻度は高まりそうだ。
週刊新潮 2013年11月14日号(2013/11/07発売)
ヤマイモ成分で記憶力改善 アルツハイマー病に効果
日本経済新聞 2012/8/5 20:34
富山大和漢医薬学総合研究所(富山市)の東田千尋准教授(神経機能学)らのグループが、ヤマイモなどに多く含まれる「ジオスゲニン」という成分に、アルツハイマー病の症状を改善する働きがあることを発見した。英オンライン科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に発表した。
東田准教授は、神経細胞の活性化に効果のある物質を研究する中で、ジオスゲニンに注目。アルツハイマー病の症状があるマウスに1日1回、20日間ジオスゲニンを投与した。その結果、患者に典型的にみられる、神経細胞の軸索という突起の変性が正常に近い状態に戻り、マウスの記憶力に改善がみられた。
さらに病気の原因となるタンパク質「アミロイドベータ」も約70%減少したという。
東田准教授によると、原因物質を減らす新薬は研究されているが、変性してしまった神経細胞を戻したり、記憶力を改善させたりする効果はまだ得られていないといい「治療薬開発の可能性が広がった」と話している。〔共同〕
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2901L_V00C12A8CR8000/
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
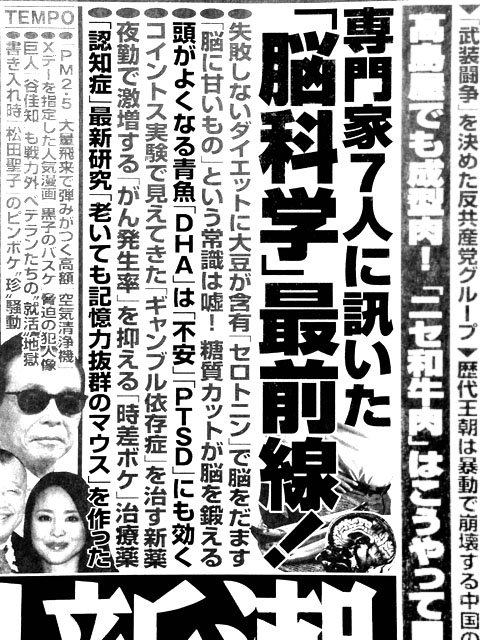
脳研究に我々が最も期待しているのは、認知症の予防・治療ではないだろうか。本人のみならず周囲を奈落の底に落としかねないこの難病に、科学者たちは日々立ち向かっている。
〈ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果〉
こんな見出しが新聞各紙に躍ったのは昨年7月のことだった。
富山大学によると、同大和漢医薬学総合研究所の東田千尋准教授らのグループが、ヤマイモなどに多く含まれているジオスゲニンという成分をアルツハイマー病のマウスに20日間投与したところ、神経細胞が回復し、記憶力の改善が見られたという。
"これを人間に当てはめた場合、1日10kgのヤマイモを食べないといけない"というオチがつくが、それでも朗報には違いない。
日本人が平均、年に約78回食べているというカレーもアルツハイマー病と関係が深そうだ。
「"クルクミン"という成分が、アルツハイマー病の進行を食い止めるとされています」
とは先の久保田名誉教授。クルクミンは、カレー粉の原料であるウコンなどに多く含まれている成分である。
カリフォルニア大学の研究チームが、細胞培養実験で3人のアルツハイマー病患者から免疫細胞を採取しクルクミンで処理したところ、アルツハイマー病の原因の一つとされるアミロイドベータというタンパク質が減少したという。他にもマウス実験などさまざまな方法でクルクミンの効能が確認されている。
「インド人はアメリカ人と比べてアルツハイマー病の発症率が4分の1であるというデータもある」(同)というのだから、食卓にカレーが登場する頻度は高まりそうだ。
週刊新潮 2013年11月14日号(2013/11/07発売)
ヤマイモ成分で記憶力改善 アルツハイマー病に効果
日本経済新聞 2012/8/5 20:34
富山大和漢医薬学総合研究所(富山市)の東田千尋准教授(神経機能学)らのグループが、ヤマイモなどに多く含まれる「ジオスゲニン」という成分に、アルツハイマー病の症状を改善する働きがあることを発見した。英オンライン科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に発表した。
東田准教授は、神経細胞の活性化に効果のある物質を研究する中で、ジオスゲニンに注目。アルツハイマー病の症状があるマウスに1日1回、20日間ジオスゲニンを投与した。その結果、患者に典型的にみられる、神経細胞の軸索という突起の変性が正常に近い状態に戻り、マウスの記憶力に改善がみられた。
さらに病気の原因となるタンパク質「アミロイドベータ」も約70%減少したという。
東田准教授によると、原因物質を減らす新薬は研究されているが、変性してしまった神経細胞を戻したり、記憶力を改善させたりする効果はまだ得られていないといい「治療薬開発の可能性が広がった」と話している。〔共同〕
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2901L_V00C12A8CR8000/
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
2013年11月08日
水素で美しく 生活習慣病対策やアンチエイジングに応用期待
【くらしナビ】
水素で美しく 生活習慣病対策やアンチエイジングに応用期待
2013.11.7 08:19
体内の有害な活性酸素を取り除く強力な抗酸化作用があるとされる水素について、このほかにも人体に有用な多くの働きがあることが最近の研究で分かってきた。生活習慣病対策やアンチエイジング(抗加齢)分野などへの幅広い応用も期待されている。

◆アレルギー抑制
水素の医学的効果に関する研究の第一人者、日本医科大学の太田成男教授(細胞生物学)によると、炎症やアレルギーを抑えたり、エネルギー代謝を促進したりする効果が、マウスなどの実験で明らかになっている。
「いずれも水素が遺伝子に作用することで、炎症を起こすホルモンの抑制や脂肪を燃やす酵素の生成にかかわる遺伝子を働かせる引き金になると考えられます。水素には活性酸素の直接除去と遺伝子への作用という“二段構え”の働きがあることが分かってきました」(太田教授)
人体への有効性を確かめる臨床研究も世界的に広がっている。
中国・山東大は今夏、メタボリック症候群の新たな治療・予防手段になる可能性があるという研究結果を発表した。それによると、潜在的なメタボ症候群とされた患者20人を対象に、分子状の水素を水に溶かした水素水(1リットル当たり水素0.4~0.5ミリグラム含有)を毎日0.9~1リットルずつ、10週間飲んでもらう実験を実施。実験前後で比べると、LDL(悪玉)コレステロールの平均値が低下した。
◆副作用なく安全
美容分野でも効果が期待されている。シミやシワ、くすみといった老化による肌トラブルの原因として活性酸素の影響が挙げられるためだ。
太田教授によると、水素分子は副作用がなく体にも安全で、水素水の形で摂取するのが最も手軽で便利。食品(飲料)として販売することも厚生労働省から認められている。水素水は市販品も数多くあるが、「含有量が明示され、水素分子を通さないアルミ製の容器に詰められた商品を選ぶといい」と話す。今年に入り米食品医薬品局(FDA)などでも食品として認可され、今後は海外でも普及に弾みがつく可能性があるという。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/131107/trd13110708250002-n1.htm
水素で美しく 生活習慣病対策やアンチエイジングに応用期待
2013.11.7 08:19
体内の有害な活性酸素を取り除く強力な抗酸化作用があるとされる水素について、このほかにも人体に有用な多くの働きがあることが最近の研究で分かってきた。生活習慣病対策やアンチエイジング(抗加齢)分野などへの幅広い応用も期待されている。

◆アレルギー抑制
水素の医学的効果に関する研究の第一人者、日本医科大学の太田成男教授(細胞生物学)によると、炎症やアレルギーを抑えたり、エネルギー代謝を促進したりする効果が、マウスなどの実験で明らかになっている。
「いずれも水素が遺伝子に作用することで、炎症を起こすホルモンの抑制や脂肪を燃やす酵素の生成にかかわる遺伝子を働かせる引き金になると考えられます。水素には活性酸素の直接除去と遺伝子への作用という“二段構え”の働きがあることが分かってきました」(太田教授)
人体への有効性を確かめる臨床研究も世界的に広がっている。
中国・山東大は今夏、メタボリック症候群の新たな治療・予防手段になる可能性があるという研究結果を発表した。それによると、潜在的なメタボ症候群とされた患者20人を対象に、分子状の水素を水に溶かした水素水(1リットル当たり水素0.4~0.5ミリグラム含有)を毎日0.9~1リットルずつ、10週間飲んでもらう実験を実施。実験前後で比べると、LDL(悪玉)コレステロールの平均値が低下した。
◆副作用なく安全
美容分野でも効果が期待されている。シミやシワ、くすみといった老化による肌トラブルの原因として活性酸素の影響が挙げられるためだ。
太田教授によると、水素分子は副作用がなく体にも安全で、水素水の形で摂取するのが最も手軽で便利。食品(飲料)として販売することも厚生労働省から認められている。水素水は市販品も数多くあるが、「含有量が明示され、水素分子を通さないアルミ製の容器に詰められた商品を選ぶといい」と話す。今年に入り米食品医薬品局(FDA)などでも食品として認可され、今後は海外でも普及に弾みがつく可能性があるという。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/131107/trd13110708250002-n1.htm
2013年11月02日
脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
ユニヴェール(本社東京、渡邊俊一会長)は、14年3月期から5カ年にわたる中期経営計画を策定し、長期的な展望に立った成長をめざしている。その施策の1つが新たな水素サプリメントの投入だ。

-今後の製品戦略について。
12月上旬をめどに、新製品「メモワール」を投入する。これは水素素材をベースに4種類の酵素を配合したサプリメント。脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」と位置づけている。
開発・研究にあたって、医学博士で佐賀女子短期大学の名誉教授である長谷川亨氏の協力を仰いだ。
月刊Network Business 2013-12より

【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

-今後の製品戦略について。
12月上旬をめどに、新製品「メモワール」を投入する。これは水素素材をベースに4種類の酵素を配合したサプリメント。脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」と位置づけている。
開発・研究にあたって、医学博士で佐賀女子短期大学の名誉教授である長谷川亨氏の協力を仰いだ。
月刊Network Business 2013-12より

【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
2013年10月29日
アルツハイマー病に驚くべき改善効果
従来、アルツハイマー病は高齢になるにつれ脳の神経細胞が急激に無くなっていく病気で、死んだ細胞を戻す治療は難しいとされてきました。
アルツハイマー病の原因
~アミロイド理論からホモシステイン酸理論へ~
2000年以降、アルツハイマー病の原因は、老人の脳神経に異常なアミロイドベータ蛋白が溜まるためと考えられていました。これに対して医学博士 長谷川教授は、老人の栄養障害や肝臓や腎臓機能の低下に伴い、過剰になった血中ホモシステイン酸が脳神経へ入り、アミロイドβ蛋白を誘導、蓄積する悪玉アミノ酸に変身して脳神経細胞を損傷することを解明しました。
これを証明するために、長谷川教授はアルツハイマー型やレビー小体型認知症の患者に「水素ブレインフード」を1~2ヵ月間投与した結果、驚くべき改善効果が得られ、2013年6月にアメリカ認知症学会で発表したので、その臨床研究データの一部を紹介します。
1. 対象患者と1日飲用量
臨床成績
アルツハイマー型6例、レビー小体型2例に対して水素ブレインフード1日9個を飲用させました。比較対照患者としてアルツハイマー型5例にプラセボ(偽物)を飲用させました。性別は男性2例、女性11例、平均年齢は、85.5±7.7歳です。
2. 血中ホモシステイン酸値に及ぼす水素ブレインフードの影響
水素ブレインフードを1ヵ月間、飲用させた前後における血中ホモシステイン酸は、全例とも減少しました(図1)。
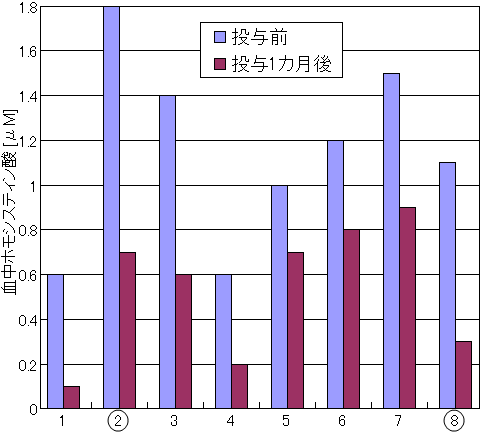
図1.血中ホモシステイン酸値に及ぼす水素ブレインフードの影響
*患者番号に○をした例は、レビー小体型認知症患者です。
3. 認知改善効果-MMSEスコアに及ぼす水素ブレインフードの影響
簡便に認知機能や記憶力を測定できる認知機能検査が、MMSEスコアです。
27~30点・・・正常値
22~26点・・・軽度認知障害の疑いがある
21点以下・・・認知症などの認知障害がある可能性が高い
と判定されます。
健常者が21点以下を取ることはきわめてまれであるとされています。
水素ブレインフードを飲用した8例では、わずか1ヵ月後に認知機能が改善しました。一方、プラセボを飲用した5例の患者のMMSEスコアは、前後不変のままでした(図2)。
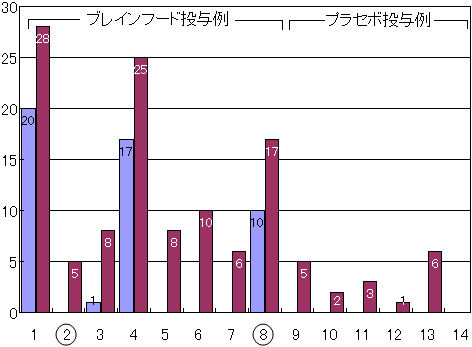
図2.MMSEスコアに及ぼす水素ブレインフードの影響
*患者番号に○をした例は、レビー小体型認知症患者です。
監修:医学博士 長谷川亨教授
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
アルツハイマー病の原因
~アミロイド理論からホモシステイン酸理論へ~
2000年以降、アルツハイマー病の原因は、老人の脳神経に異常なアミロイドベータ蛋白が溜まるためと考えられていました。これに対して医学博士 長谷川教授は、老人の栄養障害や肝臓や腎臓機能の低下に伴い、過剰になった血中ホモシステイン酸が脳神経へ入り、アミロイドβ蛋白を誘導、蓄積する悪玉アミノ酸に変身して脳神経細胞を損傷することを解明しました。
これを証明するために、長谷川教授はアルツハイマー型やレビー小体型認知症の患者に「水素ブレインフード」を1~2ヵ月間投与した結果、驚くべき改善効果が得られ、2013年6月にアメリカ認知症学会で発表したので、その臨床研究データの一部を紹介します。
1. 対象患者と1日飲用量
臨床成績
アルツハイマー型6例、レビー小体型2例に対して水素ブレインフード1日9個を飲用させました。比較対照患者としてアルツハイマー型5例にプラセボ(偽物)を飲用させました。性別は男性2例、女性11例、平均年齢は、85.5±7.7歳です。
2. 血中ホモシステイン酸値に及ぼす水素ブレインフードの影響
水素ブレインフードを1ヵ月間、飲用させた前後における血中ホモシステイン酸は、全例とも減少しました(図1)。
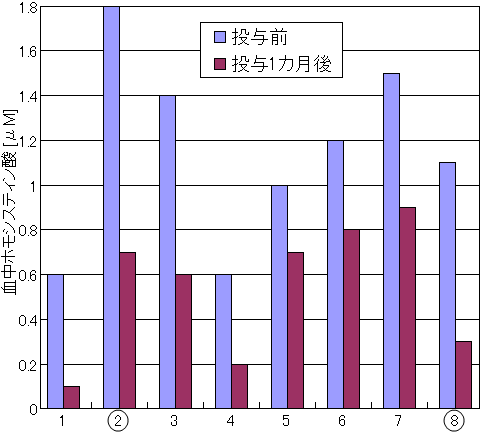
図1.血中ホモシステイン酸値に及ぼす水素ブレインフードの影響
*患者番号に○をした例は、レビー小体型認知症患者です。
3. 認知改善効果-MMSEスコアに及ぼす水素ブレインフードの影響
簡便に認知機能や記憶力を測定できる認知機能検査が、MMSEスコアです。
27~30点・・・正常値
22~26点・・・軽度認知障害の疑いがある
21点以下・・・認知症などの認知障害がある可能性が高い
と判定されます。
健常者が21点以下を取ることはきわめてまれであるとされています。
水素ブレインフードを飲用した8例では、わずか1ヵ月後に認知機能が改善しました。一方、プラセボを飲用した5例の患者のMMSEスコアは、前後不変のままでした(図2)。
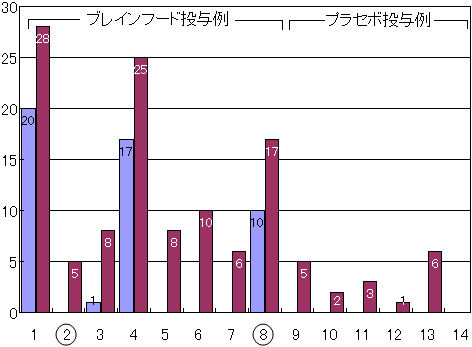
図2.MMSEスコアに及ぼす水素ブレインフードの影響
*患者番号に○をした例は、レビー小体型認知症患者です。
監修:医学博士 長谷川亨教授
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
2013年10月29日
G8サミットで初めて認知症がテーマに
2013年12月11日にロンドンで開催されるG8のハイレベル・サミットで、認知症が取り上げられる。イギリス政府は、「認知症」サミットを初めて開催することにより、認知症に対するグローバルな取り組みを進め、意欲的な国際協調と効果的な対応の実現を目指すと発表している。
英国だけでも、患者数は2020年末までに約100万人に達することが予想され、政府は既に、2011年にキャメロン首相がスタートさせたイニシアティブである「Dementia Challenge(認知症への挑戦)」を通して行動を起こすべく、国家プログラムを開始しました。
世界では現在、3560万人が認知症患者であると言われている。世界の人口高齢化が進む中、WHOによれば、20年毎に、患者数は約2倍に増加し、2030年には6570万人、2050年には1万1540万人に達することが予測される。患者数の増加については、その大部分が途上国においてであり、世界全体の患者数に占める割合は、現在の58%から2050年には71%に上昇する見込みだ。
サミットでは、加盟国の保健大臣を招待し、世界的な取り組みに大きな弾みをつけたいと考えている。各国の政策を如何に協調させ、認知症に対する効果的、且つ、国際的な解決方法を形成できるかを協議する。これには、認知症の進行を遅らせるための効果的な治療法や対処法を探し出す試みも含まれる。
そのために、OECD、世界保健機関(WHO)、産業界、国の研究機関、主要なオピニオン・リーダー、研究者、医師の専門知識や経験を活用する。
英国のジェレミー・ハント保健相は次のように述べた。
「世界では、認知症の新規患者が4秒に1人生まれており、2020年までに患者数は約7000万人に達する見込みです。
認知症には、長期的な医療の他、社会的なサポートが求められ、多額の費用が必要となります。認知症にかかるグローバルなコストについては、現在、西ヨーロッパや北米など、医療面でも先進国と言える国々が、その70%を負担していますが、患者の約60%が途上国で暮らしています。患者数の増加や高齢化に伴い、医療などのサービスや予算面のプレッシャーが増すことは必至です。」
イギリス政府のプレスリリース
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-host-g8-dementia-summit.ja
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
英国だけでも、患者数は2020年末までに約100万人に達することが予想され、政府は既に、2011年にキャメロン首相がスタートさせたイニシアティブである「Dementia Challenge(認知症への挑戦)」を通して行動を起こすべく、国家プログラムを開始しました。
世界では現在、3560万人が認知症患者であると言われている。世界の人口高齢化が進む中、WHOによれば、20年毎に、患者数は約2倍に増加し、2030年には6570万人、2050年には1万1540万人に達することが予測される。患者数の増加については、その大部分が途上国においてであり、世界全体の患者数に占める割合は、現在の58%から2050年には71%に上昇する見込みだ。
サミットでは、加盟国の保健大臣を招待し、世界的な取り組みに大きな弾みをつけたいと考えている。各国の政策を如何に協調させ、認知症に対する効果的、且つ、国際的な解決方法を形成できるかを協議する。これには、認知症の進行を遅らせるための効果的な治療法や対処法を探し出す試みも含まれる。
そのために、OECD、世界保健機関(WHO)、産業界、国の研究機関、主要なオピニオン・リーダー、研究者、医師の専門知識や経験を活用する。
英国のジェレミー・ハント保健相は次のように述べた。
「世界では、認知症の新規患者が4秒に1人生まれており、2020年までに患者数は約7000万人に達する見込みです。
認知症には、長期的な医療の他、社会的なサポートが求められ、多額の費用が必要となります。認知症にかかるグローバルなコストについては、現在、西ヨーロッパや北米など、医療面でも先進国と言える国々が、その70%を負担していますが、患者の約60%が途上国で暮らしています。患者数の増加や高齢化に伴い、医療などのサービスや予算面のプレッシャーが増すことは必至です。」
イギリス政府のプレスリリース
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-host-g8-dementia-summit.ja
【関連記事】
・ ハウステンボス認知症セミナー
・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない
・ 第9回 認知症サプリメント研究会
・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!
・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか
・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果
・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」
・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果
・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント
・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人
2013年10月26日
栄養補助食品の機能性表示拡大シンポジウム
栄養補助食品の機能性表示拡大
日本の法規制公開シンポジウム
10月7日、「日本における栄養補助食品有用性の消費者理解促進を目的とした表示拡大のための政策検討会」をテーマとしたシンポジウムが、国際栄養食品協会(略称AIFN)および在日米国商工会議所(ACCJ)の主催で開催された。デフレ脱却で安倍晋三首相が打ち出した三本の矢のひとつ「民間投資を喚起する成長戦略」の一環として、栄養補助食品に対する機能性表示拡大が2015年末までに行われることを受け、既にシステムを構築している米国栄養補助食品(ダイエタリー・サプリメント)制度や、米国とは異なる制度のEUにおける機能性表示と問題点、2015年までに単一市場の形成を目指すASEANの取り組みなど、幅広い視点から意見が交わされた。
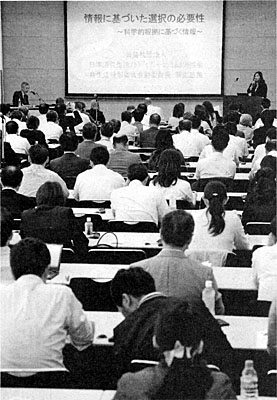
「民間投資」喚起する試金石
莫大なコスト 新規参入に高い壁
■成長戦略のひとつ
わが国では、薬事法などの諸法規制により、一般の食品について、栄養成分の機能や特定の保健目的への期待などに関する表示は禁止されている。食品の中でも、1991年に設立された「特定保健用食品」は、ヒトでの試験で有効性と安全性が確認された上で、国から許可を得て特定の保健の用途に資する旨を表示できる。また、2001年設立の「栄養機能食品」制度で、12種類のビタミンとミネラルのいずれかが一定量含まれれば、厚生労働省に届け出や申請をしなくても栄養素の機能を表示できる。
しかし、栄養機能食品の成分は限られ、特定保健用食品の申請には、成分ごとではなく、製品ごとに行わなければならず、時間(4~5年)もコスト(2億~3億円)もかかる。中小企業にとっては負担が重く、商品開発などの新規参入には高い壁があった。
一方、消費者側にも、情報量が少ないゆえにどの食品を選べば良いのか、判断に迷うケースも見られていた。いわゆる健康食品の分野の製品には、売り上げが特定保健用食品より多いにもかかわらず、きちんとした規制がない。この制度を見直し、安倍内閣が打ち出した成長戦略のひとつが栄養補助食品の新たな「機能性表示」制度である。
加藤勝信内閣官房副長官は「既存の企業や他の分野の企業も、さらには海外からも参画する流れを作りたい。単に栄養補助食品だけでなく、農産物や農産加工品も含み、(制度を)進めていくことで食育分野といった分野も出てくると思う。そして消費者がきちんと選択できる情報をどう提供していくのか。日本の平均寿命に対して健康寿命は、男性が約7歳、女性は約10歳短い。健康長寿を延仰していただく意味でも、目らの健康管理をしていただける環境作りは非常に大事なことである。政権としても積極的に推進していきたい」と述べた。
ただし、既存の法規制の仕組みは複雑だ。機能性表示が新たに拡大された場合、その表示内容によっては、薬事法などの別の法律の規制がかかることがある。栄養補助食品を企業が開発しても、薬と見なされれば商品を市場に出すのは難しくなる。
加藤宣房副長官は「企業が立案した計画が何かの法律に触れるか、触れないか、規制官庁に照会して具体的な判断を出し、安心して投資できる仕組みとして、産業競争力強化法を経済産業省が今国会で提出することになっています」と語った。
■各国の制度状況
米国ては1994年に「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」による構造・機能強調表示の制度がスタートしており、
①構造・機能強調表示
②健康強調表示
③限定的健康強調表示
④栄養成分含有表示
の法律で認められ、身体の構造や機能に及ぼす栄養補助食品の使用目的、利点などを示すことができる。
この制度についてレンド・アルモンディリー氏は「サプリメント(栄養補助食品)メーカーは包括的に強力に規制されている」ことを強調、米食品医薬品局(FDA)と米連邦取引委員会(FTC)が緊密な連米サプリメント業界強力に規制携を行い、制度の4つの柱となる
①安全性の担保
②商品製造における品質の担保
③正確、真実、かつ有効な成分ラペル
④有害情報の報告
を管理していると言う。
しかし、それは単に法規制に頼るにとどまらない。
「米国栄養評議会(CRN)では、2006年にサプリメント広告見直しプログラムを作り、業界の自主規制を後押ししています。自主規制は非常に重要で、消費者の信頼性が増し、メーカーの公平な競争も促進できる。怪しい表示をひとらずつチェックする必要がなくなるため、政府機関の負担も大幅に減らすことができます」とアルモンディリー氏は指摘する。強力な自主規制は、投資を促進し、米国の経済を支え、国際貿易力も促進すると語り、さらには、「疾病を予防し、健康を増進するため、国の医療費を下げるかもしれません」との見解を述べた。
一方、2015年に単一市場を形成する予定のASEAN(東南アジア諸国連合)でも、加盟10力国が健康補助食品を重要な経済分野と位置づけ、ワーキンググループが今年度をめどに各国の技術的な障壁をなくし、消費者の安全性を害することなく通商を行うガイドラインの策定を行っていることをズバイダ・マフムード氏が説明。すでにガイドラインはできており、今年11月開催のワーキンググループの会議「第20回TMHSPWG」で承認されると、「健康補助食品に関するASEAN協定」に盛り込まれることになる。
「もともとASEAN各国には違うシステムがあり、疾病に関する考え方にも差がある。表示に関して言えば、一般表示、疾病リスク低減表示、構造機能の表示について、有効性データのガイダンスと、実証に必要な情報を盛り込むガイドラインを一つにしました。11月にこのガイドラインが盛り込まれると、ASEANモデルは世界初となり加盟国が共同な立場で実施できる体制が整います」とした。
複数の国が集まると、制度を統一するのは難しいこともある。
28力国が加盟しているEU(欧州連合)では、加盟国の相違により、機能表示の法規制の統一がスムーズに進んでいるとはいえないことを、パトリック・コッペン氏が紹介した。
「EUでは、栄養強調表示や健康強調表示において、非常に高い基準での科学的な根拠がなければなりません。2006年に制度が導入されましたが、2010年の段階で、表示の約50%は保留されており、他の国のような高い水準での制度は実現していない。申請コストがかかるためEUでは中小企業は申請できず、新しい手法に投資しようとしても拒絶され、イノベーションが生じにくい状況です。どの程度柔軟な表示を許すか、EUでは協議を重ねていますが、栄養素の統一は調整するのが難しい」と語った。
■米国を参考 一般農水産物も視野
日本の新たな制度
わが国では、今年6月14日に閣議決定された日本再興戦略の方針に基づき、2015年3月末までに新たな機能性表示を実施する予定だ。参考にするのは、すでに包括的で強力な制度となっている米国の栄養補助食品制度である。
その策定に関わる消費者庁の塩澤信良氏は、新たな制度について「一定のルールの下、企業の責任で機能性表示を行えるようになります。栄養補助食品に加えて一般農水産物についても機能性表示ができるようになり、これは世界初の制度となる」との認識を示した上で、次のような課題も挙げた。
①完全性をどのように確保していくか②機能性表示を行う際の有効性に対する科学的根拠をどう考えていくか③消費者に誤解を招かない表示にする④機能性表示の範囲について、米国の栄養補助食品制度のように、「骨の健康を維持します」といった疾病リスク低減の表示も認めるのか⑤企業の届け出制度をどうするのか。
課題が山積みの中、塩澤氏は「今年度に、まず①と②の課題を検討し、基礎資料を得るために消費者意向調査を行う予定にしています。機能性表示を誤認しやすい一般消費者を対象に、どのような表示が分かりやすいのか、最低でもどの程度の科学的根拠が必要か、一般消費者の情報を得て新たな制度を作り、有識者の検討の場で審議していただき、制度設計につなげていきたい」と語った。
機能性表示にはいろいろな種類があり、「心疾患を防ぐ」といった疾病低減リスク表示が行われる場合には、効能効果の表示が厚労省の薬事法に抵触する可能性もある。米国では、FDAとFTCが合同カンファレンスによる連携を密にしているが、日本では消費者庁と厚労省の連携をどう確保するのかも今後課題となる。
各国で機能性表示制度が進められる中、日本の新たな制度はどうあるべきか。
「日本法規制シンポジウム」によってさまざまな意見が交わされたことで、「それを生かしてほしい」と在日米国商工会議所ダイエタリー・サプリメント委員会の天ケ瀬晴信氏は訴え、自らの米国での経験をもとに次のようにシンポジウムをまとめた。
「米国では94年に新しい表示制度が導入され、きちんとしたガイドラインにより産業が発展していく熱気を感じました。今の日本も同じ気がします。米国では規制ができてから3年ぐらいたって、消費者やメディアから批判が相次いだ時期もありました。安全性や品質を確保できない状況があったからです。それらを踏まえて米国では20年かけて培ってきた栄養補助食品に対する表示制度のノウハウがあり、日本はそのいいとこ取りができる。品質や安全性、機能性などを担保しつつ、新たな表示制度ができるのではないかと思っています」
■参加者一覧
○末木一夫氏(社団法人国際栄養食品協会専務理事)
○蒲生恵美氏(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会食生活特別委員会副委員長)
○塩湯信良氏(消費者庁・食品表示企画課食品表示調査官)
○関口洋一氏(健康食品産業協議会会長/日本水産株式会社執行役員)
○森下竜一氏(大阪大学大学院医学研究科臨床遺伝子治療学寄付講座教授)
○加藤勝信氏(内閣官房副長官)
○マンフレッド・エッガースドルファー氏(グローニングン大学健康加齢医療センター教授)
○パトリック・コッペン氏(欧州栄養補助食品協会科学ディレクター/常任理事)
○レンド・アルモンディリー氏(弁護士/米国栄養評議会法務担当)
○ズバイダ・マフムード氏(ASEAN経済統合サプリメント作業部会科学委員会委員長/ブルネイ厚生省医薬品サービス局上級科学担当官)
○天ケ瀬晴信氏(在日米国商工会議所ダイエタリー・サプリメント委員会委員長/社団法人国際栄養食品協会理事)
※氏名は講演順
《企画・制作》産経新聞社生活情報センター
産経新聞 2013年10月23日
日本の法規制公開シンポジウム
10月7日、「日本における栄養補助食品有用性の消費者理解促進を目的とした表示拡大のための政策検討会」をテーマとしたシンポジウムが、国際栄養食品協会(略称AIFN)および在日米国商工会議所(ACCJ)の主催で開催された。デフレ脱却で安倍晋三首相が打ち出した三本の矢のひとつ「民間投資を喚起する成長戦略」の一環として、栄養補助食品に対する機能性表示拡大が2015年末までに行われることを受け、既にシステムを構築している米国栄養補助食品(ダイエタリー・サプリメント)制度や、米国とは異なる制度のEUにおける機能性表示と問題点、2015年までに単一市場の形成を目指すASEANの取り組みなど、幅広い視点から意見が交わされた。
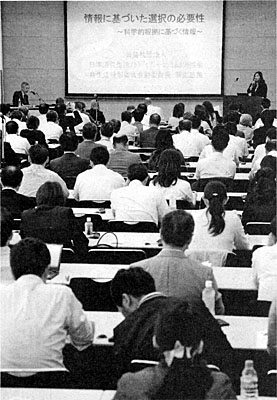
「民間投資」喚起する試金石
莫大なコスト 新規参入に高い壁
■成長戦略のひとつ
わが国では、薬事法などの諸法規制により、一般の食品について、栄養成分の機能や特定の保健目的への期待などに関する表示は禁止されている。食品の中でも、1991年に設立された「特定保健用食品」は、ヒトでの試験で有効性と安全性が確認された上で、国から許可を得て特定の保健の用途に資する旨を表示できる。また、2001年設立の「栄養機能食品」制度で、12種類のビタミンとミネラルのいずれかが一定量含まれれば、厚生労働省に届け出や申請をしなくても栄養素の機能を表示できる。
しかし、栄養機能食品の成分は限られ、特定保健用食品の申請には、成分ごとではなく、製品ごとに行わなければならず、時間(4~5年)もコスト(2億~3億円)もかかる。中小企業にとっては負担が重く、商品開発などの新規参入には高い壁があった。
一方、消費者側にも、情報量が少ないゆえにどの食品を選べば良いのか、判断に迷うケースも見られていた。いわゆる健康食品の分野の製品には、売り上げが特定保健用食品より多いにもかかわらず、きちんとした規制がない。この制度を見直し、安倍内閣が打ち出した成長戦略のひとつが栄養補助食品の新たな「機能性表示」制度である。
加藤勝信内閣官房副長官は「既存の企業や他の分野の企業も、さらには海外からも参画する流れを作りたい。単に栄養補助食品だけでなく、農産物や農産加工品も含み、(制度を)進めていくことで食育分野といった分野も出てくると思う。そして消費者がきちんと選択できる情報をどう提供していくのか。日本の平均寿命に対して健康寿命は、男性が約7歳、女性は約10歳短い。健康長寿を延仰していただく意味でも、目らの健康管理をしていただける環境作りは非常に大事なことである。政権としても積極的に推進していきたい」と述べた。
ただし、既存の法規制の仕組みは複雑だ。機能性表示が新たに拡大された場合、その表示内容によっては、薬事法などの別の法律の規制がかかることがある。栄養補助食品を企業が開発しても、薬と見なされれば商品を市場に出すのは難しくなる。
加藤宣房副長官は「企業が立案した計画が何かの法律に触れるか、触れないか、規制官庁に照会して具体的な判断を出し、安心して投資できる仕組みとして、産業競争力強化法を経済産業省が今国会で提出することになっています」と語った。
■各国の制度状況
米国ては1994年に「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」による構造・機能強調表示の制度がスタートしており、
①構造・機能強調表示
②健康強調表示
③限定的健康強調表示
④栄養成分含有表示
の法律で認められ、身体の構造や機能に及ぼす栄養補助食品の使用目的、利点などを示すことができる。
この制度についてレンド・アルモンディリー氏は「サプリメント(栄養補助食品)メーカーは包括的に強力に規制されている」ことを強調、米食品医薬品局(FDA)と米連邦取引委員会(FTC)が緊密な連米サプリメント業界強力に規制携を行い、制度の4つの柱となる
①安全性の担保
②商品製造における品質の担保
③正確、真実、かつ有効な成分ラペル
④有害情報の報告
を管理していると言う。
しかし、それは単に法規制に頼るにとどまらない。
「米国栄養評議会(CRN)では、2006年にサプリメント広告見直しプログラムを作り、業界の自主規制を後押ししています。自主規制は非常に重要で、消費者の信頼性が増し、メーカーの公平な競争も促進できる。怪しい表示をひとらずつチェックする必要がなくなるため、政府機関の負担も大幅に減らすことができます」とアルモンディリー氏は指摘する。強力な自主規制は、投資を促進し、米国の経済を支え、国際貿易力も促進すると語り、さらには、「疾病を予防し、健康を増進するため、国の医療費を下げるかもしれません」との見解を述べた。
一方、2015年に単一市場を形成する予定のASEAN(東南アジア諸国連合)でも、加盟10力国が健康補助食品を重要な経済分野と位置づけ、ワーキンググループが今年度をめどに各国の技術的な障壁をなくし、消費者の安全性を害することなく通商を行うガイドラインの策定を行っていることをズバイダ・マフムード氏が説明。すでにガイドラインはできており、今年11月開催のワーキンググループの会議「第20回TMHSPWG」で承認されると、「健康補助食品に関するASEAN協定」に盛り込まれることになる。
「もともとASEAN各国には違うシステムがあり、疾病に関する考え方にも差がある。表示に関して言えば、一般表示、疾病リスク低減表示、構造機能の表示について、有効性データのガイダンスと、実証に必要な情報を盛り込むガイドラインを一つにしました。11月にこのガイドラインが盛り込まれると、ASEANモデルは世界初となり加盟国が共同な立場で実施できる体制が整います」とした。
複数の国が集まると、制度を統一するのは難しいこともある。
28力国が加盟しているEU(欧州連合)では、加盟国の相違により、機能表示の法規制の統一がスムーズに進んでいるとはいえないことを、パトリック・コッペン氏が紹介した。
「EUでは、栄養強調表示や健康強調表示において、非常に高い基準での科学的な根拠がなければなりません。2006年に制度が導入されましたが、2010年の段階で、表示の約50%は保留されており、他の国のような高い水準での制度は実現していない。申請コストがかかるためEUでは中小企業は申請できず、新しい手法に投資しようとしても拒絶され、イノベーションが生じにくい状況です。どの程度柔軟な表示を許すか、EUでは協議を重ねていますが、栄養素の統一は調整するのが難しい」と語った。
■米国を参考 一般農水産物も視野
日本の新たな制度
わが国では、今年6月14日に閣議決定された日本再興戦略の方針に基づき、2015年3月末までに新たな機能性表示を実施する予定だ。参考にするのは、すでに包括的で強力な制度となっている米国の栄養補助食品制度である。
その策定に関わる消費者庁の塩澤信良氏は、新たな制度について「一定のルールの下、企業の責任で機能性表示を行えるようになります。栄養補助食品に加えて一般農水産物についても機能性表示ができるようになり、これは世界初の制度となる」との認識を示した上で、次のような課題も挙げた。
①完全性をどのように確保していくか②機能性表示を行う際の有効性に対する科学的根拠をどう考えていくか③消費者に誤解を招かない表示にする④機能性表示の範囲について、米国の栄養補助食品制度のように、「骨の健康を維持します」といった疾病リスク低減の表示も認めるのか⑤企業の届け出制度をどうするのか。
課題が山積みの中、塩澤氏は「今年度に、まず①と②の課題を検討し、基礎資料を得るために消費者意向調査を行う予定にしています。機能性表示を誤認しやすい一般消費者を対象に、どのような表示が分かりやすいのか、最低でもどの程度の科学的根拠が必要か、一般消費者の情報を得て新たな制度を作り、有識者の検討の場で審議していただき、制度設計につなげていきたい」と語った。
機能性表示にはいろいろな種類があり、「心疾患を防ぐ」といった疾病低減リスク表示が行われる場合には、効能効果の表示が厚労省の薬事法に抵触する可能性もある。米国では、FDAとFTCが合同カンファレンスによる連携を密にしているが、日本では消費者庁と厚労省の連携をどう確保するのかも今後課題となる。
各国で機能性表示制度が進められる中、日本の新たな制度はどうあるべきか。
「日本法規制シンポジウム」によってさまざまな意見が交わされたことで、「それを生かしてほしい」と在日米国商工会議所ダイエタリー・サプリメント委員会の天ケ瀬晴信氏は訴え、自らの米国での経験をもとに次のようにシンポジウムをまとめた。
「米国では94年に新しい表示制度が導入され、きちんとしたガイドラインにより産業が発展していく熱気を感じました。今の日本も同じ気がします。米国では規制ができてから3年ぐらいたって、消費者やメディアから批判が相次いだ時期もありました。安全性や品質を確保できない状況があったからです。それらを踏まえて米国では20年かけて培ってきた栄養補助食品に対する表示制度のノウハウがあり、日本はそのいいとこ取りができる。品質や安全性、機能性などを担保しつつ、新たな表示制度ができるのではないかと思っています」
■参加者一覧
○末木一夫氏(社団法人国際栄養食品協会専務理事)
○蒲生恵美氏(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会食生活特別委員会副委員長)
○塩湯信良氏(消費者庁・食品表示企画課食品表示調査官)
○関口洋一氏(健康食品産業協議会会長/日本水産株式会社執行役員)
○森下竜一氏(大阪大学大学院医学研究科臨床遺伝子治療学寄付講座教授)
○加藤勝信氏(内閣官房副長官)
○マンフレッド・エッガースドルファー氏(グローニングン大学健康加齢医療センター教授)
○パトリック・コッペン氏(欧州栄養補助食品協会科学ディレクター/常任理事)
○レンド・アルモンディリー氏(弁護士/米国栄養評議会法務担当)
○ズバイダ・マフムード氏(ASEAN経済統合サプリメント作業部会科学委員会委員長/ブルネイ厚生省医薬品サービス局上級科学担当官)
○天ケ瀬晴信氏(在日米国商工会議所ダイエタリー・サプリメント委員会委員長/社団法人国際栄養食品協会理事)
※氏名は講演順
《企画・制作》産経新聞社生活情報センター
産経新聞 2013年10月23日