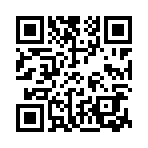2015年04月24日
水素研究は科学か非科学か・健康長寿医療センター
東京都健康長寿医療センターは24日、板橋区立文化会館で『水素研究は科学か非科学か』と題して講演を開催し、約190名の参加者があった。この講演は、同センターが平成27年度科学技術週間参加行事として研究を紹介するもので、合わせて9つの研究チームの活動もポスター発表した。
 講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。
講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。
研究者は、正確なデータを集めて検証し、再現性があることが大切である。客観性の追求・偏向の回避、例えば研究費の出どころである資金源によって、結果が左右されてはならない。
活性酸素種とフリーラジカルの生理機能

水素分子とは?
水素分子は反応性の高い活性酸素種のみ還元

最少分子H2の高い透過力と早い拡散速度、水素分子のヒドロキシラジカル除去による虚血性再灌流障害抑制、水素水とは?水に水素分子(H2)を溶かしたもの、水素水を飲むとH2はすぐに体外へ、水素水による糖尿病の抑制(臨床研究)、水素水によるパーキンソン病の治療(臨床研究)、多彩な効果を示す水素水、などについて解説した。

最後に、水素について以下のようにまとめた。
1)水素分子の生理作用は科学的に検証された
2)水素ガスは虚血性再灌流障害で効果大
3)水素水の飲用は抗酸化・抗炎症治療の新たな手段
4)人での科学的検証はさらに多くの研究が必要
5)作用機序は未だ不明な点が多い
これら資料は日医大の太田成男教授と、名古屋大学の大野欽司教授による研究を中心に紹介した。

主催:地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

東京都福祉保健局 案内チラシ
 講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。
講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。研究者は、正確なデータを集めて検証し、再現性があることが大切である。客観性の追求・偏向の回避、例えば研究費の出どころである資金源によって、結果が左右されてはならない。
活性酸素種とフリーラジカルの生理機能

水素分子とは?
水素分子は反応性の高い活性酸素種のみ還元

最少分子H2の高い透過力と早い拡散速度、水素分子のヒドロキシラジカル除去による虚血性再灌流障害抑制、水素水とは?水に水素分子(H2)を溶かしたもの、水素水を飲むとH2はすぐに体外へ、水素水による糖尿病の抑制(臨床研究)、水素水によるパーキンソン病の治療(臨床研究)、多彩な効果を示す水素水、などについて解説した。

最後に、水素について以下のようにまとめた。
1)水素分子の生理作用は科学的に検証された
2)水素ガスは虚血性再灌流障害で効果大
3)水素水の飲用は抗酸化・抗炎症治療の新たな手段
4)人での科学的検証はさらに多くの研究が必要
5)作用機序は未だ不明な点が多い
これら資料は日医大の太田成男教授と、名古屋大学の大野欽司教授による研究を中心に紹介した。

講演資料より
主催:地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

東京都福祉保健局 案内チラシ
2014年04月09日
ハウステンボス認知症セミナー「認知症の予防と改善」
日本最大のウェルネスリゾート・ハウステンボスで認知症セミナーが開催されました。認知症予防に効果が期待できる有酸素ウォーキングやリズミック体操などの体験プログラムも実施され、3月2日は満席の約60名ほどが聴講しました。

認知症予防研究の第一人者による特別講義の概要は以下の通りです。
■認知症は予防できる
田平武 (たびらたけし)氏
順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学講座客員教授(非常勤)、河村病院認知症診断・予防・治療センター長
日本では認知症の7割がアルツハイマー病で、発病の20年前から始まっています。治療薬があるものの改善することは難しく、現状では進行をとどめることしかできません。
したがって「なってからでは遅い」ので、予防に努めることが大切です。大きな危険因子として老化があります。時間的経過の加齢は万人に平等ですが、老化は個人差があります。日常生活の食事と運動によって、老化を遅らせることができます。加齢は避けられませんが、老化はコントロールできます。これがアンチエイジングです。
体を良く動かし、何事にも興味を持って積極的な生活をする。中ぐらいの運動をよくした人は軽度認知障害(MCI)が少ないことが統計的にわかっています。また、ワシントン州の日系人を10年間追跡したところ、果物や野菜ジュースがアルツハイマー病のリスクを下げることがわかりました。フランスのボルドー地域の調査で、魚をまったく食べない人は、1日に1回以上食べる人より5.3倍もアルツハイマー病になりやすくなります。
ビタミンEをよく摂る人は、アルツハイマー病になる危険率が、1/2から1/3に下がります。
最後に、ストレスがアルツハイマー病の大きな要因になるので、自分自身でコントロールすることが大切です。
・笑うこと
・気分転換すること
・心身一如につとめること
・手っ取り早くは呼吸法

■アルツハイマー予防の最前線
- 認知症は改善できる -
長谷川亨(はせがわとおる)氏
佐賀女子短期大学名誉教授、医学博士
株式会社MRD研究所 代表取締役
近年のアルツハイマー病研究は、脳にアミロイドと呼ばれる老人班が増えることに注目して、世界の有力な製薬会社は巨額の研究費を投じて、アミロイド仮説に基づいた治療薬やワクチンの開発、臨床試験を行いました。
しかし2008年に米国シカゴで開催されたアルツハイマー病国際会議で、臨床試験の失敗が報告されたのです。「確かにアミロイドの量は減ったものの、肝心の認知機能の回復は見られなかった」。そればかりか、悪化する例も出たのです。
私と田平先生もその会議に出席し、多くの研究者がショックを受けている様子を目撃しました。それ以来、アルツハイマー病の「アミロイド仮説」が揺らぎだしたのです。
そこで私たちは別のアプローチを試みました。血液中のホモシステイン酸濃度と、認知機能の指標となるMMSEスコアに相関があることを突き止めました。さらにホモシステイン酸が血液中から尿に排出される人ほど認知機能の回復が見られました。
問題は血液中のホモシステイン酸をどう下げるかです。いくつかの食品で認知症が改善することがわかっています。さらに水素に還元作用がある論文に注目して、これらをブレンドした水素ブレインフード(HBF)を開発しました。
これをある特養施設に協力いただいて試したところ、重症患者の認知機能が改善してきました。また別の例では、ほぼ植物状態で入院していた若年性アルツハイマー病の患者が、水素サプリと水素ブレインフードを食べて数カ月したら、話しができ、意思を伝えられるようにまでなりました。
ほかにも認知機能の変化についてN式老年者用精神状態尺度(NMスケール)で評価したところ、50名のうち多くの人に改善が見られました。
年をとっても自分の家族を認識できて、会話ができる。自分の家で家族と共に静かに余生を送れることで、本人も家族も満足をえられます。認知症は予防もできるし、改善もできる可能性があるので希望を持っていただきたい。
■水素の可能性
若山利文氏
水素は元素周期表の一番目にあり、最も小さい物質です。体内で活性酸素は、肉体を老化させ、さまざまな病気の原因にもなります。なかでも一番の悪玉活性酸素である『ヒドロキシルラジカル』に水素は反応して、体内で無害な水に変化します。
水素は小さいので細胞そのものに染み込みます。ですから血液脳関門によって薬などが到達しにくい脳にも入っていきます。そうした先で活性酸素を除去するので、さまざまな生理効果が臨床報告されています。
昨年9月に、第9回認知症サプリメント研究会で『水素ブレインフード』が発表され、従来の認知症対策にそったアプローチとして注目されています。予防にはもちろん改善した事例が長谷川先生より報告されました。
わりとよく知られるようになった水素水も良いのですが、水には1.6ppmしか水素は存在できません。その点、サンゴカルシウムを焼成して水素を閉じ込めると、体内の水分と反応して水素が発生します。ちょうどマラソン選手のように長い間ずうっと体内で水素を発生し続けるのが強みです。たとえば眠っている間は水素水を飲み続けることは出来ませんが、水素サプリメントだと、体内に水素が存在し続けることができます。
今後も水素の研究が進み、みなさんの健康に役立てればと願います。
[主催] ハウステンボス
[協賛] TBソアラメディカル

ハウステンボス認知症セミナー
佐世保市のテーマパーク、ハウステンボスでは、医療と観光を組み合わせた新しいツアーでの観光客の招致を進めようと、2月28日、初めて認知症の予防について学べるセミナーを開きました。
ハウステンボスでは、従来型の観光に加え、東洋医学と西洋医学を合わせた医療を提供する「医療観光」の事業を展開し国の内外からの観光客の誘致を進めています。
きょうはこの事業の一環として初めて、認知症の予防をテーマとした4つのセミナーが開かれました。
このうち、認知症の予防に効果があるとされるリズムを取りながら体を動かす体操のセミナーでは、参加者たちが健康運動指導士の手ほどきで手足の筋肉を伸ばし心地よさそうに体をほぐしていました。
また、有酸素ウォーキングというセミナーでは、参加者が両足を拳ほどの間隔で開いてかかとからまっすぐ前に踏み出すという正しい歩き方を講師から教えてもらいながらリラックスしたひとときを過ごしていました。
福岡市から参加した60代の主婦は「ハウステンボスの年間会員になっていて、内容が良さそうので参加しました」と話していました。
初回の認知症予防セミナーは、3月6日まで開かれます。
ハウステンボスの高田孝太郎執行役員は「病気を防ぐ医療をテーマパークでのホテルの滞在と組み合わせることで観光客の増加につなげていきたい」と話しています。
NHK長崎 02月28日
http://www.nhk.or.jp/nagasaki/lnews/5035194181.html
【PDFダウンロード】

認知症予防研究の第一人者による特別講義の概要は以下の通りです。
■認知症は予防できる
田平武 (たびらたけし)氏
順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学講座客員教授(非常勤)、河村病院認知症診断・予防・治療センター長
日本では認知症の7割がアルツハイマー病で、発病の20年前から始まっています。治療薬があるものの改善することは難しく、現状では進行をとどめることしかできません。
したがって「なってからでは遅い」ので、予防に努めることが大切です。大きな危険因子として老化があります。時間的経過の加齢は万人に平等ですが、老化は個人差があります。日常生活の食事と運動によって、老化を遅らせることができます。加齢は避けられませんが、老化はコントロールできます。これがアンチエイジングです。
体を良く動かし、何事にも興味を持って積極的な生活をする。中ぐらいの運動をよくした人は軽度認知障害(MCI)が少ないことが統計的にわかっています。また、ワシントン州の日系人を10年間追跡したところ、果物や野菜ジュースがアルツハイマー病のリスクを下げることがわかりました。フランスのボルドー地域の調査で、魚をまったく食べない人は、1日に1回以上食べる人より5.3倍もアルツハイマー病になりやすくなります。
ビタミンEをよく摂る人は、アルツハイマー病になる危険率が、1/2から1/3に下がります。
最後に、ストレスがアルツハイマー病の大きな要因になるので、自分自身でコントロールすることが大切です。
・笑うこと
・気分転換すること
・心身一如につとめること
・手っ取り早くは呼吸法

■アルツハイマー予防の最前線
- 認知症は改善できる -
長谷川亨(はせがわとおる)氏
佐賀女子短期大学名誉教授、医学博士
株式会社MRD研究所 代表取締役
近年のアルツハイマー病研究は、脳にアミロイドと呼ばれる老人班が増えることに注目して、世界の有力な製薬会社は巨額の研究費を投じて、アミロイド仮説に基づいた治療薬やワクチンの開発、臨床試験を行いました。
しかし2008年に米国シカゴで開催されたアルツハイマー病国際会議で、臨床試験の失敗が報告されたのです。「確かにアミロイドの量は減ったものの、肝心の認知機能の回復は見られなかった」。そればかりか、悪化する例も出たのです。
私と田平先生もその会議に出席し、多くの研究者がショックを受けている様子を目撃しました。それ以来、アルツハイマー病の「アミロイド仮説」が揺らぎだしたのです。
そこで私たちは別のアプローチを試みました。血液中のホモシステイン酸濃度と、認知機能の指標となるMMSEスコアに相関があることを突き止めました。さらにホモシステイン酸が血液中から尿に排出される人ほど認知機能の回復が見られました。
問題は血液中のホモシステイン酸をどう下げるかです。いくつかの食品で認知症が改善することがわかっています。さらに水素に還元作用がある論文に注目して、これらをブレンドした水素ブレインフード(HBF)を開発しました。
これをある特養施設に協力いただいて試したところ、重症患者の認知機能が改善してきました。また別の例では、ほぼ植物状態で入院していた若年性アルツハイマー病の患者が、水素サプリと水素ブレインフードを食べて数カ月したら、話しができ、意思を伝えられるようにまでなりました。
ほかにも認知機能の変化についてN式老年者用精神状態尺度(NMスケール)で評価したところ、50名のうち多くの人に改善が見られました。
年をとっても自分の家族を認識できて、会話ができる。自分の家で家族と共に静かに余生を送れることで、本人も家族も満足をえられます。認知症は予防もできるし、改善もできる可能性があるので希望を持っていただきたい。
■水素の可能性
若山利文氏
水素は元素周期表の一番目にあり、最も小さい物質です。体内で活性酸素は、肉体を老化させ、さまざまな病気の原因にもなります。なかでも一番の悪玉活性酸素である『ヒドロキシルラジカル』に水素は反応して、体内で無害な水に変化します。
水素は小さいので細胞そのものに染み込みます。ですから血液脳関門によって薬などが到達しにくい脳にも入っていきます。そうした先で活性酸素を除去するので、さまざまな生理効果が臨床報告されています。
昨年9月に、第9回認知症サプリメント研究会で『水素ブレインフード』が発表され、従来の認知症対策にそったアプローチとして注目されています。予防にはもちろん改善した事例が長谷川先生より報告されました。
わりとよく知られるようになった水素水も良いのですが、水には1.6ppmしか水素は存在できません。その点、サンゴカルシウムを焼成して水素を閉じ込めると、体内の水分と反応して水素が発生します。ちょうどマラソン選手のように長い間ずうっと体内で水素を発生し続けるのが強みです。たとえば眠っている間は水素水を飲み続けることは出来ませんが、水素サプリメントだと、体内に水素が存在し続けることができます。
今後も水素の研究が進み、みなさんの健康に役立てればと願います。
[主催] ハウステンボス
[協賛] TBソアラメディカル

ハウステンボス認知症セミナー
佐世保市のテーマパーク、ハウステンボスでは、医療と観光を組み合わせた新しいツアーでの観光客の招致を進めようと、2月28日、初めて認知症の予防について学べるセミナーを開きました。
ハウステンボスでは、従来型の観光に加え、東洋医学と西洋医学を合わせた医療を提供する「医療観光」の事業を展開し国の内外からの観光客の誘致を進めています。
きょうはこの事業の一環として初めて、認知症の予防をテーマとした4つのセミナーが開かれました。
このうち、認知症の予防に効果があるとされるリズムを取りながら体を動かす体操のセミナーでは、参加者たちが健康運動指導士の手ほどきで手足の筋肉を伸ばし心地よさそうに体をほぐしていました。
また、有酸素ウォーキングというセミナーでは、参加者が両足を拳ほどの間隔で開いてかかとからまっすぐ前に踏み出すという正しい歩き方を講師から教えてもらいながらリラックスしたひとときを過ごしていました。
福岡市から参加した60代の主婦は「ハウステンボスの年間会員になっていて、内容が良さそうので参加しました」と話していました。
初回の認知症予防セミナーは、3月6日まで開かれます。
ハウステンボスの高田孝太郎執行役員は「病気を防ぐ医療をテーマパークでのホテルの滞在と組み合わせることで観光客の増加につなげていきたい」と話しています。
NHK長崎 02月28日
http://www.nhk.or.jp/nagasaki/lnews/5035194181.html
【PDFダウンロード】
2014年03月14日
国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業
健康博覧会2014セミナー/シンポジウム
2014年3月14日
[機能性表示ガイドライン]
国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業
来年3月を目途に進む食品の機能性表示制度、一方で全国各地でも食品の機能性に関する新たな制度設計の試みが進み、食品機能性に取り組む20近い地方自治体、経済団体、支援機関による食品地方連絡会が結成されました。
食品機能性表示改革は全国の食品産業にどのような効果をもたらすのでしょうか?政府の司令塔を招き現状をお聞きします。
主催:食品機能性地方連絡会 協賛:UBMメディア
動きだした機能性表示
-最新情報-
内閣府 規制改革会議委員
内閣官房 健康・医療戦略水深本部 戦略参与
大阪府市統合本部 医療戦略参与
大阪大学大学院医学系研究科
森下竜一氏


いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認
特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。
平成25年度検討・平成26年度結論・措置(加工食品・農林水産物とも)
消費者庁・厚生労働省・農林水産省
食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
(消費者庁 平成25年12月17日)
目的
これらの閣議決定を受け、消費者庁長官のもと「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催し、特定保健用食品制度及び栄養機能食品制度を維持しつつ、企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、検討を行うこととする。
検討項目
(1)食品の新たな機能性表示制度に係る安全性確保の在り方
(2)食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方
(3)消費者にとって誤認のない食品の機能性表示の方法の在り方
スケジュール及び今後の進め方
現行の食品の機能性表示制度や米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を始めとする海外の食品表示制度の現状等を踏まえ、関係者からのヒアリング等を行いつつ検討を進め、平成26年夏を目途に報告書を取りまとめる。



大きな4分野の構成要素
4本足の椅子のような規則
1.成分や原料の安全性・製品中の成分の安全性の確保
2.製造基準-品質の確保
3.表示とクレーム・表示は正確で真実であり、成分は効果があること
4.有害作用報告-製品の安全性は市販後調査でモニターされている

次世代ヘルスケア協議会
主旨
健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のQOL(生活の豊かさ)の向上、国民医療費の抑制、雇用拡大及び我が国経済の成長に資するものと考えられます。このため、健康寿命延伸分野における民間の様々な製品やサービスの実態を把握し、供給・需要の両面から課題や問題点を抽出・整理し、対応策を検討するため、官民一体となって具体的な対応策の検討を行う場として同協議会を設置します。
主な検討事項
・新たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備(グレーゾーン解消等)
・健康関連サービス・製品の品質評価の在り方
・企業、個人等の健康投資を促進するための方策 等
(経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課)
成長戦略第3弾スピーチ
平成25年6月5日
健康食品の機能性表示を、解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです。
現在は、国から「トクホ」の認定を受けなければ、「強い骨をつくる」といった効果を商品に記載できません。お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう。
アメリカでは、国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば、商品に機能性表示を行うことができます。国へは事後に届出をするだけでよいのです。
今回の解禁は、単に、世界と制度をそろえるだけにとどまりません。農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思います。
目指すのは、「世界並み」ではありません。むしろ、「世界最先端」です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現。それが安倍内閣の基本方針です。

UBMメディア㈱代表取締役 牧野順一氏のコメント
「やっぱり(製品そのものに)エビデンスがないものは、そうそう(機能性を)言えないんです」
【関連記事】
食品機能性研究の新しい動き
農研機構食品総合研究所 山本(前田)万里
一般財団法人食品分析開発セン ターSUNATEC
http://www.mac.or.jp/mail/131001/02.shtml
食の安心・安全に関する情報
健康食品の機能性表示について考える
長村 洋一(鈴鹿医療科学大学)
日本食品安全協会会報 第8巻 第4号 2013年
http://www.ffcci.jp/information/img/kaiho2_8-4.pdf
2014年3月14日
[機能性表示ガイドライン]
国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業
来年3月を目途に進む食品の機能性表示制度、一方で全国各地でも食品の機能性に関する新たな制度設計の試みが進み、食品機能性に取り組む20近い地方自治体、経済団体、支援機関による食品地方連絡会が結成されました。
食品機能性表示改革は全国の食品産業にどのような効果をもたらすのでしょうか?政府の司令塔を招き現状をお聞きします。
主催:食品機能性地方連絡会 協賛:UBMメディア
動きだした機能性表示
-最新情報-
内閣府 規制改革会議委員
内閣官房 健康・医療戦略水深本部 戦略参与
大阪府市統合本部 医療戦略参与
大阪大学大学院医学系研究科
森下竜一氏


いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認
特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。
平成25年度検討・平成26年度結論・措置(加工食品・農林水産物とも)
消費者庁・厚生労働省・農林水産省
食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
(消費者庁 平成25年12月17日)
目的
これらの閣議決定を受け、消費者庁長官のもと「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催し、特定保健用食品制度及び栄養機能食品制度を維持しつつ、企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、検討を行うこととする。
検討項目
(1)食品の新たな機能性表示制度に係る安全性確保の在り方
(2)食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方
(3)消費者にとって誤認のない食品の機能性表示の方法の在り方
スケジュール及び今後の進め方
現行の食品の機能性表示制度や米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を始めとする海外の食品表示制度の現状等を踏まえ、関係者からのヒアリング等を行いつつ検討を進め、平成26年夏を目途に報告書を取りまとめる。



大きな4分野の構成要素
4本足の椅子のような規則
1.成分や原料の安全性・製品中の成分の安全性の確保
2.製造基準-品質の確保
3.表示とクレーム・表示は正確で真実であり、成分は効果があること
4.有害作用報告-製品の安全性は市販後調査でモニターされている

次世代ヘルスケア協議会
主旨
健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のQOL(生活の豊かさ)の向上、国民医療費の抑制、雇用拡大及び我が国経済の成長に資するものと考えられます。このため、健康寿命延伸分野における民間の様々な製品やサービスの実態を把握し、供給・需要の両面から課題や問題点を抽出・整理し、対応策を検討するため、官民一体となって具体的な対応策の検討を行う場として同協議会を設置します。
主な検討事項
・新たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備(グレーゾーン解消等)
・健康関連サービス・製品の品質評価の在り方
・企業、個人等の健康投資を促進するための方策 等
(経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課)
成長戦略第3弾スピーチ
平成25年6月5日
健康食品の機能性表示を、解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです。
現在は、国から「トクホ」の認定を受けなければ、「強い骨をつくる」といった効果を商品に記載できません。お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう。
アメリカでは、国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば、商品に機能性表示を行うことができます。国へは事後に届出をするだけでよいのです。
今回の解禁は、単に、世界と制度をそろえるだけにとどまりません。農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思います。
目指すのは、「世界並み」ではありません。むしろ、「世界最先端」です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現。それが安倍内閣の基本方針です。

UBMメディア㈱代表取締役 牧野順一氏のコメント
「やっぱり(製品そのものに)エビデンスがないものは、そうそう(機能性を)言えないんです」
【関連記事】
食品機能性研究の新しい動き
農研機構食品総合研究所 山本(前田)万里
一般財団法人食品分析開発セン ターSUNATEC
http://www.mac.or.jp/mail/131001/02.shtml
食の安心・安全に関する情報
健康食品の機能性表示について考える
長村 洋一(鈴鹿医療科学大学)
日本食品安全協会会報 第8巻 第4号 2013年
http://www.ffcci.jp/information/img/kaiho2_8-4.pdf
2014年02月24日
新機能性表示制度と専門家による情報発信
食品機能性表示関連の「検討会」や「ガイドライン委員会」も着々と進んでおり、日々新たなニュースが流れて来ており、目が離せない状況です。
4月時点で最も新しい情報をお伝えするセミナー行い、キーパーソンである大阪大学の森下竜一先生に来て頂いてたっぷり話をして戴く事になりました。
4月21日(月) 14:00-17:30 です。
「日本を健康にする!」研究会よりセミナー開催のお知らせ
----------------------------------
第8回機能性食品素材セミナー
『新機能性表示制度と専門家による情報発信』
----------------------------------
2013年6月の規制改革実施計画の閣議決定で、いわゆる「健康食品」の機能性表示制度についての検討が進められることとなりました。
制度が実現されれば、業界の大きな変革や市場拡大が予想され、企業にとっては様々な対応が求められます。
本シンポジウムでは、特別講演にて政府の規制改革会議においても中枢の役割を担っている森下竜一先生にご講演頂き、新機能性表示制度に向けて産学は何をすべきか、また、本研究会の主軸である管理栄養士は専門家として、どのようなアクション、消費者に対しての情報提供等が求められるかを主テーマとし、開催します。
日時:2014年4月21日(月) 14:00-17:30
会場:東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館
参加費:
「日本を健康にする!」研究会会員 10,000円、非会員 12,000円
主催:「日本を健康にする!」研究会
協力:ヘルスビジネスマガジン社
<講演者>
◆特別講演
「健康食品の機能性表示を可能とする法整備(仮)」
大阪大学大学院 医学系研究科 教授 森下竜一氏
◆講演
「申請に向け、管理栄養士に求められる役割(仮)」
愛知学院大学 心身科学部 学部長・教授 大澤俊彦氏
◆講演
「米国制度より学ぶ(仮)」
株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田猛氏
◆総括
東京海洋大学 「食の安全と機能(ヘルスフード科学)に関する研究」プロジェクト
特任教授 矢澤一良氏
-----------------------------------
<お申込方法>
下記URLより参加申込書を印刷して頂き、必要事項をご記入の上、事務局宛にお申込ください。
http://www.nihon-kenko.jp/pdf/20140421.pdf
FAXでのお申込ができない方は以下必要事項を記載の上、申込先メールアドレスへご連絡下さい。
申込先メールアドレス:info@nihon-kenko.jp
<申込メール記載事項>
参加者氏名/セミナー名(第8回機能性食品素材セミナー)/会員又は非会員/
住所/勤務先(又は学校名)/連絡先/メールアドレス
★注意事項★
御申込書を事務局へFAXして頂き、事前振込をして頂きましたら参加証をお送りします。
お申込者が多い場合は先着順に締め切らせて頂きますのでお早めにお申込下さい。
【その他、問合せ先】================
「日本を健康にする!」研究会事務局
株式会社RDサポート 担当:石井、大渕
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-15 D&F御茶ノ水ビル5F
TEL 03-5217-5565(代表) FAX 03-5217-5562
info@nihon-kenko.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月時点で最も新しい情報をお伝えするセミナー行い、キーパーソンである大阪大学の森下竜一先生に来て頂いてたっぷり話をして戴く事になりました。
4月21日(月) 14:00-17:30 です。
「日本を健康にする!」研究会よりセミナー開催のお知らせ
----------------------------------
第8回機能性食品素材セミナー
『新機能性表示制度と専門家による情報発信』
----------------------------------
2013年6月の規制改革実施計画の閣議決定で、いわゆる「健康食品」の機能性表示制度についての検討が進められることとなりました。
制度が実現されれば、業界の大きな変革や市場拡大が予想され、企業にとっては様々な対応が求められます。
本シンポジウムでは、特別講演にて政府の規制改革会議においても中枢の役割を担っている森下竜一先生にご講演頂き、新機能性表示制度に向けて産学は何をすべきか、また、本研究会の主軸である管理栄養士は専門家として、どのようなアクション、消費者に対しての情報提供等が求められるかを主テーマとし、開催します。
日時:2014年4月21日(月) 14:00-17:30
会場:東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館
参加費:
「日本を健康にする!」研究会会員 10,000円、非会員 12,000円
主催:「日本を健康にする!」研究会
協力:ヘルスビジネスマガジン社
<講演者>
◆特別講演
「健康食品の機能性表示を可能とする法整備(仮)」
大阪大学大学院 医学系研究科 教授 森下竜一氏
◆講演
「申請に向け、管理栄養士に求められる役割(仮)」
愛知学院大学 心身科学部 学部長・教授 大澤俊彦氏
◆講演
「米国制度より学ぶ(仮)」
株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田猛氏
◆総括
東京海洋大学 「食の安全と機能(ヘルスフード科学)に関する研究」プロジェクト
特任教授 矢澤一良氏
-----------------------------------
<お申込方法>
下記URLより参加申込書を印刷して頂き、必要事項をご記入の上、事務局宛にお申込ください。
http://www.nihon-kenko.jp/pdf/20140421.pdf
FAXでのお申込ができない方は以下必要事項を記載の上、申込先メールアドレスへご連絡下さい。
申込先メールアドレス:info@nihon-kenko.jp
<申込メール記載事項>
参加者氏名/セミナー名(第8回機能性食品素材セミナー)/会員又は非会員/
住所/勤務先(又は学校名)/連絡先/メールアドレス
★注意事項★
御申込書を事務局へFAXして頂き、事前振込をして頂きましたら参加証をお送りします。
お申込者が多い場合は先着順に締め切らせて頂きますのでお早めにお申込下さい。
【その他、問合せ先】================
「日本を健康にする!」研究会事務局
株式会社RDサポート 担当:石井、大渕
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-15 D&F御茶ノ水ビル5F
TEL 03-5217-5565(代表) FAX 03-5217-5562
info@nihon-kenko.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2013年10月13日
電離水素水の性質と応用
平成25年度第2回大学等シーズ活用セミナー(10/25) 受講生募集のお知らせ
~産学官連携で最新の技術や研究をヒントに、何かやってみませんか?!~
大学等の高等教育機関、公設試験場の最新の技術や研究機関を紹介するセミナーです。
今回は、呉工業高等専門学校 及川栄作教授をお招きし、「電離水素水の性質と応用」についてご解説頂きます。
次の事業展開のキッカケやヒントを得るチャンスにして頂きたいと思いますので、是非、ご参加ください。
■内容・講師:
電離水素水の性質と応用
我々が開発したH-イオンを豊富に含む「電離水素水」の性質と応用方法について紹介する。
現在、電離水素水の研究結果には、植物の延命や香料・抗酸化剤の抽出に効果があることが判明している。今後は、バイオディーゼル油、アロマオイルの精製など飲料水の開発への応用を期待している。
本セミナーでは、電離水素水が持つこれらの性質や応用方法の可能性について、最前線の研究開発状況と水素水市場、今後の動向について講演する。
講師:独立行政法人国立高等専門学校機構 呉工業高等専門学校
教授 博士(工学) 及川栄作 氏

■開催日時・会場
開催日時:2013年10月25日(金)14時00分~16時00分 (受付:13時30分~)
会場:独立行政法人国立高等専門学校機構
呉工業高等専門学校 専攻科棟2階 講義室1
(呉市阿賀南2-2-11)
■お申込
平成25年10月22日(火) までに
参加申込書 Word , PDF(←ダウンロードしてください) を、FAXでお送りいただくか、又はメールにてお申込みください。
※定員に達したため等、お受けいただけない場合にのみご連絡差し上げます。
FAXの場合⇒ (0823)72-0333
※本紙「参加申込表」に必要事項をご記入のうえ、上記FAX番号へお申込ください。
E-mailの場合⇒ kuressc@kure-city.jp
※「貴団体名」「貴役職」「御氏名」「ご連絡先電話番号」をご記入のうえ、上記E-maiアドレスへお申込ください。
■お問合せ・その他
定員: 30名
受講料: 無料
お問合せ:(公財)くれ産業振興センター 担当:上本
tel: (0823)76-3766 E-mail:uemoto-kssc@kure-city.jp
http://kuressc.or.jp/index.php/news/20131025/
~産学官連携で最新の技術や研究をヒントに、何かやってみませんか?!~
大学等の高等教育機関、公設試験場の最新の技術や研究機関を紹介するセミナーです。
今回は、呉工業高等専門学校 及川栄作教授をお招きし、「電離水素水の性質と応用」についてご解説頂きます。
次の事業展開のキッカケやヒントを得るチャンスにして頂きたいと思いますので、是非、ご参加ください。
■内容・講師:
電離水素水の性質と応用
我々が開発したH-イオンを豊富に含む「電離水素水」の性質と応用方法について紹介する。
現在、電離水素水の研究結果には、植物の延命や香料・抗酸化剤の抽出に効果があることが判明している。今後は、バイオディーゼル油、アロマオイルの精製など飲料水の開発への応用を期待している。
本セミナーでは、電離水素水が持つこれらの性質や応用方法の可能性について、最前線の研究開発状況と水素水市場、今後の動向について講演する。
講師:独立行政法人国立高等専門学校機構 呉工業高等専門学校
教授 博士(工学) 及川栄作 氏

■開催日時・会場
開催日時:2013年10月25日(金)14時00分~16時00分 (受付:13時30分~)
会場:独立行政法人国立高等専門学校機構
呉工業高等専門学校 専攻科棟2階 講義室1
(呉市阿賀南2-2-11)
■お申込
平成25年10月22日(火) までに
参加申込書 Word , PDF(←ダウンロードしてください) を、FAXでお送りいただくか、又はメールにてお申込みください。
※定員に達したため等、お受けいただけない場合にのみご連絡差し上げます。
FAXの場合⇒ (0823)72-0333
※本紙「参加申込表」に必要事項をご記入のうえ、上記FAX番号へお申込ください。
E-mailの場合⇒ kuressc@kure-city.jp
※「貴団体名」「貴役職」「御氏名」「ご連絡先電話番号」をご記入のうえ、上記E-maiアドレスへお申込ください。
■お問合せ・その他
定員: 30名
受講料: 無料
お問合せ:(公財)くれ産業振興センター 担当:上本
tel: (0823)76-3766 E-mail:uemoto-kssc@kure-city.jp
http://kuressc.or.jp/index.php/news/20131025/
2012年07月10日
セミナー準備
日時
会場
案内パンフレット
ウェブサイト
申込フォーム(web)
申込用紙
振込先口座
事業主体
連絡先
配布テキスト(印刷・製本)
アンケート
インストラクターエントリーシート
関連情報をウェブで
プロジェクター
パワーポイント
レーザーポインター
延長ケーブル
ノートPC
スペアのPC
講師が事前に勉強しておく
リハーサル
受講者リスト
時間割
会場受付担当
タイムキーパー
会場
案内パンフレット
ウェブサイト
申込フォーム(web)
申込用紙
振込先口座
事業主体
連絡先
配布テキスト(印刷・製本)
アンケート
インストラクターエントリーシート
関連情報をウェブで
プロジェクター
パワーポイント
レーザーポインター
延長ケーブル
ノートPC
スペアのPC
講師が事前に勉強しておく
リハーサル
受講者リスト
時間割
会場受付担当
タイムキーパー