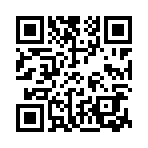2014年05月03日
健康食品”変わる表示”2014年5月2日放送 NHK総合
首都圏ネットワーク
特集 健康食品 “変わる表示”

史上規模が1兆2000億円とも言われる、健康食品。来年の春から、“骨を丈夫にする”、“心臓の健康を維持する”といった、身体にどのように機能するかを示した表示が可能になる。新しい制度で、国は「国民が自分に合った製品を選ぶことができるようになる」としていて消費者庁の案なども出された。スタジオで、科学文化部の藤谷萌絵が解説。機能の表示は企業責任で科学的根拠を示せれば可能になる見込みである。


一方、健康食品のウソの広告や誇大な広告のトラブルが後を絶たないことから、消費者団体から懸念の声も上がっている。消費者団体連絡会・河野康子事務局長は「何か被害があった時には消費者も救済されるくらいしっかりした制度設計をしてほしい」と話した。新しい制度は運用開始来年3月を予定。


特集 健康食品 “変わる表示”

史上規模が1兆2000億円とも言われる、健康食品。来年の春から、“骨を丈夫にする”、“心臓の健康を維持する”といった、身体にどのように機能するかを示した表示が可能になる。新しい制度で、国は「国民が自分に合った製品を選ぶことができるようになる」としていて消費者庁の案なども出された。スタジオで、科学文化部の藤谷萌絵が解説。機能の表示は企業責任で科学的根拠を示せれば可能になる見込みである。


一方、健康食品のウソの広告や誇大な広告のトラブルが後を絶たないことから、消費者団体から懸念の声も上がっている。消費者団体連絡会・河野康子事務局長は「何か被害があった時には消費者も救済されるくらいしっかりした制度設計をしてほしい」と話した。新しい制度は運用開始来年3月を予定。


コロナウィルスの治療に水素と酸素の混合気体を吸入
100分で名著「苦海浄土」石牟礼道子
週刊文春・水素水「効果ゼロ」報道に異議あり!
NHKスペシャル シリーズ認知症革命 ついにわかった!予防への道
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
高齢者最多3384万人 団塊世代、全て65歳以上に
100分で名著「苦海浄土」石牟礼道子
週刊文春・水素水「効果ゼロ」報道に異議あり!
NHKスペシャル シリーズ認知症革命 ついにわかった!予防への道
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
高齢者最多3384万人 団塊世代、全て65歳以上に
Posted by suiso at 21:21
│話題
│話題
この記事へのコメント
新制度の骨格が明らかに
2014年5月 2日 21:16
<ビタミン13種は対象外に>
米国型の新・機能性表示制度の導入に向けて、消費者庁は2日、「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開き、新制度で実施する機能性表示について、可能とする表示内容や、表示するために求められる科学的根拠のレベルなど制度の骨格を示した。科学的エビデンスを重視した透明性の高い制度を目指す姿勢を鮮明にしたと言える。新制度の核となる部分の大半が今回明らかとなり、新制度の導入に向けた議論は熱を帯びてきた。
消費者庁案によると、新制度は企業の自己責任のもとで機能性を表示できる仕組みとする。栄養機能食品や特定保健用食品(トクホ)とは別の制度として位置づける。
新制度は、サプリメント・一般加工食品・生鮮食品を含む食品全般を対象とする。ただし、アルコール飲料、ナトリウムや糖分を過剰に摂取させる食品などは、健康への悪影響が考えられるために対象としない。
対象とする成分は、直接的または間接的に定量できるものに限定。この点は、安全性確保対策で示した案と同じ。ただし、厚生労働省の「2015年版食事摂取基準」で摂取基準が策定されているビタミン・ミネラルなどの栄養成分については、栄養機能食品制度やトクホ制度で取り扱うこととし、新制度の対象外とする方針だ。摂取基準が策定されているビタミンは13種。ミネラルにはカルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・セレンなどがある。
摂取基準が策定されている栄養成分に、n-3系脂肪酸も含まれるが、n-3系脂肪酸を構成するDHAやEPAは摂取基準が策定されておらず、新制度の対象となる。また、摂取基準が策定されているビタミンAは新制度の対象外だが、ビタミンAの前駆体であるβ-カロテンやβ-クリプトキサンチンなどは対象となる。
安全性確保対策で求められたように、機能性の担保についても、企業は最終製品の規格を設定し、登録検査機関等で製品分析を実施して、規格どおりに成分量が入っているかどうかを確認する必要がある。
<未成年者や妊産婦は新制度の対象外>
消費者庁案によると、新制度の対象者は、生活習慣病などに「罹患する前」または「境界線上」の人とする。すでに罹患している人は対象としない。これは、トクホの考え方を踏襲したものだ。
また、未成年者、妊産婦や妊娠計画中の女性、授乳婦については対象としない方針を示した。前回の検討会で公表した「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査結果」により、これらの層では、いわゆる健康食品について「摂取することで病気が治る」、「病気の予防になる」などと誤認する傾向にあることがわかった。
<トクホと同様の表示が可能に>
2日開催の第5回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」で、消費者庁は新・機能性表示制度で可能となる機能性表示の概要を示した。
案によると、生活習慣病などに「罹患する前」または「境界線上」の人を対象とした「健康維持・増進に関する表現」を認める。トクホで許可されている表示と同じ程度の表現が可能となる。ただし、疾病名を含む表示は対象としない。この点がトクホ制度と異なる。トクホ制度では疾病リスク低減(骨粗しょう症)の表示もあるが、新制度では疾病名を絡めた表示は認めない。
また、主観的な指標によってしか評価できない機能に関する表示も、新制度の対象とする。たとえば、疲労や眠気などがこれに該当すると予想される。ただし、評価に用いる指標が、日本人にも当てはまり、さらに学術的に広く支持されていることが要件となる。一部の国で使用され、日本人に当てはめることが困難な指標による評価は対象外となる。妥当性のある指標として、たとえば、日本の医療機関が診断で使用しているものなどが想定される。
<科学的根拠のレベルを示す>
機能性表示を行なうための科学的根拠のレベルも示された。健康食品業界の関係者が、もっとも関心を寄せている点だ。消費者庁案によると、機能性を実証する手法として、(1)最終製品を用いたヒト試験による実証、(2)適切な研究レビューによる実証――のどちらかを選択できる。どちらの手法でも、企業が自己責任のもとで評価し、機能性を表示する。
データベース上の文献によるレビュー(成分ベースでも可)を認めた点や、国は審査せずに企業が自ら評価する点が、トクホ制度と根本的に異なる。このためトクホと違って、表示にかかる費用も小さく、表示が可能となるまでの期間も短くて済む。
会合で消費者庁は、「文献が少ない農林水産物などは(1)の方法で対応し、サプリメントなどは(2)で対応できるということで提案した」(食品表示企画課)と説明した。
最終製品を用いた実証では、企業は安全性と有効性についてヒト試験を行なう。ヒト試験の方法は、原則トクホと同じ内容としている。ただし、有効性試験については、研究計画を「UMIN臨床試験登録システム」等に事前登録することが求められる。UMIN臨床試験登録システムはあらゆる臨床試験を対象とし、世界中のだれでも閲覧することが可能。また、試験結果については、「CONSORT声明」等の国際的な指針に準拠し、査読付き論文で報告されたものに限定する考えだ。
研究計画の事前登録は、ポジティブな研究結果だけを公表する「出版バイアス」の排除が主な目的。また、CONSORT声明等の準拠によって、記載漏れを防ぎ、論文の質を向上させるという狙いがある。トクホの場合、消費者委員会や食品安全委員会などで審査され、疑義が生じれば、企業に資料の再提出などを求めることが可能。しかし、新制度は企業が自ら評価して表示することから、トクホ制度にない新たな取り組みを課すこととなった。
ヒト試験の事前登録や、研究計画や論文作成についてCONSORT声明等に準拠するという考え方は、2年前に消費者庁の「食品の機能性評価モデル事業」によって業界に突き付けられた課題だった。
<「システマティック・レビュー」が必須>
第5回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」で示された消費者庁案によると、企業が機能性表示の根拠を実証する場合、「最終製品を用いたヒト試験」または「適切な研究レビュー」のどちらかを選択する。
健康食品企業の大多数は、データベース上の文献を検索して行なう「適切な研究レビュー」を選択すると予想される。消費者庁案によると、その際に求められる科学的根拠のレベルは、食品の形態によって差をつける方針。サプリメント形状の食品については、ヒト介入試験によってポジティブな結果が得られていることが要件となる。一方、一般加工食品や生鮮食品については、ヒト介入試験でも観察研究でもよい。サプリメント形状の食品よりも、ハードルを低くしたかたちだ。
企業がレビューする際には、査読付きの学術論文など1次研究(いわゆる原著論文)を用いた「システマティック・レビュー」が必須となる。「トータリティ・オブ・エビデンス」の考え方に基づき、企業は自己責任のもとで、成分の機能性をシステマティック・レビューによって総合的に評価しなければならない。
システマティック・レビューとは、あるテーマに関する研究データを収集・解析し、総合的に評価する手法。系統的レビューとも呼ばれる。(1)検索条件を事前に設定、(2)関連する国内外の研究を網羅的に収集・精査、(3)総合的な観点から評価、(4)だれもが再現できるように、検索条件から結果に至るまでのプロセスをすべて公表――などを柱とする。
また、トータリティ・オブ・エビデンスは、ポジティブなデータだけでなく、ネガティブなデータも含めて、総合的に判断するというもの。このため、文献検索によって良好な結果の研究論文が多数出てきても、否定的な研究論文が同じくらいあれば、根拠として認められない可能性もある。
これらの手法に基づく「総合評価」も、新制度の特徴の一つ。個々の製品ベースで評価するトクホ制度と大きく異なる点だ。
消費者庁案によると、システマティック・レビューを実施する場合、(1)検索条件、(2)採択・不採択の文献情報、(3)結果に至るプロセス、(4)スポンサー・共同スポンサー、利益相反に関する情報、(5)出版バイアスの検討結果――などの詳細も公表しなければならない。これにより、制度の透明性を高めて、だれもが再現できる仕組みを目指す考えだ。
また、海外で実施された研究もレビューの対象とする。世界中の論文を収集することが基本となるが、試験デザインなどが日本人にとって妥当かどうかを考慮しなければならない。
こうした要件に沿って実施されたシステマティック・レビューの結果、「査読付きのヒト研究論文が1本もなかった場合」、または「表示しようとする機能について、査読付きのヒト研究論文が支持していない場合」には科学的根拠が不十分とみなされる。つまり、機能性を表示できないことになる。
システマティック・レビューについても可能な限り、「UMIN臨床試験登録システム」等への事前登録を求める方針が示された。出版バイアスをできるだけ排除するためだ。さらに、新たな研究結果を含めて定期的に再検討し、公表することも努力規定として案に盛り込んだ。
<「国による評価を受けたものではない」などの表示が要件に>
消費者庁は、機能性に関する情報の開示についても案を示した。
「機能性表示の内容について国による評価を受けたものではない旨」、「未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む)および授乳婦を対象としたものではない旨」、「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言」の容器包装への表示を必須要件とする。
<「生鮮食品」の議論を開始>
第5回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」では、生鮮食品についての議論も始まった。昨年6月の閣議決定で、新・機能性表示制度の対象に加工食品と農林水産物が明記された。新制度は健康食品などの加工食品だけでなく、生鮮食品も含めた仕組みとなる。
会合で農林水産省の担当官は、安全性・機能性に関する科学的根拠の事例に、「温州みかん」と「べにふうき緑茶(ペットボトル飲料)」を挙げて説明した。
温州みかん(β-クリプトキサンチン)については、3つの観察研究を取り上げた。前向きコホート研究では、β-クリプトキサンチンの血中濃度が高い閉経後の女性は、血中濃度が低い人と比べ、骨粗しょう症の発症リスクが低いことがわかった。また、べにふうき緑茶(メチル化カテキン)のヒト介入試験を紹介。二重盲検無作為プラセボ対照群間比較試験により、べにふうき緑茶を長期飲用しているスギ花粉症状をもつ人は、やぶきた緑茶を飲用している人と比べ、症状の悪化が軽減されることがわかった。
農水省は、想定される機能性表示のイメージ(例)を提示した。温州みかんについては、「本品はβ-クリプトキサンチンを含み、骨の健康を保つ食品です。更年期以降の女性の方に適しています」。べきふうき緑茶では、「本品はメチル化カテキンを含んでいるため、花粉が気になる方の目や鼻の調子を整えます」と想定している。
一方、新制度の生鮮食品をめぐる問題点も挙げた。産地や収穫時期などによって、成分含有量にばらつきが出ることを考慮しなければならないと説明した。
<「品種と産地」の問題を指摘>
生鮮食品について大谷敏郎委員(食品総合研究所所長)は、「農産物の場合、成分に関与するのは品種であり、産地である。品種と産地が同一性を担保するカテゴリーであると考えている」と指摘した。
また、相良治美委員(月刊「食生活」編集長)は、「作り手側(生産者)のメリットは何か。温州みかんの産地は多いが、成分量の差などを知りたい」などと質問。児玉浩子委員(帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科教授)は、「(消費者の行動が)サプリメントに傾いているので、体に良い食べ物を摂るために、生鮮食品に機能性表示を行なうのは良いこと」と話した。
<機能性は相互作用の実証「不要」>
2日開催の「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」では、機能性表示に関する制度の枠組みが明らかにされ、委員の間で活発な意見交換が見られた。
この日示された消費者庁案によると、複数の成分についてそれぞれの機能性を表示する場合、「成分ごとに機能性を実証すればよい」としている。新制度の安全性確保対策では、成分ごとの安全性評価と、複数の成分を同時に摂取した際の相互作用の評価が求められる。一方、機能性については相互作用に関する実証を求めない方針とした。
これに対し、清水俊雄委員(名古屋文理大学健康生活学部フードビジネス学科教授)は異論を唱えた。健康食品の新聞広告に関する調査結果をもとに、半分以上の健康食品が複数の有効成分を配合している実態を紹介。「有効成分を複数混合すると、効果も安全性も異なる。製品そのもの、またはそれと同等の組成をもつ被験物質で実証する必要がある」と主張した。
寺本民生委員(帝京大学臨床研究センター長)は、清水委員の意見を支持。「最終製品での確認は重要。各成分で(有効性が)はっきりしていても、最終製品ではっきりしていなかったら意味がない」とし、消費者庁案に難色を示した。
このように、健康食品業界にとって受け入れ難い意見が相次いだが、業界代表委員から反論の声は最後まで上がらなかった。
<「虚偽がある場合のペナルティが大事」の声も>
会合では複数の委員から、ルール違反を犯した企業への対応を求める意見が出た。
松澤佑次座長(大阪大学名誉教授、住友病院院長)は、「基本は企業の責任に任せるが、虚偽がある場合にどこまでペナルティを出せるか。このことが大事な気がする」と述べた。合田幸広委員(国立医薬品食品衛生研究所薬品部長)は、「企業の性善説に立った制度であるため、モニタリングが大切となる。モニタリングのための予算措置が必要」と提言した。
また、梅垣敬三委員(国立健康・栄養研究所情報センター長)は、「(有効性に関する)最近のデータはネガティブなものが多い。有効だったものが、無効となることがしょっちゅう起こっている」と指摘。「どこのデータを使用しているのかをだれがチェックするのか。この点を具体的に決定しておくことが大切」と話した。
これらの意見に対し、消費者庁の担当官は「入口から出口まで国が関与する。違反があれば、強制的に対応できる仕組みにする」(食品表示企画課)と答えた。
次回会合は5月30日に開催する。
http://ib-kenko.jp/2014/05/_0502_dm1248_6.html
2014年5月 2日 21:16
<ビタミン13種は対象外に>
米国型の新・機能性表示制度の導入に向けて、消費者庁は2日、「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開き、新制度で実施する機能性表示について、可能とする表示内容や、表示するために求められる科学的根拠のレベルなど制度の骨格を示した。科学的エビデンスを重視した透明性の高い制度を目指す姿勢を鮮明にしたと言える。新制度の核となる部分の大半が今回明らかとなり、新制度の導入に向けた議論は熱を帯びてきた。
消費者庁案によると、新制度は企業の自己責任のもとで機能性を表示できる仕組みとする。栄養機能食品や特定保健用食品(トクホ)とは別の制度として位置づける。
新制度は、サプリメント・一般加工食品・生鮮食品を含む食品全般を対象とする。ただし、アルコール飲料、ナトリウムや糖分を過剰に摂取させる食品などは、健康への悪影響が考えられるために対象としない。
対象とする成分は、直接的または間接的に定量できるものに限定。この点は、安全性確保対策で示した案と同じ。ただし、厚生労働省の「2015年版食事摂取基準」で摂取基準が策定されているビタミン・ミネラルなどの栄養成分については、栄養機能食品制度やトクホ制度で取り扱うこととし、新制度の対象外とする方針だ。摂取基準が策定されているビタミンは13種。ミネラルにはカルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・セレンなどがある。
摂取基準が策定されている栄養成分に、n-3系脂肪酸も含まれるが、n-3系脂肪酸を構成するDHAやEPAは摂取基準が策定されておらず、新制度の対象となる。また、摂取基準が策定されているビタミンAは新制度の対象外だが、ビタミンAの前駆体であるβ-カロテンやβ-クリプトキサンチンなどは対象となる。
安全性確保対策で求められたように、機能性の担保についても、企業は最終製品の規格を設定し、登録検査機関等で製品分析を実施して、規格どおりに成分量が入っているかどうかを確認する必要がある。
<未成年者や妊産婦は新制度の対象外>
消費者庁案によると、新制度の対象者は、生活習慣病などに「罹患する前」または「境界線上」の人とする。すでに罹患している人は対象としない。これは、トクホの考え方を踏襲したものだ。
また、未成年者、妊産婦や妊娠計画中の女性、授乳婦については対象としない方針を示した。前回の検討会で公表した「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査結果」により、これらの層では、いわゆる健康食品について「摂取することで病気が治る」、「病気の予防になる」などと誤認する傾向にあることがわかった。
<トクホと同様の表示が可能に>
2日開催の第5回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」で、消費者庁は新・機能性表示制度で可能となる機能性表示の概要を示した。
案によると、生活習慣病などに「罹患する前」または「境界線上」の人を対象とした「健康維持・増進に関する表現」を認める。トクホで許可されている表示と同じ程度の表現が可能となる。ただし、疾病名を含む表示は対象としない。この点がトクホ制度と異なる。トクホ制度では疾病リスク低減(骨粗しょう症)の表示もあるが、新制度では疾病名を絡めた表示は認めない。
また、主観的な指標によってしか評価できない機能に関する表示も、新制度の対象とする。たとえば、疲労や眠気などがこれに該当すると予想される。ただし、評価に用いる指標が、日本人にも当てはまり、さらに学術的に広く支持されていることが要件となる。一部の国で使用され、日本人に当てはめることが困難な指標による評価は対象外となる。妥当性のある指標として、たとえば、日本の医療機関が診断で使用しているものなどが想定される。
<科学的根拠のレベルを示す>
機能性表示を行なうための科学的根拠のレベルも示された。健康食品業界の関係者が、もっとも関心を寄せている点だ。消費者庁案によると、機能性を実証する手法として、(1)最終製品を用いたヒト試験による実証、(2)適切な研究レビューによる実証――のどちらかを選択できる。どちらの手法でも、企業が自己責任のもとで評価し、機能性を表示する。
データベース上の文献によるレビュー(成分ベースでも可)を認めた点や、国は審査せずに企業が自ら評価する点が、トクホ制度と根本的に異なる。このためトクホと違って、表示にかかる費用も小さく、表示が可能となるまでの期間も短くて済む。
会合で消費者庁は、「文献が少ない農林水産物などは(1)の方法で対応し、サプリメントなどは(2)で対応できるということで提案した」(食品表示企画課)と説明した。
最終製品を用いた実証では、企業は安全性と有効性についてヒト試験を行なう。ヒト試験の方法は、原則トクホと同じ内容としている。ただし、有効性試験については、研究計画を「UMIN臨床試験登録システム」等に事前登録することが求められる。UMIN臨床試験登録システムはあらゆる臨床試験を対象とし、世界中のだれでも閲覧することが可能。また、試験結果については、「CONSORT声明」等の国際的な指針に準拠し、査読付き論文で報告されたものに限定する考えだ。
研究計画の事前登録は、ポジティブな研究結果だけを公表する「出版バイアス」の排除が主な目的。また、CONSORT声明等の準拠によって、記載漏れを防ぎ、論文の質を向上させるという狙いがある。トクホの場合、消費者委員会や食品安全委員会などで審査され、疑義が生じれば、企業に資料の再提出などを求めることが可能。しかし、新制度は企業が自ら評価して表示することから、トクホ制度にない新たな取り組みを課すこととなった。
ヒト試験の事前登録や、研究計画や論文作成についてCONSORT声明等に準拠するという考え方は、2年前に消費者庁の「食品の機能性評価モデル事業」によって業界に突き付けられた課題だった。
<「システマティック・レビュー」が必須>
第5回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」で示された消費者庁案によると、企業が機能性表示の根拠を実証する場合、「最終製品を用いたヒト試験」または「適切な研究レビュー」のどちらかを選択する。
健康食品企業の大多数は、データベース上の文献を検索して行なう「適切な研究レビュー」を選択すると予想される。消費者庁案によると、その際に求められる科学的根拠のレベルは、食品の形態によって差をつける方針。サプリメント形状の食品については、ヒト介入試験によってポジティブな結果が得られていることが要件となる。一方、一般加工食品や生鮮食品については、ヒト介入試験でも観察研究でもよい。サプリメント形状の食品よりも、ハードルを低くしたかたちだ。
企業がレビューする際には、査読付きの学術論文など1次研究(いわゆる原著論文)を用いた「システマティック・レビュー」が必須となる。「トータリティ・オブ・エビデンス」の考え方に基づき、企業は自己責任のもとで、成分の機能性をシステマティック・レビューによって総合的に評価しなければならない。
システマティック・レビューとは、あるテーマに関する研究データを収集・解析し、総合的に評価する手法。系統的レビューとも呼ばれる。(1)検索条件を事前に設定、(2)関連する国内外の研究を網羅的に収集・精査、(3)総合的な観点から評価、(4)だれもが再現できるように、検索条件から結果に至るまでのプロセスをすべて公表――などを柱とする。
また、トータリティ・オブ・エビデンスは、ポジティブなデータだけでなく、ネガティブなデータも含めて、総合的に判断するというもの。このため、文献検索によって良好な結果の研究論文が多数出てきても、否定的な研究論文が同じくらいあれば、根拠として認められない可能性もある。
これらの手法に基づく「総合評価」も、新制度の特徴の一つ。個々の製品ベースで評価するトクホ制度と大きく異なる点だ。
消費者庁案によると、システマティック・レビューを実施する場合、(1)検索条件、(2)採択・不採択の文献情報、(3)結果に至るプロセス、(4)スポンサー・共同スポンサー、利益相反に関する情報、(5)出版バイアスの検討結果――などの詳細も公表しなければならない。これにより、制度の透明性を高めて、だれもが再現できる仕組みを目指す考えだ。
また、海外で実施された研究もレビューの対象とする。世界中の論文を収集することが基本となるが、試験デザインなどが日本人にとって妥当かどうかを考慮しなければならない。
こうした要件に沿って実施されたシステマティック・レビューの結果、「査読付きのヒト研究論文が1本もなかった場合」、または「表示しようとする機能について、査読付きのヒト研究論文が支持していない場合」には科学的根拠が不十分とみなされる。つまり、機能性を表示できないことになる。
システマティック・レビューについても可能な限り、「UMIN臨床試験登録システム」等への事前登録を求める方針が示された。出版バイアスをできるだけ排除するためだ。さらに、新たな研究結果を含めて定期的に再検討し、公表することも努力規定として案に盛り込んだ。
<「国による評価を受けたものではない」などの表示が要件に>
消費者庁は、機能性に関する情報の開示についても案を示した。
「機能性表示の内容について国による評価を受けたものではない旨」、「未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む)および授乳婦を対象としたものではない旨」、「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言」の容器包装への表示を必須要件とする。
<「生鮮食品」の議論を開始>
第5回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」では、生鮮食品についての議論も始まった。昨年6月の閣議決定で、新・機能性表示制度の対象に加工食品と農林水産物が明記された。新制度は健康食品などの加工食品だけでなく、生鮮食品も含めた仕組みとなる。
会合で農林水産省の担当官は、安全性・機能性に関する科学的根拠の事例に、「温州みかん」と「べにふうき緑茶(ペットボトル飲料)」を挙げて説明した。
温州みかん(β-クリプトキサンチン)については、3つの観察研究を取り上げた。前向きコホート研究では、β-クリプトキサンチンの血中濃度が高い閉経後の女性は、血中濃度が低い人と比べ、骨粗しょう症の発症リスクが低いことがわかった。また、べにふうき緑茶(メチル化カテキン)のヒト介入試験を紹介。二重盲検無作為プラセボ対照群間比較試験により、べにふうき緑茶を長期飲用しているスギ花粉症状をもつ人は、やぶきた緑茶を飲用している人と比べ、症状の悪化が軽減されることがわかった。
農水省は、想定される機能性表示のイメージ(例)を提示した。温州みかんについては、「本品はβ-クリプトキサンチンを含み、骨の健康を保つ食品です。更年期以降の女性の方に適しています」。べきふうき緑茶では、「本品はメチル化カテキンを含んでいるため、花粉が気になる方の目や鼻の調子を整えます」と想定している。
一方、新制度の生鮮食品をめぐる問題点も挙げた。産地や収穫時期などによって、成分含有量にばらつきが出ることを考慮しなければならないと説明した。
<「品種と産地」の問題を指摘>
生鮮食品について大谷敏郎委員(食品総合研究所所長)は、「農産物の場合、成分に関与するのは品種であり、産地である。品種と産地が同一性を担保するカテゴリーであると考えている」と指摘した。
また、相良治美委員(月刊「食生活」編集長)は、「作り手側(生産者)のメリットは何か。温州みかんの産地は多いが、成分量の差などを知りたい」などと質問。児玉浩子委員(帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科教授)は、「(消費者の行動が)サプリメントに傾いているので、体に良い食べ物を摂るために、生鮮食品に機能性表示を行なうのは良いこと」と話した。
<機能性は相互作用の実証「不要」>
2日開催の「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」では、機能性表示に関する制度の枠組みが明らかにされ、委員の間で活発な意見交換が見られた。
この日示された消費者庁案によると、複数の成分についてそれぞれの機能性を表示する場合、「成分ごとに機能性を実証すればよい」としている。新制度の安全性確保対策では、成分ごとの安全性評価と、複数の成分を同時に摂取した際の相互作用の評価が求められる。一方、機能性については相互作用に関する実証を求めない方針とした。
これに対し、清水俊雄委員(名古屋文理大学健康生活学部フードビジネス学科教授)は異論を唱えた。健康食品の新聞広告に関する調査結果をもとに、半分以上の健康食品が複数の有効成分を配合している実態を紹介。「有効成分を複数混合すると、効果も安全性も異なる。製品そのもの、またはそれと同等の組成をもつ被験物質で実証する必要がある」と主張した。
寺本民生委員(帝京大学臨床研究センター長)は、清水委員の意見を支持。「最終製品での確認は重要。各成分で(有効性が)はっきりしていても、最終製品ではっきりしていなかったら意味がない」とし、消費者庁案に難色を示した。
このように、健康食品業界にとって受け入れ難い意見が相次いだが、業界代表委員から反論の声は最後まで上がらなかった。
<「虚偽がある場合のペナルティが大事」の声も>
会合では複数の委員から、ルール違反を犯した企業への対応を求める意見が出た。
松澤佑次座長(大阪大学名誉教授、住友病院院長)は、「基本は企業の責任に任せるが、虚偽がある場合にどこまでペナルティを出せるか。このことが大事な気がする」と述べた。合田幸広委員(国立医薬品食品衛生研究所薬品部長)は、「企業の性善説に立った制度であるため、モニタリングが大切となる。モニタリングのための予算措置が必要」と提言した。
また、梅垣敬三委員(国立健康・栄養研究所情報センター長)は、「(有効性に関する)最近のデータはネガティブなものが多い。有効だったものが、無効となることがしょっちゅう起こっている」と指摘。「どこのデータを使用しているのかをだれがチェックするのか。この点を具体的に決定しておくことが大切」と話した。
これらの意見に対し、消費者庁の担当官は「入口から出口まで国が関与する。違反があれば、強制的に対応できる仕組みにする」(食品表示企画課)と答えた。
次回会合は5月30日に開催する。
http://ib-kenko.jp/2014/05/_0502_dm1248_6.html
Posted by 新制度の骨格が明らかに at 2014年05月04日 14:56