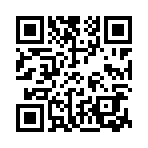2013年11月16日
大腸発生水素による酸化ストレス軽減と生活習慣病予防の可能性
■大腸発生水素による酸化ストレス軽減と生活習慣病予防の可能性
名寄市立大学 保健福祉学部栄養学科・教授 西村直道
はじめに
食物繊維は、コレステロール正常化作用(低下作用)、血糖値上昇抑制作用、便通改善作用、大腸がん発症抑制作用などさまざまな生理作用を有することが報告され、現在でもこれらの作用に関連する研究ならびに開発が行われている。しかし、食物繊維の生理作用は本当にこれまでに報告されているものだけであろうか。数多くの研究がなされ、これまでの既存の考え方では合理的に説明できないような現象も多々見受けられる。同じような経験をしている人は結構多いはずである。にもかかわらず、新たな考え方や可能性を示すことができなかったのは、私を含め食物繊維の研究を行っている研究者の怠慢であったかもしれない。今回ここでは我々が最近4年間で力を注ぎ、たどり着いた新しい食物繊維の機能を解説したい。
食物繊維は大腸に常在する多数の細菌によって発酵分解を受ける。このとき多くの発酵産物が生成され、その中には大腸上皮細胞の主要なエネルギ一源となり、大腸がん発症の抑制因子としても働く酪酸も存在する。酪酸のほかにも酢酸やプロピオン酸など短鎖脂肪酸が比較的多量に生成される。これらに生理作用が認められるため、食物繊維の生理作用に関する研究もこれらの成分に焦点を当てたものが多く見られる。発酵産物としてガス成分も多量に生成されるにもかかわらず、こちらの研究がおろそかになっていたのは否めない。我々が研究の焦点としている水素(H2)も同様であった。H2は極性がなく反応性に富んでいないことから、大腸で発生したH2は生体に何ら作用を及ぼすことのない物質として捉えていたのである。無機化学においてH2分子が白金やパラジウムのような触媒存在下で還元性を示すことは古くから知られていた。生体内でも同様にH2が還元性を示す可能性はあったわけであるが、先に示したような触媒が存在しない生体内で有力なエビデンスを示した研究は長い間なかった。
H2分子による生体内抗酸化と大腸発生H2の可能性
2007年にOsawaらは、脳虚血-再灌流(IR)処置によって酸化ストレスを与えたラットにH2ガスを吸入させることによって、生成されたヒドロキシラジカルが特異的に捕捉され、酸化障害が軽減されることを見出した。この研究は、生体内でH2が還元性を示すことを初めて明らかにしたものであり、その後も、さまざまな酸化ストレスに対しH2分子が抗酸化作用を示すことが報告されている。一方、食物繊維をはじめとする難消化性糖質は、大腸内発酵によるH2生成を促し、そのH2は呼気および放屁に排泄されることが知られている。我々は、このH2も同じように生体内で抗酸化作用を発揮する可能性をひらめいた。大腸内発酵を利用してH2を生体内に供給できれば、安定的かつ持続的に生体内還元性を維持できると期待される。生体内における不必要な酸化反応を防御することで、酸化障害を発端とする生活習慣病の発症や進展を抑えることが可能であろう。
我々は、Savaianoらの報告にもとづいて、ラクトース(20g)摂取後のヒト呼気中H2濃度の変動から、ヒト門脈血中の平均的H2濃度を推定した。一般的な生理学的データより換気量に約500mL/分、呼吸数に16~18回/分を用いて、8時間で呼気中に排出されるH2量の推算を行った。その結果、20gのラクトース摂取で96~108mL/8hのH2が排泄されることがわかった。さらに、拍出量に約5L/分を用い、門脈血流量を消化管に流入する血流量(全血流量の約28%)と同じとして算出した。この結果、門脈血中の平均H2濃度は6.4~7.2μMであると推定できた。このH2濃度は、我々のラットによる実験結果(後述)ともほぼ一致しており、この濃度で酸化ストレスが軽減されることを確認している。また、これまでに酸化ストレスの軽減を示したH2ガスやH2水による研究でも、同程度の血中H2濃度が報告されている。したがって、大腸でH2生成を促進する基質を十分に供給すれば、生体で酸化ストレスを軽減できうることを示唆している。
大腸発生H2による生体内抗酸化と酸化障害軽減
実験動物のブリーダーでは、動物の腸内細菌叢を均一化するため、出生直後にいくつかの腸内細菌を接種している。それにもかかわらず、発酵基質となる高アミロースデンプン(HAS;難消化性画分を50~60%含む)やペクチンを摂取させたときのラットH2生成能に大きな違いが存在する。そこで、このばらつきを利用してH2生成量と酸化障害との関係を調べた。H2生成能にばらつきのある66匹ラットにHASを与えると、7日後の門脈H2濃度に大きな違いが各個体に認められた。これらのラットすべてに肝IR処置で酸化ストレスを与え、血漿アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)活性(肝障害マーカー)の変化を観察した。門脈H2濃度をカテゴリ変数(五分位数)として血漿ALT活性変動を解析すると、図1のような関係がみられる。門脈H2濃度が低い場合、肝IR酸化障害によって血漿ALT活性は高値を示したが、H2濃度が8.4μmol/L近辺でメジアンは最小値を示した。それ以上のH2濃度では血漿ALT活性はわずかに上昇を示した。これは門脈H2濃度が極端に低い領域では、酸化ストレスに対する防御能がないことを示している。門脈H2濃度が高い場合、大腸内発酵が活発であり、それにともなってさまざまな物質が生成される。その中には酸化障害による炎症を助長するものもあるかもしれない。例えば、細胞毒性の強いアンモニアなどは、虚血-再灌流によって機能の低下した肝臓では炎症を引き起こす可能性も考えられる。H2は生体内における酸化障害を抑制する能力を有するが、大腸H2生成を高める場合、やみくもに発酵を盛んにすることを考えるだけでなく、その他の発酵産物の影響が大きくなる可能性も考慮する必要があるだろう。
次に、高H2生成能ラットを用い、発酵性の高いHASやペクチンを与えたときの酸化ストレスヘの影響を調べた。セルロースを食物繊維源とする精製飼料を与えたラットの(放屁+呼気)H2排出量が0.13μmol/5min以上を示す個体を選別し、HASやペクチンを与えると門脈H2濃度は3~15倍に上昇する(図2)。このようなラットの肝臓にIR処置で酸化ストレスを与えると、IRによって低下した肝グルタチオンの還元型/酸化型比はHASやペクチン投与によって改善した(図2)。これぱHASやペクチン投与によって多量に生成したH2が肝臓で還元性を示し、IRによって酸化状態に傾いたものを回復させたと考えられる。これに伴って、IRによって著しく上昇した血漿ALT活性は、HASやペクチン投与ラットで低下した(図2、3)。これらの結果より、大腸内で生成したH2は門脈を経て肝臓で酸化ストレスを軽減しうることが明らかとなった。また、これまでに虚血後の短時間(30~60分)の再灌流だけでなく、長時間(24~48時間)の再灌流による酸化障害にも、HAS投与によるH2生成が有効であることも示した。
糖尿病、虚血性疾患、動脈硬化症、アルツハイマー病などのような生活習慣病の多くは、酸化ストレスの増大に伴った障害によって発症および進展が誘導される。また、肥満も生体内酸化ストレスを増大させ、生活習慣病発症の引き金となっている。大腸で生成したH2でこれらの酸化ストレスを軽減できれば、さまざまな生活習慣病予防につながることが期待される。そのためには生体内のさまざまな組織に安定的に持続してH2を供給することが重要であるといえよう。
大腸H2生成と持続的H2供給
生体内へのH2の直接的な供給方法として、H2ガスの吸入やH2水の飲水がある。実験動物やヒトを対象とした研究もなされており、それらがH2供給法として有効であることは間違いない。しかし、日常生活における持続的な供給という観点に立てば、決してこれらの方法が有効とはいえない。H2ガスの吸入は病院などで大掛かりな設備が必要であるし、吸入をやめればH2が供給されなくなる。また、H2水であれば、投与直後のH2供給量は多いが、飲める量に限界もある。H2の水への溶解度はとても低い(0.8mmol/L)ため、生体内に高濃度のH2を長時間にわたって供給し続けることは困難である。さらに、摂取後にH2血中濃度がピークを迎え、元に戻るまでの時間も30分程度しかない。この点において、大腸内発酵によるH2の供給は合理的である。大腸に発酵基質を十分量存在すれば、たとえ睡眠時に食事を摂っていなくとも生体内に24時間H2を供給できるはずである。
我々はこれまでにラットを用いた実験で、十分量の発酵基質を大腸に送れば、24時間H2生成が高く維持されることを確認している(図4の20%HAS食群)。一方、大腸内で24時間に資化できる量とほは等量の基質を与えると、投与開始から24時間後のH2生成量はほとんど消失する(図4の10%HAS食群)。このことから大腸に十分量の発酵基質を送り届けることの重要性がわかる。大腸内に滞留している時間も重要であり、十分量に基質を供給しても、滞留時間が短ければ、基質当たりのH2生成が抑えられると考えられる。さらに、H2が長期間にわたって安定的に生成し続けることも生体内還元力を高めるために欠かせない。単一の発酵基質をラットに与えると、投与初期はH2生成量が多く、その後減少するという現象を頻繁に目にする。酸化還元電位の低い大腸内に常在する嫌気性細菌は発酵基質として大腸に流入してきた糖質を主に利用し、ATPを生成している。つまり、発酵基質からH+を獲得し、電子伝達系で自由エネルギーを獲得している。しかし、嫌気性細菌では酸素を利用できないため、H+およびe-からH2ガスを生成する。この状態が過剰になると、H2分圧が高まるため、H2生成がうまく進まなくなる。これが長期間にわたって、極端に高いH2生成能を維持できない理由かもしれない。このような状態にH+およびe-を利用してメタン、硫化水素、酢酸を生成する細菌が活性化すると、H2分圧が下がるため、H2生成がうまく進むかもしれないが、H+がほかに利用されてしまうため、H2ガスの生成はやはり低下する可能性が高い。ヒトの食生活を考えれば、単一の発酵基質を摂取し続けることはありえないが、サプリメントのように単一のものを長期間多量に摂取しても、高H2生成能を長期にわたって維持することは期待できないかもしれない。今後生体内で安定的かつ持続的に多量のH2を生成できるような発酵環境条件を見出すことが重要な課題となると思われる。また、大腸内発酵産物で有用とされている酪酸生成との関係も考えておく必要はあるだろう。H2生成を高めても、逆に酪酸生成は低下するかもしれない。このようなときにどういった発酵がヒトにとってベストもしくはベターであるかを考慮すべきだと考える。
おわりに
H2分子の生体内抗酸化作用はすでに多くの報告がされており、疑う余地はほぽない。大腸内発酵によってH2が生成され、何ら生体に影響をもたらさない分子として考えられていたが、我々の研究によってその抗酸化作用が明らかになった。これまで食物繊維の生理作用として、現象は再現よく観察されるにもかかわらず、それを説明するに足る作用機構が明らかになっていないものがある。その一部はこの大腸発生H2による作用で説明できるかもしれない。まさしく、これは食物繊維の新機能と言えるのではないだろうか。最近の我々の研究で、大腸で生じたH2が腹腔に拡散し、とりわけ脂肪組織に局在していることも見出した。食物繊維など難消化性糖質の摂取で脂肪組織をはじめとする腹腔内の組織にもH2が供給されるという事実は、肥満時の脂肪組織における酸化ストレスも軽減できる可能性を示している。こういった酸化ストレスを大腸生成H2によって制御できれば、食物繊維が新たな局面で生活習慣病予防に大きく寄与すると思われる。この機能を踏まえ、食物繊維の可能性をさらに探究していく価値は多いにあると考える。また、これまでの概念や思考にとらわれず、食物繊維の消化管を介して引き起こす生理作用にさまざまな角度からアプローチしていく気概が食物繊維の研究や開発に取り組む研究者に欠かせないだろう。
食品と開発2013年1月号 UBMメディア

名寄市立大学 保健福祉学部栄養学科・教授 西村直道
はじめに
食物繊維は、コレステロール正常化作用(低下作用)、血糖値上昇抑制作用、便通改善作用、大腸がん発症抑制作用などさまざまな生理作用を有することが報告され、現在でもこれらの作用に関連する研究ならびに開発が行われている。しかし、食物繊維の生理作用は本当にこれまでに報告されているものだけであろうか。数多くの研究がなされ、これまでの既存の考え方では合理的に説明できないような現象も多々見受けられる。同じような経験をしている人は結構多いはずである。にもかかわらず、新たな考え方や可能性を示すことができなかったのは、私を含め食物繊維の研究を行っている研究者の怠慢であったかもしれない。今回ここでは我々が最近4年間で力を注ぎ、たどり着いた新しい食物繊維の機能を解説したい。
食物繊維は大腸に常在する多数の細菌によって発酵分解を受ける。このとき多くの発酵産物が生成され、その中には大腸上皮細胞の主要なエネルギ一源となり、大腸がん発症の抑制因子としても働く酪酸も存在する。酪酸のほかにも酢酸やプロピオン酸など短鎖脂肪酸が比較的多量に生成される。これらに生理作用が認められるため、食物繊維の生理作用に関する研究もこれらの成分に焦点を当てたものが多く見られる。発酵産物としてガス成分も多量に生成されるにもかかわらず、こちらの研究がおろそかになっていたのは否めない。我々が研究の焦点としている水素(H2)も同様であった。H2は極性がなく反応性に富んでいないことから、大腸で発生したH2は生体に何ら作用を及ぼすことのない物質として捉えていたのである。無機化学においてH2分子が白金やパラジウムのような触媒存在下で還元性を示すことは古くから知られていた。生体内でも同様にH2が還元性を示す可能性はあったわけであるが、先に示したような触媒が存在しない生体内で有力なエビデンスを示した研究は長い間なかった。
H2分子による生体内抗酸化と大腸発生H2の可能性
2007年にOsawaらは、脳虚血-再灌流(IR)処置によって酸化ストレスを与えたラットにH2ガスを吸入させることによって、生成されたヒドロキシラジカルが特異的に捕捉され、酸化障害が軽減されることを見出した。この研究は、生体内でH2が還元性を示すことを初めて明らかにしたものであり、その後も、さまざまな酸化ストレスに対しH2分子が抗酸化作用を示すことが報告されている。一方、食物繊維をはじめとする難消化性糖質は、大腸内発酵によるH2生成を促し、そのH2は呼気および放屁に排泄されることが知られている。我々は、このH2も同じように生体内で抗酸化作用を発揮する可能性をひらめいた。大腸内発酵を利用してH2を生体内に供給できれば、安定的かつ持続的に生体内還元性を維持できると期待される。生体内における不必要な酸化反応を防御することで、酸化障害を発端とする生活習慣病の発症や進展を抑えることが可能であろう。
我々は、Savaianoらの報告にもとづいて、ラクトース(20g)摂取後のヒト呼気中H2濃度の変動から、ヒト門脈血中の平均的H2濃度を推定した。一般的な生理学的データより換気量に約500mL/分、呼吸数に16~18回/分を用いて、8時間で呼気中に排出されるH2量の推算を行った。その結果、20gのラクトース摂取で96~108mL/8hのH2が排泄されることがわかった。さらに、拍出量に約5L/分を用い、門脈血流量を消化管に流入する血流量(全血流量の約28%)と同じとして算出した。この結果、門脈血中の平均H2濃度は6.4~7.2μMであると推定できた。このH2濃度は、我々のラットによる実験結果(後述)ともほぼ一致しており、この濃度で酸化ストレスが軽減されることを確認している。また、これまでに酸化ストレスの軽減を示したH2ガスやH2水による研究でも、同程度の血中H2濃度が報告されている。したがって、大腸でH2生成を促進する基質を十分に供給すれば、生体で酸化ストレスを軽減できうることを示唆している。
大腸発生H2による生体内抗酸化と酸化障害軽減
実験動物のブリーダーでは、動物の腸内細菌叢を均一化するため、出生直後にいくつかの腸内細菌を接種している。それにもかかわらず、発酵基質となる高アミロースデンプン(HAS;難消化性画分を50~60%含む)やペクチンを摂取させたときのラットH2生成能に大きな違いが存在する。そこで、このばらつきを利用してH2生成量と酸化障害との関係を調べた。H2生成能にばらつきのある66匹ラットにHASを与えると、7日後の門脈H2濃度に大きな違いが各個体に認められた。これらのラットすべてに肝IR処置で酸化ストレスを与え、血漿アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)活性(肝障害マーカー)の変化を観察した。門脈H2濃度をカテゴリ変数(五分位数)として血漿ALT活性変動を解析すると、図1のような関係がみられる。門脈H2濃度が低い場合、肝IR酸化障害によって血漿ALT活性は高値を示したが、H2濃度が8.4μmol/L近辺でメジアンは最小値を示した。それ以上のH2濃度では血漿ALT活性はわずかに上昇を示した。これは門脈H2濃度が極端に低い領域では、酸化ストレスに対する防御能がないことを示している。門脈H2濃度が高い場合、大腸内発酵が活発であり、それにともなってさまざまな物質が生成される。その中には酸化障害による炎症を助長するものもあるかもしれない。例えば、細胞毒性の強いアンモニアなどは、虚血-再灌流によって機能の低下した肝臓では炎症を引き起こす可能性も考えられる。H2は生体内における酸化障害を抑制する能力を有するが、大腸H2生成を高める場合、やみくもに発酵を盛んにすることを考えるだけでなく、その他の発酵産物の影響が大きくなる可能性も考慮する必要があるだろう。
次に、高H2生成能ラットを用い、発酵性の高いHASやペクチンを与えたときの酸化ストレスヘの影響を調べた。セルロースを食物繊維源とする精製飼料を与えたラットの(放屁+呼気)H2排出量が0.13μmol/5min以上を示す個体を選別し、HASやペクチンを与えると門脈H2濃度は3~15倍に上昇する(図2)。このようなラットの肝臓にIR処置で酸化ストレスを与えると、IRによって低下した肝グルタチオンの還元型/酸化型比はHASやペクチン投与によって改善した(図2)。これぱHASやペクチン投与によって多量に生成したH2が肝臓で還元性を示し、IRによって酸化状態に傾いたものを回復させたと考えられる。これに伴って、IRによって著しく上昇した血漿ALT活性は、HASやペクチン投与ラットで低下した(図2、3)。これらの結果より、大腸内で生成したH2は門脈を経て肝臓で酸化ストレスを軽減しうることが明らかとなった。また、これまでに虚血後の短時間(30~60分)の再灌流だけでなく、長時間(24~48時間)の再灌流による酸化障害にも、HAS投与によるH2生成が有効であることも示した。
糖尿病、虚血性疾患、動脈硬化症、アルツハイマー病などのような生活習慣病の多くは、酸化ストレスの増大に伴った障害によって発症および進展が誘導される。また、肥満も生体内酸化ストレスを増大させ、生活習慣病発症の引き金となっている。大腸で生成したH2でこれらの酸化ストレスを軽減できれば、さまざまな生活習慣病予防につながることが期待される。そのためには生体内のさまざまな組織に安定的に持続してH2を供給することが重要であるといえよう。
大腸H2生成と持続的H2供給
生体内へのH2の直接的な供給方法として、H2ガスの吸入やH2水の飲水がある。実験動物やヒトを対象とした研究もなされており、それらがH2供給法として有効であることは間違いない。しかし、日常生活における持続的な供給という観点に立てば、決してこれらの方法が有効とはいえない。H2ガスの吸入は病院などで大掛かりな設備が必要であるし、吸入をやめればH2が供給されなくなる。また、H2水であれば、投与直後のH2供給量は多いが、飲める量に限界もある。H2の水への溶解度はとても低い(0.8mmol/L)ため、生体内に高濃度のH2を長時間にわたって供給し続けることは困難である。さらに、摂取後にH2血中濃度がピークを迎え、元に戻るまでの時間も30分程度しかない。この点において、大腸内発酵によるH2の供給は合理的である。大腸に発酵基質を十分量存在すれば、たとえ睡眠時に食事を摂っていなくとも生体内に24時間H2を供給できるはずである。
我々はこれまでにラットを用いた実験で、十分量の発酵基質を大腸に送れば、24時間H2生成が高く維持されることを確認している(図4の20%HAS食群)。一方、大腸内で24時間に資化できる量とほは等量の基質を与えると、投与開始から24時間後のH2生成量はほとんど消失する(図4の10%HAS食群)。このことから大腸に十分量の発酵基質を送り届けることの重要性がわかる。大腸内に滞留している時間も重要であり、十分量に基質を供給しても、滞留時間が短ければ、基質当たりのH2生成が抑えられると考えられる。さらに、H2が長期間にわたって安定的に生成し続けることも生体内還元力を高めるために欠かせない。単一の発酵基質をラットに与えると、投与初期はH2生成量が多く、その後減少するという現象を頻繁に目にする。酸化還元電位の低い大腸内に常在する嫌気性細菌は発酵基質として大腸に流入してきた糖質を主に利用し、ATPを生成している。つまり、発酵基質からH+を獲得し、電子伝達系で自由エネルギーを獲得している。しかし、嫌気性細菌では酸素を利用できないため、H+およびe-からH2ガスを生成する。この状態が過剰になると、H2分圧が高まるため、H2生成がうまく進まなくなる。これが長期間にわたって、極端に高いH2生成能を維持できない理由かもしれない。このような状態にH+およびe-を利用してメタン、硫化水素、酢酸を生成する細菌が活性化すると、H2分圧が下がるため、H2生成がうまく進むかもしれないが、H+がほかに利用されてしまうため、H2ガスの生成はやはり低下する可能性が高い。ヒトの食生活を考えれば、単一の発酵基質を摂取し続けることはありえないが、サプリメントのように単一のものを長期間多量に摂取しても、高H2生成能を長期にわたって維持することは期待できないかもしれない。今後生体内で安定的かつ持続的に多量のH2を生成できるような発酵環境条件を見出すことが重要な課題となると思われる。また、大腸内発酵産物で有用とされている酪酸生成との関係も考えておく必要はあるだろう。H2生成を高めても、逆に酪酸生成は低下するかもしれない。このようなときにどういった発酵がヒトにとってベストもしくはベターであるかを考慮すべきだと考える。
おわりに
H2分子の生体内抗酸化作用はすでに多くの報告がされており、疑う余地はほぽない。大腸内発酵によってH2が生成され、何ら生体に影響をもたらさない分子として考えられていたが、我々の研究によってその抗酸化作用が明らかになった。これまで食物繊維の生理作用として、現象は再現よく観察されるにもかかわらず、それを説明するに足る作用機構が明らかになっていないものがある。その一部はこの大腸発生H2による作用で説明できるかもしれない。まさしく、これは食物繊維の新機能と言えるのではないだろうか。最近の我々の研究で、大腸で生じたH2が腹腔に拡散し、とりわけ脂肪組織に局在していることも見出した。食物繊維など難消化性糖質の摂取で脂肪組織をはじめとする腹腔内の組織にもH2が供給されるという事実は、肥満時の脂肪組織における酸化ストレスも軽減できる可能性を示している。こういった酸化ストレスを大腸生成H2によって制御できれば、食物繊維が新たな局面で生活習慣病予防に大きく寄与すると思われる。この機能を踏まえ、食物繊維の可能性をさらに探究していく価値は多いにあると考える。また、これまでの概念や思考にとらわれず、食物繊維の消化管を介して引き起こす生理作用にさまざまな角度からアプローチしていく気概が食物繊維の研究や開発に取り組む研究者に欠かせないだろう。
食品と開発2013年1月号 UBMメディア

マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計