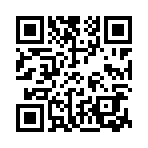2013年07月25日
健食の機能性表示制度、導入決定 米国の表示制度を改良
政府は健康食品の機能性表示導入を決めた。企業責任に基づく新表示制度が2014年度にも示される。健食の規制緩和については、厚労省時代から再三にわたる検討を繰り返してきたが、結論はいつも「健康食品はカヤの外」。健康食品を吸い上げることを目指した「条件付き特保」に至っては、数年の運用でたったの1件しか許可されていない。こうした状況を打破したのは、政権交代によって復活した「規制改革会議」だ。4ヵ月という短い期間で、健康食品の抜本的な表示規制緩和に道筋をつけた。これを受けて行政サイドは、米国の制度を参考に、企業責任によって機能性表示を認める新制度の設計に入る。折しも来年は、1994年の米国「DSHEA」施行から20年。周回遅れながら、日本の健食新制度はようやく実現へ歩み出す。「何でも表示できる」と先走るのは禁物だが、“ヨーイドン”に備えたシミュレーションは必要がある。

■規制改革会議が台風の目に
昨年末に発足した安倍新政権は、2013年に入り、景気回復に向けた施策を次々と打ち出した。1 月11日に、日本経済再生に向けた緊急経済対策を閣議決定。農林水産省の「機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト」が取り上げられるなど、政権交代に伴う期待感は健康食品産業でも膨らみつつあった。そして上半期における“台風の目”となった「規制改革会議」が初会合を開いたのが1月24日。この時はまだ、健康食品の表示については取り上げられていなかった。こうした状況下で、消費者委員会が『健康食品』の表示等の在り方に関する建議を取りまとめたのが1月29日。建議事項は、表示・広告の適正化に向けた取組強化や、機能性表示に関する検討など。表示規制緩和については、「栄養機能食品の拡充の検討」にとどまり、業界内では「そんなもんだろう」と、もとより期待していない声が聞かれた。このあきらめムードが吹き飛んだのが、規制改革会議が2 月15日に開いた第2回会合である。「一般健康食品の機能性表示の容認」という検討項目が示された。
規制改革会議は首相の諮問機関で、安倍首相が「成長戦略の一丁目一番地」と位置付けた規制改革に関する議論を行うために設置。岩盤のような規制を改革するとの強い意志のもと、エネルギー・環境、健康・医療、雇用、創業などの分野に大胆に切り込んだ。要望は、国民や経済界から寄せられたものを整理した。「一般健康食品の機能性表示の容認」を提言したのは、大阪大学大学院医学系研究科教授の森下竜一氏。機能性表示の導入によって、国民の健康改善にとどまらず、産業振興や雇用創出が期待できると主張した。そして健食の機能性表示容認は、優先検討事項とすることが決まった。その後ワーキンググループでの検討にうつり、健康食品産業協議会や日本健康・栄養食品協会、日本通信販売協会などからヒアリングした。「現行制度は妥当」と主張する消費者庁との綱引きの結果、軍配は規制改革会議に。6月5日、ついに答申がまとまり、「一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備」が盛り込まれた。
この間の折衝で注目すべき点がもうひとつある。この件では厚生労働省からもヒアリングを実施。健康食品を食品衛生法で定義づけることには抵抗したが、特保のように健康増進法などで別途定義することに「異論はない」と理解を示した。さらに、安全性への配慮が必要と前置きした上で、「健康増進法等による仕組みにおいて機能性表示を認めることについて異論はない」と回答した。厚労省の所管法に立ち入ってこなければ、表示の部分は消費者庁に任せるとの立場を示唆した。健康食品を「いわゆる」付きで呼び、その存在をなかなか認めなかった厚労省のこの回答に、業界はどよめいた。背景には、医薬品ネット販売を規制する省令を「無効」とする最高裁判決が影響したとの見方も。
規制改革会議の答申を受けて政府は6月14日、「日本再興戦略」「規制改革実施計画」を閣議決定。「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認」について、2014年度に結論・措置することが正式に決まった。新制度設計に当たっては、「企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に行う」ことを付け加えた。ここに至って、健康食品表示の規制緩和は国の方針として決定した。
健康産業新聞1489号(2013.7.3)より一部抜粋
■規制改革に関する答申~経済再生への突破口~
平成25 年6月5日
規制改革会議
③一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備
国民の健康に長生きしたいとの意識の高まりから、健康食品の市場規模は約1兆8千億円にも達すると言われている。しかしながら、我が国においては、いわゆる健康食品を始め、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)以外の食品は、一定以上の機能性成分を含むことが科学的に確認された農林水産物も含め、その容器包装に健康の保持増進の効果等を表示することは認められていない。このため、国民が自ら選択してそうした機能のある食品を購入しようとしても、自分に合った製品を選ぶための情報を得られないのが現状である。
また、特定保健用食品は、許可を受けるための手続の負担(費用、期間等)が大きく中小企業には活用しにくいことなど、課題が多く、栄養機能食品は対象成分が限られていることから、現行制度の改善だけで消費者のニーズに十分対応することは難しい。このような観点から、国民のセルフメディケーションに資する食品の表示制度が必要である。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130605/item3.pdf
■消費者基本計画 閣議決定
平成22年3月30日
平成25年6月28日一部改定
6.いわゆる健康食品の表示等(施策番号:76、76-2、77関係)【消費者庁、厚生労働省、農林水産省】
消費者が正しい情報に基づき適切にいわゆる健康食品の利用の要否や適否を判断できる環境整備を行うため、いわゆる健康食品に関する表示・広告の適正化に向けた取組の強化、安全性に関する取組の推進、機能性の表示に関する検討、及び特性等に関する消費者理解の促進等を図ります。
(1)
・食品表示に関する景品表示法と健康増進法の一元的な法執行体制の構築
・いわゆる健康食品の表示に関する景品表示法と健康増進法の観点からの「留意事項(法解釈の指針)」の取りまとめ
(2)
・栄養機能食品制度において新たな栄養成分を追加することや、特定保健用食品制度における審査の基準や手続の明確化について検討
(3)
・いわゆる健康食品の過剰摂取や要配慮者の摂取等、消費者の正しい理解のための情報提供に努めるとともに、いわゆる健康食品に起因する消費者事故への対応を推進
(4)
・いわゆる健康食品による健康被害情報の収集・解析手法の研究・健康被害防止に関し、必要に応じ、所要の措置の実施
・いわゆる健康食品の安全性確保に関する取組の実施
(5)
・いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討
76.消費者庁による「健康食品の表示に関する検討会」の論点整理及び消費者委員会による「『健康食品』の表示等の在り方に関する建議」を踏まえ、食品表示に関する景品表示法と健康増進法の一元的な法執行を推進するとともに、いわゆる健康食品に関する「留意事項(法解釈の指針)」を取りまとめ、その周知徹底により表示・広告の適正化を図ります。また、特定保健用食品の審査基準の明確化や栄養機能食品の対象成分の拡充の検討等、所要の措置を講じます。
76-2.いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討します。
77.いわゆる健康食品に関する消費者の理解の促進を図るため、いわゆる健康食品に関して正しい情報を提供できる体制の整備を図ります。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130628_kihon.pdf
■規制改革実施計画
平成25年6月14日
閣議決定
③一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備
12.いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認
特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。
13.特定保健用食品制度におけるサプリメント等の形状規制の廃止の周知徹底
現行の特定保健用食品制度において、錠剤、カプセル等形状の食品(サプリメントを含む。)を認めることを改めて明確にするとともに、指導等の内容に齟齬がないよう各都道府県、各保健所設置市、各特別区の衛生主管部(局)に対して周知徹底を図る。
14.食品表示に関する指導上、無承認無許可医薬品の指導取締りの対象としない明らかに食品と認識される物の範囲の周知徹底
食品表示に関する指導において、薬事法における「無承認無許可医薬品の指導取締り」の対象としない「明らかに食品と認識される物」の範囲を運用上も明確にするため、厚生労働省は、その範囲について周知徹底する。併せて食品表示に関する規制における虚偽誇大な表示等に該当するものの指導の際に、薬事法における指導取締りとの齟齬がないよう、消費者庁は、各都道府県、各保健所設置市、各特別区の衛生主管部(局)に上記の「明らかに食品と認識される物」の範囲及び虚偽誇大な表示等に該当するものの指導の根拠等について周知徹底する。
15.消費者にわかりやすい表示への見直し
特定保健用食品や栄養機能食品においても、適切な摂取を促すとともに、消費者の選択に資する分かりやすい表示について検討の上、早期に見直しを図る。併せて、表示を行う事業者等が、表示に関するルール(広告等との違いを含む。)を的確に理解でき、適切な表示(及び広告等)がなされるよう、現在、法・制度ごとにあるガイドラインやパンフレット等を、医薬品との判別も含めて、食品表示全般に係るものとして一本化する。
16.特定保健用食品の許可申請手続きの合理化、迅速化
特定保健用食品の許可申請手続きについて、有効性及び安全性の確認を前提として、審査工程の見直しを行うことで審査の合理化、迅速化を図り、申請企業の負担を軽減する。これに当たり、これまで申請されたものの許可に至らなかった件数(申請者が取り下げたケースも含む。)や、手続きの負担(費用、期間等)がその要因と考えられる事例等を把握し、改善点を明確にし、審査内容、手続きの透明化も含め、見直しに至るまでの具体的な工程表を策定・公表する。
17.栄養機能食品の対象拡大
栄養表示基準や食事摂取基準との整合を図るとともに、海外の事例も参考に、栄養機能を表示できる対象成分を拡大する。
出典:規制改革実施計画 平成25年6月14日 閣議決定
参考:「健康食品」の表示等の在り方に関する調査報告

■規制改革会議が台風の目に
昨年末に発足した安倍新政権は、2013年に入り、景気回復に向けた施策を次々と打ち出した。1 月11日に、日本経済再生に向けた緊急経済対策を閣議決定。農林水産省の「機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト」が取り上げられるなど、政権交代に伴う期待感は健康食品産業でも膨らみつつあった。そして上半期における“台風の目”となった「規制改革会議」が初会合を開いたのが1月24日。この時はまだ、健康食品の表示については取り上げられていなかった。こうした状況下で、消費者委員会が『健康食品』の表示等の在り方に関する建議を取りまとめたのが1月29日。建議事項は、表示・広告の適正化に向けた取組強化や、機能性表示に関する検討など。表示規制緩和については、「栄養機能食品の拡充の検討」にとどまり、業界内では「そんなもんだろう」と、もとより期待していない声が聞かれた。このあきらめムードが吹き飛んだのが、規制改革会議が2 月15日に開いた第2回会合である。「一般健康食品の機能性表示の容認」という検討項目が示された。
規制改革会議は首相の諮問機関で、安倍首相が「成長戦略の一丁目一番地」と位置付けた規制改革に関する議論を行うために設置。岩盤のような規制を改革するとの強い意志のもと、エネルギー・環境、健康・医療、雇用、創業などの分野に大胆に切り込んだ。要望は、国民や経済界から寄せられたものを整理した。「一般健康食品の機能性表示の容認」を提言したのは、大阪大学大学院医学系研究科教授の森下竜一氏。機能性表示の導入によって、国民の健康改善にとどまらず、産業振興や雇用創出が期待できると主張した。そして健食の機能性表示容認は、優先検討事項とすることが決まった。その後ワーキンググループでの検討にうつり、健康食品産業協議会や日本健康・栄養食品協会、日本通信販売協会などからヒアリングした。「現行制度は妥当」と主張する消費者庁との綱引きの結果、軍配は規制改革会議に。6月5日、ついに答申がまとまり、「一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備」が盛り込まれた。
この間の折衝で注目すべき点がもうひとつある。この件では厚生労働省からもヒアリングを実施。健康食品を食品衛生法で定義づけることには抵抗したが、特保のように健康増進法などで別途定義することに「異論はない」と理解を示した。さらに、安全性への配慮が必要と前置きした上で、「健康増進法等による仕組みにおいて機能性表示を認めることについて異論はない」と回答した。厚労省の所管法に立ち入ってこなければ、表示の部分は消費者庁に任せるとの立場を示唆した。健康食品を「いわゆる」付きで呼び、その存在をなかなか認めなかった厚労省のこの回答に、業界はどよめいた。背景には、医薬品ネット販売を規制する省令を「無効」とする最高裁判決が影響したとの見方も。
規制改革会議の答申を受けて政府は6月14日、「日本再興戦略」「規制改革実施計画」を閣議決定。「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認」について、2014年度に結論・措置することが正式に決まった。新制度設計に当たっては、「企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に行う」ことを付け加えた。ここに至って、健康食品表示の規制緩和は国の方針として決定した。
健康産業新聞1489号(2013.7.3)より一部抜粋
■規制改革に関する答申~経済再生への突破口~
平成25 年6月5日
規制改革会議
③一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備
国民の健康に長生きしたいとの意識の高まりから、健康食品の市場規模は約1兆8千億円にも達すると言われている。しかしながら、我が国においては、いわゆる健康食品を始め、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)以外の食品は、一定以上の機能性成分を含むことが科学的に確認された農林水産物も含め、その容器包装に健康の保持増進の効果等を表示することは認められていない。このため、国民が自ら選択してそうした機能のある食品を購入しようとしても、自分に合った製品を選ぶための情報を得られないのが現状である。
また、特定保健用食品は、許可を受けるための手続の負担(費用、期間等)が大きく中小企業には活用しにくいことなど、課題が多く、栄養機能食品は対象成分が限られていることから、現行制度の改善だけで消費者のニーズに十分対応することは難しい。このような観点から、国民のセルフメディケーションに資する食品の表示制度が必要である。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130605/item3.pdf
■消費者基本計画 閣議決定
平成22年3月30日
平成25年6月28日一部改定
6.いわゆる健康食品の表示等(施策番号:76、76-2、77関係)【消費者庁、厚生労働省、農林水産省】
消費者が正しい情報に基づき適切にいわゆる健康食品の利用の要否や適否を判断できる環境整備を行うため、いわゆる健康食品に関する表示・広告の適正化に向けた取組の強化、安全性に関する取組の推進、機能性の表示に関する検討、及び特性等に関する消費者理解の促進等を図ります。
(1)
・食品表示に関する景品表示法と健康増進法の一元的な法執行体制の構築
・いわゆる健康食品の表示に関する景品表示法と健康増進法の観点からの「留意事項(法解釈の指針)」の取りまとめ
(2)
・栄養機能食品制度において新たな栄養成分を追加することや、特定保健用食品制度における審査の基準や手続の明確化について検討
(3)
・いわゆる健康食品の過剰摂取や要配慮者の摂取等、消費者の正しい理解のための情報提供に努めるとともに、いわゆる健康食品に起因する消費者事故への対応を推進
(4)
・いわゆる健康食品による健康被害情報の収集・解析手法の研究・健康被害防止に関し、必要に応じ、所要の措置の実施
・いわゆる健康食品の安全性確保に関する取組の実施
(5)
・いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討
76.消費者庁による「健康食品の表示に関する検討会」の論点整理及び消費者委員会による「『健康食品』の表示等の在り方に関する建議」を踏まえ、食品表示に関する景品表示法と健康増進法の一元的な法執行を推進するとともに、いわゆる健康食品に関する「留意事項(法解釈の指針)」を取りまとめ、その周知徹底により表示・広告の適正化を図ります。また、特定保健用食品の審査基準の明確化や栄養機能食品の対象成分の拡充の検討等、所要の措置を講じます。
76-2.いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討します。
77.いわゆる健康食品に関する消費者の理解の促進を図るため、いわゆる健康食品に関して正しい情報を提供できる体制の整備を図ります。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130628_kihon.pdf
■規制改革実施計画
平成25年6月14日
閣議決定
③一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備
12.いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認
特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。
13.特定保健用食品制度におけるサプリメント等の形状規制の廃止の周知徹底
現行の特定保健用食品制度において、錠剤、カプセル等形状の食品(サプリメントを含む。)を認めることを改めて明確にするとともに、指導等の内容に齟齬がないよう各都道府県、各保健所設置市、各特別区の衛生主管部(局)に対して周知徹底を図る。
14.食品表示に関する指導上、無承認無許可医薬品の指導取締りの対象としない明らかに食品と認識される物の範囲の周知徹底
食品表示に関する指導において、薬事法における「無承認無許可医薬品の指導取締り」の対象としない「明らかに食品と認識される物」の範囲を運用上も明確にするため、厚生労働省は、その範囲について周知徹底する。併せて食品表示に関する規制における虚偽誇大な表示等に該当するものの指導の際に、薬事法における指導取締りとの齟齬がないよう、消費者庁は、各都道府県、各保健所設置市、各特別区の衛生主管部(局)に上記の「明らかに食品と認識される物」の範囲及び虚偽誇大な表示等に該当するものの指導の根拠等について周知徹底する。
15.消費者にわかりやすい表示への見直し
特定保健用食品や栄養機能食品においても、適切な摂取を促すとともに、消費者の選択に資する分かりやすい表示について検討の上、早期に見直しを図る。併せて、表示を行う事業者等が、表示に関するルール(広告等との違いを含む。)を的確に理解でき、適切な表示(及び広告等)がなされるよう、現在、法・制度ごとにあるガイドラインやパンフレット等を、医薬品との判別も含めて、食品表示全般に係るものとして一本化する。
16.特定保健用食品の許可申請手続きの合理化、迅速化
特定保健用食品の許可申請手続きについて、有効性及び安全性の確認を前提として、審査工程の見直しを行うことで審査の合理化、迅速化を図り、申請企業の負担を軽減する。これに当たり、これまで申請されたものの許可に至らなかった件数(申請者が取り下げたケースも含む。)や、手続きの負担(費用、期間等)がその要因と考えられる事例等を把握し、改善点を明確にし、審査内容、手続きの透明化も含め、見直しに至るまでの具体的な工程表を策定・公表する。
17.栄養機能食品の対象拡大
栄養表示基準や食事摂取基準との整合を図るとともに、海外の事例も参考に、栄養機能を表示できる対象成分を拡大する。
出典:規制改革実施計画 平成25年6月14日 閣議決定
参考:「健康食品」の表示等の在り方に関する調査報告
コロナウィルスの治療に水素と酸素の混合気体を吸入
100分で名著「苦海浄土」石牟礼道子
週刊文春・水素水「効果ゼロ」報道に異議あり!
NHKスペシャル シリーズ認知症革命 ついにわかった!予防への道
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
高齢者最多3384万人 団塊世代、全て65歳以上に
100分で名著「苦海浄土」石牟礼道子
週刊文春・水素水「効果ゼロ」報道に異議あり!
NHKスペシャル シリーズ認知症革命 ついにわかった!予防への道
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
高齢者最多3384万人 団塊世代、全て65歳以上に
Posted by suiso at 11:12
│話題
│話題