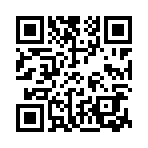2014年02月24日
新機能性表示制度と専門家による情報発信
食品機能性表示関連の「検討会」や「ガイドライン委員会」も着々と進んでおり、日々新たなニュースが流れて来ており、目が離せない状況です。
4月時点で最も新しい情報をお伝えするセミナー行い、キーパーソンである大阪大学の森下竜一先生に来て頂いてたっぷり話をして戴く事になりました。
4月21日(月) 14:00-17:30 です。
「日本を健康にする!」研究会よりセミナー開催のお知らせ
----------------------------------
第8回機能性食品素材セミナー
『新機能性表示制度と専門家による情報発信』
----------------------------------
2013年6月の規制改革実施計画の閣議決定で、いわゆる「健康食品」の機能性表示制度についての検討が進められることとなりました。
制度が実現されれば、業界の大きな変革や市場拡大が予想され、企業にとっては様々な対応が求められます。
本シンポジウムでは、特別講演にて政府の規制改革会議においても中枢の役割を担っている森下竜一先生にご講演頂き、新機能性表示制度に向けて産学は何をすべきか、また、本研究会の主軸である管理栄養士は専門家として、どのようなアクション、消費者に対しての情報提供等が求められるかを主テーマとし、開催します。
日時:2014年4月21日(月) 14:00-17:30
会場:東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館
参加費:
「日本を健康にする!」研究会会員 10,000円、非会員 12,000円
主催:「日本を健康にする!」研究会
協力:ヘルスビジネスマガジン社
<講演者>
◆特別講演
「健康食品の機能性表示を可能とする法整備(仮)」
大阪大学大学院 医学系研究科 教授 森下竜一氏
◆講演
「申請に向け、管理栄養士に求められる役割(仮)」
愛知学院大学 心身科学部 学部長・教授 大澤俊彦氏
◆講演
「米国制度より学ぶ(仮)」
株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田猛氏
◆総括
東京海洋大学 「食の安全と機能(ヘルスフード科学)に関する研究」プロジェクト
特任教授 矢澤一良氏
-----------------------------------
<お申込方法>
下記URLより参加申込書を印刷して頂き、必要事項をご記入の上、事務局宛にお申込ください。
http://www.nihon-kenko.jp/pdf/20140421.pdf
FAXでのお申込ができない方は以下必要事項を記載の上、申込先メールアドレスへご連絡下さい。
申込先メールアドレス:info@nihon-kenko.jp
<申込メール記載事項>
参加者氏名/セミナー名(第8回機能性食品素材セミナー)/会員又は非会員/
住所/勤務先(又は学校名)/連絡先/メールアドレス
★注意事項★
御申込書を事務局へFAXして頂き、事前振込をして頂きましたら参加証をお送りします。
お申込者が多い場合は先着順に締め切らせて頂きますのでお早めにお申込下さい。
【その他、問合せ先】================
「日本を健康にする!」研究会事務局
株式会社RDサポート 担当:石井、大渕
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-15 D&F御茶ノ水ビル5F
TEL 03-5217-5565(代表) FAX 03-5217-5562
info@nihon-kenko.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月時点で最も新しい情報をお伝えするセミナー行い、キーパーソンである大阪大学の森下竜一先生に来て頂いてたっぷり話をして戴く事になりました。
4月21日(月) 14:00-17:30 です。
「日本を健康にする!」研究会よりセミナー開催のお知らせ
----------------------------------
第8回機能性食品素材セミナー
『新機能性表示制度と専門家による情報発信』
----------------------------------
2013年6月の規制改革実施計画の閣議決定で、いわゆる「健康食品」の機能性表示制度についての検討が進められることとなりました。
制度が実現されれば、業界の大きな変革や市場拡大が予想され、企業にとっては様々な対応が求められます。
本シンポジウムでは、特別講演にて政府の規制改革会議においても中枢の役割を担っている森下竜一先生にご講演頂き、新機能性表示制度に向けて産学は何をすべきか、また、本研究会の主軸である管理栄養士は専門家として、どのようなアクション、消費者に対しての情報提供等が求められるかを主テーマとし、開催します。
日時:2014年4月21日(月) 14:00-17:30
会場:東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館
参加費:
「日本を健康にする!」研究会会員 10,000円、非会員 12,000円
主催:「日本を健康にする!」研究会
協力:ヘルスビジネスマガジン社
<講演者>
◆特別講演
「健康食品の機能性表示を可能とする法整備(仮)」
大阪大学大学院 医学系研究科 教授 森下竜一氏
◆講演
「申請に向け、管理栄養士に求められる役割(仮)」
愛知学院大学 心身科学部 学部長・教授 大澤俊彦氏
◆講演
「米国制度より学ぶ(仮)」
株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田猛氏
◆総括
東京海洋大学 「食の安全と機能(ヘルスフード科学)に関する研究」プロジェクト
特任教授 矢澤一良氏
-----------------------------------
<お申込方法>
下記URLより参加申込書を印刷して頂き、必要事項をご記入の上、事務局宛にお申込ください。
http://www.nihon-kenko.jp/pdf/20140421.pdf
FAXでのお申込ができない方は以下必要事項を記載の上、申込先メールアドレスへご連絡下さい。
申込先メールアドレス:info@nihon-kenko.jp
<申込メール記載事項>
参加者氏名/セミナー名(第8回機能性食品素材セミナー)/会員又は非会員/
住所/勤務先(又は学校名)/連絡先/メールアドレス
★注意事項★
御申込書を事務局へFAXして頂き、事前振込をして頂きましたら参加証をお送りします。
お申込者が多い場合は先着順に締め切らせて頂きますのでお早めにお申込下さい。
【その他、問合せ先】================
「日本を健康にする!」研究会事務局
株式会社RDサポート 担当:石井、大渕
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-15 D&F御茶ノ水ビル5F
TEL 03-5217-5565(代表) FAX 03-5217-5562
info@nihon-kenko.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計
この記事へのコメント
第2回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会 議事録
1. 日時
平成26 年1月31 日(金)9:45~11:45
2. 場所
山王パークタワー6 階 消費者委員会 大会議室
3. 出席委員
松澤座長、赤松委員、梅垣委員、大谷委員、河野委員、合田委員、児玉委員、相良委員、清水委員、関口委員、津谷委員、宮島委員、森田委員
4.出席者(省庁関係者)
(内閣府)山本食品安全委員会事務局評価第二課長
(消費者庁)阿南長官、山崎次長、川口審議官、竹田食品表示企画課長、谷口食品表示企画課課長補佐(総括)
(厚生労働省)赤川医薬食品局監視指導・麻薬対策課長、長谷部医薬食品局食品安全部基準審査課長、岡崎医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室健康食品安全対策専門官
(農林水産省)國井消費・安全局表示・規格課長、島田農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室長
5. 議事次第
1.開会
2.食品の新たな機能性表示制度における安全性の確保について
3.その他
4.閉会
○消費者庁竹田課長 ただいまから第2回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催いたします。
本日は、寺本委員におかれましては、御都合により欠席との御連絡をいただいております。14名中13名の委員に御出席をいただいております。
なお、前回、御欠席でありました河野委員が、本日出席されておりますので紹介いたします。
それから、本日もオブザーバーとして、厚生労働省、農林水産省から御出席をいただいております。
なお、今回から、内閣府食品安全委員会事務局評価第二課長の山本課長にも出席いただくことになりました。
○消費者庁竹田課長
では、松澤座長に議事の進行をお願いします。
○松澤座長 それでは、私の司会進行によりまして議事を進めます。今回の議題は、「食品の新たな機能性表示における安全性の確保について」で、これから何回かは、食品の機能表示の中での安全性の確保についてルールを決めていきます。
本日は、「食品の新たな機能性表示における安全性の確保について」、事務局から説明をして、その後、ディスカッションをしていきます。
○消費者庁谷口課長補佐 消費者庁の谷口です。
それでは、私から資料1につきまして説明します。「食品の新たな機能性表示制度における安全性の確保について」という資料です。
まず、2ページ目に目次がございます。この資料全体は大きく4つの項目で構成しております。初めに、安全性の確保に係る検討事項として、本日の論点を示しております。次に、日本における状況として、現在の我が国の食品の安全性確保のための制度について説明しております。その次に、米国における状況で、今般の検討に当たって参考にするアメリカのダイエタリーサプリメント制度について、今回の論点にかかわる部分を紹介したいと思います。最後に、4つ目の項目として、今回の論点についての対応方針(案)を示しております。この資料は、以上の構成としております。
早速、3ページ目「安全性の確保に係る検討事項」です。
前回、第1回の資料におきまして、想定される主な論点として示したもののうち安全性の確保に係るものを上げております。本日は、このうち線で囲んだ部分の「対象となる食品及び成分の考え方並びに摂取量の在り方」という論点につきまして、特に、安全性の評価と情報開示という2つの面から取り上げます。その他の論点につきましては、別の回でまた議論いただきたいと思っております。
4ページ目からは、「日本における状況」です。
まず、5ページ目ですけれども、「食品の安全性確保のための基本的な規定」です。
全ての食品につきましては、食品衛生法の規定に基づきまして安全性の確保が求められています。さらに、食品のうち機能性表示ができる特定保健用食品と栄養機能食品、これは2つ合わせて「保健機能食品」と言いますけれども、これについては、食品衛生法の規定に加えまして健康増進法に基づく規定も適用される、そのような位置づけになっております。
それぞれにつきましては、次のページからもう少し詳しく説明します。
6ページ目です。「食品衛生法の規定」です。
主な規定として4つあげております。1つ目が、食品等事業者の責務です。食品等事業者は、自らの責任において食品の安全性を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされているものです。
2つ目、健康を損なうおそれのある食品などの販売等の禁止です。腐敗したものや有毒・有害な物質が含まれるものなど、健康を損なうおそれのある食品は、販売等をしてはならない規定です。
3つ目、これは、新開発食品の販売禁止です。科学技術の発展や輸入食品の多様化で、それまで食経験のないようなものを摂取する可能性や、食経験があっても、食経験のない水準あるいは方法で摂取する可能性があるので、新開発された食品については、一般に飲食に供されることがなかったもの、通常の方法とは著しく異なる方法により飲食に供されているもので、健康を損なうおそれがない旨の確証がないものなどにつきましては、被害の発生を防止するために販売を禁止することができるとされております。
4つ目、食品又は添加物の基準及び規格です。これは、飲食による被害を未然に防止するための積極的な公衆衛生の見地からの規定で、食品や添加物の製造の基準、成分についての規格を定めることができることとされておりまして、その規格、基準に合わない食品や添加物は販売等してはならない規定です。
このような食品衛生法の規定が、食品全般についてかかっている規定です。
次に、7ページ目からですけれども、こちらは「栄養機能食品の規定」です。
まず対象食品としては、一部に鶏卵というものを含みますけれども、基本的に「生鮮食品を除く食品」とされております。
対象となる食品・成分の要件についてですけれども、まず、対象成分は、ここに上げているビタミン12種類、ミネラル5種類に限られています。また、この対象成分の含有量についての上限、下限という範囲が定められてございます。この上限量につきましては、食事摂取基準の耐容上限量や医薬部外品の最大分量等を考慮して決められたものです。
栄養機能食品につきましては、特定保健用食品とは異なり、個別の許可は不要でして、事業者が規格に適合していることを自己認証する制度となっております。
続きまして8ページ目は、「栄養機能食品の規定②(表示事項)」です。
このページのパッケージ表示例で、赤字で示している部分が表示しなければならない項目です。このうち特に安全性に関するものとしては、四角で囲っておりますけれども、1日当たりの摂取目安量、摂取する上での注意事項がございます。また、特定保健用食品とは異なり、消費者庁の個別審査を受けたものではないという旨の表示も必要となっております。これが栄養機能食品の表示事項です。
続きまして、次のページからは、特定保健用食品の規定です。
対象食品につきましては、「販売に供する食品」で、特段の限定はありません。生鮮食品も対象とはなっておりますけれども、実態として、現時点では生鮮食品で許可を受けたものはありません。
対象となる食品・成分の要件として、ここでは8つありますけれども、このうち特に安全性に関連するものとしては、適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること、関与成分について、性状、試験方法が明らかにされていることなどもありますけれども、特に4番目にあります「食品又は関与成分が、添付資料からみて安全なものであること」が一番重要なものかと思っております。
これにつきましては、このページの下半分のところに、安全性の評価に必要な資料として、もう少し詳しく書いておりますけれども、食経験、in vitro試験、動物試験、ヒト試験などの資料を提出いただきまして、消費者委員会、食品安全委員会で審査されることとなっております。その際に基礎となる資料としては、食経験につきましては、食習慣を踏まえた関与成分の摂取量のデータ、その市販された時期、これまでの販売量などのデータがあげられます。また、試験管試験や動物試験につきましては、各種の毒性試験データがあげられますけれども、食経験が十分にあるものについては、このようなデータは省略できるとされてます。またヒト試験としては、長期投与試験や過剰摂取試験のデータが必要となっています。
次の10ページ目です。「特定保健用食品の規定②(表示事項)」です。
先ほどの栄養機能食品のページと同様に、パッケージ表示例で、赤字で示してある部分が表示しなければならない項目です。このうち特に安全性に関連するものとしては、同じく四角で囲っております1日当たりの摂取目安量、摂取する上での注意事項といったものがあります。また、血糖や血圧に関連するものは、製品によっては、医師等への相談が必要であるといったような注意換起の表示が求められるものもあります。これらの表示内容につきましても、特定保健用食品においては、許可審査の対象となっています。
続きまして11ページ目は、「錠剤、カプセル状等食品の原材料に関する自主点検ガイドライン」です。これは、法令の規制ではありませんけれども、通知で示されているものです。
錠剤、カプセル状などの食品につきましては、過剰摂取等による健康被害の発生を防ぐ観点から、その安全性確保により一層の注意が必要で、事業者の自主的な取り組みを促しています。
その考え方ですが、錠剤、カプセル状等の食品については、過剰摂取の可能性があるため、食経験のみでは健康を害するおそれがないとは言えないため、文献検索により安全性・毒性情報等の収集を行うことや、食経験では安全性を担保できない場合には、その原材料等を用いて毒性試験を行うこと、こういったことを基本として、事業者自らが安全性点検を実施するです。その安全性の点検を実施するに当たっての手法が、この通知の中でフローチャートとして示されております。
続きまして、12ページ目は、「『いわゆる健康食品』の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針」です。これも法令の規制ではありませんけれども、通知で示されているものです。
特定保健用食品や栄養機能食品以外のいわゆる健康食品につきましては、健康被害等を防止するとともに、消費者の適切な利用に資するため必要な事項を表示するよう促しています。
表示事項として、1日当たりの摂取目安量、摂取する上での注意事項、さらには、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言で、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」といったような事項を表示すべきであるとしております。
また、表示方法及び留意事項として、見やすく表示すること、文字の大きさを8ポイント以上といったものもありますし、また、摂取する上での注意事項などを表示するに当たりましては、国立健康・栄養研究所のウェブサイトで提供されております「『健康食品』の安全性・有効性情報」等の科学的かつ客観的な情報データベース等を活用することがあげられております。また、表示の根拠について、ホームページなどで消費者に対し積極的に情報を開示することなどもあげられております。
日本における状況は、ここまでです。
次の13ページからは「米国における状況」です。今般の検討に際して参考にするアメリカのダイエタリーサプリメント制度について紹介します。
まず14ページ目、「ダイエタリーサプリメント制度の対象となる食品と成分の考え方」です。
対象食品ですが、これは、ダイエタリーサプリメントの定義で規定されている内容で、1つ目、食事を補充する目的で、以下の食品成分を含む食品で、ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸、その他の食品成分、これらの濃縮物などがあげられております。
さらに2番目、形状についても規定されておりまして、タブレット、カプセル、粉末、ソフトジェルなどとされております。
また、一般的な食品として、又はそれだけで食事として用いられるものではないということ、「ダイエタリーサプリメント」と表示するものがあげられております。
次に、対象成分についてですけれども、ダイエタリーサプリメントに使用できる成分として、4つの類型のものがあります。1つ目、ダイエタリーサプリメントの法律が施行された年である1994年10月15日以前にダイエタリーサプリメントの形で販売されていた成分は使用できるとなっております。
反対に2番目に、それ以前に販売されていなかったような成分については、新規成分(New Dietary Ingredient:NDI)として、所定の安全性評価を行い、販売の75日前までに米国食品医薬品局(FDA)に届けなければならないとされております。
3つ目が、一般的に安全とみなされる(Generally Recognized As Safe:GRAS)成分についても使用できることとなっております。
4番目、これら1から3までに上げた成分以外で、食品添加物として使用の許可を受けたものも使用できることとなっております。
次の15ページでは、NDIについて、もう少し詳しく説明しております。
「NDIとは」で、先ほどの繰り返しになりますけれども、1994年以前にアメリカでダイエタリーサプリメントの形で販売されていなかった成分です。こういった成分をダイエタリーサプリメントに使う場合には、所定の安全性評価を行った上で、販売の75日前までに届け出ることとされております。
届出事項としては、当該成分の名称、製品中の含有量、使用条件などのほかに、食経験その他の安全性に係るエビデンスがあげられております。この安全性に係るエビデンスにつきまして、どのようなものを示すべきかについて、FDAがガイダンス案を公表しております。このページの下半分のところですけれども、ガイダンス案で、決定されたものではありませんけれども、一定の考え方が示されています。
そこでは、その安全性の情報につきましては、適切な食経験の歴史、安全性試験、又はこれらの両方を含めるべきとされております。この適切な食経験の考え方につきましては、評価する要素として、食経験の長さ、どういった年齢、性別の集団なのか、摂取量、摂取形態、摂取頻度などがあげられております。また、食経験に関しまして、期間として、25年間の広範な使用が最低限必要と考えているが、科学的根拠はほとんどないため、現時点では具体的な推奨はできないともされています。当該成分の使用条件が食経験と異なる場合など、食経験だけでは不十分な場合には、各種の毒性試験やヒト試験など安全性の試験を提出することが適当とされております。
次の16ページですけれども、こちらは、GRAS成分について、もう少し詳しく説明したものです。
「GRASとは」で、安全性評価に関する専門家の見解により、科学的な手続を経て「一般的に安全である」と判断された成分のことです。一般的に安全であるとみなされるためには、食品添加物の承認を得る場合と、量的、質的にも同等のエビデンスが要求されています。このGRASの審査は、原則的に企業が自ら実施することとなっております。
GRASであることの確認事項として、その物質自体に関する事項のほか、使用時期、使用レベルなどの使用に関する事項、その検出方法、その安全性を証明する情報などがあげられております。
続きまして、17ページを御覧ください。ダイエタリーサプリメントの義務表示事項です。①から⑥まで番号をつけて整理しております。
まず、①は具体的な名称ですのでマスキングしておりますけれども、商品名とダイエタリーサプリメントである旨です。②は内容量です。③は原材料ですけれども、別途、⑥の栄養成分表示で記載することとなっておりますその関与成分は除かれているで、それ以外の原材料を記載することとなっております。順番が前後しますが、⑥の栄養成分表示については、通常の食品の栄養成分表示、Nutrition Factというものとは異なりまして、Supplement Factとして表示することとなっております。1回当たりの推奨摂取量や義務表示である主要な栄養成分の含有量を表示するほかに、その関与成分として含まれる成分の名称と量も記載することとなっております。④が、これもマスキングしておりますけれども、製造者などの名称と連絡先として住所又は電話番号を書くことで、有害事象があったときなどの連絡先になります。次に、⑤ですけれども、これは免責表示でして、機能性表示をする場合には、この表示はFDAによって評価されたものではないという旨と、この製品は病気の治療等を目的としたものではないという旨を記載する必要があるです。
ここまでが米国における状況です。
次の18ページからは、今回の論点につきましての「対応方針(案)」です。
19ページ目が、対応方針案の概要です。
まず、基本的方向性ですけれども、1つ目の丸で、機能性を表示する食品については、機能に関与する成分が増強される場合が多いことから、安全性の確保を第一に考慮するとしております。次に、2つ目の丸で、そのためには、当該食品の関与成分が明らかにされていることが必要であるとしており、3つ目の丸で、対象となる食品は、これらの点を満たした食品とするとしております。今回の検討の前提となります昨年6月の閣議決定に書かれておりますけれども、保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物で、対象として、食品の形状等で限定はしありませんけれども、安全性の確保を第一に考えますと、やはり何が効いているかわからないというようなものではなくて、関与成分が明らかにされていることが必要と考えております。一方で、4つ目の丸であげておりますけれども、今回検討する制度は、企業等の責任においてされるものですので、特定保健用食品のように、国が事前に確認して許可するといったようなものではないということにも留意が必要としております。
このような基本的方向性を踏まえた上で、対応方針(案)として2つあげております。
1点目は、関与成分を中心とする食品の安全性について、事業者は自ら評価する。2点目は、その評価結果は、広く情報開示することです。それぞれにつきましては、次のページ以降でもう少し詳しく説明します。
20ページ目を御覧ください。この対応方針案の①の安全性について事業者自ら評価するについてです。
その背景ですが、繰り返しますけれども、機能性を表示する食品については、関与成分が増強されることが多いので、関与成分を中心とする食品の安全性の確保を第一に考慮することとしております。また、今回参考とするアメリカのダイエタリーサプリメント制度では、使用できる成分であるNDIやGRASにつきまして、いずれも事業者において、食経験や安全性試験に基づく評価が求められております。また、いわゆる健康食品につきましては、医薬品との飲み合わせによる健康被害なども懸念されています。
こういった背景を踏まえまして、対応方針の具体(案)の概略を下に示しております。
安全性について、以下の観点から、事業者が自ら評価するで、左側のアが、関与成分を中心とする食品そのものの安全性という観点です。これにつきましては、まず、食経験に関する情報の評価が必要です。これを踏まえた上で、食経験よりも摂取量が増加するなど、食経験に関する情報だけでは十分ではない場合につきましては、さらにその安全性試験に関する情報の評価が必要になってきます。その際には、特定保健用食品で行われているような安全性評価の情報が参考になるかと考えております。
右側のイが、関与成分と医薬品等の相互作用の観点です。関与成分が単独では安全なものであったとしても、成分によっては、ほかの医薬品の効果を弱めたり、逆に増進したりといったこともありますし、1つの製品の中に複数の関与成分が含まれる場合に、関与成分同士で相互作用がないのかといった観点からも評価が必要と考えております。
このような観点から安全性について評価するわけですけれども、その際には、例えば錠剤、カプセル等の形状の食品を評価するに当たって、一般的な食品の状態での食経験で十分と言えるのかなど、その食品が錠剤、カプセル状のものなのか、その他の通常の加工食品なのか、あるいは生鮮食品なのかといった食品形状の違いにも留意するとしております。
続きまして、21ページ目を御覧ください。対応方針(案)①の続きです。前のページでは概略で示していますけれども、このページでもう少し具体的に書いております。
まず、ア.関与成分を中心とする食品そのものの安全性についてです。
(1)の食経験の評価についてですけれども、左側の四角囲みにあげております食習慣を踏まえた摂取量のデータや市販された時期、摂取集団、摂取形態、摂取頻度など、こういった情報に基づきまして食経験の評価を行うで、右側の四角囲みにあげているような、例えば日本全国規模で機能性を表示する食品以上に広範囲の摂取集団において、同等以上の摂取量での一定期間の食経験があるのかといったこと、もしくは日本での食経験はないけれども、日本人と食生活や栄養状態などが似ている国、地域での食経験があるかということなどを確認することが考えられます。
次に、(2)の安全性試験の評価ですけれども、これは、食経験よりも、摂取量が増加するなど、食経験に関する情報では十分ではない場合には、特定保健用食品の安全性評価に必要な情報などを参考にしまして安全性試験に関する情報を評価してはどうかとしております。
こういった安全性評価につきましては、そのデータが成分ベースでのものなのか、当該成分を含む食品、いわゆる製品ベースなのかということにも留意する必要があると考えます。例えば、成分ベースでの安全性評価の結果がその成分を含む製品に適用できることに合理的な根拠があるのかといったことが考えられますので、注意する必要があります。
次に、相互作用については、飲み合わせ等による健康被害を防止するため、摂取上の注意を要するかという観点から、関与成分と医薬品との相互作用があるのか、関与成分を複数含む場合に、関与成分同士の相互作用があるのか、といったような事項を評価します。
続きまして、22ページ目を御覧ください。このページは、対応方針(案)の②、安全性評価の結果を広く情報開示するについてです。
その背景ですけれども、繰り返しになりますが、今回検討する制度は、企業等の責任においてされるものであり、特定保健用食品のように国が事前に確認して許可するものではありませんが、一方で、健康の保持・増進に役立つという機能性が表示されるで過剰摂取されるおそれがあるなど、機能を表示しない通常の食品とは異なったような摂取方法が想定されます。そのため、今回の制度につきましては、企業等の責任ではありますけれども、より安全性に配慮した制度にしていきたいです。
そこで、対応方針の具体(案)として、事業者が評価した安全性に係る情報は、消費者を健康被害から守る上で極めて重要なものですので、広く情報開示をする必要があるとしております。その際には、先ほどもありましたけれども、その食品の形状の違いにも留意する必要があります。例えば、錠剤、カプセルといった形態の食品につきましては、医薬品との誤認を防ぐための記載が必要かどうかも考えられます。
また、この情報開示につきましては、大きく分けて2つの手段があるかと考えております。1つ目は、(1)の容器包装への表示です。消費者に確実に伝えるべき事項として、例えば関与成分名や1日当たりの摂取目安量、摂取上の注意といったもの、さらに、国の評価を受けたものではないこと、疾病の治療等を目的としたものではないこと、こういったものにつきまして、商品の容器包装、ラベルに記載することで確実に情報提供することとしております。
2つ目、(2)の表示以外の情報開示です。こちらは、(1)の容器包装が表示できるスペースが限られているなどの問題点がありますので、せっかく事業者が評価した安全性に係る情報について、全て記載することは大変難しいところです。そのため、容器包装への表示以外の方法による情報開示についても検討してはどうかとしております。この2点が今回の対応方針案として示しています。
私からの説明は以上です。
○松澤座長 ありがとうございました。
かなりの内容を一気に説明していただいたので十分御理解いただいたかどうか、ディスカッションの時間が十分ありますので、ただいまの説明につきまして、不明な点や質問がありましたらどうぞ。
○宮島委員 日本通信販売協会の宮島です。
今、座長のおっしゃったとおりで、非常にボリュームのある資料ですので、質問させていただきたいと思います。
食品の範囲の件ですけれども、対象となる食品及び成分について、19ページに「当該食品の関与成分が明らかにされていることが必要」という文言が入っておりますけれども、これは、考え方として、9ページの特定保健用食品に近い考え方なのかで、それから、さきに説明なさった14ページの米国の制度とは範囲が大きく異なると思います。一方で、制度設計に当たって、米国の制度を参考にとありますので、当該食品の関与成分ということをうたいますと、特に、健康食品の分野に限って言えば、米国のダイエタリーサプリメント制度よりも対象製品の範囲が大幅に狭まる可能性があるのではないかということを質問させていただきたいと思います。
私は、この表示の問題というのは、生活者の立場からわかりやすい表示を常に思っているのですけれども、もう一つは、これからTPPとかいろいろあると、やはり国際化も考えていかなければいけない。日本に入ってくるサプリメント、あるいは我々が出すサプリメントを考えると、国際化あるいは国際標準も考えていかなければいけないと思うので、なるべく諸外国に近い制度も検討していくべきではないかと思っておりますので、その辺をちょっと事務局にお伺いします。
以上です。
○松澤座長 いかがでしょうか、今の御質問、消費者庁の皆様から答えていただけますか。
○消費者庁谷口課長補佐 関与成分が明らかにされていることが必要と申し上げておりますけれども、少なくとも、機能性を表示することにつきましては、どういった成分が効いているのか、効果があるのかということが明らかになっている必要があると考えておりますが、その程度につきましては、ある程度幅があるのかなと考えております。全ての関与成分について、つまびらかに物質レベルで明らかになっている必要はないかと思っておりますし、それは、現行の特定保健用食品制度でも同様で、エキスといったような形でも許可を受けるといったこともあります。そういった形でいきますと、特段、何らかほかの制度より狭くなっているとかといったことではないと思っておりますし、逆に、アメリカのダイエタリーサプリメント制度よりも、形状の規制をせず、通常の加工食品や、農林水産物も、今回の制度については対象範囲として考えておりますので、むしろ広くなっていると考えられるかと思っております。
○松澤座長 よろしいでしょうか。どうぞ。
○河野委員 前回、欠席して申しわけございませんでした。
今回、私たちが検討すべきこととして、「対象となる食品」と書いてございます。前回の協議の中で、今回検討するべき食品について共通理解が得られていたかどうかを確認させてください。というのは、やはりいわゆる健康食品の話ではないと理解して話を進めないと、この検討会のタイトル「食品の新たな機能性表示制度」というものは進んでいかないのかなと思っております。また、改めまして政府から出された規制改革実施計画の中に書かれているものも、農林水産物を含むということなので、ここでは、狭い範囲の議論をすべきなのか、それとも対象を広げて、特定保健用食品と栄養機能食品以外は全て食品ですから、食品表示法も係ってきますし、そのことについてここは、それ以外のものに機能性を表示するときの条件を整えていくのか理解をさせていただければと思っています。
○松澤座長 前回もそれが少しディスカッションになりまして、食品の定義をここで論じるのは何なのかでしたが、基本的には全て含むというところですね。健康に関した機能をうたう場合には全てですね。ただ、本来の固まりのというか、素材だったら、安全性というのはここまで疑うのかということがありますね。食べてきた経験とかで。ただ、それが今、サプリメントのように、そこから抽出したものが、ちょっと薬に近い形で食品の範疇の中にそれも入っているとすれば、この安全性の確保はかなり重要だというディスカッションでこの前は行っています。それでよろしいでしょうか。
○河野委員 続けてよろしいでしょうか。
○松澤座長 どうぞ。
○河野委員 では、全ての食品が対象であるのですね。安全性というのは、私たち消費者にとってみても非常に重要な観点でして、そのことを皆さんで協議してくださるのはありがたいのですが、ただ、今日資料に出されていたところで幾つか、こちらのほうが多分重要であるのにもかかわらず、その重要な部分がただし書きのような形で資料にあらわれていると感じられる部分があります。
今の座長先生のお話を伺いますと、例えば20ページのスライドの一番下、関与成分を中心とする食品そのものの安全性、食経験も含めてですけれども、「その際、錠剤・カプセル・液状等の食品/その他の加工食品/生鮮食品の食品形状の違いにも留意」ではなくて、違いを最初からある程度しっかりと分けないと、それぞれの安全性を担保する要件は違ってくるのではないかと。先ほどおっしゃっていたように、抽出して凝縮されたものに対する安全の確保はどうすべきなのか、それから、生鮮の農林水産物に対する安全の確保とはこう考えるべきなのかという順番が逆のようにちょっと感じております。
さらに21ページでも、最終的に私たちは、今回示されるべき機能が、私たちのふだんの食生活、つまり健康を維持し、増進させるのに非常に寄与するという視点で食品を見ていくことになると思いますから、そうした場合、21ページの上の箱の一番下に書いてある「なお」のところなのですけれども、「成分での安全性評価か、当該成分を含む食品での安全性評価であるかに留意」と書かれていますが、これは当然のことながら、成分を見るということと、それから、特定保健用食品は商品で見ますけれども、そういった形で、どのぐらいの量という、とにかく全てにおいて、今回の安全性のポイントは量だと感じておりますので、その量を担保するには、成分で見るのか含まれている食品で見るのかというのは、これは「なお」ではなく、やはり先に検討すべき課題かなと感じております。そのあたりはどんなふうに合意が図られるのでしょうか。
○松澤座長 竹田課長、お願いします。
○消費者庁竹田課長 今、指摘のありましたいわゆる医薬品に近いような形状のもの、普通の加工食品のようなもの、生鮮食品、それぞれ摂取の仕方が違ってくるという指摘は、前回受けております。それは、我々も認識してございます。
今回提示していますのは、安全性の考え方でハードルの設定をどうするかでして、1つ目は、食経験があるという考えです。それが十分でなければ、安全性の評価というもう一つのものをやっていただかないといけないという考え方です。この考え方自体は、横串で全ての食品に共通だと思っています。ただ、そこから先に行くときに、先生おっしゃるように、形状によって過剰摂取等の可能性があるとか、あるいは生鮮食品では、食べられる量に限界があるのでしょうとか、それぞれ属性、特性がありますので、基本的な考え方は共通なのですけれども、求めるレベルの高さが恐らく変わってくるという指摘だと思いますので、そこは、先生と消費者庁の間に考え方の齟齬はないのではないかと思っています。
それから、2点目の指摘ですが、それも前回あったと思いますけれども、座長から今ありました抽出、濃縮するものにつきましては、目当てのその関与成分だけではなくて、例えば微量の毒素が入っていたりとか、夾雑物があったりということがありますから、そういうものも例えば同じように抽出、濃縮されるのであれば、それは食品全体としてどうなのかということは、当然スコープに入ってくる話だとは我々認識をしてございます。そうした点も踏まえて意見を頂戴できればと思っています。
○松澤座長 よろしいでしょうか。ほかにございますか。どうぞ、梅垣委員。
○梅垣委員 私も形状のことを明確にしないとだめだと思います。錠剤、カプセルとか粉末のものを皆さん、一般の人が食品と思っているのですかという、ここは非常に重要なのです。今、いわゆる健康食品で問題になっているのは医薬品との誤認です。それから過剰摂取です。当然、特定成分を濃縮すると過剰摂取します。
アメリカのダイエタリーサプリメントの1つのメリットとしては、薬でもないし食品でもない、別のカテゴリーとして位置づけているわけです。だから、そういう考え方を最初にしておかないと、生鮮食品で細かくデータを出せといったら、生鮮食品はつくり方によって全然違いますから、それは無理があるのです。錠剤とかカプセルとか濃縮物にすると、やはり普通の食品ではないので、別の考え方をしなければいけない。やはり先ほどお話のあったように、形状で明確に区別して議論していくのが、私はまず必要だと思います。
○松澤座長 いかがでしょうか。どうぞ、大谷委員。
○大谷委員 今のにも関連しますけれども、5ページのところの図が、私は非常に重要だと思っています。医薬品と食品が大きく分けられておりますね。この中で特定保健用食品と栄養機能食品は保健機能食品と説明され、その外側に健康食品という青い丸があり、そのまた大枠のところに白い四角がございます。この白い四角は一般食品ですから全部が食品のカテゴリーだと思います。本来は、その中に生鮮食品と加工食品があって、さらにここでは青いところが「健康食品」と書いてありますけれども、ここが多分、「いわゆる健康食品」というのが正しいのではないかと思っています。従って、このあたりをまずきちんと書き込んでおかないと、なかなか次の議論で、どこをやっているのかわからなくなると思っております。
○松澤座長 基本的に食品の定義がどこへ行くのかというのが一番大きなポイントだと思いますが、今日のここの議論は、それが、錠剤やカプセル形状で売られるのを食品のカテゴリーに入れた、そういうことで進んでいますね。だから、薬とは分けていると。薬事法でない、口に入れる健康を増進させる目的のもので、疾患の治療ではありませんね。そういうものを食品のカテゴリーに入れていると最初に定義してしまうかどうかですね。そこはいかがでしょうか。
○消費者庁竹田課長 今、指摘ありましたけれども、日本の法制上は、医薬品以外は食品ということになっていますので、その中で、今、大谷先生から指摘がありましたけれども、いわゆる健康食品と、それから、その他の加工食品、生鮮食品があるのです。今回は、特定保健用食品、栄養機能食品以外の全ての食品について、機能性表示の可能性を検討して制度をつくるので、形状等による差異は、当然、先ほどの指摘のように考慮はいたしますけれども、全てを食品として共通の横串の制度としてつくっていくのが、今回の我々の案です。
○松澤座長 よろしいですか。どうぞ。
○合田委員 今の食品で錠剤、カプセルと分けるという話が出ていましたけれども、僕は、両方合わせて今まで議論していたので、それで行っていいのではないかと思うのですね。それは、日本の法制上は、もうそれを合わせてやってしまうので、そこで区別しても、結局は対応しようがないのではないかと思うのです。
議論すべきは、ここで言われているのは、今、「関与成分」という言葉が出ていますね。
関与成分がどういうものであるかというのを、最初、宮島委員が少し触れられたと思いますが、そこを議論すると、今の食品全体、ホールの形で見るか、それからいわゆる錠剤、カプセルで見るか、それはどちらもその関与成分の考え方で決まるのではないかと思います。
関与成分という言葉を言うと、それは、やはり安全性で何かコントロールしようと思うと、そのものは量的なコントロールになりますね。量的なコントロールをしようと思うと、それは必ず何らかの方法で分析ができるというのが一番大事であって、一般食品であったとしても、例えばビタミンCは分析ができますから、どのぐらいあるかがわかりますね。それで、ある一定以上の量がある、一定以下の量はないというコントロールができますね。ですから、少なくとも何か機能性を言って安全性を考慮しようと思うと、その関与成分の量が何らかの方法で測れて、それで検証ができる、そういう考え方でいくのが、ここの検討会で一番進むべき方向性ではないかと私は考えています。
○松澤座長 ありがとうございました。そういうことで、今の方針としてはそれをベースとして考えましょう。それで、安全性に関しては、その中で抽出したり増強したりするときに、安全性がかなり重要視されるので、そのルール、その表示方法を考える方向で進みたいと思っております。
どうぞ。
○児玉委員 今のカプセルか生鮮食品かによって、安全性に関しても、いろいろなことを細かく分ける必要はないと思うのですけれども、最終的には、それが安全であることをそれぞれの企業が責任を持つということと思います。それであれば、抽出したものであっても、生鮮食品でも、続けても安全ですよというものをきちんとやっていれば、それぞれの製品とか形状によって変える必要はないのではないかと、先ほどの意見で思いました。
それと、今、アメリカでダイエタリーサプリメントはかなり古くからされていて、多分前回のときに、そこでの今の課題とか、問題になっていることを紹介されたのですけれども、せっかく今度新しい制度をつくるわけですから、アメリカのダイエタリーサプリメント制度での安全性の問題というものをできるだけクリアできるような形で、制度をしっかりしたものにしていただきたいと思います。
1つ、私もよくわからないのですけれども、20ページ、今回の方針のところの対応方針の具体(案)として、下のところですが、アは当然だと思うのですが、イが入っていますね。ほかの関与成分と医薬品とかほかのものとの相互作用、これを明記するというのは、これはアメリカのそれになかったことで、新しく出ているのかなと今ちょっと感じたのですけれども、アメリカでの制度の反省のもとに記載しているのかという点も教えていただきたいということと、もう一つ、サプリメントは、カプセルというのはすごくイメージがわかるのですが、生鮮食品の機能性表示のイメージが湧かない。例えば牛乳はカルシウムがたくさん含まれていると、牛乳を今度の新しい表示のものに表示できるのかとか、あとは、芋には食物繊維がたくさん含まれていると。そのあたりの、むしろ生鮮食品の表示の対象というもののイメージが少し湧かないような気がするのです。
○松澤座長 いかがですか。アメリカのダイエタリーサプリメントの相互作用についての課題は出ているのでしょうか。
○消費者庁竹田課長 アメリカの相互作用のほうは少々お時間をください。
生鮮食品のほうですけれども、まさに大谷先生の専門分野でもあるのですけれども、基本的には、摂取したグループと摂取しないグループで有意な差が出てくるので、具体的な品目を挙げてというのは、私どもまだ知見がございませんので、きちんとお答えすることができないのですけれども、今、農林水産省でも農産物の機能性について予算をつけて検討されておりますので、追ってそういったお話も紹介いただければと思っております。
○松澤座長 常識的に、芋とかそういうものを機能性食品とするというのはちょっとなじまないのでしょうね。そんなことを言い出したら、全ての食品を分析すると何か含まれているわけだから、そういう食習慣とか食文化の問題と機能の問題を混同しないようにすべきだと思います。ただし最近、イタリアなどではリコピンの含有量の多いトマトなどの機能性食品的にやっているとも聞いていますが。 大谷先生。
○大谷委員 ちょっと補足させていただきますと、今、座長がおっしゃったように、一般の生鮮食品のこういう表示というのは全くなじまないのですが、今、私どものプロジェクトでやっていますのは、例えばミカンやお茶の中に関与成分を特定しておいて、それがどれだけ効果があるかをヒトの試験で見ようというのがあります。そういうものについては、ある程度、いろいろ制限があるとは思いますけれども、表示のほうにつなげていけるのではないかと思っています。
その場合、今、議論にありましたように、牛乳は生鮮食品かもしれないけれども、では、ヨーグルトはどうなのか、もうちょっと加工度が上がっていったら、それは加工食品ではありませんかとか、そういうものはいずれこの場で議論になるとは思います。それぞれによって表示の仕方あるいはチェックの仕方が違ってくるかと思っております。
○松澤座長 こういう問題は、機能のディスカッションのところでまた出てくる問題だと思いますので、今は特に安全性に特化して、表示方法をみんなでディスカッションしていただきたいと思っております。
ほかに。どうぞ。
○梅垣委員 ちょっと戻ってしまうけれども、安全性の確保というのは、製品側の要因と利用方法の要因の2つあるのですね。そもそも表示は誰のためかというと、消費者のための表示なのです。消費者が理解できないような表示をしてしまうと、結局は安全性確保ができないわけです。そのときに、先ほどの議論の蒸し返しになりますけれども、形状が錠剤、カプセルであれば、当然利用方法が変わってきます。そこを踏まえてこの表示を考えていかないとだめだと思うのです。
商品を売るための表示ではなくて、消費者が製品を選択するための表示とするのであれば、例えば生鮮食品の機能表示をしてもいいと私は思うのです。それは、消費者教育というか、消費者がこういう食品をとれば健康になれるという思いで表示をするのだったら、それはもう全然違うのです。だから、表示の考え方のもと、売るための表示なのか消費者にきっちり製品を選択してもらって健康になってもらうための表示なのかで、これは全く違うと思うのです。そういうことを考えると、私は、形状のところはある程度考慮しておいたほうがいいのではないかと思います。
○松澤座長 竹田課長、お願いします。
○消費者庁竹田課長 消費者の商品選択に資する誤解のないようなラベリングをするというのは、初回に阿南長官からも申し上げましたけれども、消費者庁の基本的な方針です。
それから、今、指摘いただきました形状について、表示すべき事項が異なってくるのではないかという指摘については、我々そう思っておりますので、また具体のお話のときに、形状の違いによってもっと踏み込んだ表示が必要になってくるのではないかとか、そうした議論は当然していただきたいと思っております。全てが同じでいいということにはならないとは思っております。
○松澤座長 ほかにございますか。どうぞ。
○津谷委員 現状の確認なのですが、このスライドの7ページ目なのですけれども、栄養機能食品の対象は、「鶏卵以外の生鮮食品を除く食品」、一方、9ページの特定保健用食品は、「販売に供する食品(生鮮食品も対象)」。違いは、生鮮食品を含むか含まないかということと、もう一つは、この「販売に供する」と書いてあるのがよくわからないのですが、自家菜園でレタスか何かをつくって食べるのは、販売に供しませんから、例えば特定保健用食品の種を売って、自分のところでつくって、何かフルーツができたらそれを食べるというのは、種は買うわけですけれども、自分で育成しているから販売ではない、そういったことを考えて言っているのか、何かこの「販売」という言葉が入っている意味はあるのですか。
○松澤座長 文言の問題を確認したいと思います。
○消費者庁谷口課長補佐 栄養機能食品につきましても、こちら、栄養表示基準の対象になっているものですけれども、こちらも当然、販売に供する食品でして、こちらは記述が抜けているだけで、同じものです。
○津谷委員 今後の議論が混乱しないように、先ほど宮島さんがおっしゃった関与成分なのですが、やはり産業育成とか輸出入ということを考えると、的確な英語名があるようなものにしておかないと、いろいろ将来混乱が起きるのではないかと思いますね。
先ほどアメリカの制度が説明されて、原文だとSubstanceとかIngredientという言葉が、日本語で両方とも「成分」と書いてありますが、そこの区別も何かよくできていない気がしますので、用語は早目に決めて、定義と、何かそれに相当する英語があればというか、日本人が英語をつくるのも変な感じですけれども、対応する英語を決めておいたほうがいいと思います。
○松澤座長 そういう文言の整理をちょっと一遍確認して。さっきの鶏卵以外何とかを除くと、わかりにくいですよね。
○消費者庁谷口課長補佐 はい。
○松澤座長 鶏卵が入るということだね。
○児玉委員 これは、もう決まっているのですね。これで承認されて、もう定義されている。
○松澤座長 そうです。
どうぞ、宮島委員。
○宮島委員 今、津谷先生からもお話がありました関与成分ですが、規制改革実施計画では、「保健機能を有する成分」という表現になっていると思います。そこをわざわざ「関与成分」に変える必要があるのか、もともと今回のこの検討会は、いわゆる健康食品を初めとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認がテーマになっているわけで、いわゆる健康食品などの機能性表示を容認するものと私は理解しているのですけれども、関与成分であるとか特定保健用食品が出てくると、やはり今、既にある特定保健用食品の制度とどういう違いが出てくるのかとか、特定保健用食品に類するような形のものになるのかとか、そういう懸念をちょっと抱くところがあります。やはり文言の整理というのは非常に大事なことだと私は思いますから、定義はきちんとしていただきたいと思っています。
それから、これは御参考までにですが、先ほど薬との飲み合わせのお話がちょっと出ていました。私はファンケルという会社で、健康相談がありますけれども、8年前から薬とサプリメントの飲み合わせという問合せをしています。今どうかというと、健康相談の1カ月の相談の30%が、今こういう薬を飲んでいるけれども、このサプリメントを飲んでいいのかとか、そういう問合せになっています。必要があればデータベースを開示することはできますけれども、今は御参考までに、それだけ増えてきていると報告します。
以上です。
○松澤座長 そういう意味で相互作用の明記は重要になると思いますが、いかがですか。ここに、5ページの図で示されているように、要するに表示というカテゴリー、明確に特定保健用食品と今回の物で分けられるかどうかですけれども、それは今回、自己表示するか、別のところでデータをとるか、そういう違いだと我々は理解していまして、なかなか特定保健用食品の定義そのものも非常に微妙なので、今回は、我々は企業が自己表示する側からのルールづくりと考えておりますので、よろしいでしょうか。
ほかに。どうぞ。
1. 日時
平成26 年1月31 日(金)9:45~11:45
2. 場所
山王パークタワー6 階 消費者委員会 大会議室
3. 出席委員
松澤座長、赤松委員、梅垣委員、大谷委員、河野委員、合田委員、児玉委員、相良委員、清水委員、関口委員、津谷委員、宮島委員、森田委員
4.出席者(省庁関係者)
(内閣府)山本食品安全委員会事務局評価第二課長
(消費者庁)阿南長官、山崎次長、川口審議官、竹田食品表示企画課長、谷口食品表示企画課課長補佐(総括)
(厚生労働省)赤川医薬食品局監視指導・麻薬対策課長、長谷部医薬食品局食品安全部基準審査課長、岡崎医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室健康食品安全対策専門官
(農林水産省)國井消費・安全局表示・規格課長、島田農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室長
5. 議事次第
1.開会
2.食品の新たな機能性表示制度における安全性の確保について
3.その他
4.閉会
○消費者庁竹田課長 ただいまから第2回「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催いたします。
本日は、寺本委員におかれましては、御都合により欠席との御連絡をいただいております。14名中13名の委員に御出席をいただいております。
なお、前回、御欠席でありました河野委員が、本日出席されておりますので紹介いたします。
それから、本日もオブザーバーとして、厚生労働省、農林水産省から御出席をいただいております。
なお、今回から、内閣府食品安全委員会事務局評価第二課長の山本課長にも出席いただくことになりました。
○消費者庁竹田課長
では、松澤座長に議事の進行をお願いします。
○松澤座長 それでは、私の司会進行によりまして議事を進めます。今回の議題は、「食品の新たな機能性表示における安全性の確保について」で、これから何回かは、食品の機能表示の中での安全性の確保についてルールを決めていきます。
本日は、「食品の新たな機能性表示における安全性の確保について」、事務局から説明をして、その後、ディスカッションをしていきます。
○消費者庁谷口課長補佐 消費者庁の谷口です。
それでは、私から資料1につきまして説明します。「食品の新たな機能性表示制度における安全性の確保について」という資料です。
まず、2ページ目に目次がございます。この資料全体は大きく4つの項目で構成しております。初めに、安全性の確保に係る検討事項として、本日の論点を示しております。次に、日本における状況として、現在の我が国の食品の安全性確保のための制度について説明しております。その次に、米国における状況で、今般の検討に当たって参考にするアメリカのダイエタリーサプリメント制度について、今回の論点にかかわる部分を紹介したいと思います。最後に、4つ目の項目として、今回の論点についての対応方針(案)を示しております。この資料は、以上の構成としております。
早速、3ページ目「安全性の確保に係る検討事項」です。
前回、第1回の資料におきまして、想定される主な論点として示したもののうち安全性の確保に係るものを上げております。本日は、このうち線で囲んだ部分の「対象となる食品及び成分の考え方並びに摂取量の在り方」という論点につきまして、特に、安全性の評価と情報開示という2つの面から取り上げます。その他の論点につきましては、別の回でまた議論いただきたいと思っております。
4ページ目からは、「日本における状況」です。
まず、5ページ目ですけれども、「食品の安全性確保のための基本的な規定」です。
全ての食品につきましては、食品衛生法の規定に基づきまして安全性の確保が求められています。さらに、食品のうち機能性表示ができる特定保健用食品と栄養機能食品、これは2つ合わせて「保健機能食品」と言いますけれども、これについては、食品衛生法の規定に加えまして健康増進法に基づく規定も適用される、そのような位置づけになっております。
それぞれにつきましては、次のページからもう少し詳しく説明します。
6ページ目です。「食品衛生法の規定」です。
主な規定として4つあげております。1つ目が、食品等事業者の責務です。食品等事業者は、自らの責任において食品の安全性を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされているものです。
2つ目、健康を損なうおそれのある食品などの販売等の禁止です。腐敗したものや有毒・有害な物質が含まれるものなど、健康を損なうおそれのある食品は、販売等をしてはならない規定です。
3つ目、これは、新開発食品の販売禁止です。科学技術の発展や輸入食品の多様化で、それまで食経験のないようなものを摂取する可能性や、食経験があっても、食経験のない水準あるいは方法で摂取する可能性があるので、新開発された食品については、一般に飲食に供されることがなかったもの、通常の方法とは著しく異なる方法により飲食に供されているもので、健康を損なうおそれがない旨の確証がないものなどにつきましては、被害の発生を防止するために販売を禁止することができるとされております。
4つ目、食品又は添加物の基準及び規格です。これは、飲食による被害を未然に防止するための積極的な公衆衛生の見地からの規定で、食品や添加物の製造の基準、成分についての規格を定めることができることとされておりまして、その規格、基準に合わない食品や添加物は販売等してはならない規定です。
このような食品衛生法の規定が、食品全般についてかかっている規定です。
次に、7ページ目からですけれども、こちらは「栄養機能食品の規定」です。
まず対象食品としては、一部に鶏卵というものを含みますけれども、基本的に「生鮮食品を除く食品」とされております。
対象となる食品・成分の要件についてですけれども、まず、対象成分は、ここに上げているビタミン12種類、ミネラル5種類に限られています。また、この対象成分の含有量についての上限、下限という範囲が定められてございます。この上限量につきましては、食事摂取基準の耐容上限量や医薬部外品の最大分量等を考慮して決められたものです。
栄養機能食品につきましては、特定保健用食品とは異なり、個別の許可は不要でして、事業者が規格に適合していることを自己認証する制度となっております。
続きまして8ページ目は、「栄養機能食品の規定②(表示事項)」です。
このページのパッケージ表示例で、赤字で示している部分が表示しなければならない項目です。このうち特に安全性に関するものとしては、四角で囲っておりますけれども、1日当たりの摂取目安量、摂取する上での注意事項がございます。また、特定保健用食品とは異なり、消費者庁の個別審査を受けたものではないという旨の表示も必要となっております。これが栄養機能食品の表示事項です。
続きまして、次のページからは、特定保健用食品の規定です。
対象食品につきましては、「販売に供する食品」で、特段の限定はありません。生鮮食品も対象とはなっておりますけれども、実態として、現時点では生鮮食品で許可を受けたものはありません。
対象となる食品・成分の要件として、ここでは8つありますけれども、このうち特に安全性に関連するものとしては、適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること、関与成分について、性状、試験方法が明らかにされていることなどもありますけれども、特に4番目にあります「食品又は関与成分が、添付資料からみて安全なものであること」が一番重要なものかと思っております。
これにつきましては、このページの下半分のところに、安全性の評価に必要な資料として、もう少し詳しく書いておりますけれども、食経験、in vitro試験、動物試験、ヒト試験などの資料を提出いただきまして、消費者委員会、食品安全委員会で審査されることとなっております。その際に基礎となる資料としては、食経験につきましては、食習慣を踏まえた関与成分の摂取量のデータ、その市販された時期、これまでの販売量などのデータがあげられます。また、試験管試験や動物試験につきましては、各種の毒性試験データがあげられますけれども、食経験が十分にあるものについては、このようなデータは省略できるとされてます。またヒト試験としては、長期投与試験や過剰摂取試験のデータが必要となっています。
次の10ページ目です。「特定保健用食品の規定②(表示事項)」です。
先ほどの栄養機能食品のページと同様に、パッケージ表示例で、赤字で示してある部分が表示しなければならない項目です。このうち特に安全性に関連するものとしては、同じく四角で囲っております1日当たりの摂取目安量、摂取する上での注意事項といったものがあります。また、血糖や血圧に関連するものは、製品によっては、医師等への相談が必要であるといったような注意換起の表示が求められるものもあります。これらの表示内容につきましても、特定保健用食品においては、許可審査の対象となっています。
続きまして11ページ目は、「錠剤、カプセル状等食品の原材料に関する自主点検ガイドライン」です。これは、法令の規制ではありませんけれども、通知で示されているものです。
錠剤、カプセル状などの食品につきましては、過剰摂取等による健康被害の発生を防ぐ観点から、その安全性確保により一層の注意が必要で、事業者の自主的な取り組みを促しています。
その考え方ですが、錠剤、カプセル状等の食品については、過剰摂取の可能性があるため、食経験のみでは健康を害するおそれがないとは言えないため、文献検索により安全性・毒性情報等の収集を行うことや、食経験では安全性を担保できない場合には、その原材料等を用いて毒性試験を行うこと、こういったことを基本として、事業者自らが安全性点検を実施するです。その安全性の点検を実施するに当たっての手法が、この通知の中でフローチャートとして示されております。
続きまして、12ページ目は、「『いわゆる健康食品』の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針」です。これも法令の規制ではありませんけれども、通知で示されているものです。
特定保健用食品や栄養機能食品以外のいわゆる健康食品につきましては、健康被害等を防止するとともに、消費者の適切な利用に資するため必要な事項を表示するよう促しています。
表示事項として、1日当たりの摂取目安量、摂取する上での注意事項、さらには、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言で、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」といったような事項を表示すべきであるとしております。
また、表示方法及び留意事項として、見やすく表示すること、文字の大きさを8ポイント以上といったものもありますし、また、摂取する上での注意事項などを表示するに当たりましては、国立健康・栄養研究所のウェブサイトで提供されております「『健康食品』の安全性・有効性情報」等の科学的かつ客観的な情報データベース等を活用することがあげられております。また、表示の根拠について、ホームページなどで消費者に対し積極的に情報を開示することなどもあげられております。
日本における状況は、ここまでです。
次の13ページからは「米国における状況」です。今般の検討に際して参考にするアメリカのダイエタリーサプリメント制度について紹介します。
まず14ページ目、「ダイエタリーサプリメント制度の対象となる食品と成分の考え方」です。
対象食品ですが、これは、ダイエタリーサプリメントの定義で規定されている内容で、1つ目、食事を補充する目的で、以下の食品成分を含む食品で、ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸、その他の食品成分、これらの濃縮物などがあげられております。
さらに2番目、形状についても規定されておりまして、タブレット、カプセル、粉末、ソフトジェルなどとされております。
また、一般的な食品として、又はそれだけで食事として用いられるものではないということ、「ダイエタリーサプリメント」と表示するものがあげられております。
次に、対象成分についてですけれども、ダイエタリーサプリメントに使用できる成分として、4つの類型のものがあります。1つ目、ダイエタリーサプリメントの法律が施行された年である1994年10月15日以前にダイエタリーサプリメントの形で販売されていた成分は使用できるとなっております。
反対に2番目に、それ以前に販売されていなかったような成分については、新規成分(New Dietary Ingredient:NDI)として、所定の安全性評価を行い、販売の75日前までに米国食品医薬品局(FDA)に届けなければならないとされております。
3つ目が、一般的に安全とみなされる(Generally Recognized As Safe:GRAS)成分についても使用できることとなっております。
4番目、これら1から3までに上げた成分以外で、食品添加物として使用の許可を受けたものも使用できることとなっております。
次の15ページでは、NDIについて、もう少し詳しく説明しております。
「NDIとは」で、先ほどの繰り返しになりますけれども、1994年以前にアメリカでダイエタリーサプリメントの形で販売されていなかった成分です。こういった成分をダイエタリーサプリメントに使う場合には、所定の安全性評価を行った上で、販売の75日前までに届け出ることとされております。
届出事項としては、当該成分の名称、製品中の含有量、使用条件などのほかに、食経験その他の安全性に係るエビデンスがあげられております。この安全性に係るエビデンスにつきまして、どのようなものを示すべきかについて、FDAがガイダンス案を公表しております。このページの下半分のところですけれども、ガイダンス案で、決定されたものではありませんけれども、一定の考え方が示されています。
そこでは、その安全性の情報につきましては、適切な食経験の歴史、安全性試験、又はこれらの両方を含めるべきとされております。この適切な食経験の考え方につきましては、評価する要素として、食経験の長さ、どういった年齢、性別の集団なのか、摂取量、摂取形態、摂取頻度などがあげられております。また、食経験に関しまして、期間として、25年間の広範な使用が最低限必要と考えているが、科学的根拠はほとんどないため、現時点では具体的な推奨はできないともされています。当該成分の使用条件が食経験と異なる場合など、食経験だけでは不十分な場合には、各種の毒性試験やヒト試験など安全性の試験を提出することが適当とされております。
次の16ページですけれども、こちらは、GRAS成分について、もう少し詳しく説明したものです。
「GRASとは」で、安全性評価に関する専門家の見解により、科学的な手続を経て「一般的に安全である」と判断された成分のことです。一般的に安全であるとみなされるためには、食品添加物の承認を得る場合と、量的、質的にも同等のエビデンスが要求されています。このGRASの審査は、原則的に企業が自ら実施することとなっております。
GRASであることの確認事項として、その物質自体に関する事項のほか、使用時期、使用レベルなどの使用に関する事項、その検出方法、その安全性を証明する情報などがあげられております。
続きまして、17ページを御覧ください。ダイエタリーサプリメントの義務表示事項です。①から⑥まで番号をつけて整理しております。
まず、①は具体的な名称ですのでマスキングしておりますけれども、商品名とダイエタリーサプリメントである旨です。②は内容量です。③は原材料ですけれども、別途、⑥の栄養成分表示で記載することとなっておりますその関与成分は除かれているで、それ以外の原材料を記載することとなっております。順番が前後しますが、⑥の栄養成分表示については、通常の食品の栄養成分表示、Nutrition Factというものとは異なりまして、Supplement Factとして表示することとなっております。1回当たりの推奨摂取量や義務表示である主要な栄養成分の含有量を表示するほかに、その関与成分として含まれる成分の名称と量も記載することとなっております。④が、これもマスキングしておりますけれども、製造者などの名称と連絡先として住所又は電話番号を書くことで、有害事象があったときなどの連絡先になります。次に、⑤ですけれども、これは免責表示でして、機能性表示をする場合には、この表示はFDAによって評価されたものではないという旨と、この製品は病気の治療等を目的としたものではないという旨を記載する必要があるです。
ここまでが米国における状況です。
次の18ページからは、今回の論点につきましての「対応方針(案)」です。
19ページ目が、対応方針案の概要です。
まず、基本的方向性ですけれども、1つ目の丸で、機能性を表示する食品については、機能に関与する成分が増強される場合が多いことから、安全性の確保を第一に考慮するとしております。次に、2つ目の丸で、そのためには、当該食品の関与成分が明らかにされていることが必要であるとしており、3つ目の丸で、対象となる食品は、これらの点を満たした食品とするとしております。今回の検討の前提となります昨年6月の閣議決定に書かれておりますけれども、保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物で、対象として、食品の形状等で限定はしありませんけれども、安全性の確保を第一に考えますと、やはり何が効いているかわからないというようなものではなくて、関与成分が明らかにされていることが必要と考えております。一方で、4つ目の丸であげておりますけれども、今回検討する制度は、企業等の責任においてされるものですので、特定保健用食品のように、国が事前に確認して許可するといったようなものではないということにも留意が必要としております。
このような基本的方向性を踏まえた上で、対応方針(案)として2つあげております。
1点目は、関与成分を中心とする食品の安全性について、事業者は自ら評価する。2点目は、その評価結果は、広く情報開示することです。それぞれにつきましては、次のページ以降でもう少し詳しく説明します。
20ページ目を御覧ください。この対応方針案の①の安全性について事業者自ら評価するについてです。
その背景ですが、繰り返しますけれども、機能性を表示する食品については、関与成分が増強されることが多いので、関与成分を中心とする食品の安全性の確保を第一に考慮することとしております。また、今回参考とするアメリカのダイエタリーサプリメント制度では、使用できる成分であるNDIやGRASにつきまして、いずれも事業者において、食経験や安全性試験に基づく評価が求められております。また、いわゆる健康食品につきましては、医薬品との飲み合わせによる健康被害なども懸念されています。
こういった背景を踏まえまして、対応方針の具体(案)の概略を下に示しております。
安全性について、以下の観点から、事業者が自ら評価するで、左側のアが、関与成分を中心とする食品そのものの安全性という観点です。これにつきましては、まず、食経験に関する情報の評価が必要です。これを踏まえた上で、食経験よりも摂取量が増加するなど、食経験に関する情報だけでは十分ではない場合につきましては、さらにその安全性試験に関する情報の評価が必要になってきます。その際には、特定保健用食品で行われているような安全性評価の情報が参考になるかと考えております。
右側のイが、関与成分と医薬品等の相互作用の観点です。関与成分が単独では安全なものであったとしても、成分によっては、ほかの医薬品の効果を弱めたり、逆に増進したりといったこともありますし、1つの製品の中に複数の関与成分が含まれる場合に、関与成分同士で相互作用がないのかといった観点からも評価が必要と考えております。
このような観点から安全性について評価するわけですけれども、その際には、例えば錠剤、カプセル等の形状の食品を評価するに当たって、一般的な食品の状態での食経験で十分と言えるのかなど、その食品が錠剤、カプセル状のものなのか、その他の通常の加工食品なのか、あるいは生鮮食品なのかといった食品形状の違いにも留意するとしております。
続きまして、21ページ目を御覧ください。対応方針(案)①の続きです。前のページでは概略で示していますけれども、このページでもう少し具体的に書いております。
まず、ア.関与成分を中心とする食品そのものの安全性についてです。
(1)の食経験の評価についてですけれども、左側の四角囲みにあげております食習慣を踏まえた摂取量のデータや市販された時期、摂取集団、摂取形態、摂取頻度など、こういった情報に基づきまして食経験の評価を行うで、右側の四角囲みにあげているような、例えば日本全国規模で機能性を表示する食品以上に広範囲の摂取集団において、同等以上の摂取量での一定期間の食経験があるのかといったこと、もしくは日本での食経験はないけれども、日本人と食生活や栄養状態などが似ている国、地域での食経験があるかということなどを確認することが考えられます。
次に、(2)の安全性試験の評価ですけれども、これは、食経験よりも、摂取量が増加するなど、食経験に関する情報では十分ではない場合には、特定保健用食品の安全性評価に必要な情報などを参考にしまして安全性試験に関する情報を評価してはどうかとしております。
こういった安全性評価につきましては、そのデータが成分ベースでのものなのか、当該成分を含む食品、いわゆる製品ベースなのかということにも留意する必要があると考えます。例えば、成分ベースでの安全性評価の結果がその成分を含む製品に適用できることに合理的な根拠があるのかといったことが考えられますので、注意する必要があります。
次に、相互作用については、飲み合わせ等による健康被害を防止するため、摂取上の注意を要するかという観点から、関与成分と医薬品との相互作用があるのか、関与成分を複数含む場合に、関与成分同士の相互作用があるのか、といったような事項を評価します。
続きまして、22ページ目を御覧ください。このページは、対応方針(案)の②、安全性評価の結果を広く情報開示するについてです。
その背景ですけれども、繰り返しになりますが、今回検討する制度は、企業等の責任においてされるものであり、特定保健用食品のように国が事前に確認して許可するものではありませんが、一方で、健康の保持・増進に役立つという機能性が表示されるで過剰摂取されるおそれがあるなど、機能を表示しない通常の食品とは異なったような摂取方法が想定されます。そのため、今回の制度につきましては、企業等の責任ではありますけれども、より安全性に配慮した制度にしていきたいです。
そこで、対応方針の具体(案)として、事業者が評価した安全性に係る情報は、消費者を健康被害から守る上で極めて重要なものですので、広く情報開示をする必要があるとしております。その際には、先ほどもありましたけれども、その食品の形状の違いにも留意する必要があります。例えば、錠剤、カプセルといった形態の食品につきましては、医薬品との誤認を防ぐための記載が必要かどうかも考えられます。
また、この情報開示につきましては、大きく分けて2つの手段があるかと考えております。1つ目は、(1)の容器包装への表示です。消費者に確実に伝えるべき事項として、例えば関与成分名や1日当たりの摂取目安量、摂取上の注意といったもの、さらに、国の評価を受けたものではないこと、疾病の治療等を目的としたものではないこと、こういったものにつきまして、商品の容器包装、ラベルに記載することで確実に情報提供することとしております。
2つ目、(2)の表示以外の情報開示です。こちらは、(1)の容器包装が表示できるスペースが限られているなどの問題点がありますので、せっかく事業者が評価した安全性に係る情報について、全て記載することは大変難しいところです。そのため、容器包装への表示以外の方法による情報開示についても検討してはどうかとしております。この2点が今回の対応方針案として示しています。
私からの説明は以上です。
○松澤座長 ありがとうございました。
かなりの内容を一気に説明していただいたので十分御理解いただいたかどうか、ディスカッションの時間が十分ありますので、ただいまの説明につきまして、不明な点や質問がありましたらどうぞ。
○宮島委員 日本通信販売協会の宮島です。
今、座長のおっしゃったとおりで、非常にボリュームのある資料ですので、質問させていただきたいと思います。
食品の範囲の件ですけれども、対象となる食品及び成分について、19ページに「当該食品の関与成分が明らかにされていることが必要」という文言が入っておりますけれども、これは、考え方として、9ページの特定保健用食品に近い考え方なのかで、それから、さきに説明なさった14ページの米国の制度とは範囲が大きく異なると思います。一方で、制度設計に当たって、米国の制度を参考にとありますので、当該食品の関与成分ということをうたいますと、特に、健康食品の分野に限って言えば、米国のダイエタリーサプリメント制度よりも対象製品の範囲が大幅に狭まる可能性があるのではないかということを質問させていただきたいと思います。
私は、この表示の問題というのは、生活者の立場からわかりやすい表示を常に思っているのですけれども、もう一つは、これからTPPとかいろいろあると、やはり国際化も考えていかなければいけない。日本に入ってくるサプリメント、あるいは我々が出すサプリメントを考えると、国際化あるいは国際標準も考えていかなければいけないと思うので、なるべく諸外国に近い制度も検討していくべきではないかと思っておりますので、その辺をちょっと事務局にお伺いします。
以上です。
○松澤座長 いかがでしょうか、今の御質問、消費者庁の皆様から答えていただけますか。
○消費者庁谷口課長補佐 関与成分が明らかにされていることが必要と申し上げておりますけれども、少なくとも、機能性を表示することにつきましては、どういった成分が効いているのか、効果があるのかということが明らかになっている必要があると考えておりますが、その程度につきましては、ある程度幅があるのかなと考えております。全ての関与成分について、つまびらかに物質レベルで明らかになっている必要はないかと思っておりますし、それは、現行の特定保健用食品制度でも同様で、エキスといったような形でも許可を受けるといったこともあります。そういった形でいきますと、特段、何らかほかの制度より狭くなっているとかといったことではないと思っておりますし、逆に、アメリカのダイエタリーサプリメント制度よりも、形状の規制をせず、通常の加工食品や、農林水産物も、今回の制度については対象範囲として考えておりますので、むしろ広くなっていると考えられるかと思っております。
○松澤座長 よろしいでしょうか。どうぞ。
○河野委員 前回、欠席して申しわけございませんでした。
今回、私たちが検討すべきこととして、「対象となる食品」と書いてございます。前回の協議の中で、今回検討するべき食品について共通理解が得られていたかどうかを確認させてください。というのは、やはりいわゆる健康食品の話ではないと理解して話を進めないと、この検討会のタイトル「食品の新たな機能性表示制度」というものは進んでいかないのかなと思っております。また、改めまして政府から出された規制改革実施計画の中に書かれているものも、農林水産物を含むということなので、ここでは、狭い範囲の議論をすべきなのか、それとも対象を広げて、特定保健用食品と栄養機能食品以外は全て食品ですから、食品表示法も係ってきますし、そのことについてここは、それ以外のものに機能性を表示するときの条件を整えていくのか理解をさせていただければと思っています。
○松澤座長 前回もそれが少しディスカッションになりまして、食品の定義をここで論じるのは何なのかでしたが、基本的には全て含むというところですね。健康に関した機能をうたう場合には全てですね。ただ、本来の固まりのというか、素材だったら、安全性というのはここまで疑うのかということがありますね。食べてきた経験とかで。ただ、それが今、サプリメントのように、そこから抽出したものが、ちょっと薬に近い形で食品の範疇の中にそれも入っているとすれば、この安全性の確保はかなり重要だというディスカッションでこの前は行っています。それでよろしいでしょうか。
○河野委員 続けてよろしいでしょうか。
○松澤座長 どうぞ。
○河野委員 では、全ての食品が対象であるのですね。安全性というのは、私たち消費者にとってみても非常に重要な観点でして、そのことを皆さんで協議してくださるのはありがたいのですが、ただ、今日資料に出されていたところで幾つか、こちらのほうが多分重要であるのにもかかわらず、その重要な部分がただし書きのような形で資料にあらわれていると感じられる部分があります。
今の座長先生のお話を伺いますと、例えば20ページのスライドの一番下、関与成分を中心とする食品そのものの安全性、食経験も含めてですけれども、「その際、錠剤・カプセル・液状等の食品/その他の加工食品/生鮮食品の食品形状の違いにも留意」ではなくて、違いを最初からある程度しっかりと分けないと、それぞれの安全性を担保する要件は違ってくるのではないかと。先ほどおっしゃっていたように、抽出して凝縮されたものに対する安全の確保はどうすべきなのか、それから、生鮮の農林水産物に対する安全の確保とはこう考えるべきなのかという順番が逆のようにちょっと感じております。
さらに21ページでも、最終的に私たちは、今回示されるべき機能が、私たちのふだんの食生活、つまり健康を維持し、増進させるのに非常に寄与するという視点で食品を見ていくことになると思いますから、そうした場合、21ページの上の箱の一番下に書いてある「なお」のところなのですけれども、「成分での安全性評価か、当該成分を含む食品での安全性評価であるかに留意」と書かれていますが、これは当然のことながら、成分を見るということと、それから、特定保健用食品は商品で見ますけれども、そういった形で、どのぐらいの量という、とにかく全てにおいて、今回の安全性のポイントは量だと感じておりますので、その量を担保するには、成分で見るのか含まれている食品で見るのかというのは、これは「なお」ではなく、やはり先に検討すべき課題かなと感じております。そのあたりはどんなふうに合意が図られるのでしょうか。
○松澤座長 竹田課長、お願いします。
○消費者庁竹田課長 今、指摘のありましたいわゆる医薬品に近いような形状のもの、普通の加工食品のようなもの、生鮮食品、それぞれ摂取の仕方が違ってくるという指摘は、前回受けております。それは、我々も認識してございます。
今回提示していますのは、安全性の考え方でハードルの設定をどうするかでして、1つ目は、食経験があるという考えです。それが十分でなければ、安全性の評価というもう一つのものをやっていただかないといけないという考え方です。この考え方自体は、横串で全ての食品に共通だと思っています。ただ、そこから先に行くときに、先生おっしゃるように、形状によって過剰摂取等の可能性があるとか、あるいは生鮮食品では、食べられる量に限界があるのでしょうとか、それぞれ属性、特性がありますので、基本的な考え方は共通なのですけれども、求めるレベルの高さが恐らく変わってくるという指摘だと思いますので、そこは、先生と消費者庁の間に考え方の齟齬はないのではないかと思っています。
それから、2点目の指摘ですが、それも前回あったと思いますけれども、座長から今ありました抽出、濃縮するものにつきましては、目当てのその関与成分だけではなくて、例えば微量の毒素が入っていたりとか、夾雑物があったりということがありますから、そういうものも例えば同じように抽出、濃縮されるのであれば、それは食品全体としてどうなのかということは、当然スコープに入ってくる話だとは我々認識をしてございます。そうした点も踏まえて意見を頂戴できればと思っています。
○松澤座長 よろしいでしょうか。ほかにございますか。どうぞ、梅垣委員。
○梅垣委員 私も形状のことを明確にしないとだめだと思います。錠剤、カプセルとか粉末のものを皆さん、一般の人が食品と思っているのですかという、ここは非常に重要なのです。今、いわゆる健康食品で問題になっているのは医薬品との誤認です。それから過剰摂取です。当然、特定成分を濃縮すると過剰摂取します。
アメリカのダイエタリーサプリメントの1つのメリットとしては、薬でもないし食品でもない、別のカテゴリーとして位置づけているわけです。だから、そういう考え方を最初にしておかないと、生鮮食品で細かくデータを出せといったら、生鮮食品はつくり方によって全然違いますから、それは無理があるのです。錠剤とかカプセルとか濃縮物にすると、やはり普通の食品ではないので、別の考え方をしなければいけない。やはり先ほどお話のあったように、形状で明確に区別して議論していくのが、私はまず必要だと思います。
○松澤座長 いかがでしょうか。どうぞ、大谷委員。
○大谷委員 今のにも関連しますけれども、5ページのところの図が、私は非常に重要だと思っています。医薬品と食品が大きく分けられておりますね。この中で特定保健用食品と栄養機能食品は保健機能食品と説明され、その外側に健康食品という青い丸があり、そのまた大枠のところに白い四角がございます。この白い四角は一般食品ですから全部が食品のカテゴリーだと思います。本来は、その中に生鮮食品と加工食品があって、さらにここでは青いところが「健康食品」と書いてありますけれども、ここが多分、「いわゆる健康食品」というのが正しいのではないかと思っています。従って、このあたりをまずきちんと書き込んでおかないと、なかなか次の議論で、どこをやっているのかわからなくなると思っております。
○松澤座長 基本的に食品の定義がどこへ行くのかというのが一番大きなポイントだと思いますが、今日のここの議論は、それが、錠剤やカプセル形状で売られるのを食品のカテゴリーに入れた、そういうことで進んでいますね。だから、薬とは分けていると。薬事法でない、口に入れる健康を増進させる目的のもので、疾患の治療ではありませんね。そういうものを食品のカテゴリーに入れていると最初に定義してしまうかどうかですね。そこはいかがでしょうか。
○消費者庁竹田課長 今、指摘ありましたけれども、日本の法制上は、医薬品以外は食品ということになっていますので、その中で、今、大谷先生から指摘がありましたけれども、いわゆる健康食品と、それから、その他の加工食品、生鮮食品があるのです。今回は、特定保健用食品、栄養機能食品以外の全ての食品について、機能性表示の可能性を検討して制度をつくるので、形状等による差異は、当然、先ほどの指摘のように考慮はいたしますけれども、全てを食品として共通の横串の制度としてつくっていくのが、今回の我々の案です。
○松澤座長 よろしいですか。どうぞ。
○合田委員 今の食品で錠剤、カプセルと分けるという話が出ていましたけれども、僕は、両方合わせて今まで議論していたので、それで行っていいのではないかと思うのですね。それは、日本の法制上は、もうそれを合わせてやってしまうので、そこで区別しても、結局は対応しようがないのではないかと思うのです。
議論すべきは、ここで言われているのは、今、「関与成分」という言葉が出ていますね。
関与成分がどういうものであるかというのを、最初、宮島委員が少し触れられたと思いますが、そこを議論すると、今の食品全体、ホールの形で見るか、それからいわゆる錠剤、カプセルで見るか、それはどちらもその関与成分の考え方で決まるのではないかと思います。
関与成分という言葉を言うと、それは、やはり安全性で何かコントロールしようと思うと、そのものは量的なコントロールになりますね。量的なコントロールをしようと思うと、それは必ず何らかの方法で分析ができるというのが一番大事であって、一般食品であったとしても、例えばビタミンCは分析ができますから、どのぐらいあるかがわかりますね。それで、ある一定以上の量がある、一定以下の量はないというコントロールができますね。ですから、少なくとも何か機能性を言って安全性を考慮しようと思うと、その関与成分の量が何らかの方法で測れて、それで検証ができる、そういう考え方でいくのが、ここの検討会で一番進むべき方向性ではないかと私は考えています。
○松澤座長 ありがとうございました。そういうことで、今の方針としてはそれをベースとして考えましょう。それで、安全性に関しては、その中で抽出したり増強したりするときに、安全性がかなり重要視されるので、そのルール、その表示方法を考える方向で進みたいと思っております。
どうぞ。
○児玉委員 今のカプセルか生鮮食品かによって、安全性に関しても、いろいろなことを細かく分ける必要はないと思うのですけれども、最終的には、それが安全であることをそれぞれの企業が責任を持つということと思います。それであれば、抽出したものであっても、生鮮食品でも、続けても安全ですよというものをきちんとやっていれば、それぞれの製品とか形状によって変える必要はないのではないかと、先ほどの意見で思いました。
それと、今、アメリカでダイエタリーサプリメントはかなり古くからされていて、多分前回のときに、そこでの今の課題とか、問題になっていることを紹介されたのですけれども、せっかく今度新しい制度をつくるわけですから、アメリカのダイエタリーサプリメント制度での安全性の問題というものをできるだけクリアできるような形で、制度をしっかりしたものにしていただきたいと思います。
1つ、私もよくわからないのですけれども、20ページ、今回の方針のところの対応方針の具体(案)として、下のところですが、アは当然だと思うのですが、イが入っていますね。ほかの関与成分と医薬品とかほかのものとの相互作用、これを明記するというのは、これはアメリカのそれになかったことで、新しく出ているのかなと今ちょっと感じたのですけれども、アメリカでの制度の反省のもとに記載しているのかという点も教えていただきたいということと、もう一つ、サプリメントは、カプセルというのはすごくイメージがわかるのですが、生鮮食品の機能性表示のイメージが湧かない。例えば牛乳はカルシウムがたくさん含まれていると、牛乳を今度の新しい表示のものに表示できるのかとか、あとは、芋には食物繊維がたくさん含まれていると。そのあたりの、むしろ生鮮食品の表示の対象というもののイメージが少し湧かないような気がするのです。
○松澤座長 いかがですか。アメリカのダイエタリーサプリメントの相互作用についての課題は出ているのでしょうか。
○消費者庁竹田課長 アメリカの相互作用のほうは少々お時間をください。
生鮮食品のほうですけれども、まさに大谷先生の専門分野でもあるのですけれども、基本的には、摂取したグループと摂取しないグループで有意な差が出てくるので、具体的な品目を挙げてというのは、私どもまだ知見がございませんので、きちんとお答えすることができないのですけれども、今、農林水産省でも農産物の機能性について予算をつけて検討されておりますので、追ってそういったお話も紹介いただければと思っております。
○松澤座長 常識的に、芋とかそういうものを機能性食品とするというのはちょっとなじまないのでしょうね。そんなことを言い出したら、全ての食品を分析すると何か含まれているわけだから、そういう食習慣とか食文化の問題と機能の問題を混同しないようにすべきだと思います。ただし最近、イタリアなどではリコピンの含有量の多いトマトなどの機能性食品的にやっているとも聞いていますが。 大谷先生。
○大谷委員 ちょっと補足させていただきますと、今、座長がおっしゃったように、一般の生鮮食品のこういう表示というのは全くなじまないのですが、今、私どものプロジェクトでやっていますのは、例えばミカンやお茶の中に関与成分を特定しておいて、それがどれだけ効果があるかをヒトの試験で見ようというのがあります。そういうものについては、ある程度、いろいろ制限があるとは思いますけれども、表示のほうにつなげていけるのではないかと思っています。
その場合、今、議論にありましたように、牛乳は生鮮食品かもしれないけれども、では、ヨーグルトはどうなのか、もうちょっと加工度が上がっていったら、それは加工食品ではありませんかとか、そういうものはいずれこの場で議論になるとは思います。それぞれによって表示の仕方あるいはチェックの仕方が違ってくるかと思っております。
○松澤座長 こういう問題は、機能のディスカッションのところでまた出てくる問題だと思いますので、今は特に安全性に特化して、表示方法をみんなでディスカッションしていただきたいと思っております。
ほかに。どうぞ。
○梅垣委員 ちょっと戻ってしまうけれども、安全性の確保というのは、製品側の要因と利用方法の要因の2つあるのですね。そもそも表示は誰のためかというと、消費者のための表示なのです。消費者が理解できないような表示をしてしまうと、結局は安全性確保ができないわけです。そのときに、先ほどの議論の蒸し返しになりますけれども、形状が錠剤、カプセルであれば、当然利用方法が変わってきます。そこを踏まえてこの表示を考えていかないとだめだと思うのです。
商品を売るための表示ではなくて、消費者が製品を選択するための表示とするのであれば、例えば生鮮食品の機能表示をしてもいいと私は思うのです。それは、消費者教育というか、消費者がこういう食品をとれば健康になれるという思いで表示をするのだったら、それはもう全然違うのです。だから、表示の考え方のもと、売るための表示なのか消費者にきっちり製品を選択してもらって健康になってもらうための表示なのかで、これは全く違うと思うのです。そういうことを考えると、私は、形状のところはある程度考慮しておいたほうがいいのではないかと思います。
○松澤座長 竹田課長、お願いします。
○消費者庁竹田課長 消費者の商品選択に資する誤解のないようなラベリングをするというのは、初回に阿南長官からも申し上げましたけれども、消費者庁の基本的な方針です。
それから、今、指摘いただきました形状について、表示すべき事項が異なってくるのではないかという指摘については、我々そう思っておりますので、また具体のお話のときに、形状の違いによってもっと踏み込んだ表示が必要になってくるのではないかとか、そうした議論は当然していただきたいと思っております。全てが同じでいいということにはならないとは思っております。
○松澤座長 ほかにございますか。どうぞ。
○津谷委員 現状の確認なのですが、このスライドの7ページ目なのですけれども、栄養機能食品の対象は、「鶏卵以外の生鮮食品を除く食品」、一方、9ページの特定保健用食品は、「販売に供する食品(生鮮食品も対象)」。違いは、生鮮食品を含むか含まないかということと、もう一つは、この「販売に供する」と書いてあるのがよくわからないのですが、自家菜園でレタスか何かをつくって食べるのは、販売に供しませんから、例えば特定保健用食品の種を売って、自分のところでつくって、何かフルーツができたらそれを食べるというのは、種は買うわけですけれども、自分で育成しているから販売ではない、そういったことを考えて言っているのか、何かこの「販売」という言葉が入っている意味はあるのですか。
○松澤座長 文言の問題を確認したいと思います。
○消費者庁谷口課長補佐 栄養機能食品につきましても、こちら、栄養表示基準の対象になっているものですけれども、こちらも当然、販売に供する食品でして、こちらは記述が抜けているだけで、同じものです。
○津谷委員 今後の議論が混乱しないように、先ほど宮島さんがおっしゃった関与成分なのですが、やはり産業育成とか輸出入ということを考えると、的確な英語名があるようなものにしておかないと、いろいろ将来混乱が起きるのではないかと思いますね。
先ほどアメリカの制度が説明されて、原文だとSubstanceとかIngredientという言葉が、日本語で両方とも「成分」と書いてありますが、そこの区別も何かよくできていない気がしますので、用語は早目に決めて、定義と、何かそれに相当する英語があればというか、日本人が英語をつくるのも変な感じですけれども、対応する英語を決めておいたほうがいいと思います。
○松澤座長 そういう文言の整理をちょっと一遍確認して。さっきの鶏卵以外何とかを除くと、わかりにくいですよね。
○消費者庁谷口課長補佐 はい。
○松澤座長 鶏卵が入るということだね。
○児玉委員 これは、もう決まっているのですね。これで承認されて、もう定義されている。
○松澤座長 そうです。
どうぞ、宮島委員。
○宮島委員 今、津谷先生からもお話がありました関与成分ですが、規制改革実施計画では、「保健機能を有する成分」という表現になっていると思います。そこをわざわざ「関与成分」に変える必要があるのか、もともと今回のこの検討会は、いわゆる健康食品を初めとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認がテーマになっているわけで、いわゆる健康食品などの機能性表示を容認するものと私は理解しているのですけれども、関与成分であるとか特定保健用食品が出てくると、やはり今、既にある特定保健用食品の制度とどういう違いが出てくるのかとか、特定保健用食品に類するような形のものになるのかとか、そういう懸念をちょっと抱くところがあります。やはり文言の整理というのは非常に大事なことだと私は思いますから、定義はきちんとしていただきたいと思っています。
それから、これは御参考までにですが、先ほど薬との飲み合わせのお話がちょっと出ていました。私はファンケルという会社で、健康相談がありますけれども、8年前から薬とサプリメントの飲み合わせという問合せをしています。今どうかというと、健康相談の1カ月の相談の30%が、今こういう薬を飲んでいるけれども、このサプリメントを飲んでいいのかとか、そういう問合せになっています。必要があればデータベースを開示することはできますけれども、今は御参考までに、それだけ増えてきていると報告します。
以上です。
○松澤座長 そういう意味で相互作用の明記は重要になると思いますが、いかがですか。ここに、5ページの図で示されているように、要するに表示というカテゴリー、明確に特定保健用食品と今回の物で分けられるかどうかですけれども、それは今回、自己表示するか、別のところでデータをとるか、そういう違いだと我々は理解していまして、なかなか特定保健用食品の定義そのものも非常に微妙なので、今回は、我々は企業が自己表示する側からのルールづくりと考えておりますので、よろしいでしょうか。
ほかに。どうぞ。
Posted by 第2回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会 (1/2) at 2014年03月16日 20:57
○河野委員 では、話を少し先に、落ちつかないところもありますが、先に幾つか質問があります。
20ページの今後の検討ですが、まず、安全性について「関与成分を中心とする食品」と書かれていますが、複数入っていた場合どういうふうになるのかは、共通理解が必要だと思うのですね。製造の過程でいろいろ入ってくる場合もありますし、現状を考えますと、これもあるけれども、これもあるという複数の成分が関与する場合もあるので、そのときにどう安全性の担保を考えるかが1点目。
それから、あくまでも今回参考にすべきアメリカのDietary Supplement Health and Education Act( DSHEA)は、形状が決まっているのですね。あれは形状が決まっていて、私たちは、先ほどの理解ですと、形状が決まっていない、いわゆる食品全般についての機能性なので、参考にする場合は、そこのところをしっかり切り分けて議論をしていかないと、大きく間違ってしまうと思っております。
○松澤座長 今の複数成分のことについてはどうお考えですか。
○消費者庁竹田課長 AとBが入っていて、こういう作用機序で機能しますであれば、そこは、それぞれ明確にしていただかないといけないということが1つだと思います。あとは、示しているとおり、では、そのAとBを一緒に摂取したときにどういうことになるのかといったことについては、きちんと評価をしていただかないといけないのではないかと考えております。
○松澤座長 どうぞ。
○赤松委員 今の複数のもので気になることが、私は一度、栄養機能食品の調査をしたときに、栄養機能食品の対象となっている成分と表面のうたい文句が異なっていることがありました。したがいまして、安全性を対象としたものと効果をうたうのは、一致させるようにしていただきたいと思います。
○松澤座長 よろしいですか。その成分というのは、先生がおっしゃっているのは、こういうサプリメント的なものも含めてですか。食品というのはいろいろなものがいっぱい入っていますよね。だから、それをどうするか非常に難しい。今から20年ぐらい前に、牛乳を飲むとコレステロールが上がって心筋梗塞になると新聞に大きく出て、その後、牛乳を飲むとカルシウムがとれて骨粗鬆症に効くと論争があった。その中の1つの成分だけで言うと見方が非常に乖離するので、食品は大体その丸ごとの問題なので、それがいいか悪いかは全体で考えないと、どういうことを対象にするかによって決まるので。
今ここで言っている成分とは、そこから抽出したいろいろな物質が濃縮した形で入っているものが、常識的にはそれが対象のような気がしますけれども。あと、食品の形のものの成分の一個一個を言い出すかどうかは、余程その機能が特異のものでない限り、悪いかいいかという話ではなくて、やはり機能をうたっている成分がいいかどうか、安全かどうかという話になる感じがします。大谷先生、そこはどうでしょうか。
○大谷委員 ちょっと補足させていただきますと、例えばお茶の場合ですと、関与成分としてメチル化カテキンがあるのですけれども、例えば、医薬品との関係ですと、カフェインが入っていますのでテオフィリンとの関係が出てきます。そういう場合には少し複雑になりますけれども、基本的には、先生がおっしゃるように関与成分との関係が重要になると思います。
○松澤座長 どうぞ、清水先生、お願いします。
○清水委員 今の議論は、安全性を確保するためにどうするかですけれども、まず、成分か、21ページに書いてあります食品そのものかということです。今のお話で、ほとんどのいわゆる健康食品というのは、関与する成分が複数入っているわけで、その成分が、量と、それから2つなのか、3つなのか、その相互作用も含めてどういう効果があるか、そして、その安全性がどれだけ確保されているかが重要です。安全性について、まず、成分について確認されている、そして、複数のものが入っていれば、トータルのものとして、製品として安全性が確保されている、その両方の安全性が確保されて初めて安全性の確保と言えると思うのですね。
アメリカでもヨーロッパでも、まず機能性を言う場合に、食品のキャラクタライゼーションという言葉が言われます。これは、その食品中にどういう成分又はグループの化合物が入っているかを特定できなければいけないので、キャラクタライゼーションした成分についての安全性と有効性、そして、その複数の成分が入っているトータルの食品としての安全性と有効性、その2つが、もちろん安全性の評価のレベルは変わってくるわけですけれども、その両方があって初めて安全性の確保と言えると思っています。
○松澤座長 どうぞ。
○森田委員 今、例えば複数の関与成分ですとか、それから対象食品と話が行っておりますけれども、まずは、関与成分1つのところからスタートして、そこからそれぞれ、今回この参考にするのは、ダイエタリーサプリメント制度のNDIであり、そして特定保健用食品の考え方であり、それをまずはめて、その上で安全性をきちんと確認するということと思います。その安全性をきちんと確認したものを、企業が自主的にきちんと調べるということを今、話し合っていると思うのですね。
恐らく、例えば農産物とか、先ほどのお茶のメチル化カテキンとか、大豆イソフラボンとか、それぞれ成分を考えていくと、やはりその成分ごとの関与成分というところで量という問題が出てくるし、それがサプリメントだと、やはりもっとそれを一つ一つきちんとしなくてはいけないわけで、まずはそこの1つの安全性の成分に関して、先ほど特定保健用食品の考え方を持ってきてもいいのかとか、それから、例えばアメリカのNDIでしたら、DSHEAの場合はきちんと定義がありますので、それをそのまま持ってきていいのかというのは、常にそこは混乱すると思うのですが、今、安全性をやっているのは、そのDSHEAも持ってきて、特定保健用食品も持ってきてとやっていれば、かなりそこはきちんと安全性に関して食経験をやっていると、ほかの一般的な食品のようなものもクリアできていくと思うのですね。なので、まずはそこの部分で特定保健用食品とかDSHEAのNDIの持ってきたものが妥当かどうかというところ、あと、私はまだ、逆に言うともっとあってもいいのではないかと思っておりまして、では、それを自主的に企業が確認したときに、それを誰が検証するのかとか、それは届け出制度にしてもらわないとどうなのかとか、全体的なその制度設計の部分というところでまずは、これは多分、安全性のときに何度も何度も話し合うと思うのですけれども、そういうことではないかと思っています。なので、まずは関与成分というところで話を深めてもらえればと思います。
○松澤座長 いろいろなディスカッション、意見が出ましたが、今日は、その21ページ、22ページ、そういう方向でいいかどうかという最終的な検討をいただいて終わりたいと思うのですが、今までのディスカッションに基づいて、この①と②についての意見をお願いします。
どうぞ。
○関口委員 ここでは関与成分について安全性を議論しているのですが、例えばイチョウ葉エキスの安全性担保には、関与成分と一緒に抽出されてくるギンコール酸をある濃度以下でないといけない事例もあります。また、濃縮するから有害成分も濃縮されるリスクがあるのではないか議論がありますが、その場合は当然、関与成分としては問題ないけれども、あるAさんがつくると、きちんといろいろ配慮して、一緒に濃縮されているものは排除するけれども、例えばBさんはやっていないこともありますので、当然この両方、関与成分と、それから、後で議論になるかもしれませんけれども、プロセスにかかわることも議論が必要なのではないかと思います。
○児玉委員 よろしいですか。それに関しては、恐らく19ページの基本的方向性のところで、「一般の食品成分と同等の安全性を有していることが必要」とあります。ですから、これが一番基本的になっていると思いますので、今の複数の関与成分云々ということに関しても、幾つかあったとして、表示ですので、3つ効果がある物質があるとして、では、どれを表示するか、それは企業が決めるわけですね。それに関して表示をした場合、ほかのものに関しても安全である。もしかしたら2つ表示できるかもわからない。その辺のところはまたこれから議論になると思うのですけれども、ですから、その表示する機能に関して、その関与成分が明らかにされている、それ以外のものに関しては、「一般の食品成分で安全性を有しているもの」というのが一番初めの前提条件になりますので、やはりその辺のところが混乱しないようにと思います。
○松澤座長 ほかにありますか。どうぞ。
○合田委員 成分表示をするというのは、最後のところでは品質管理につながるのだと思うのですね。今、関口委員が言われたこともそこと関連すると思いますけれども、品質管理をするとすると、最終的には分析法があって、そのものに関して後で検証ができる、誰かが検証ができることが非常に重要です。
もう一つ、品質管理の方法として製造工程を管理する方法がございますけれども、製造工程を管理するのは、そこを義務的にさせなければいけませんから、これはかなり難しいと思うのですね。そうすると、やはり量で何かコントロールできるものが1つあって、それでこの表示制度が進むのだと思います。ですから、何がどういう形になったとしても、検証ができることを常にフィードバックしながら、この議論を進める必要があると思います。
そうしますと、例えばこの21ページに書かれているものも、そういう概念で見れば、量的なコントロールができている、何か検証ができれば、僕はそこそこ納得できるかなと考えています。
○松澤座長 よろしいですか。具体的な検証ができるというのは、それをうたっておいて、どこかでチェックすることですね。
○合田委員 そういうことです。当然、つくられる企業の方は、そこも意識をしてつくられると思いますけれども、そういう意味から言うと、誰かが後で、表示されているのだから、そのとおりかを調べられるというのが大事だと思います。
実際、私は健康食品の分析を過去にたくさんやっていますけれども、書かれているものが入っていないものが非常にたくさんございます。ですから、そういうものを表示するのは、やはりこれはよくないことだと思います。ですから、少なくともその成分の量、それからもう一つは、有害成分の問題も言われましたけれども、有害成分について入っているのであれば、それが入っていないということも証明できる、分析ができるということが横にあって、こういう表示制度が進むのだろうと思います。
○松澤座長 それは食品衛生法のカテゴリーですね。
○合田委員 そうです。
○松澤座長 だから、そういうことでの縛りは当然できるで、その成分が入っている表示が本当か、どうかというのは、健康増進法のカテゴリー。だから、そういう意味での縛りというか法的な縛りはできると。だから、自己責任でやっている場合には、そういうチェックも起こり得る、そういうふうに考えたら、それを全部一個一個成分というのは物理的に無理だと思います。そういうことを前提としたルールづくりになると思いますが、もう一つは、食経験が十分でない、情報が十分でない場合は、やはり特定保健用食品と同じようにしっかりとやっていただくということは盛り込むことになりますね。
どうぞ。
○相良委員 済みません、ちょっと議論を引き戻してしまうかもしれないのですが、先ほど梅垣先生がおっしゃっていたように、私が多分、アカデミックな議論から一番縁遠い存在で、すごく一般目線でお話をさせていただくと、やはり錠剤のものはお薬というイメージがあります。それで、食品だと言われて買っても、やはり飲むときには、家庭内では、例えば食事の後にサプリメントを摂取するというのは、お薬を飲むという感覚があるし、あとは、先生方には申しわけないのですが、もしかしたら処方箋をいただいてもらうお薬より信頼している可能性があると思います。
これは身近な例でもよく見かけるのですが、それはなぜかというと、やはり自分で選択したという意思が入っているからで、お医者様に言われて飲むものと、そこに何かプラス、すがりたいというか、もっとよりよく健康を維持したいという自分の気持ちから選択した何か食品というところに自分の中ではすごく信頼があって、処方箋で、例えばある1,000円ぐらいのお薬をもらっても、サプリメントを自分で5,000円とかでも出す方は一般消費者で多いのではないでしょうかということがあるので、プラスそういったことを考えると、飲み方という点でも、恐らくすごく消費者の独自性というか、もうちょっとよくなるのではないかと思って、過剰摂取の問題が必ずそこに出てきてしまうのではないかと私は思っています。
それは身近な、例えば自分の祖母を見ていても、膝が痛いときに、何種類もそういったサプリメントを並べて飲んでいたりとか、そこには上限がどうとかといった、多分先生方にとっては常識である概念は全然なくて、これを飲めばいいという気持ち、食品というよりは、何か薬に近いような気持ちで飲んでいるのではないかというのをまず感じていますので、それは1つお話しさせていただきたい。
あとは、先ほどから議論されていますこの関与成分の話ですけれども、そこに「食経験」という項目が入っているのですが、これが、例えば食品としてだったら食経験はわかるのですけれども、成分としてとか、あとは、例えばレモン何個分というのは、それは食経験でどう判断するのか教えていただけないでしょうか。レモン自体は、もしかしたら丸ごと食べた方っていらっしゃるのでしょうか。私は、何となくレモンはレモンの果汁を飲むイメージだし、レモン1,000個分を食べたこともありませんし、食経験をどこまで、レモン自体は食べたことがあっても、それを何個分とか、その濃縮された成分である場合、先ほどのイチョウ葉とかグルコサミンですとか、それを食経験に照らし合わせるのはどのようにやるのか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
○松澤座長 どうぞ、竹田課長。
○消費者庁竹田課長 1点目の指摘は、先ほど梅垣先生からもございましたけれども、形状の違いによって過剰摂取の可能性が出てくるのではないかと。そういうことを踏まえますと、先ほど消費者の選択に資するような、間違いのない、誤解のないような表示が必要だという指摘がありますので、そういう意味で、例えば表示すべき事項に違いが出てくる、濃淡が出てくることは十分あると考えております。
それから、2点目ですけれども、食経験を考えるときには、先生指摘のように、やはり普通の日本人がこれまで常識的に食べてきた量かは、1つ問われると思います。それが、抽出とか濃縮を加えることで、例えば100倍になるとか200倍になるといったときには、食経験があると言えるかどうか当然議論になってくると考えております。
○相良委員 ありがとうございます。
○松澤座長 どうぞ。
○津谷委員 今、相良さんがおっしゃったように、「薬」と言ったり「お薬」と言ったりしますよね。例えば、「飲む薬」とか、効くものが薬ですので、有効性なり効果が何か幾らかでもあると、どうしても人は「薬」と言ってしまうと思うのですが、今、消費者庁でやっている大規模なアンケート調査にそういったものが入っていればいいなと私は思うのですね。人々がどういう具合に認知しているかですね。
それと、食経験のことなのですけれども、21ページに、「具体的なエビデンスに基づき、食経験を評価」と書いてあって、左の四角の枠の中に、「食習慣等を踏まえ……」等6項目ありますね。3番の「これまでの販売量」というのは、今日の配付資料の特定保健用食品にもあるものなのですが、私は、特定保健用食品の販売量というのは、何ケースとか、何錠とか、何トンとか、余り意味なくて、やはりどのぐらいの消費者数というか、それを使用した数と、例えば年間とか、あるいはそれがいつから、その一種の積分として考えるべきです。1,000年前から使っていたと言っても毎年10人しか使わないものと、この半年で10万人使ったものとありますから、歴史と時間的な軸と具体的にある時間帯の中で、それを使った人の数の両方だと思うのですね。
それが、この21ページのスライド左の四角の一番下に「摂取者の規模」と書いてありますね。これがきっと人数のことだと思いますね。人数はすごく大事で、先ほどラベルとか、消費者とのコミュニケーションで大事なリスクコミュニケーションがありますね。1,000人のうち1人に悪さがあるのですとか、100万人のうち1人ですとか、あるいは3人に1人がちょっと胃の調子が悪くなりますよという、基本的にはリスク・ベネフィット・コミュニケーションになるわけですけれども、特にリスクが食品の場合には重要になりますので、その人数がわかるのがすごく大事です。そうすると、現在の特定保健用食品はそれを求めていませんから、やはり特定保健用食品もいずれそれが必要になるのではないかという気がします。
それと、この「エビデンスに基づき」で、その下に「安全性試験」とありますが、既にもう副作用が出ているもの、健康被害が出ているものがあるわけですね。その実態がきちんと把握できることも大事ですね。私は、昔WHOで働いていたこともあるのですが、ウプサラモニタリングセンターという、スウェーデンのウプサラというところにあるモニタリングセンターで、もともとWHOがやっていたのを、今そのセンターがWHOの協力センターとしてやっていて、世界中の副作用が一元的に集まるようになっています。その中に、健康食品の副作用情報も入っているのですね。日本では厚生労働省がナショナルセンターに指定されていますから、たしか医薬食品局の安全対策課か何かで、それは、例えば消費者委員会も同じ国の機関ですから使えるはずですし、ノルウェーなどは、ブランチがいろいろなところを扱っているのですけれども、梅垣先生のところもきっとそれを使っていろいろな情報を集められれば良いと思います。
実際に新規にこういったものを自己評価でやるときにも、そういったデータベースを漏れなくシステマティックに検索する、評価する。システマティックレビューの概念を取り入れて、どのデータベースをどういう検索式で調べたか、結果がどうか、そこも開示したほうがいいと思いますね。結果だけではなくて、単純に言うと文献検索する方法ですね。
○松澤座長 それは先生、安全性だけではなくて機能の面でもですね。だから、全体としてそういうデータ表示の方法というか基盤を開示したほうがいいと。
○津谷委員 プロセスを開示したほうがいい。
○松澤座長 そういうプロセスを開示したほうがいい。それはちょっと書きとめていただいて。
○津谷委員 それと同時に、今、臨床試験登録制度が皆さん御存じのとおり存在して、私もかかわっているのですけれども、パブリケーションバイアスをなくすというのが最大の目的ですね。今お話ししたようなシステマティックレビューをやるときも、システマティックにやったところ、いろいろな有害事象が見つかってしまった場合、これはやはりちょっと黙っておこうという人が必ず出てくるのですね。ですから、そのシステマティックレビューそのものも、今、登録制度が世界には存在して、2001年からもう始まって、プロスペクトというイギリスでやっているシステムがあるのですけれども、私も幾つかそこには登録してシステマティックレビューをやっていますが、システマティックは、そのプロセスを開示するということ、システマティックレビューをやっていることそのものを事前に公開することなのですね。そういうシステムが世界にあるわけですから大事だと思います。
○松澤座長 清水先生、どうぞ。
○清水委員 ちょっと今、津谷先生が言われたことと重なるところもあるのですが、まず、食経験については、ある、ないということを食経験で言うのはできません。食経験は、程度だと考えています。
では、どのような情報についてその程度を知るかについては、まず量、その量というのは、もちろん質にもかかわるわけで、純度とか、それから一緒に入っているものがどう違うのか、それと、どのぐらいの頻度で、どのぐらいの人数の人が、どのぐらいの期間食べていたのか。そして、その食べていた人が、日本で安全性を確保であれば、日本人と同じ食生活をしていた人たちなのか、同等性がどこまであるのかについて、それぞれどこまで食経験があったのかということを総合的に判断して、食経験がどこまであるか、逆に言うと、食経験が十分あるということが、安全性の評価試験を、これは減らしていいですねという合理的な理由になるわけで、食経験がどれだけあるかということが、食品の安全性試験をどこまでやるかということにつながることが非常に重要だと思います。
○松澤座長 これは、21ページの右の評価のところの、多少文言がいろいろ違うけれども、こういう方針でよろしいでしょうか。
○清水委員 それと、1点追加で、特定保健用食品については、実際にその製品をどういう人がどれだけ摂取したかが、特定保健用食品の食経験として申請資料に入っていることは追加したいと思います。
○松澤座長 21ページの方針に関しては、文言というか摂取集団、先ほど津谷委員からお話がありましたような、販売量のあらわし方とか、そういうことで評価と、そこらはまた考えていただいてと思いますので、この21ページ、相互作用なども非常に強調した対応方針だと、先ほどの児玉先生からの話がありましたように、そういう方向でいいかと思いますが、22ページに関してはいかがでしょうか。どうぞ。
○森田委員 21ページの内容を22ページで「広く情報開示する」とあるのですけれども、これは、例えば食経験ですとかそういうことは、企業が自主的に、こういう食経験があるからとか、これは食経験が足りないから、もっとデータを、安全性に関する情報の評価とか、そういう情報もあわせて開示すると理解してよろしいのでしょうか。まずそこが質問です。
○松澤座長 それでいいですか。
○消費者庁竹田課長 指摘のとおりです。
○森田委員 では、それを検証するのは、先ほど合田先生は量の検証とおっしゃいましたけれども、これは企業が自主的にやって、それをやるときに、その内容をどこで検証するのか、あとは、例えばそれが間違っていたときにどう監視をするのか、そういったことがないと、皆さんそれぞれ、これは例えばガイダンスになるのかどうかもよくわからないのですけれども、こういうガイドラインみたいなものが、この①の内容ですね、例えばこういう食経験がこうだとか、安全性のデータはこうだとか、そういうガイドラインに従ってやっているかどうかを誰がどう検証するのかとか、例えば届け出制度にするのかとか、そういう仕組みをどうお考えか教えてください。
○消費者庁竹田課長 具体的な制度の仕組みにつきましては、初回に提示したように、考えられる論点をつぶした上で、最後に提示と考えていますので、そこについて今、明確なフレームを示せる段階ではございません。
その上で、基本的には、その事業者の方が、今回、科学的根拠を自ら評価して、表示をするので、そこのところは、事業者の方がきちんと評価をしていただく。先生が指摘になりましたように、きちんとしたものにしていただくためにも、情報というものは、購入される消費者に向けてつまびらかにされなければいけない。そのプロセスを通じてきちんとした評価がなされるというところを担保したいと考えております。
○森田委員 わかりました。ただ、事業者が取り組みやすいようにするためには、やはりガイドラインですとか、そういったものがないと、皆さんそれぞれ違う物差しで取り組まれては困ると思います。
○消費者庁竹田課長 それは、先生ごもっともでして、どういうことをしたらいいのかについては、一定の考え方を示していかないといけないだろうと思っております。
○松澤座長 この検討会でその基本のコンセプトを確立して、あとはわかりやすく一般に公開ということになると思います。
合田先生。
○合田委員 今の回答で納得したのですけれども、11ページのところで、自主点検ガイドラインでも少し似たような考え方があります。先ほど津谷先生も言われましたけれども、事前に広く情報を集めることが、まず、安全性を確認することにとって非常に大事なことです。かつて、アマメシバの事件がありましたけれども、文献を調べていさえすれば、ああいう不幸なことは起こらなかったのですね。1つは、単純にそのものだけが原因で、事故が起きたかどうかというのはありますけれども。成分的な情報も含めて、まず広く調べて、それから、今のシステマティックレビューのようなことを実行できれば言うことはありませんし、まず、文献情報から得られることがあって、それが、今、森田先生が言われたように、公開されて、こういうことを調べてありますよというデータが、ネットで検索すると、さっと一番最初のところに出てくるようなサイトがあって、見られるというのがやはり前提ではないかと思います。
そうすれば、しっかりした人がしっかりと調べていますよということがわかりますね。それが消費者にとっては一番安心できることではないかと思います。
○松澤座長 梅垣先生、どうぞ。
○梅垣委員 この自主点検ガイドラインとかは、厚生労働省のときに既にかなり議論されているのですね。それで、何が問題かというと、これの実行がなかなかできない。例えばGMPが、錠剤、カプセルだと必須にしないと国際的にも多分通用しないと思うのですけれども、それが全然ここの中には入っていない。GMPは、普通の生鮮食品には適用できありませんが、錠剤、カプセルとか、濃縮物に対してはGMPの義務づけとかをしないと、国際的には絶対通用しないし、日本の製品は海外には出せない。それで、海外から入ってきますから、産業振興という面でももうすごく問題になると思います。だから、その点を考えていかなければいけないと私は思います。
とにかくGMPが全然ここの中に入ってきていないのと、ガイドラインがいろいろ前から出ているけれども、これが実行されていない、現実的にはできていない。例えば、GMPなどは、私のところでもホームページでいろいろ情報提供しているのですけれども、やはり進まないのですね。これはなぜ進まないかというと、消費者がGMPが何かというのがわからない。商品を買うときの判断基準は、有名人とか何か偉い先生が勧めている、それを参考にしているのです。それは全く意味がないことなのだけれども、消費者の人は、そういう情報を見て商品を買われるから、企業もGMPを取ろうとしないのです。だから、そこのところを改善する考え方を取り入れないと、幾らいいものをつくっても進まないと思います。
○松澤座長 竹田課長。
○消費者庁竹田課長 今のGMPのお話は、次回以降、品質管理のところで議論いただきたいと思っております。
それから、今、指摘いただきました実効性の担保につきましては、制度の仕組み方のところできちんと考えて、我々として提示したいと思っております。
○松澤座長 まだスタートしたばかりで、いきなり最終的な制度を作るのは難しいので、この検討会の間に先生の具体的な提案とかを述べていただきたいと。まずは、今は安全の確保のためのルールづくりというか基本方針を決めていただきたい。
ほかにございますでしょうか。どうぞ。
○清水委員 今日の検討事項、3ページの「対象となる食品及び成分の考え方並びに摂取量の在り方」、そして、「関与成分を中心とする食品の安全性についての事業者自らによる評価」について、いろいろな議論があったのですが、では、この評価をどういう試験、成分の分析、種々の安全性の評価、それから食経験など事業者が行う評価の項目を決めていくのが今日の目的ではないのですか。もう少し具体的に、どこまで決めるのかを伺いたいのですけれども。
○消費者庁竹田課長 それこそ具体的な制度設計のお話はまだ少し先になるとは思っておりますので、基本的には、こうした考え方でというのか、こうしたフレームでいかがでしょうかです。基本、こうした考え方でいいのであれば、肉づけをした上で、またさらに最終的にはどんな形になるかというところで議論いただくと思っております。
○清水委員 では、最後にやると。
○消費者庁竹田課長 いきなり制度の詰めみたいなことを毎回毎回というのは、少し困難な部分がありますので、考え方、フレームについて議論いただければと思っております。
○清水委員 基本的な考え方でいいですね。
○松澤座長 どうぞ。
○森田委員 順番というのはよくわかるのですけれども、ただ、この資料の対応方針案だけを見ますと、企業が本当に自主的にやれば、それで、それをどういう形で、例えば届け出制度にするとか、そういうことがある程度わかっていないと、例えばこういう細かいことを幾ら詰めて、ここで安全性のこととかを詰めていっても、それは、いや、あくまで自主的なもので、アメリカの制度などはそうですけれども、自主的にやっているからといっても、いろいろな安全性の問題は出てきているわけですね。だから、やはり何となく出口を見せていただきながら、一番最初の進め方になるのですけれども、先ほど梅垣先生がおっしゃっていたGMPに関することや、どうやって危険な商品が流通するのを防止したり、有害事象をどうするかとか、そういうものも、毎回これを1回ずつやるのではなくて、全体的にこの4つの部分を同時進行みたいに進める考えでもよろしいのでしょうか。
ある程度そこが見えていないと、今回の基本対応方針だけだとやはりちょっと見えないので、出口の感じというのを時々確認しながらやったほうがいいと思います。
○松澤座長 時間が余りないので、今から全部やるわけにはいきませんけれども、要するに、基本的に機能の表示のほうがもっと重要かもしれませんね。もちろん、薬の場合は安全性が極めて重要なのですけれども、これに関して、だから、薬に近いような形態のものについて今やっているのでして、あとのそういう機能についても、自主的に表示したものが本当に正しいかどうか野放しだとルールをつくっても余り意味がないので、ある程度はそういう方向は時々意見を言っていただきながら、最終的にどうするかという検討はしていくことになると思います。食品という膨大なものをどこまで縛れるかは難しいところですけれども、例えば産地の表示などでも、偽装だったら徹底的に社会的に糾弾される、そういうレベル、自主表示というのは大体そんなものですね。だから、抜き打ち的に何かチェックするとか、そういうことは具体的にはいろいろ頭の中で考えていただいて、これはまだもうちょっとありますので、今ここでいきなり自主表示をどうやって審査するかなんて言い出したら、これは大変な話になってしまうと思います。
○消費者庁竹田課長 今、座長から指摘がありましたように、基本的には、重要な論点についてそれぞれ議論いただいて、その時々で前回のこんな議論にと立ち戻った質問、意見を頂戴するのは全く構わないと思っております。
それで、初回にスケジュールを提示したのですけれども、安全性の議論をしていただいて、それから機能性の議論をしていただいて、それから、最後に総合的に縦横を眺める、「論点整理」と書いていますけれども、そうした議論をいただきますので、そちらでもまた再度きちんと議論を深めてまいりたいと思っております。
○松澤座長 どうぞ。
○河野委員 消費者から見ますと、確かに機能というよりは、口に入るものですから、まず安全をどう確保するかは非常に関心が高いところでして、今日最初にその3ページで示していただいたこの4つに関して言うと、トータルで概要が見えて、「ああ、安全なんだな」と納得するような条件だとは思っているのですね。
今日は、その成分と、それから摂取量、摂取量に関してはどこに提示されているのかが、私としてはちょっと見つけられない感じもするのですけれども、成分の安全を担保するためには、こういう条件でやりましょうねと示されたと。
それで、できればここに書かれていることを、先ほどの、食経験をどういう条件がクリアされれば食経験があると消費者は受け取れるのかと。情報開示される、それに行き着く、そういうこともありますけれども、まずここで最低限、食経験があるとはどういう条件なのか、有識者の先生方がいらっしゃいますから幾つか押さえておいていただきたいのです。では、食経験がないというときはどういうことなのか。ないとなったら、例えば20ページの安全性試験、いわゆる科学的な根拠を示すと。その科学的な根拠の示し方は、どういう条件がついたら、私たちは、「ああ、この成分は安心して口に入れていいものなのか」と理解できるのか、そのあたりをある程度ここで合意しておかないと、また同じことが繰り返されるのではないかというイメージは持っています。
安全性というと、原材料はどうなのかとか、それから、先ほどから出ている製造工程はどうなのか、それから、今日やっている量と、それから摂取にかかわる部分ですね。あと、トータルで考えたときに、「安全性」という一つの言葉でなかなかくくれないので、こういうふうに分けてやるというのもいいのですけれども、まず、今日の部分で、ある程度の合意をとっていただきたい。条件についてぜひ確認をしていただければと思っています。
○松澤座長 ちょっとお答え願えますか。最初、食経験とはどういう定義かですが、いかがですか。普通、食べ物で食経験のないものが入ってきたときのことは、非常に特殊な例ですよね。
○河野委員 例えば、先ほどのアマメシバとかコンフリーとかいろいろ例がありますよね。
それから、大豆と大豆イソフラボンの問題とか、食経験があるというのを消費者はどう理解すればいいのかというあたりを。
○松澤座長 お答え願います。
○消費者庁竹田課長 なかなか何人で、何食で、何年間というように具体的に提示するのは非常に難しいとは思っていますけれども、定性的なお話になりますけれども、例えば○○県○○島で実は食べていたとか、そういうものであれば、食経験としては足りていないのだろうと考えます。21ページに示しております繰り返しになってしまいますけれども、全国規模で、一般的に皆さんが知っていて、普通に食べられている、売られている、それで、それなりの期間摂取されているところが、恐らく定性的には委員の皆様と観念でしょうか、基準は共有できると思うのですけれども、そこについてさらに突っ込んで、もっとこれぐらいがあれば、具体的に指摘いただければと考えております。
○松澤座長 合田先生、お願いします。
○合田委員 食経験というのは、基本的には、食習慣、食生活と含めて考えるべきことです。21ページに書かれているところで、ちょうど四角の中に「摂取形態、摂取方法、摂取頻度、摂取者の規模等」がありますね。これはまさに食生活がどうであったかをより細かく言うとここで示されていることです。結局、食習慣とか食生活と同じ状態であって初めて、その安全性が担保されていると一応言えるだろうとなりますから。アマメシバのように、例えば現地で実際には、普通に庭に生えているアマメシバをとってきて食べるというような食経験だったのですね。ですけれども、それを乾燥させて粉末にしてジュースに入れて飲むとか、牛乳に入れて飲むという食経験はなかったわけですね。だから、そこには食経験があるとは多分言わないことになります。
それから、ソテツみそなどの場合に、あれはソテツの有害成分を最初に除いて、最後、みその形態にした形によって初めて食経験があります。ですから、ソテツに食経験があるということは言わありません。
ですから、常にどういう食習慣の中でこれが食べられてきた経験があるかということを確認して、それを開示していただく、そういうことで皆さん、多分同意がとれるのではないかと私は思います。
○松澤座長 基本的に、食文化とも関係しますから、それと成分の機能というものとは分けないとだめですね。だから、日本人が食べているものでも、生卵のぶっかけなんて、ほかの国の人はほとんど食べませんね。ヒヨコになりかけの卵は食べる人に、生卵のぶっかけをやったら、気持ち悪くて食べられないと言うわけですから、そういうふうにして、文化と経験は、やはり食文化の話と機能とまた話がちょっと違うので。フグなんかを最初に食べた人は、すごいなと思うし。
梅垣先生。
○梅垣委員 追加ですけれども、やはり調理、加工の方法も考えておかないと、例えばジャガイモは安全だと言っても、芽の部分はみんな除いていますよね。だから、そういう調理、加工の方法というものも食経験の中の重要な要因です。
先ほどのアマメシバの話ですけれども、あれは利用目的が一番の問題なのです。痩せるために台湾でかなりとった。栄養補給とかというのではなくて、痩せるという別の目的にしてしまったので、大量に摂取して健康被害が出た。日本でも閉塞性の細気管支炎が出たのは、健康にいいと言って粉末とか錠剤を摂取したから問題が起きたのです。
○松澤座長 どうぞ。
○大谷委員 食経験の問題では、量の問題があると思いますが、生鮮物に関しては、産地が非常に特別なところでして、例えばお茶の産地ですと1日10杯飲むとか、ミカンも5個、6個、10個食べるとか、そういうところのデータというのはございます。そういう意味では生鮮物に関しては、ある程度担保できるだろうと考えております。
○津谷委員 よろしいでしょうか。15ページに米国の例としてNDIと、この下半分に「食経験その他安全性に係るエビデンスについて」と書いてあって、丸の2つ目の下に「食経験の長さ(期間)、摂食集団」云々とあるのですが、今回、消費者庁でつくっていただいた21ページの左の四角、さっき6項目と言いましたが、実際に書くと9項目、後に「等」がついているのですけれども、この米国とちょっと順番が違ったりしているのですが、何か日本ではもっといいものをつくったという、そういう順番なのでしょうか。
○松澤座長 どうぞ。
○森田委員 同じ点なのですが、よろしいでしょうか。
私も同じようにそこのところを思っていまして、ここに書かれている食経験は、多分アメリカのNDIのここのページのものと、それから、恐らく特定保健用食品の食経験に関するデータというところで、特定保健用食品で条件づけられている参考データの食経験に関するデータというところが合わさって、そこでつくられているという形で、両方だと思っているのですけれども、その両方で食経験を、食経験プラス安全性の評価で、それをクリアしたということを条件にしていると見えたのですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。NDIの食経験その他に関するエビデンスについてです。
○松澤座長 15ページ。
○森田委員 それから、特定保健用食品の食経験に関するデータというのが別途あると思うのですが、それと合わせて、この21ページの「食経験に関する情報の評価」と「安全性試験に関する情報の評価」をつくられたのかどうかと。よく読みますと、NDIには長期試験とかがあるのだけれども、こっちは長期試験がないとか、比べてみると違うような感じがあって、先生がおっしゃるとおり、項目が違っていたり、NDIなのか特定保健用食品なのかよくわからないのですが。
○消費者庁谷口課長補佐 両方参考にしてつくっているところではございますが、一つ一つの項目について精査して、これは必要、これは必要という形で厳密に決定して、今、あげたものではございませんので、そこまでの厳密な精査はできていないと了解いただけたらと思います。
○松澤座長 どうぞ。
○児玉委員 食経験に関しては、皆さん非常に、イメージもそれぞれの先生方で違うと思うのですね。ですから、できましたら、先ほどガイドラインとおっしゃったのですけれども、具体的に幾つか示していただくほうがディスカッションしやすいのではないかと思います。今、皆さん方からの意見を参考にして、例えばこういうふうに提示するのがいいですね、こういうものはだめですよとか、何個かそういう具体例を示していただくほうがディスカッションしやすいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。難しいですか。
○松澤座長 ほかにございますか。どうぞ。
○宮島委員 事務局にちょっとお願いですが、進め方ですけれども、安全性というのは4回まであって、それから、5回目から機能性とまた大きく変わると思うのですね。そこの時点で振り返りというかレビューをぜひやっていただきたい。
最後にまとめるのではなくて、やはり中間で振り返りが必要だと思っていますので、それはぜひお願いしたい。
それから、これは意見ですけれども、22ページで、先ほどちょっと情報開示ということと企業等の責任があったのですが、私は情報開示には2つあると思っていて、例えば我々のホームページでお客様向けに開示するときに、非常に細かくて文章だらけ、文字だらけというのはほとんど読んでいただけません。皆さん御承知のとおり、1つの文章で漢字が36%を超えると解読率が極端に落ちるというデータもあるので、やはり読みやすいものと、それから、それのもとになる精緻なデータと2つ必要になると思うのですね。
どちらも開示することはもちろん構わないのですけれども、読んでいただかないと全く意味がないので、そういう読みやすさ、わかりやすさというものをぜひ、まだこの段階では早いのですけれども、考えていただきたいと思います。
それからあと、企業の責任もあるのですが、これはやはりアメリカのような非常に訴訟社会で考えている自己責任と日本なんかの考え方と違うと思うので、ある程度、その考え方とか定義というものは少しまとめておく必要があるのではないかと思っています。
以上です。
○松澤座長 ありがとうございました。情報開示と一つ一つの食品への表示を明確にが基本で、それの方法というか、具体的にはそれも詰めていくことになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ほかに何か。どうぞ。
○関口委員 食経験による安全性担保の判定基準として、アメリカの様に、GRASにしてもNDIにしても年で切る、1958年とか1994年、これも1つの考え方としてはあると考えます。
それから、安全性を判断するために、情報社会なので、先生方おっしゃられたように、グローバルに副作用等の情報なども集まりますので、この点も必要だと思います。グランドファザー制をどの様に考えるかという事も重要だと思います。
最後に二点。一点目は22ページに「医薬品を服用している者は医師に相談」と書いてありますが、薬剤師の方も入れておいたほうが良いと思います。
二点目は、厚生労働省のガイドラインを基に、実は、まだまだ有効にどんどん利用されているとは言いませんけれども、健康食品認証制度協議会が健康食品の安全性確保のために第三者認証制度を立ち上げており、第三者チェックをやっておりますので、そういうことも実際やられておりますということの紹介です。
○松澤座長 どうもありがとうございました。
ぼつぼつ時間が来たのですが、まだほかに何か、5分ありますが、よろしいでしょうか。
どうぞ。
○赤松委員 重なる意見ですが、情報開示について、今、出されている案が2つあります。それは、1つは、その食品自体に載せるものと、あと、ホームページなど、そのほかに載せるということ。しかし消費者はこれだけで安全であるとは認識していません。これは一方通行のコミュニケーションです。企業がこれをすれば、何か企業の責任がなくなるという、消費者に責任を押しつけているようなところもあります。
やはり私が何度も言っているような教育も必要ですし、それ以外のところで安全性や危険を考えていることも私たちは認識しておかなければいけないと思っています。
先ほどから梅垣先生がおっしゃっているように、錠剤であるものと野菜というものの違いで、安全であるか危険であるかと思ったり、その企業がすごく歴史のあるところであるとやはり信頼してしまうとか、どこでつくられているのかでも安全性を判断していたりとか、その安全性や危険というものは、この表示をすればいいだけ、開示をすればいいだけではないと認識しておかなければいけないと思っております。
○松澤座長 どうぞ。
○消費者庁竹田課長 先ほども、売るためではなくて、消費者にとって商品選択に資するような、という指摘がありましたけれども、そういった考え方でどういう表示事項が求められるかといった点については、当然考えてまいりたいと思っております。
それから、ラベリングと、別途の情報開示だけで不十分ではないかと前回も指摘を頂戴しましたけれども、当然、消費者の方に、こういうジャンルの食品とは一体どういうものなのか理解を深めていただくことについては、別途それは引き続き必要だと思っておりますので、そうしたことも検討していきたいと考えております。
○松澤座長 よろしいでしょうか。
○津谷委員 先ほど関口さんから、グランドファザー制とかGRASの話が出て、これがスライド14枚目なのですけれども、ここに対象成分として4つあると。2つ質問がありまして、日本にはこういうコンセプトがあるのか、昔から使っていて広く使われていれば、とりあえず安全とみなしましょう、あるいは有効性をみなしましょうということもあるのか。
それは、医薬品とダイエタリーサプリメントと両方あるのですけれども、もう一つ、4番に食品添加物が出てきますね。私は、たしかこのGRASとは食品添加物から始まった概念だと聞いているのですけれども、ちょっとこの辺が、私も今、勉強しているのですけれども、これは、食品添加物でGRASであればダイエタリーサプリメントに入れていいという解釈になるのか。日本でも、食品添加物として、日本のポジティブリストに載っているものを健康食品に入れることがありますよね。どうもその辺が混乱していてよくわからないのですけれども。
以上です。
○松澤座長 いかがですか。お答えできますか。
○消費者庁竹田課長 日本の制度の中で同じような考え方というのは、先生がおっしゃるようなものであれば、いわゆる既存添加物がそういう事例に当たるのではないかと思っております。
○松澤座長 どうぞ。
○厚生労働省長谷部課長 後のほうの質問で、食品添加物であれば食品に入れていいかというところですが、食品添加物として指定したときに、対象食品を決めているものもございますし、あとは使用基準を決めているものもございます。何も決めていないものについては普通に使っていいということになりますが、対象食品と使用基準を決めているものについては、その範囲内のみ使用することが可能だという制度になっております。
○松澤座長 いろいろ意見、先生、何かありますか。
○清水委員 先ほど赤松先生が消費者教育ということを言われて、今回の新たな機能性表示の食品についての消費者教育又は情報開示のことでちょっとお話ししたいのですけれども、いろいろ消費者のヒアリングとかアンケート調査をやってみると、特定保健用食品についてはよく知っているのですが、栄養機能食品については、20%から30%の認知度しかない。栄養機能食品と栄養補助食品の区別がつかないということもあります。栄養補助食品と特定保健用食品の違いは、制度の違いと、あとマークがあるかないかがあります。今回の新たな機能性表示の食品をつくるのであれば、この新たな機能性表示の食品には、こういう情報開示ができています、又はこういうことが必要なのですということが消費者にわからないと、その情報を得ようとする消費者も少なくなってしまうです。明確にこの新たな機能性表示の食品が制度としてできました、そして商品も区別ができました、例えばマークとかですね、そういうものをつくるのも、安全性確保、情報開示のためにも必要なのではないかと思います。
○松澤座長 ありがとうございます。そういうことのためにこの検討会が発足したのだと思います。ここである程度のコンセプトを確立して、これまではそういうことがなかったわけですから、今おっしゃったように補助とか何かわからないままだった。
大体意見もいただいたと思いますが、基本的には、安全性の確保についての基本コンセプトは、そう大きな齟齬がないということで、本日はこれで終わりたいと思います。
この方向で消費者庁で制度として詰めていただいて、引き続き、安全性に関してはあと3回ぐらいやるのですか、できるだけまたディスカッションをしっかりして進めていきたいと思います。
○消費者庁竹田課長 最後に、次回は2月25日、16時からの開催を予定しております。会場につきましては、また別途、御連絡させていただきます。
本日はありがとうございました。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140131_gijiroku.pdf
20ページの今後の検討ですが、まず、安全性について「関与成分を中心とする食品」と書かれていますが、複数入っていた場合どういうふうになるのかは、共通理解が必要だと思うのですね。製造の過程でいろいろ入ってくる場合もありますし、現状を考えますと、これもあるけれども、これもあるという複数の成分が関与する場合もあるので、そのときにどう安全性の担保を考えるかが1点目。
それから、あくまでも今回参考にすべきアメリカのDietary Supplement Health and Education Act( DSHEA)は、形状が決まっているのですね。あれは形状が決まっていて、私たちは、先ほどの理解ですと、形状が決まっていない、いわゆる食品全般についての機能性なので、参考にする場合は、そこのところをしっかり切り分けて議論をしていかないと、大きく間違ってしまうと思っております。
○松澤座長 今の複数成分のことについてはどうお考えですか。
○消費者庁竹田課長 AとBが入っていて、こういう作用機序で機能しますであれば、そこは、それぞれ明確にしていただかないといけないということが1つだと思います。あとは、示しているとおり、では、そのAとBを一緒に摂取したときにどういうことになるのかといったことについては、きちんと評価をしていただかないといけないのではないかと考えております。
○松澤座長 どうぞ。
○赤松委員 今の複数のもので気になることが、私は一度、栄養機能食品の調査をしたときに、栄養機能食品の対象となっている成分と表面のうたい文句が異なっていることがありました。したがいまして、安全性を対象としたものと効果をうたうのは、一致させるようにしていただきたいと思います。
○松澤座長 よろしいですか。その成分というのは、先生がおっしゃっているのは、こういうサプリメント的なものも含めてですか。食品というのはいろいろなものがいっぱい入っていますよね。だから、それをどうするか非常に難しい。今から20年ぐらい前に、牛乳を飲むとコレステロールが上がって心筋梗塞になると新聞に大きく出て、その後、牛乳を飲むとカルシウムがとれて骨粗鬆症に効くと論争があった。その中の1つの成分だけで言うと見方が非常に乖離するので、食品は大体その丸ごとの問題なので、それがいいか悪いかは全体で考えないと、どういうことを対象にするかによって決まるので。
今ここで言っている成分とは、そこから抽出したいろいろな物質が濃縮した形で入っているものが、常識的にはそれが対象のような気がしますけれども。あと、食品の形のものの成分の一個一個を言い出すかどうかは、余程その機能が特異のものでない限り、悪いかいいかという話ではなくて、やはり機能をうたっている成分がいいかどうか、安全かどうかという話になる感じがします。大谷先生、そこはどうでしょうか。
○大谷委員 ちょっと補足させていただきますと、例えばお茶の場合ですと、関与成分としてメチル化カテキンがあるのですけれども、例えば、医薬品との関係ですと、カフェインが入っていますのでテオフィリンとの関係が出てきます。そういう場合には少し複雑になりますけれども、基本的には、先生がおっしゃるように関与成分との関係が重要になると思います。
○松澤座長 どうぞ、清水先生、お願いします。
○清水委員 今の議論は、安全性を確保するためにどうするかですけれども、まず、成分か、21ページに書いてあります食品そのものかということです。今のお話で、ほとんどのいわゆる健康食品というのは、関与する成分が複数入っているわけで、その成分が、量と、それから2つなのか、3つなのか、その相互作用も含めてどういう効果があるか、そして、その安全性がどれだけ確保されているかが重要です。安全性について、まず、成分について確認されている、そして、複数のものが入っていれば、トータルのものとして、製品として安全性が確保されている、その両方の安全性が確保されて初めて安全性の確保と言えると思うのですね。
アメリカでもヨーロッパでも、まず機能性を言う場合に、食品のキャラクタライゼーションという言葉が言われます。これは、その食品中にどういう成分又はグループの化合物が入っているかを特定できなければいけないので、キャラクタライゼーションした成分についての安全性と有効性、そして、その複数の成分が入っているトータルの食品としての安全性と有効性、その2つが、もちろん安全性の評価のレベルは変わってくるわけですけれども、その両方があって初めて安全性の確保と言えると思っています。
○松澤座長 どうぞ。
○森田委員 今、例えば複数の関与成分ですとか、それから対象食品と話が行っておりますけれども、まずは、関与成分1つのところからスタートして、そこからそれぞれ、今回この参考にするのは、ダイエタリーサプリメント制度のNDIであり、そして特定保健用食品の考え方であり、それをまずはめて、その上で安全性をきちんと確認するということと思います。その安全性をきちんと確認したものを、企業が自主的にきちんと調べるということを今、話し合っていると思うのですね。
恐らく、例えば農産物とか、先ほどのお茶のメチル化カテキンとか、大豆イソフラボンとか、それぞれ成分を考えていくと、やはりその成分ごとの関与成分というところで量という問題が出てくるし、それがサプリメントだと、やはりもっとそれを一つ一つきちんとしなくてはいけないわけで、まずはそこの1つの安全性の成分に関して、先ほど特定保健用食品の考え方を持ってきてもいいのかとか、それから、例えばアメリカのNDIでしたら、DSHEAの場合はきちんと定義がありますので、それをそのまま持ってきていいのかというのは、常にそこは混乱すると思うのですが、今、安全性をやっているのは、そのDSHEAも持ってきて、特定保健用食品も持ってきてとやっていれば、かなりそこはきちんと安全性に関して食経験をやっていると、ほかの一般的な食品のようなものもクリアできていくと思うのですね。なので、まずはそこの部分で特定保健用食品とかDSHEAのNDIの持ってきたものが妥当かどうかというところ、あと、私はまだ、逆に言うともっとあってもいいのではないかと思っておりまして、では、それを自主的に企業が確認したときに、それを誰が検証するのかとか、それは届け出制度にしてもらわないとどうなのかとか、全体的なその制度設計の部分というところでまずは、これは多分、安全性のときに何度も何度も話し合うと思うのですけれども、そういうことではないかと思っています。なので、まずは関与成分というところで話を深めてもらえればと思います。
○松澤座長 いろいろなディスカッション、意見が出ましたが、今日は、その21ページ、22ページ、そういう方向でいいかどうかという最終的な検討をいただいて終わりたいと思うのですが、今までのディスカッションに基づいて、この①と②についての意見をお願いします。
どうぞ。
○関口委員 ここでは関与成分について安全性を議論しているのですが、例えばイチョウ葉エキスの安全性担保には、関与成分と一緒に抽出されてくるギンコール酸をある濃度以下でないといけない事例もあります。また、濃縮するから有害成分も濃縮されるリスクがあるのではないか議論がありますが、その場合は当然、関与成分としては問題ないけれども、あるAさんがつくると、きちんといろいろ配慮して、一緒に濃縮されているものは排除するけれども、例えばBさんはやっていないこともありますので、当然この両方、関与成分と、それから、後で議論になるかもしれませんけれども、プロセスにかかわることも議論が必要なのではないかと思います。
○児玉委員 よろしいですか。それに関しては、恐らく19ページの基本的方向性のところで、「一般の食品成分と同等の安全性を有していることが必要」とあります。ですから、これが一番基本的になっていると思いますので、今の複数の関与成分云々ということに関しても、幾つかあったとして、表示ですので、3つ効果がある物質があるとして、では、どれを表示するか、それは企業が決めるわけですね。それに関して表示をした場合、ほかのものに関しても安全である。もしかしたら2つ表示できるかもわからない。その辺のところはまたこれから議論になると思うのですけれども、ですから、その表示する機能に関して、その関与成分が明らかにされている、それ以外のものに関しては、「一般の食品成分で安全性を有しているもの」というのが一番初めの前提条件になりますので、やはりその辺のところが混乱しないようにと思います。
○松澤座長 ほかにありますか。どうぞ。
○合田委員 成分表示をするというのは、最後のところでは品質管理につながるのだと思うのですね。今、関口委員が言われたこともそこと関連すると思いますけれども、品質管理をするとすると、最終的には分析法があって、そのものに関して後で検証ができる、誰かが検証ができることが非常に重要です。
もう一つ、品質管理の方法として製造工程を管理する方法がございますけれども、製造工程を管理するのは、そこを義務的にさせなければいけませんから、これはかなり難しいと思うのですね。そうすると、やはり量で何かコントロールできるものが1つあって、それでこの表示制度が進むのだと思います。ですから、何がどういう形になったとしても、検証ができることを常にフィードバックしながら、この議論を進める必要があると思います。
そうしますと、例えばこの21ページに書かれているものも、そういう概念で見れば、量的なコントロールができている、何か検証ができれば、僕はそこそこ納得できるかなと考えています。
○松澤座長 よろしいですか。具体的な検証ができるというのは、それをうたっておいて、どこかでチェックすることですね。
○合田委員 そういうことです。当然、つくられる企業の方は、そこも意識をしてつくられると思いますけれども、そういう意味から言うと、誰かが後で、表示されているのだから、そのとおりかを調べられるというのが大事だと思います。
実際、私は健康食品の分析を過去にたくさんやっていますけれども、書かれているものが入っていないものが非常にたくさんございます。ですから、そういうものを表示するのは、やはりこれはよくないことだと思います。ですから、少なくともその成分の量、それからもう一つは、有害成分の問題も言われましたけれども、有害成分について入っているのであれば、それが入っていないということも証明できる、分析ができるということが横にあって、こういう表示制度が進むのだろうと思います。
○松澤座長 それは食品衛生法のカテゴリーですね。
○合田委員 そうです。
○松澤座長 だから、そういうことでの縛りは当然できるで、その成分が入っている表示が本当か、どうかというのは、健康増進法のカテゴリー。だから、そういう意味での縛りというか法的な縛りはできると。だから、自己責任でやっている場合には、そういうチェックも起こり得る、そういうふうに考えたら、それを全部一個一個成分というのは物理的に無理だと思います。そういうことを前提としたルールづくりになると思いますが、もう一つは、食経験が十分でない、情報が十分でない場合は、やはり特定保健用食品と同じようにしっかりとやっていただくということは盛り込むことになりますね。
どうぞ。
○相良委員 済みません、ちょっと議論を引き戻してしまうかもしれないのですが、先ほど梅垣先生がおっしゃっていたように、私が多分、アカデミックな議論から一番縁遠い存在で、すごく一般目線でお話をさせていただくと、やはり錠剤のものはお薬というイメージがあります。それで、食品だと言われて買っても、やはり飲むときには、家庭内では、例えば食事の後にサプリメントを摂取するというのは、お薬を飲むという感覚があるし、あとは、先生方には申しわけないのですが、もしかしたら処方箋をいただいてもらうお薬より信頼している可能性があると思います。
これは身近な例でもよく見かけるのですが、それはなぜかというと、やはり自分で選択したという意思が入っているからで、お医者様に言われて飲むものと、そこに何かプラス、すがりたいというか、もっとよりよく健康を維持したいという自分の気持ちから選択した何か食品というところに自分の中ではすごく信頼があって、処方箋で、例えばある1,000円ぐらいのお薬をもらっても、サプリメントを自分で5,000円とかでも出す方は一般消費者で多いのではないでしょうかということがあるので、プラスそういったことを考えると、飲み方という点でも、恐らくすごく消費者の独自性というか、もうちょっとよくなるのではないかと思って、過剰摂取の問題が必ずそこに出てきてしまうのではないかと私は思っています。
それは身近な、例えば自分の祖母を見ていても、膝が痛いときに、何種類もそういったサプリメントを並べて飲んでいたりとか、そこには上限がどうとかといった、多分先生方にとっては常識である概念は全然なくて、これを飲めばいいという気持ち、食品というよりは、何か薬に近いような気持ちで飲んでいるのではないかというのをまず感じていますので、それは1つお話しさせていただきたい。
あとは、先ほどから議論されていますこの関与成分の話ですけれども、そこに「食経験」という項目が入っているのですが、これが、例えば食品としてだったら食経験はわかるのですけれども、成分としてとか、あとは、例えばレモン何個分というのは、それは食経験でどう判断するのか教えていただけないでしょうか。レモン自体は、もしかしたら丸ごと食べた方っていらっしゃるのでしょうか。私は、何となくレモンはレモンの果汁を飲むイメージだし、レモン1,000個分を食べたこともありませんし、食経験をどこまで、レモン自体は食べたことがあっても、それを何個分とか、その濃縮された成分である場合、先ほどのイチョウ葉とかグルコサミンですとか、それを食経験に照らし合わせるのはどのようにやるのか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
○松澤座長 どうぞ、竹田課長。
○消費者庁竹田課長 1点目の指摘は、先ほど梅垣先生からもございましたけれども、形状の違いによって過剰摂取の可能性が出てくるのではないかと。そういうことを踏まえますと、先ほど消費者の選択に資するような、間違いのない、誤解のないような表示が必要だという指摘がありますので、そういう意味で、例えば表示すべき事項に違いが出てくる、濃淡が出てくることは十分あると考えております。
それから、2点目ですけれども、食経験を考えるときには、先生指摘のように、やはり普通の日本人がこれまで常識的に食べてきた量かは、1つ問われると思います。それが、抽出とか濃縮を加えることで、例えば100倍になるとか200倍になるといったときには、食経験があると言えるかどうか当然議論になってくると考えております。
○相良委員 ありがとうございます。
○松澤座長 どうぞ。
○津谷委員 今、相良さんがおっしゃったように、「薬」と言ったり「お薬」と言ったりしますよね。例えば、「飲む薬」とか、効くものが薬ですので、有効性なり効果が何か幾らかでもあると、どうしても人は「薬」と言ってしまうと思うのですが、今、消費者庁でやっている大規模なアンケート調査にそういったものが入っていればいいなと私は思うのですね。人々がどういう具合に認知しているかですね。
それと、食経験のことなのですけれども、21ページに、「具体的なエビデンスに基づき、食経験を評価」と書いてあって、左の四角の枠の中に、「食習慣等を踏まえ……」等6項目ありますね。3番の「これまでの販売量」というのは、今日の配付資料の特定保健用食品にもあるものなのですが、私は、特定保健用食品の販売量というのは、何ケースとか、何錠とか、何トンとか、余り意味なくて、やはりどのぐらいの消費者数というか、それを使用した数と、例えば年間とか、あるいはそれがいつから、その一種の積分として考えるべきです。1,000年前から使っていたと言っても毎年10人しか使わないものと、この半年で10万人使ったものとありますから、歴史と時間的な軸と具体的にある時間帯の中で、それを使った人の数の両方だと思うのですね。
それが、この21ページのスライド左の四角の一番下に「摂取者の規模」と書いてありますね。これがきっと人数のことだと思いますね。人数はすごく大事で、先ほどラベルとか、消費者とのコミュニケーションで大事なリスクコミュニケーションがありますね。1,000人のうち1人に悪さがあるのですとか、100万人のうち1人ですとか、あるいは3人に1人がちょっと胃の調子が悪くなりますよという、基本的にはリスク・ベネフィット・コミュニケーションになるわけですけれども、特にリスクが食品の場合には重要になりますので、その人数がわかるのがすごく大事です。そうすると、現在の特定保健用食品はそれを求めていませんから、やはり特定保健用食品もいずれそれが必要になるのではないかという気がします。
それと、この「エビデンスに基づき」で、その下に「安全性試験」とありますが、既にもう副作用が出ているもの、健康被害が出ているものがあるわけですね。その実態がきちんと把握できることも大事ですね。私は、昔WHOで働いていたこともあるのですが、ウプサラモニタリングセンターという、スウェーデンのウプサラというところにあるモニタリングセンターで、もともとWHOがやっていたのを、今そのセンターがWHOの協力センターとしてやっていて、世界中の副作用が一元的に集まるようになっています。その中に、健康食品の副作用情報も入っているのですね。日本では厚生労働省がナショナルセンターに指定されていますから、たしか医薬食品局の安全対策課か何かで、それは、例えば消費者委員会も同じ国の機関ですから使えるはずですし、ノルウェーなどは、ブランチがいろいろなところを扱っているのですけれども、梅垣先生のところもきっとそれを使っていろいろな情報を集められれば良いと思います。
実際に新規にこういったものを自己評価でやるときにも、そういったデータベースを漏れなくシステマティックに検索する、評価する。システマティックレビューの概念を取り入れて、どのデータベースをどういう検索式で調べたか、結果がどうか、そこも開示したほうがいいと思いますね。結果だけではなくて、単純に言うと文献検索する方法ですね。
○松澤座長 それは先生、安全性だけではなくて機能の面でもですね。だから、全体としてそういうデータ表示の方法というか基盤を開示したほうがいいと。
○津谷委員 プロセスを開示したほうがいい。
○松澤座長 そういうプロセスを開示したほうがいい。それはちょっと書きとめていただいて。
○津谷委員 それと同時に、今、臨床試験登録制度が皆さん御存じのとおり存在して、私もかかわっているのですけれども、パブリケーションバイアスをなくすというのが最大の目的ですね。今お話ししたようなシステマティックレビューをやるときも、システマティックにやったところ、いろいろな有害事象が見つかってしまった場合、これはやはりちょっと黙っておこうという人が必ず出てくるのですね。ですから、そのシステマティックレビューそのものも、今、登録制度が世界には存在して、2001年からもう始まって、プロスペクトというイギリスでやっているシステムがあるのですけれども、私も幾つかそこには登録してシステマティックレビューをやっていますが、システマティックは、そのプロセスを開示するということ、システマティックレビューをやっていることそのものを事前に公開することなのですね。そういうシステムが世界にあるわけですから大事だと思います。
○松澤座長 清水先生、どうぞ。
○清水委員 ちょっと今、津谷先生が言われたことと重なるところもあるのですが、まず、食経験については、ある、ないということを食経験で言うのはできません。食経験は、程度だと考えています。
では、どのような情報についてその程度を知るかについては、まず量、その量というのは、もちろん質にもかかわるわけで、純度とか、それから一緒に入っているものがどう違うのか、それと、どのぐらいの頻度で、どのぐらいの人数の人が、どのぐらいの期間食べていたのか。そして、その食べていた人が、日本で安全性を確保であれば、日本人と同じ食生活をしていた人たちなのか、同等性がどこまであるのかについて、それぞれどこまで食経験があったのかということを総合的に判断して、食経験がどこまであるか、逆に言うと、食経験が十分あるということが、安全性の評価試験を、これは減らしていいですねという合理的な理由になるわけで、食経験がどれだけあるかということが、食品の安全性試験をどこまでやるかということにつながることが非常に重要だと思います。
○松澤座長 これは、21ページの右の評価のところの、多少文言がいろいろ違うけれども、こういう方針でよろしいでしょうか。
○清水委員 それと、1点追加で、特定保健用食品については、実際にその製品をどういう人がどれだけ摂取したかが、特定保健用食品の食経験として申請資料に入っていることは追加したいと思います。
○松澤座長 21ページの方針に関しては、文言というか摂取集団、先ほど津谷委員からお話がありましたような、販売量のあらわし方とか、そういうことで評価と、そこらはまた考えていただいてと思いますので、この21ページ、相互作用なども非常に強調した対応方針だと、先ほどの児玉先生からの話がありましたように、そういう方向でいいかと思いますが、22ページに関してはいかがでしょうか。どうぞ。
○森田委員 21ページの内容を22ページで「広く情報開示する」とあるのですけれども、これは、例えば食経験ですとかそういうことは、企業が自主的に、こういう食経験があるからとか、これは食経験が足りないから、もっとデータを、安全性に関する情報の評価とか、そういう情報もあわせて開示すると理解してよろしいのでしょうか。まずそこが質問です。
○松澤座長 それでいいですか。
○消費者庁竹田課長 指摘のとおりです。
○森田委員 では、それを検証するのは、先ほど合田先生は量の検証とおっしゃいましたけれども、これは企業が自主的にやって、それをやるときに、その内容をどこで検証するのか、あとは、例えばそれが間違っていたときにどう監視をするのか、そういったことがないと、皆さんそれぞれ、これは例えばガイダンスになるのかどうかもよくわからないのですけれども、こういうガイドラインみたいなものが、この①の内容ですね、例えばこういう食経験がこうだとか、安全性のデータはこうだとか、そういうガイドラインに従ってやっているかどうかを誰がどう検証するのかとか、例えば届け出制度にするのかとか、そういう仕組みをどうお考えか教えてください。
○消費者庁竹田課長 具体的な制度の仕組みにつきましては、初回に提示したように、考えられる論点をつぶした上で、最後に提示と考えていますので、そこについて今、明確なフレームを示せる段階ではございません。
その上で、基本的には、その事業者の方が、今回、科学的根拠を自ら評価して、表示をするので、そこのところは、事業者の方がきちんと評価をしていただく。先生が指摘になりましたように、きちんとしたものにしていただくためにも、情報というものは、購入される消費者に向けてつまびらかにされなければいけない。そのプロセスを通じてきちんとした評価がなされるというところを担保したいと考えております。
○森田委員 わかりました。ただ、事業者が取り組みやすいようにするためには、やはりガイドラインですとか、そういったものがないと、皆さんそれぞれ違う物差しで取り組まれては困ると思います。
○消費者庁竹田課長 それは、先生ごもっともでして、どういうことをしたらいいのかについては、一定の考え方を示していかないといけないだろうと思っております。
○松澤座長 この検討会でその基本のコンセプトを確立して、あとはわかりやすく一般に公開ということになると思います。
合田先生。
○合田委員 今の回答で納得したのですけれども、11ページのところで、自主点検ガイドラインでも少し似たような考え方があります。先ほど津谷先生も言われましたけれども、事前に広く情報を集めることが、まず、安全性を確認することにとって非常に大事なことです。かつて、アマメシバの事件がありましたけれども、文献を調べていさえすれば、ああいう不幸なことは起こらなかったのですね。1つは、単純にそのものだけが原因で、事故が起きたかどうかというのはありますけれども。成分的な情報も含めて、まず広く調べて、それから、今のシステマティックレビューのようなことを実行できれば言うことはありませんし、まず、文献情報から得られることがあって、それが、今、森田先生が言われたように、公開されて、こういうことを調べてありますよというデータが、ネットで検索すると、さっと一番最初のところに出てくるようなサイトがあって、見られるというのがやはり前提ではないかと思います。
そうすれば、しっかりした人がしっかりと調べていますよということがわかりますね。それが消費者にとっては一番安心できることではないかと思います。
○松澤座長 梅垣先生、どうぞ。
○梅垣委員 この自主点検ガイドラインとかは、厚生労働省のときに既にかなり議論されているのですね。それで、何が問題かというと、これの実行がなかなかできない。例えばGMPが、錠剤、カプセルだと必須にしないと国際的にも多分通用しないと思うのですけれども、それが全然ここの中には入っていない。GMPは、普通の生鮮食品には適用できありませんが、錠剤、カプセルとか、濃縮物に対してはGMPの義務づけとかをしないと、国際的には絶対通用しないし、日本の製品は海外には出せない。それで、海外から入ってきますから、産業振興という面でももうすごく問題になると思います。だから、その点を考えていかなければいけないと私は思います。
とにかくGMPが全然ここの中に入ってきていないのと、ガイドラインがいろいろ前から出ているけれども、これが実行されていない、現実的にはできていない。例えば、GMPなどは、私のところでもホームページでいろいろ情報提供しているのですけれども、やはり進まないのですね。これはなぜ進まないかというと、消費者がGMPが何かというのがわからない。商品を買うときの判断基準は、有名人とか何か偉い先生が勧めている、それを参考にしているのです。それは全く意味がないことなのだけれども、消費者の人は、そういう情報を見て商品を買われるから、企業もGMPを取ろうとしないのです。だから、そこのところを改善する考え方を取り入れないと、幾らいいものをつくっても進まないと思います。
○松澤座長 竹田課長。
○消費者庁竹田課長 今のGMPのお話は、次回以降、品質管理のところで議論いただきたいと思っております。
それから、今、指摘いただきました実効性の担保につきましては、制度の仕組み方のところできちんと考えて、我々として提示したいと思っております。
○松澤座長 まだスタートしたばかりで、いきなり最終的な制度を作るのは難しいので、この検討会の間に先生の具体的な提案とかを述べていただきたいと。まずは、今は安全の確保のためのルールづくりというか基本方針を決めていただきたい。
ほかにございますでしょうか。どうぞ。
○清水委員 今日の検討事項、3ページの「対象となる食品及び成分の考え方並びに摂取量の在り方」、そして、「関与成分を中心とする食品の安全性についての事業者自らによる評価」について、いろいろな議論があったのですが、では、この評価をどういう試験、成分の分析、種々の安全性の評価、それから食経験など事業者が行う評価の項目を決めていくのが今日の目的ではないのですか。もう少し具体的に、どこまで決めるのかを伺いたいのですけれども。
○消費者庁竹田課長 それこそ具体的な制度設計のお話はまだ少し先になるとは思っておりますので、基本的には、こうした考え方でというのか、こうしたフレームでいかがでしょうかです。基本、こうした考え方でいいのであれば、肉づけをした上で、またさらに最終的にはどんな形になるかというところで議論いただくと思っております。
○清水委員 では、最後にやると。
○消費者庁竹田課長 いきなり制度の詰めみたいなことを毎回毎回というのは、少し困難な部分がありますので、考え方、フレームについて議論いただければと思っております。
○清水委員 基本的な考え方でいいですね。
○松澤座長 どうぞ。
○森田委員 順番というのはよくわかるのですけれども、ただ、この資料の対応方針案だけを見ますと、企業が本当に自主的にやれば、それで、それをどういう形で、例えば届け出制度にするとか、そういうことがある程度わかっていないと、例えばこういう細かいことを幾ら詰めて、ここで安全性のこととかを詰めていっても、それは、いや、あくまで自主的なもので、アメリカの制度などはそうですけれども、自主的にやっているからといっても、いろいろな安全性の問題は出てきているわけですね。だから、やはり何となく出口を見せていただきながら、一番最初の進め方になるのですけれども、先ほど梅垣先生がおっしゃっていたGMPに関することや、どうやって危険な商品が流通するのを防止したり、有害事象をどうするかとか、そういうものも、毎回これを1回ずつやるのではなくて、全体的にこの4つの部分を同時進行みたいに進める考えでもよろしいのでしょうか。
ある程度そこが見えていないと、今回の基本対応方針だけだとやはりちょっと見えないので、出口の感じというのを時々確認しながらやったほうがいいと思います。
○松澤座長 時間が余りないので、今から全部やるわけにはいきませんけれども、要するに、基本的に機能の表示のほうがもっと重要かもしれませんね。もちろん、薬の場合は安全性が極めて重要なのですけれども、これに関して、だから、薬に近いような形態のものについて今やっているのでして、あとのそういう機能についても、自主的に表示したものが本当に正しいかどうか野放しだとルールをつくっても余り意味がないので、ある程度はそういう方向は時々意見を言っていただきながら、最終的にどうするかという検討はしていくことになると思います。食品という膨大なものをどこまで縛れるかは難しいところですけれども、例えば産地の表示などでも、偽装だったら徹底的に社会的に糾弾される、そういうレベル、自主表示というのは大体そんなものですね。だから、抜き打ち的に何かチェックするとか、そういうことは具体的にはいろいろ頭の中で考えていただいて、これはまだもうちょっとありますので、今ここでいきなり自主表示をどうやって審査するかなんて言い出したら、これは大変な話になってしまうと思います。
○消費者庁竹田課長 今、座長から指摘がありましたように、基本的には、重要な論点についてそれぞれ議論いただいて、その時々で前回のこんな議論にと立ち戻った質問、意見を頂戴するのは全く構わないと思っております。
それで、初回にスケジュールを提示したのですけれども、安全性の議論をしていただいて、それから機能性の議論をしていただいて、それから、最後に総合的に縦横を眺める、「論点整理」と書いていますけれども、そうした議論をいただきますので、そちらでもまた再度きちんと議論を深めてまいりたいと思っております。
○松澤座長 どうぞ。
○河野委員 消費者から見ますと、確かに機能というよりは、口に入るものですから、まず安全をどう確保するかは非常に関心が高いところでして、今日最初にその3ページで示していただいたこの4つに関して言うと、トータルで概要が見えて、「ああ、安全なんだな」と納得するような条件だとは思っているのですね。
今日は、その成分と、それから摂取量、摂取量に関してはどこに提示されているのかが、私としてはちょっと見つけられない感じもするのですけれども、成分の安全を担保するためには、こういう条件でやりましょうねと示されたと。
それで、できればここに書かれていることを、先ほどの、食経験をどういう条件がクリアされれば食経験があると消費者は受け取れるのかと。情報開示される、それに行き着く、そういうこともありますけれども、まずここで最低限、食経験があるとはどういう条件なのか、有識者の先生方がいらっしゃいますから幾つか押さえておいていただきたいのです。では、食経験がないというときはどういうことなのか。ないとなったら、例えば20ページの安全性試験、いわゆる科学的な根拠を示すと。その科学的な根拠の示し方は、どういう条件がついたら、私たちは、「ああ、この成分は安心して口に入れていいものなのか」と理解できるのか、そのあたりをある程度ここで合意しておかないと、また同じことが繰り返されるのではないかというイメージは持っています。
安全性というと、原材料はどうなのかとか、それから、先ほどから出ている製造工程はどうなのか、それから、今日やっている量と、それから摂取にかかわる部分ですね。あと、トータルで考えたときに、「安全性」という一つの言葉でなかなかくくれないので、こういうふうに分けてやるというのもいいのですけれども、まず、今日の部分で、ある程度の合意をとっていただきたい。条件についてぜひ確認をしていただければと思っています。
○松澤座長 ちょっとお答え願えますか。最初、食経験とはどういう定義かですが、いかがですか。普通、食べ物で食経験のないものが入ってきたときのことは、非常に特殊な例ですよね。
○河野委員 例えば、先ほどのアマメシバとかコンフリーとかいろいろ例がありますよね。
それから、大豆と大豆イソフラボンの問題とか、食経験があるというのを消費者はどう理解すればいいのかというあたりを。
○松澤座長 お答え願います。
○消費者庁竹田課長 なかなか何人で、何食で、何年間というように具体的に提示するのは非常に難しいとは思っていますけれども、定性的なお話になりますけれども、例えば○○県○○島で実は食べていたとか、そういうものであれば、食経験としては足りていないのだろうと考えます。21ページに示しております繰り返しになってしまいますけれども、全国規模で、一般的に皆さんが知っていて、普通に食べられている、売られている、それで、それなりの期間摂取されているところが、恐らく定性的には委員の皆様と観念でしょうか、基準は共有できると思うのですけれども、そこについてさらに突っ込んで、もっとこれぐらいがあれば、具体的に指摘いただければと考えております。
○松澤座長 合田先生、お願いします。
○合田委員 食経験というのは、基本的には、食習慣、食生活と含めて考えるべきことです。21ページに書かれているところで、ちょうど四角の中に「摂取形態、摂取方法、摂取頻度、摂取者の規模等」がありますね。これはまさに食生活がどうであったかをより細かく言うとここで示されていることです。結局、食習慣とか食生活と同じ状態であって初めて、その安全性が担保されていると一応言えるだろうとなりますから。アマメシバのように、例えば現地で実際には、普通に庭に生えているアマメシバをとってきて食べるというような食経験だったのですね。ですけれども、それを乾燥させて粉末にしてジュースに入れて飲むとか、牛乳に入れて飲むという食経験はなかったわけですね。だから、そこには食経験があるとは多分言わないことになります。
それから、ソテツみそなどの場合に、あれはソテツの有害成分を最初に除いて、最後、みその形態にした形によって初めて食経験があります。ですから、ソテツに食経験があるということは言わありません。
ですから、常にどういう食習慣の中でこれが食べられてきた経験があるかということを確認して、それを開示していただく、そういうことで皆さん、多分同意がとれるのではないかと私は思います。
○松澤座長 基本的に、食文化とも関係しますから、それと成分の機能というものとは分けないとだめですね。だから、日本人が食べているものでも、生卵のぶっかけなんて、ほかの国の人はほとんど食べませんね。ヒヨコになりかけの卵は食べる人に、生卵のぶっかけをやったら、気持ち悪くて食べられないと言うわけですから、そういうふうにして、文化と経験は、やはり食文化の話と機能とまた話がちょっと違うので。フグなんかを最初に食べた人は、すごいなと思うし。
梅垣先生。
○梅垣委員 追加ですけれども、やはり調理、加工の方法も考えておかないと、例えばジャガイモは安全だと言っても、芽の部分はみんな除いていますよね。だから、そういう調理、加工の方法というものも食経験の中の重要な要因です。
先ほどのアマメシバの話ですけれども、あれは利用目的が一番の問題なのです。痩せるために台湾でかなりとった。栄養補給とかというのではなくて、痩せるという別の目的にしてしまったので、大量に摂取して健康被害が出た。日本でも閉塞性の細気管支炎が出たのは、健康にいいと言って粉末とか錠剤を摂取したから問題が起きたのです。
○松澤座長 どうぞ。
○大谷委員 食経験の問題では、量の問題があると思いますが、生鮮物に関しては、産地が非常に特別なところでして、例えばお茶の産地ですと1日10杯飲むとか、ミカンも5個、6個、10個食べるとか、そういうところのデータというのはございます。そういう意味では生鮮物に関しては、ある程度担保できるだろうと考えております。
○津谷委員 よろしいでしょうか。15ページに米国の例としてNDIと、この下半分に「食経験その他安全性に係るエビデンスについて」と書いてあって、丸の2つ目の下に「食経験の長さ(期間)、摂食集団」云々とあるのですが、今回、消費者庁でつくっていただいた21ページの左の四角、さっき6項目と言いましたが、実際に書くと9項目、後に「等」がついているのですけれども、この米国とちょっと順番が違ったりしているのですが、何か日本ではもっといいものをつくったという、そういう順番なのでしょうか。
○松澤座長 どうぞ。
○森田委員 同じ点なのですが、よろしいでしょうか。
私も同じようにそこのところを思っていまして、ここに書かれている食経験は、多分アメリカのNDIのここのページのものと、それから、恐らく特定保健用食品の食経験に関するデータというところで、特定保健用食品で条件づけられている参考データの食経験に関するデータというところが合わさって、そこでつくられているという形で、両方だと思っているのですけれども、その両方で食経験を、食経験プラス安全性の評価で、それをクリアしたということを条件にしていると見えたのですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。NDIの食経験その他に関するエビデンスについてです。
○松澤座長 15ページ。
○森田委員 それから、特定保健用食品の食経験に関するデータというのが別途あると思うのですが、それと合わせて、この21ページの「食経験に関する情報の評価」と「安全性試験に関する情報の評価」をつくられたのかどうかと。よく読みますと、NDIには長期試験とかがあるのだけれども、こっちは長期試験がないとか、比べてみると違うような感じがあって、先生がおっしゃるとおり、項目が違っていたり、NDIなのか特定保健用食品なのかよくわからないのですが。
○消費者庁谷口課長補佐 両方参考にしてつくっているところではございますが、一つ一つの項目について精査して、これは必要、これは必要という形で厳密に決定して、今、あげたものではございませんので、そこまでの厳密な精査はできていないと了解いただけたらと思います。
○松澤座長 どうぞ。
○児玉委員 食経験に関しては、皆さん非常に、イメージもそれぞれの先生方で違うと思うのですね。ですから、できましたら、先ほどガイドラインとおっしゃったのですけれども、具体的に幾つか示していただくほうがディスカッションしやすいのではないかと思います。今、皆さん方からの意見を参考にして、例えばこういうふうに提示するのがいいですね、こういうものはだめですよとか、何個かそういう具体例を示していただくほうがディスカッションしやすいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。難しいですか。
○松澤座長 ほかにございますか。どうぞ。
○宮島委員 事務局にちょっとお願いですが、進め方ですけれども、安全性というのは4回まであって、それから、5回目から機能性とまた大きく変わると思うのですね。そこの時点で振り返りというかレビューをぜひやっていただきたい。
最後にまとめるのではなくて、やはり中間で振り返りが必要だと思っていますので、それはぜひお願いしたい。
それから、これは意見ですけれども、22ページで、先ほどちょっと情報開示ということと企業等の責任があったのですが、私は情報開示には2つあると思っていて、例えば我々のホームページでお客様向けに開示するときに、非常に細かくて文章だらけ、文字だらけというのはほとんど読んでいただけません。皆さん御承知のとおり、1つの文章で漢字が36%を超えると解読率が極端に落ちるというデータもあるので、やはり読みやすいものと、それから、それのもとになる精緻なデータと2つ必要になると思うのですね。
どちらも開示することはもちろん構わないのですけれども、読んでいただかないと全く意味がないので、そういう読みやすさ、わかりやすさというものをぜひ、まだこの段階では早いのですけれども、考えていただきたいと思います。
それからあと、企業の責任もあるのですが、これはやはりアメリカのような非常に訴訟社会で考えている自己責任と日本なんかの考え方と違うと思うので、ある程度、その考え方とか定義というものは少しまとめておく必要があるのではないかと思っています。
以上です。
○松澤座長 ありがとうございました。情報開示と一つ一つの食品への表示を明確にが基本で、それの方法というか、具体的にはそれも詰めていくことになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ほかに何か。どうぞ。
○関口委員 食経験による安全性担保の判定基準として、アメリカの様に、GRASにしてもNDIにしても年で切る、1958年とか1994年、これも1つの考え方としてはあると考えます。
それから、安全性を判断するために、情報社会なので、先生方おっしゃられたように、グローバルに副作用等の情報なども集まりますので、この点も必要だと思います。グランドファザー制をどの様に考えるかという事も重要だと思います。
最後に二点。一点目は22ページに「医薬品を服用している者は医師に相談」と書いてありますが、薬剤師の方も入れておいたほうが良いと思います。
二点目は、厚生労働省のガイドラインを基に、実は、まだまだ有効にどんどん利用されているとは言いませんけれども、健康食品認証制度協議会が健康食品の安全性確保のために第三者認証制度を立ち上げており、第三者チェックをやっておりますので、そういうことも実際やられておりますということの紹介です。
○松澤座長 どうもありがとうございました。
ぼつぼつ時間が来たのですが、まだほかに何か、5分ありますが、よろしいでしょうか。
どうぞ。
○赤松委員 重なる意見ですが、情報開示について、今、出されている案が2つあります。それは、1つは、その食品自体に載せるものと、あと、ホームページなど、そのほかに載せるということ。しかし消費者はこれだけで安全であるとは認識していません。これは一方通行のコミュニケーションです。企業がこれをすれば、何か企業の責任がなくなるという、消費者に責任を押しつけているようなところもあります。
やはり私が何度も言っているような教育も必要ですし、それ以外のところで安全性や危険を考えていることも私たちは認識しておかなければいけないと思っています。
先ほどから梅垣先生がおっしゃっているように、錠剤であるものと野菜というものの違いで、安全であるか危険であるかと思ったり、その企業がすごく歴史のあるところであるとやはり信頼してしまうとか、どこでつくられているのかでも安全性を判断していたりとか、その安全性や危険というものは、この表示をすればいいだけ、開示をすればいいだけではないと認識しておかなければいけないと思っております。
○松澤座長 どうぞ。
○消費者庁竹田課長 先ほども、売るためではなくて、消費者にとって商品選択に資するような、という指摘がありましたけれども、そういった考え方でどういう表示事項が求められるかといった点については、当然考えてまいりたいと思っております。
それから、ラベリングと、別途の情報開示だけで不十分ではないかと前回も指摘を頂戴しましたけれども、当然、消費者の方に、こういうジャンルの食品とは一体どういうものなのか理解を深めていただくことについては、別途それは引き続き必要だと思っておりますので、そうしたことも検討していきたいと考えております。
○松澤座長 よろしいでしょうか。
○津谷委員 先ほど関口さんから、グランドファザー制とかGRASの話が出て、これがスライド14枚目なのですけれども、ここに対象成分として4つあると。2つ質問がありまして、日本にはこういうコンセプトがあるのか、昔から使っていて広く使われていれば、とりあえず安全とみなしましょう、あるいは有効性をみなしましょうということもあるのか。
それは、医薬品とダイエタリーサプリメントと両方あるのですけれども、もう一つ、4番に食品添加物が出てきますね。私は、たしかこのGRASとは食品添加物から始まった概念だと聞いているのですけれども、ちょっとこの辺が、私も今、勉強しているのですけれども、これは、食品添加物でGRASであればダイエタリーサプリメントに入れていいという解釈になるのか。日本でも、食品添加物として、日本のポジティブリストに載っているものを健康食品に入れることがありますよね。どうもその辺が混乱していてよくわからないのですけれども。
以上です。
○松澤座長 いかがですか。お答えできますか。
○消費者庁竹田課長 日本の制度の中で同じような考え方というのは、先生がおっしゃるようなものであれば、いわゆる既存添加物がそういう事例に当たるのではないかと思っております。
○松澤座長 どうぞ。
○厚生労働省長谷部課長 後のほうの質問で、食品添加物であれば食品に入れていいかというところですが、食品添加物として指定したときに、対象食品を決めているものもございますし、あとは使用基準を決めているものもございます。何も決めていないものについては普通に使っていいということになりますが、対象食品と使用基準を決めているものについては、その範囲内のみ使用することが可能だという制度になっております。
○松澤座長 いろいろ意見、先生、何かありますか。
○清水委員 先ほど赤松先生が消費者教育ということを言われて、今回の新たな機能性表示の食品についての消費者教育又は情報開示のことでちょっとお話ししたいのですけれども、いろいろ消費者のヒアリングとかアンケート調査をやってみると、特定保健用食品についてはよく知っているのですが、栄養機能食品については、20%から30%の認知度しかない。栄養機能食品と栄養補助食品の区別がつかないということもあります。栄養補助食品と特定保健用食品の違いは、制度の違いと、あとマークがあるかないかがあります。今回の新たな機能性表示の食品をつくるのであれば、この新たな機能性表示の食品には、こういう情報開示ができています、又はこういうことが必要なのですということが消費者にわからないと、その情報を得ようとする消費者も少なくなってしまうです。明確にこの新たな機能性表示の食品が制度としてできました、そして商品も区別ができました、例えばマークとかですね、そういうものをつくるのも、安全性確保、情報開示のためにも必要なのではないかと思います。
○松澤座長 ありがとうございます。そういうことのためにこの検討会が発足したのだと思います。ここである程度のコンセプトを確立して、これまではそういうことがなかったわけですから、今おっしゃったように補助とか何かわからないままだった。
大体意見もいただいたと思いますが、基本的には、安全性の確保についての基本コンセプトは、そう大きな齟齬がないということで、本日はこれで終わりたいと思います。
この方向で消費者庁で制度として詰めていただいて、引き続き、安全性に関してはあと3回ぐらいやるのですか、できるだけまたディスカッションをしっかりして進めていきたいと思います。
○消費者庁竹田課長 最後に、次回は2月25日、16時からの開催を予定しております。会場につきましては、また別途、御連絡させていただきます。
本日はありがとうございました。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140131_gijiroku.pdf
Posted by 第2回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会 (2/2) at 2014年03月16日 20:58