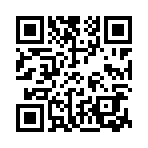2011年11月11日
腸内環境と食物繊維
腸内環境と食物繊維
東京大学大学院医学系研究科講師 奥恒行
はじめに
かつてわが国が低栄養に悩まされていた時代には、腸内に生息する細菌と健康との関わりについての関心は低かった。しかし、日本人の食生活が豊かになり、がん、心臓病、糖尿病などの慢性疾患が増加するに伴って食生活が見直され、同時に食事成分に影響を受けやすい腸内細菌との関係に関心が集まるようになってきた。腸内細菌叢(草が群がって生えているような細菌集団の分布、腸内フローラともいう)の改善を通して生体に有益な影響をもたらそうとするブロバイオティクスの概念構築は、これらの関心を反映したものと言える。
腸管には100種類100兆個の腸内細菌が生息して腸内細菌叢を形成している。腸内細菌のなかには、ビフィズス菌、ユウバクテリウム、乳酸菌などの有用菌、大腸菌やウェルシュ菌などの有害菌のほか、通常は良いこともしないが身体の調子が悪くなるといたずらをする日和見的な菌などがいる。
このように腸内細菌叢は多種多様な細菌で構成されているが、これらが互いに共生あるいは拮抗関係を保ちながら絶えず増殖しては排泄を繰り返している。このため、外来病原菌などが侵入しても簡単には腸管に定着・増殖することができない。また、何らかの要因によって腸内環境が悪化すると、便秘が生じやすくなったり便性が悪くなったりする。さらに、有害物質の生成量が増加して慢性疾患の誘発や老化の促進が助長され、健康状態は徐々に悪くなっていく。難消化性糖質である食物繊維やオリゴ糖などを食生活に上手に取り入れて腸内環境を改善すれば、現代人の食生活の危険度が軽減され、健康の維持・増進に寄与することが期待できる。
腸内細菌叢の健康との関わり
腸内細菌叢を構成する細菌は種類や数が多く、腸管内の代謝は極めて複雑になっている。従って腸内細菌叢が乱れると、大腸内の全体的な代謝バランスも変化する。その結果、宿主(生体)の健康状態が影響を受けることになる。
ある種の腸内細菌はビタミンやたんぱく質を合成するとともに、消化吸収されない糖質を利用可能な短鎖脂肪酸に転換し、宿主のエネルギー源にすることができる。また、腸内に常在する有用菌は外来病原菌やO-157(病原性大腸菌)などのバリアーとなって腸管感染を阻止する役割も果している。さらに、ある種の有用菌は生体の消化管免疫機能を向上させ、生体防御にも寄与している。
一方、有害菌によって生成される有害物質にはアンモニア、硫化物、アミン、フェノール、インドールなどの腐敗産物、ニトロソ化合物やエポキシドなどの発がん物質、細菌毒素、二次胆汁酸などがある。これらの有害物質は腸管自体に直接障害をもたらすとともに、一部は体内に吸収されていろいろな臓器に障害をもたらし、いろいろな慢性疾患の誘発に関与していると考えられる。腸内細菌叢を改善することは有害物質の生成を少なくするので、それらに起因あるいは助長される大腸がんを始めとする慢性疾忠を減少させる。図1は、低食物繊維・高脂肪食と大腸がんとの関係を模式化したものである。
難消化性オりゴ糖の1つであるラクチュロースは、肝性脳症の症状改善剤として用いられる。これは、大腸における腐敗菌によるアンモニア生成を減少させ、肝臓の解毒の負担を軽減するためである。難消化性オリゴ糖はいずれも腸内細菌叢を改善する効果がある。また、多糖類である食物繊維にも同様の生理効果が期待できる。
腸内細菌叢の変動要因
腸内細菌叢は、健康な人ではバランスがとれた状態で安定している。これが、年齢、生活環境、ストレス、健康状態などの種々の要因により影響を受けて変動する。異常な腸内細菌叢は抗生物質投与、放射線治療、がん、外科手術、胃腸障害、老化、その他の病気などの場合に多く見られる。このような状態では、ビフィズス菌などの有用菌が減少あるいは消失し、ウェルシュ菌などの有害菌が多くなる。従って、ビフィズス菌が減少あるいは消失しているような腸内環境は、身体が不健康な状態にあるといえる。
赤ん坊は無菌的な状態で生まれるが、生後数日で腸内細菌が棲み付きビフィズス菌が優勢になり腸内環境が安定する。特に、母乳栄養児は人工栄養児に比べて腸内のビフィズズ菌が多く見られる。乳児が離乳食を食べるようになると、ビフィズス菌は1/10くらいに減少して、ユウバクテリウムやバクテロイデスが増加し、次第に成人の腸内環境に近づいて行く。
壮年期を過ぎて老年期に入るとビフィズス菌の減少が顕著になり、中にはビフィズス菌が検出できない人も多くなる。これに対し、有害菌であるウェルシュ菌や大腸菌などは増加する。加齢に伴うこのような腸内細菌叢の変化は、嗜好による食事内容の変化だけでなく、消化液の分泌、腸粘膜の剥離脱落などの生理機能の変化にも関係していると考えられる。腸内細菌叢の変化による腸内環境の悪化は、さらに老化を促進することにもなる。
腸内細菌叢が食事内容(成分)と深く関わっていることは、いろいろな疫学調査や実験により明らかにされている。高脂肪食や高たんぱく質食は有用菌を減少させ、有害菌を増加させる。例えば、高脂肪食を摂取するカナダ人と脂肪摂取量が少ない日本人の腸内細菌叢を比較すると、カナダ人には有害菌のバクテロイデスや大腸菌群が多く、有用菌のビフィズス菌やユウバクテリウムが有意に少ないという。また、標準的な米国人が摂取する牛肉量を2倍にした食事を摂取させると、ビフィズス菌やラクトバチルスが減少して有害菌であるクロストリジウムが増加し、腸管内でアンモニア、アミン、インドール類、フェノール類などの有害物質がたくさん作られるようになり、腸内環境が悪くなる。高脂肪・高たんぱく質・低食物繊維食は、腸内細菌叢を悪化させるので、肉類が少なく食物繊維の多い食事を取ることを心掛ける必要がある。
食物繊維と腸内細菌
食物繊維は人の消化酵素で消化されない食物成分で、主として多糖類およびリグニンからなっており、水溶性と不溶性に大別される。食物繊維は保水性や膨潤性が高く、吸着性やイオン交換能をもっている。このため、便量を多くして便通を促進したり、血清コレステロール値を改善したり、血糖上昇を抑制したり、大腸がんを予防する効果などを発現する。
食物繊維は消化されないので、難消化性オリゴ糖と同様に小腸を素通りして腸内細菌の生息場所である大腸に到達する。食物繊維のなかでも、不溶性は利用されにくいが水溶性であるペクチンやグアーガム、グルコマンナンなどは腸内細菌によって容易に利用される。このとき酢酸やピロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸のほか、炭酸ガス、水素ガス、メタンガスなどが産生される。短鎖脂肪酸は吸収されてエネルギー源としても利用されるが、腸管腔内を酸性にし、アルカリ性を好む腐敗菌や病原菌などの有害菌の増殖を抑制し、耐酸性のビフィズス菌などを増殖させる。
また、このような腸内環境では、インドール、スカトール、硫化物などの腐敗物が減少するとともに発がん物質などの生成も抑制される。インドールやスカトールが少なくなれば、オナラや糞便の悪臭は軽減される。さらに短鎖脂肪酸は、大腸を刺激してぜん動運動を促したり、腸管内の浸透圧を高めたりして排便を促進する。加えて、各々の短鎖脂肪酸は粘膜上皮細胞の分化誘導などの特有な生理機能を発現すると考えられている。小麦ふすまなどは腸内細菌に利用される水溶性食物繊維を含むと同時に、不溶性食物繊維が便容量を効果的に増大して排便を促進するので、大腸内容物の入れ替わり時間が短縮されて腸内細菌叢の改善が速やかに行われると考えられる。
菜食主義者は食物繊維の摂取量が多いため、その腸内細菌叢は有用菌であるラクトバチルスが多く、有害菌のクロストリジウムや大腸菌が少ない。また、同一人に白米または食物繊維の多い玄米を食べさせると、玄米食ではビフィズス菌が増加して腐敗菌の代表であるウェルシュ菌や大腸菌群が減少する。さらに、高脂肪食を摂取して有害菌が多くなった状態において食物繊維を多く摂取させると、有害菌が多かった腸内細菌叢が有用菌優勢の菌叢に改善されるという。このとき、有害菌により産生される腐敗物質も減少する。
一般的に高齢になると有用菌が減少して有害菌が増加するために、さまざまな有書物質(アンモニア、硫化水案、アミン、インドール、フェノールなど)が多量に生成されるようになり、これが吸収されてますます老化を早めると考えられている。有用菌の減少によって短鎖脂肪酸の生成が少なくなると、腸管内がアルカリ性に傾くために腸管内で作られたアンモニアの吸収が促進され、アミンの生成が増加する。沖縄や棡原(ゆずりはら)村の長寿高齢者は、都市在住高齢者に比べ腸内細菌叢のウェルシュ菌やラクトバチルスの菌数が少なく、ビフィズス菌が多いことが明らかにされている。棡原村の長寿高齢者は、雑穀類やいもなどを中心とした、食物繊維を多く含む食事を摂取しているためであろう。
おわりに
日本人の食物繊維摂取量は減少し続けており、現在では国民1人当たり1日に15~16g程度になっている。また、都市在住女子学生の食物繊維摂取量は1日当たりわずか11~12gまで滅少しているという調査結果もある。逆に、脂質摂取量は年々増加して約60gにもなり、脂肪エネルギー比率は至適範囲の20~25%を越えている。つまり、現在の日本人の食事内容は高脂肪・低食物繊維食になっているといえるだろう。食物繊維の目標摂取量が1日20~25gであることを考慮すれば、排便や腸内環境改善の上からも食物繊維をかなり積極的に摂取しなければならない状態にあるといえる。
参考文献
・辨野義己,光岡知足:(1985)発癌因子としての腸内フローラ,ヒトの腸内フローラに及ぼす食事成分の影響,光岡知足編,場内フローラと成人病,p.29-60,学会出版センター,東京
Kellogg's UPDATE No.38
東京大学大学院医学系研究科講師 奥恒行
はじめに
かつてわが国が低栄養に悩まされていた時代には、腸内に生息する細菌と健康との関わりについての関心は低かった。しかし、日本人の食生活が豊かになり、がん、心臓病、糖尿病などの慢性疾患が増加するに伴って食生活が見直され、同時に食事成分に影響を受けやすい腸内細菌との関係に関心が集まるようになってきた。腸内細菌叢(草が群がって生えているような細菌集団の分布、腸内フローラともいう)の改善を通して生体に有益な影響をもたらそうとするブロバイオティクスの概念構築は、これらの関心を反映したものと言える。
腸管には100種類100兆個の腸内細菌が生息して腸内細菌叢を形成している。腸内細菌のなかには、ビフィズス菌、ユウバクテリウム、乳酸菌などの有用菌、大腸菌やウェルシュ菌などの有害菌のほか、通常は良いこともしないが身体の調子が悪くなるといたずらをする日和見的な菌などがいる。
このように腸内細菌叢は多種多様な細菌で構成されているが、これらが互いに共生あるいは拮抗関係を保ちながら絶えず増殖しては排泄を繰り返している。このため、外来病原菌などが侵入しても簡単には腸管に定着・増殖することができない。また、何らかの要因によって腸内環境が悪化すると、便秘が生じやすくなったり便性が悪くなったりする。さらに、有害物質の生成量が増加して慢性疾患の誘発や老化の促進が助長され、健康状態は徐々に悪くなっていく。難消化性糖質である食物繊維やオリゴ糖などを食生活に上手に取り入れて腸内環境を改善すれば、現代人の食生活の危険度が軽減され、健康の維持・増進に寄与することが期待できる。
腸内細菌叢の健康との関わり
腸内細菌叢を構成する細菌は種類や数が多く、腸管内の代謝は極めて複雑になっている。従って腸内細菌叢が乱れると、大腸内の全体的な代謝バランスも変化する。その結果、宿主(生体)の健康状態が影響を受けることになる。
ある種の腸内細菌はビタミンやたんぱく質を合成するとともに、消化吸収されない糖質を利用可能な短鎖脂肪酸に転換し、宿主のエネルギー源にすることができる。また、腸内に常在する有用菌は外来病原菌やO-157(病原性大腸菌)などのバリアーとなって腸管感染を阻止する役割も果している。さらに、ある種の有用菌は生体の消化管免疫機能を向上させ、生体防御にも寄与している。
一方、有害菌によって生成される有害物質にはアンモニア、硫化物、アミン、フェノール、インドールなどの腐敗産物、ニトロソ化合物やエポキシドなどの発がん物質、細菌毒素、二次胆汁酸などがある。これらの有害物質は腸管自体に直接障害をもたらすとともに、一部は体内に吸収されていろいろな臓器に障害をもたらし、いろいろな慢性疾患の誘発に関与していると考えられる。腸内細菌叢を改善することは有害物質の生成を少なくするので、それらに起因あるいは助長される大腸がんを始めとする慢性疾忠を減少させる。図1は、低食物繊維・高脂肪食と大腸がんとの関係を模式化したものである。
難消化性オりゴ糖の1つであるラクチュロースは、肝性脳症の症状改善剤として用いられる。これは、大腸における腐敗菌によるアンモニア生成を減少させ、肝臓の解毒の負担を軽減するためである。難消化性オリゴ糖はいずれも腸内細菌叢を改善する効果がある。また、多糖類である食物繊維にも同様の生理効果が期待できる。
腸内細菌叢の変動要因
腸内細菌叢は、健康な人ではバランスがとれた状態で安定している。これが、年齢、生活環境、ストレス、健康状態などの種々の要因により影響を受けて変動する。異常な腸内細菌叢は抗生物質投与、放射線治療、がん、外科手術、胃腸障害、老化、その他の病気などの場合に多く見られる。このような状態では、ビフィズス菌などの有用菌が減少あるいは消失し、ウェルシュ菌などの有害菌が多くなる。従って、ビフィズス菌が減少あるいは消失しているような腸内環境は、身体が不健康な状態にあるといえる。
赤ん坊は無菌的な状態で生まれるが、生後数日で腸内細菌が棲み付きビフィズス菌が優勢になり腸内環境が安定する。特に、母乳栄養児は人工栄養児に比べて腸内のビフィズズ菌が多く見られる。乳児が離乳食を食べるようになると、ビフィズス菌は1/10くらいに減少して、ユウバクテリウムやバクテロイデスが増加し、次第に成人の腸内環境に近づいて行く。
壮年期を過ぎて老年期に入るとビフィズス菌の減少が顕著になり、中にはビフィズス菌が検出できない人も多くなる。これに対し、有害菌であるウェルシュ菌や大腸菌などは増加する。加齢に伴うこのような腸内細菌叢の変化は、嗜好による食事内容の変化だけでなく、消化液の分泌、腸粘膜の剥離脱落などの生理機能の変化にも関係していると考えられる。腸内細菌叢の変化による腸内環境の悪化は、さらに老化を促進することにもなる。
腸内細菌叢が食事内容(成分)と深く関わっていることは、いろいろな疫学調査や実験により明らかにされている。高脂肪食や高たんぱく質食は有用菌を減少させ、有害菌を増加させる。例えば、高脂肪食を摂取するカナダ人と脂肪摂取量が少ない日本人の腸内細菌叢を比較すると、カナダ人には有害菌のバクテロイデスや大腸菌群が多く、有用菌のビフィズス菌やユウバクテリウムが有意に少ないという。また、標準的な米国人が摂取する牛肉量を2倍にした食事を摂取させると、ビフィズス菌やラクトバチルスが減少して有害菌であるクロストリジウムが増加し、腸管内でアンモニア、アミン、インドール類、フェノール類などの有害物質がたくさん作られるようになり、腸内環境が悪くなる。高脂肪・高たんぱく質・低食物繊維食は、腸内細菌叢を悪化させるので、肉類が少なく食物繊維の多い食事を取ることを心掛ける必要がある。
食物繊維と腸内細菌
食物繊維は人の消化酵素で消化されない食物成分で、主として多糖類およびリグニンからなっており、水溶性と不溶性に大別される。食物繊維は保水性や膨潤性が高く、吸着性やイオン交換能をもっている。このため、便量を多くして便通を促進したり、血清コレステロール値を改善したり、血糖上昇を抑制したり、大腸がんを予防する効果などを発現する。
食物繊維は消化されないので、難消化性オリゴ糖と同様に小腸を素通りして腸内細菌の生息場所である大腸に到達する。食物繊維のなかでも、不溶性は利用されにくいが水溶性であるペクチンやグアーガム、グルコマンナンなどは腸内細菌によって容易に利用される。このとき酢酸やピロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸のほか、炭酸ガス、水素ガス、メタンガスなどが産生される。短鎖脂肪酸は吸収されてエネルギー源としても利用されるが、腸管腔内を酸性にし、アルカリ性を好む腐敗菌や病原菌などの有害菌の増殖を抑制し、耐酸性のビフィズス菌などを増殖させる。
また、このような腸内環境では、インドール、スカトール、硫化物などの腐敗物が減少するとともに発がん物質などの生成も抑制される。インドールやスカトールが少なくなれば、オナラや糞便の悪臭は軽減される。さらに短鎖脂肪酸は、大腸を刺激してぜん動運動を促したり、腸管内の浸透圧を高めたりして排便を促進する。加えて、各々の短鎖脂肪酸は粘膜上皮細胞の分化誘導などの特有な生理機能を発現すると考えられている。小麦ふすまなどは腸内細菌に利用される水溶性食物繊維を含むと同時に、不溶性食物繊維が便容量を効果的に増大して排便を促進するので、大腸内容物の入れ替わり時間が短縮されて腸内細菌叢の改善が速やかに行われると考えられる。
菜食主義者は食物繊維の摂取量が多いため、その腸内細菌叢は有用菌であるラクトバチルスが多く、有害菌のクロストリジウムや大腸菌が少ない。また、同一人に白米または食物繊維の多い玄米を食べさせると、玄米食ではビフィズス菌が増加して腐敗菌の代表であるウェルシュ菌や大腸菌群が減少する。さらに、高脂肪食を摂取して有害菌が多くなった状態において食物繊維を多く摂取させると、有害菌が多かった腸内細菌叢が有用菌優勢の菌叢に改善されるという。このとき、有害菌により産生される腐敗物質も減少する。
一般的に高齢になると有用菌が減少して有害菌が増加するために、さまざまな有書物質(アンモニア、硫化水案、アミン、インドール、フェノールなど)が多量に生成されるようになり、これが吸収されてますます老化を早めると考えられている。有用菌の減少によって短鎖脂肪酸の生成が少なくなると、腸管内がアルカリ性に傾くために腸管内で作られたアンモニアの吸収が促進され、アミンの生成が増加する。沖縄や棡原(ゆずりはら)村の長寿高齢者は、都市在住高齢者に比べ腸内細菌叢のウェルシュ菌やラクトバチルスの菌数が少なく、ビフィズス菌が多いことが明らかにされている。棡原村の長寿高齢者は、雑穀類やいもなどを中心とした、食物繊維を多く含む食事を摂取しているためであろう。
おわりに
日本人の食物繊維摂取量は減少し続けており、現在では国民1人当たり1日に15~16g程度になっている。また、都市在住女子学生の食物繊維摂取量は1日当たりわずか11~12gまで滅少しているという調査結果もある。逆に、脂質摂取量は年々増加して約60gにもなり、脂肪エネルギー比率は至適範囲の20~25%を越えている。つまり、現在の日本人の食事内容は高脂肪・低食物繊維食になっているといえるだろう。食物繊維の目標摂取量が1日20~25gであることを考慮すれば、排便や腸内環境改善の上からも食物繊維をかなり積極的に摂取しなければならない状態にあるといえる。
参考文献
・辨野義己,光岡知足:(1985)発癌因子としての腸内フローラ,ヒトの腸内フローラに及ぼす食事成分の影響,光岡知足編,場内フローラと成人病,p.29-60,学会出版センター,東京
Kellogg's UPDATE No.38
マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計
Posted by suiso at 11:11
│学術発表
│学術発表