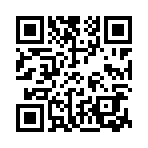2011年11月04日
機能性食品素材開発を睨んだ食物繊維の水素産生に関する基礎研究
平成23年度 ノーステック財団「研究開発助成事業」若手研究人材育成事業 若手研究人材・ネットワーク育成補助金
「タイトル:機能性食品素材開発を睨んだ食物繊維の水素産生に関する基礎研究」
研究者名:田邊宏基
所属・役職:名寄市立大学・助教
背景・目的
近年、体液中の水素が活性酸素種を還元するとの新規知見が報告され、水素ガス吸入の有効性が検討されている。我々は食物繊維(DF)が先の方法と同程度の水素を体内へ供給すると確認した。本研究で水素供給におけるDFの時間的限界を解明し、DFを多く含む農産物非食部に価値を付加し、有用な食品素材の開発へ繋ぐ。
研究の成果
ラットに対照飼料またはDFとして10%および20%のレジスタントスターチ (RS) を添加した飼料を14日間摂取させ、1日に排出される水素量を経時的に測定した。その結果、全水素排出量はRSの添加量に関わらず全ての時間帯で対照飼料群に比べ有意な増加を示した (図1)。しかしながら、 20%RS飼料群に比べ10%RS飼料群では大きな日内変動が確認された。これは睡眠時に大腸内の発酵基質が殆ど消費され、水素産生量が低下するためであると考えられる。一方、腸内細菌の日内変動による水素産生量の変化は本試験では確認できなかった。水素産生において日内変動の主たる要因は発酵基質の消費速度であると考えられる。以上の結果から恒常的に水素を産生し続けるためには、次回摂食まで腸内に残るDFのタイプと摂取量が必要になる事が示唆された。
将来展望
本試験の結果から、現在注目されているオリゴ糖では速やかに腸内細菌に分解、利用されてしまうため、継続的に水素を産生し続けることは難しいと考えられる。従って、第一に構成糖が同じで重合度の異なるDFを用いて水素産生の継続性を比較、検討する必要がある。推測通り重合度の高いDFで継続性が確認できれば、農産物非食部から時間と労力をかけてオリゴ糖を抽出する必要なく、粗の状態で付加価値を付けることが可能である。第二に、これまでは単純化するためにグルコースを構成糖とするRSを用いてきたが、他の糖で構成されたDFで試験を行い、最も水素を産生しやすい農産物非食部を選出する必要がある。
◆「若手研究者交流会」と理事長賞授与式を開催しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月4日(金)、当財団が若手研究者(40歳以下)の人材育成を目的として実施しているタレント(Talent)補助金助成対象者19名が参加しての交流会を開催しました。学会では、若手研究者の交流が活発に行われておりますが、工学、医学、歯学、薬学など異分野間での研究者交流はあまり行われておらず、当日は論文作製や学生への教育、臨床など多様な業務を抱える同世代の研究者間で情報交換を行なうことができました。今後は大学研究者のみならず、道内企業の若手研究者・技術者の連携も深めていこうと考えています。
また、助成対象研究テーマの中から、名寄市立大学保健福祉学部栄養学科助教 田邊宏基氏の「機能性食品素材開発を睨んだ食物繊維の水素産生に関する基礎研究」が先進性を認められ、今年度の理事長賞を受賞しました。
http://www.noastec.jp/topics/2011/11/post-70.html
「タイトル:機能性食品素材開発を睨んだ食物繊維の水素産生に関する基礎研究」
研究者名:田邊宏基
所属・役職:名寄市立大学・助教
背景・目的
近年、体液中の水素が活性酸素種を還元するとの新規知見が報告され、水素ガス吸入の有効性が検討されている。我々は食物繊維(DF)が先の方法と同程度の水素を体内へ供給すると確認した。本研究で水素供給におけるDFの時間的限界を解明し、DFを多く含む農産物非食部に価値を付加し、有用な食品素材の開発へ繋ぐ。
研究の成果
ラットに対照飼料またはDFとして10%および20%のレジスタントスターチ (RS) を添加した飼料を14日間摂取させ、1日に排出される水素量を経時的に測定した。その結果、全水素排出量はRSの添加量に関わらず全ての時間帯で対照飼料群に比べ有意な増加を示した (図1)。しかしながら、 20%RS飼料群に比べ10%RS飼料群では大きな日内変動が確認された。これは睡眠時に大腸内の発酵基質が殆ど消費され、水素産生量が低下するためであると考えられる。一方、腸内細菌の日内変動による水素産生量の変化は本試験では確認できなかった。水素産生において日内変動の主たる要因は発酵基質の消費速度であると考えられる。以上の結果から恒常的に水素を産生し続けるためには、次回摂食まで腸内に残るDFのタイプと摂取量が必要になる事が示唆された。
将来展望
本試験の結果から、現在注目されているオリゴ糖では速やかに腸内細菌に分解、利用されてしまうため、継続的に水素を産生し続けることは難しいと考えられる。従って、第一に構成糖が同じで重合度の異なるDFを用いて水素産生の継続性を比較、検討する必要がある。推測通り重合度の高いDFで継続性が確認できれば、農産物非食部から時間と労力をかけてオリゴ糖を抽出する必要なく、粗の状態で付加価値を付けることが可能である。第二に、これまでは単純化するためにグルコースを構成糖とするRSを用いてきたが、他の糖で構成されたDFで試験を行い、最も水素を産生しやすい農産物非食部を選出する必要がある。
◆「若手研究者交流会」と理事長賞授与式を開催しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月4日(金)、当財団が若手研究者(40歳以下)の人材育成を目的として実施しているタレント(Talent)補助金助成対象者19名が参加しての交流会を開催しました。学会では、若手研究者の交流が活発に行われておりますが、工学、医学、歯学、薬学など異分野間での研究者交流はあまり行われておらず、当日は論文作製や学生への教育、臨床など多様な業務を抱える同世代の研究者間で情報交換を行なうことができました。今後は大学研究者のみならず、道内企業の若手研究者・技術者の連携も深めていこうと考えています。
また、助成対象研究テーマの中から、名寄市立大学保健福祉学部栄養学科助教 田邊宏基氏の「機能性食品素材開発を睨んだ食物繊維の水素産生に関する基礎研究」が先進性を認められ、今年度の理事長賞を受賞しました。
http://www.noastec.jp/topics/2011/11/post-70.html
マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計
水素に関する最近の研究
水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
水素の医療利用に関する論文、280報を超す
認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計