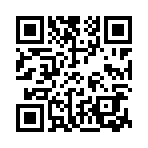2014年03月14日
国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業
健康博覧会2014セミナー/シンポジウム
2014年3月14日
[機能性表示ガイドライン]
国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業
来年3月を目途に進む食品の機能性表示制度、一方で全国各地でも食品の機能性に関する新たな制度設計の試みが進み、食品機能性に取り組む20近い地方自治体、経済団体、支援機関による食品地方連絡会が結成されました。
食品機能性表示改革は全国の食品産業にどのような効果をもたらすのでしょうか?政府の司令塔を招き現状をお聞きします。
主催:食品機能性地方連絡会 協賛:UBMメディア
動きだした機能性表示
-最新情報-
内閣府 規制改革会議委員
内閣官房 健康・医療戦略水深本部 戦略参与
大阪府市統合本部 医療戦略参与
大阪大学大学院医学系研究科
森下竜一氏


いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認
特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。
平成25年度検討・平成26年度結論・措置(加工食品・農林水産物とも)
消費者庁・厚生労働省・農林水産省
食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
(消費者庁 平成25年12月17日)
目的
これらの閣議決定を受け、消費者庁長官のもと「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催し、特定保健用食品制度及び栄養機能食品制度を維持しつつ、企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、検討を行うこととする。
検討項目
(1)食品の新たな機能性表示制度に係る安全性確保の在り方
(2)食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方
(3)消費者にとって誤認のない食品の機能性表示の方法の在り方
スケジュール及び今後の進め方
現行の食品の機能性表示制度や米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を始めとする海外の食品表示制度の現状等を踏まえ、関係者からのヒアリング等を行いつつ検討を進め、平成26年夏を目途に報告書を取りまとめる。



大きな4分野の構成要素
4本足の椅子のような規則
1.成分や原料の安全性・製品中の成分の安全性の確保
2.製造基準-品質の確保
3.表示とクレーム・表示は正確で真実であり、成分は効果があること
4.有害作用報告-製品の安全性は市販後調査でモニターされている

次世代ヘルスケア協議会
主旨
健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のQOL(生活の豊かさ)の向上、国民医療費の抑制、雇用拡大及び我が国経済の成長に資するものと考えられます。このため、健康寿命延伸分野における民間の様々な製品やサービスの実態を把握し、供給・需要の両面から課題や問題点を抽出・整理し、対応策を検討するため、官民一体となって具体的な対応策の検討を行う場として同協議会を設置します。
主な検討事項
・新たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備(グレーゾーン解消等)
・健康関連サービス・製品の品質評価の在り方
・企業、個人等の健康投資を促進するための方策 等
(経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課)
成長戦略第3弾スピーチ
平成25年6月5日
健康食品の機能性表示を、解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです。
現在は、国から「トクホ」の認定を受けなければ、「強い骨をつくる」といった効果を商品に記載できません。お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう。
アメリカでは、国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば、商品に機能性表示を行うことができます。国へは事後に届出をするだけでよいのです。
今回の解禁は、単に、世界と制度をそろえるだけにとどまりません。農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思います。
目指すのは、「世界並み」ではありません。むしろ、「世界最先端」です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現。それが安倍内閣の基本方針です。

UBMメディア㈱代表取締役 牧野順一氏のコメント
「やっぱり(製品そのものに)エビデンスがないものは、そうそう(機能性を)言えないんです」
【関連記事】
食品機能性研究の新しい動き
農研機構食品総合研究所 山本(前田)万里
一般財団法人食品分析開発セン ターSUNATEC
http://www.mac.or.jp/mail/131001/02.shtml
食の安心・安全に関する情報
健康食品の機能性表示について考える
長村 洋一(鈴鹿医療科学大学)
日本食品安全協会会報 第8巻 第4号 2013年
http://www.ffcci.jp/information/img/kaiho2_8-4.pdf
2014年3月14日
[機能性表示ガイドライン]
国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業
来年3月を目途に進む食品の機能性表示制度、一方で全国各地でも食品の機能性に関する新たな制度設計の試みが進み、食品機能性に取り組む20近い地方自治体、経済団体、支援機関による食品地方連絡会が結成されました。
食品機能性表示改革は全国の食品産業にどのような効果をもたらすのでしょうか?政府の司令塔を招き現状をお聞きします。
主催:食品機能性地方連絡会 協賛:UBMメディア
動きだした機能性表示
-最新情報-
内閣府 規制改革会議委員
内閣官房 健康・医療戦略水深本部 戦略参与
大阪府市統合本部 医療戦略参与
大阪大学大学院医学系研究科
森下竜一氏


いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認
特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。
平成25年度検討・平成26年度結論・措置(加工食品・農林水産物とも)
消費者庁・厚生労働省・農林水産省
食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
(消費者庁 平成25年12月17日)
目的
これらの閣議決定を受け、消費者庁長官のもと「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催し、特定保健用食品制度及び栄養機能食品制度を維持しつつ、企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、検討を行うこととする。
検討項目
(1)食品の新たな機能性表示制度に係る安全性確保の在り方
(2)食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方
(3)消費者にとって誤認のない食品の機能性表示の方法の在り方
スケジュール及び今後の進め方
現行の食品の機能性表示制度や米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を始めとする海外の食品表示制度の現状等を踏まえ、関係者からのヒアリング等を行いつつ検討を進め、平成26年夏を目途に報告書を取りまとめる。



大きな4分野の構成要素
4本足の椅子のような規則
1.成分や原料の安全性・製品中の成分の安全性の確保
2.製造基準-品質の確保
3.表示とクレーム・表示は正確で真実であり、成分は効果があること
4.有害作用報告-製品の安全性は市販後調査でモニターされている

次世代ヘルスケア協議会
主旨
健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のQOL(生活の豊かさ)の向上、国民医療費の抑制、雇用拡大及び我が国経済の成長に資するものと考えられます。このため、健康寿命延伸分野における民間の様々な製品やサービスの実態を把握し、供給・需要の両面から課題や問題点を抽出・整理し、対応策を検討するため、官民一体となって具体的な対応策の検討を行う場として同協議会を設置します。
主な検討事項
・新たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備(グレーゾーン解消等)
・健康関連サービス・製品の品質評価の在り方
・企業、個人等の健康投資を促進するための方策 等
(経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課)
成長戦略第3弾スピーチ
平成25年6月5日
健康食品の機能性表示を、解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです。
現在は、国から「トクホ」の認定を受けなければ、「強い骨をつくる」といった効果を商品に記載できません。お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう。
アメリカでは、国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば、商品に機能性表示を行うことができます。国へは事後に届出をするだけでよいのです。
今回の解禁は、単に、世界と制度をそろえるだけにとどまりません。農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思います。
目指すのは、「世界並み」ではありません。むしろ、「世界最先端」です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現。それが安倍内閣の基本方針です。

UBMメディア㈱代表取締役 牧野順一氏のコメント
「やっぱり(製品そのものに)エビデンスがないものは、そうそう(機能性を)言えないんです」
【関連記事】
食品機能性研究の新しい動き
農研機構食品総合研究所 山本(前田)万里
一般財団法人食品分析開発セン ターSUNATEC
http://www.mac.or.jp/mail/131001/02.shtml
食の安心・安全に関する情報
健康食品の機能性表示について考える
長村 洋一(鈴鹿医療科学大学)
日本食品安全協会会報 第8巻 第4号 2013年
http://www.ffcci.jp/information/img/kaiho2_8-4.pdf
Posted by suiso at 16:20
│セミナー
│セミナー
この記事へのコメント
食品衛生法の規定
食品等事業者の責務
食品等事業者は、販売食品等について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。
健康を損なうおそれのある食品などの販売等の禁止
次に掲げる食品又は添加物は、販売等をしてはならないとされている。
①腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの
②有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの
③病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの
④不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの
新開発食品の販売禁止
次に掲げるものは、食品衛生上の危害の発生を防止するため、厚生労働大臣は販売を禁止することができるとされている。
①一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む食品
②一般に飲食に供されているものであるが、通常の方法とは著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの
③食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものが含まれていることが疑われるもの
食品又は添加物の基準及び規格
公衆衛生の見地から販売に供する食品若しくは添加物の製造等の基準又は成分についての規格を、厚生労働大臣は定めることができる。これらの基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により製造等した食品若しくは添加物又はその規格に合わない食品若しくは添加物を販売等をしてはならないとされている。
(出典)食品衛生法(昭和22年法律第233号)
「食品衛生法の規定」は大きく4つあります。
1つ目が、食品等事業者の責務です。食品等事業者は、自らの責任において食品の安全性を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
2つ目、健康を損なうおそれのある食品などの販売等の禁止です。腐敗したものや有毒・有害な物質が含まれるものなど、健康を損なうおそれのある食品は、販売等をしてはならない規定です。
3つ目、新開発食品の販売禁止です。科学技術の発展や輸入食品の多様化で、それまで食経験のないようなものを摂取する可能性や、食経験があっても、食経験のない水準あるいは方法で摂取する可能性があるということで、新開発された食品については、一般に飲食に供されることがなかったもの、通常の方法とは著しく異なる方法により飲食に供されているもので、健康を損なうおそれがない旨の確証がないものなどは、被害の発生を防止するために販売を禁止できます。
4つ目、食品又は添加物の基準及び規格です。これは、飲食による被害を未然に防止するための積極的な公衆衛生の見地からの規定で、食品や添加物の製造の基準、成分についての規格を定めることができ、その規格、基準に合わない食品や添加物は販売等してはならない規定です。
このような食品衛生法の規定が、食品全般にかかる規定です。
「第2回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」より
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140131_gijiroku.pdf
食品等事業者の責務
食品等事業者は、販売食品等について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。
健康を損なうおそれのある食品などの販売等の禁止
次に掲げる食品又は添加物は、販売等をしてはならないとされている。
①腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの
②有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの
③病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの
④不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの
新開発食品の販売禁止
次に掲げるものは、食品衛生上の危害の発生を防止するため、厚生労働大臣は販売を禁止することができるとされている。
①一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む食品
②一般に飲食に供されているものであるが、通常の方法とは著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの
③食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかったものが含まれていることが疑われるもの
食品又は添加物の基準及び規格
公衆衛生の見地から販売に供する食品若しくは添加物の製造等の基準又は成分についての規格を、厚生労働大臣は定めることができる。これらの基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により製造等した食品若しくは添加物又はその規格に合わない食品若しくは添加物を販売等をしてはならないとされている。
(出典)食品衛生法(昭和22年法律第233号)
「食品衛生法の規定」は大きく4つあります。
1つ目が、食品等事業者の責務です。食品等事業者は、自らの責任において食品の安全性を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
2つ目、健康を損なうおそれのある食品などの販売等の禁止です。腐敗したものや有毒・有害な物質が含まれるものなど、健康を損なうおそれのある食品は、販売等をしてはならない規定です。
3つ目、新開発食品の販売禁止です。科学技術の発展や輸入食品の多様化で、それまで食経験のないようなものを摂取する可能性や、食経験があっても、食経験のない水準あるいは方法で摂取する可能性があるということで、新開発された食品については、一般に飲食に供されることがなかったもの、通常の方法とは著しく異なる方法により飲食に供されているもので、健康を損なうおそれがない旨の確証がないものなどは、被害の発生を防止するために販売を禁止できます。
4つ目、食品又は添加物の基準及び規格です。これは、飲食による被害を未然に防止するための積極的な公衆衛生の見地からの規定で、食品や添加物の製造の基準、成分についての規格を定めることができ、その規格、基準に合わない食品や添加物は販売等してはならない規定です。
このような食品衛生法の規定が、食品全般にかかる規定です。
「第2回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」より
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140131_gijiroku.pdf
Posted by 食品衛生法の規定 at 2014年03月16日 21:32