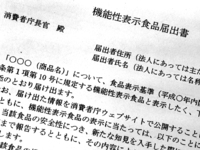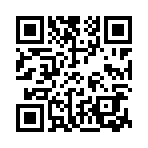2014年03月11日
マイナス水素の力 できるか新素材・室温超伝導
マイナス水素の力 できるか新素材・室温超伝導
朝日新聞 2014年2月10日

原子番号1、元素記号H。数ある元素の中で最も基本的な「水素」について、最近意外なことがわかってきた。特殊な存在と思われていた「マイナスの水素」が、そこそこ安定していて、いろんな物質の中で活躍しているようなのだ。うまく使いこなせば、室温で超伝導になる物質や電気を通すセメントなど、これまでにない新素材がつくれるかもしれない。
100種類以上ある元素を規則正しく並べた周期表。「水兵リーべ僕の船」という語呂合わせで覚えた人も多いだろう。その先頭に来るのが水素。定位置は一番左上だ。
だが、京都大の陰山洋教授(無機化学)は「水素は右上にも置くべきだという考えも出てきた」という。
水索はもともと陽イオンにも陰イオンにもなれるが、化学の授業では、陽イオンになりやすい典型的な元素と習う。「H」の右肩に小さい「+」がある記号で表される「水素イオン」はごくありふれた存在で、水に濃く溶けていると酸性になることでも知られる。
一方、『マイナスの水素』は記号だと「H」に小さい「-」がつく。正式名は「水素化物イオン」だ。これは、自分より陽イオンになりやすい元素と結合する場合などに限ってあらわれる例外的な存在と考えられてきた。周期表の規則性からみても、そう考えるのが自然だった。ところが、「マイナスの水素」が安定して存在する物質が、最新の材料研究で次々と見つかっている。
そもそも、水素原子が水素イオンになるか「マイナスの水素」になるかは、電子1個を失うか、電子1個をもらうかの違いしかない。「マイナスの水素」を例外的な存在と考えるのは、先入観にすぎないかもしれない。

化学の常識覆す
東京工業大の細野秀雄教授が「マイナスの水素」の意外な活躍を見つけたのは、新しい超伝導物質を探索している時だった。
細野さんたちは、2008年、超伝導にならないと思われていた鉄の酸化物が超伝導になることを発表した。元々の酸化物に含まれていた酸素の一部を、大きさが同程度で陰イオンになりやすいフッ素で置き換えたのが決め手だった。
だが、フッ素は少ししか置き換われないので、ほかの陰イオンを試してみると、「マイナスの水素」が同様に酸素の一部と置き換わることがわかった。
酸素と水素か一緒にあると、酸素か陰イオンに、水素は陽イオンになる、というのが化学の常識。酸化物の中で「マイナスの水素」が安定して存在できるのは予想外のことだ。
しかや『マイナスの水素』の方がフッ素より3倍多く酸素を置き換えられた。おかげで、置き換える量によって性格の違う2種類の超伝導があるとわかった。細野さんは「『マイナスの水素』は室温超伝導への有望なルートではないか」という。
京大の陰山さんは13年、ごく普通のセラミックス(酸化物)を元に、酸素の2割を「マイナスの水素」に置き換えた物質をつくったと発表した。電子と「マイナスの水素」の両方が酸化物の中を動き回り、電池の電極に使えれば電圧が高くなるという。陰山さんは「燃料電池自動車や電気自動車のパワーが倍増するかもしれない」という。
進む実用化研究
「マイナスの水素」の積極的な活用は研究が始まったばかりだが、影響が及ぶ範囲は広い。
細野さんらは『電気を通すセメント』もつくった。まず、アルミナセメント(カルシウムとアルミニウムの酸化物)に「マイナスの水素」を入れる。これに光を当てると、セメントの中で「マイナスの水素」が電子2個を出して水素イオンに変わる。その電子が動き回って電気を通すようになる。
東工大の林克郎准教授は「『マイナスの水素』は水素イオンより不安定なものの、ある程度は安定して存在できる。光のエネルギーで両者の間にある峠を越えさせている」と説明する。
この特性を生かして、太陽電池や薄型テレビの画面に欠かせない「電気を通す透明な部品」(透明電極)を安価につくる研究も進む。いまはインジウムというレアメタル(希少金属)が欠かせないが、「マイナスの水素」を使えばカルシウムやアルミニウムなどでつくれるかもしれない。
コンピューターを使って物質の性質を予想する理論計算も影響を受ける可能性がある。物質の中にある水素は水素イオンと想定して計算することが多い。それが実は「マイナスの水素」だったとしたら、計算の前提が変わってしまうからだ。東京大の常行真司教授は「マイナスとプラスでは、性質もいるべき場所も違う。前提が変われば結果も変わってしまう」と話す。
(鍛洽信太郎)
朝日新聞 2014年2月10日

原子番号1、元素記号H。数ある元素の中で最も基本的な「水素」について、最近意外なことがわかってきた。特殊な存在と思われていた「マイナスの水素」が、そこそこ安定していて、いろんな物質の中で活躍しているようなのだ。うまく使いこなせば、室温で超伝導になる物質や電気を通すセメントなど、これまでにない新素材がつくれるかもしれない。
100種類以上ある元素を規則正しく並べた周期表。「水兵リーべ僕の船」という語呂合わせで覚えた人も多いだろう。その先頭に来るのが水素。定位置は一番左上だ。
だが、京都大の陰山洋教授(無機化学)は「水素は右上にも置くべきだという考えも出てきた」という。
水索はもともと陽イオンにも陰イオンにもなれるが、化学の授業では、陽イオンになりやすい典型的な元素と習う。「H」の右肩に小さい「+」がある記号で表される「水素イオン」はごくありふれた存在で、水に濃く溶けていると酸性になることでも知られる。
一方、『マイナスの水素』は記号だと「H」に小さい「-」がつく。正式名は「水素化物イオン」だ。これは、自分より陽イオンになりやすい元素と結合する場合などに限ってあらわれる例外的な存在と考えられてきた。周期表の規則性からみても、そう考えるのが自然だった。ところが、「マイナスの水素」が安定して存在する物質が、最新の材料研究で次々と見つかっている。
そもそも、水素原子が水素イオンになるか「マイナスの水素」になるかは、電子1個を失うか、電子1個をもらうかの違いしかない。「マイナスの水素」を例外的な存在と考えるのは、先入観にすぎないかもしれない。

化学の常識覆す
東京工業大の細野秀雄教授が「マイナスの水素」の意外な活躍を見つけたのは、新しい超伝導物質を探索している時だった。
細野さんたちは、2008年、超伝導にならないと思われていた鉄の酸化物が超伝導になることを発表した。元々の酸化物に含まれていた酸素の一部を、大きさが同程度で陰イオンになりやすいフッ素で置き換えたのが決め手だった。
だが、フッ素は少ししか置き換われないので、ほかの陰イオンを試してみると、「マイナスの水素」が同様に酸素の一部と置き換わることがわかった。
酸素と水素か一緒にあると、酸素か陰イオンに、水素は陽イオンになる、というのが化学の常識。酸化物の中で「マイナスの水素」が安定して存在できるのは予想外のことだ。
しかや『マイナスの水素』の方がフッ素より3倍多く酸素を置き換えられた。おかげで、置き換える量によって性格の違う2種類の超伝導があるとわかった。細野さんは「『マイナスの水素』は室温超伝導への有望なルートではないか」という。
京大の陰山さんは13年、ごく普通のセラミックス(酸化物)を元に、酸素の2割を「マイナスの水素」に置き換えた物質をつくったと発表した。電子と「マイナスの水素」の両方が酸化物の中を動き回り、電池の電極に使えれば電圧が高くなるという。陰山さんは「燃料電池自動車や電気自動車のパワーが倍増するかもしれない」という。
進む実用化研究
「マイナスの水素」の積極的な活用は研究が始まったばかりだが、影響が及ぶ範囲は広い。
細野さんらは『電気を通すセメント』もつくった。まず、アルミナセメント(カルシウムとアルミニウムの酸化物)に「マイナスの水素」を入れる。これに光を当てると、セメントの中で「マイナスの水素」が電子2個を出して水素イオンに変わる。その電子が動き回って電気を通すようになる。
東工大の林克郎准教授は「『マイナスの水素』は水素イオンより不安定なものの、ある程度は安定して存在できる。光のエネルギーで両者の間にある峠を越えさせている」と説明する。
この特性を生かして、太陽電池や薄型テレビの画面に欠かせない「電気を通す透明な部品」(透明電極)を安価につくる研究も進む。いまはインジウムというレアメタル(希少金属)が欠かせないが、「マイナスの水素」を使えばカルシウムやアルミニウムなどでつくれるかもしれない。
コンピューターを使って物質の性質を予想する理論計算も影響を受ける可能性がある。物質の中にある水素は水素イオンと想定して計算することが多い。それが実は「マイナスの水素」だったとしたら、計算の前提が変わってしまうからだ。東京大の常行真司教授は「マイナスとプラスでは、性質もいるべき場所も違う。前提が変われば結果も変わってしまう」と話す。
(鍛洽信太郎)
「インチキ水素水」ブログ、「中傷だ」と日本トリムが研究者提訴
産経新聞が、事実に反する水素水の記事をコッソリ訂正
「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター
マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響
心停止の患者 水素で脳ダメージ軽減 臨床研究開始へ
ユニヴェールの水素サプリメント・ラヴィがリニューアル
産経新聞が、事実に反する水素水の記事をコッソリ訂正
「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター
マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響
心停止の患者 水素で脳ダメージ軽減 臨床研究開始へ
ユニヴェールの水素サプリメント・ラヴィがリニューアル